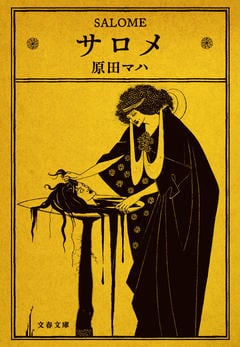“天才”と言われる人には皆どこか似たような傾向があるように思う。あくまで私の見解だが、まず好奇心と探究心のカルマに自我を乗っ取られ、知的欲求の暴走に身を委ねることで生きる彼らには、自己顕示欲などというものを意識するゆとりはない。だから自らを天才だと自覚することもないし、自覚の必要もない。こうした突出したカルマを持った人間は、一般人から多大な賞賛を受け、羨望の対象となりながらも、疎まれ、孤立を強いられる。気持ちの赴くままにどこまでも思索し、無我夢中で技術力を磨き、納得のいく結果を生むまで生命を燃焼させている、そんな人間は、心地よい怠惰に身を委ねて生きることを正当化したい人間にとってただの目障りでしかない。メンタルの枯渇感を必死になって満たそうと尽くせば尽くすほど、底無しの孤独という負荷を背負わなければならなくなるのが、天才の宿命なのだ。こういうふうに考えていくと、天才というのは、ある意味目障りな人間への称号のような気がしないでもない。
スティーブ・ジョブズにしてもアインシュタインにしても、そして今回のレオナルド・ダ・ヴィンチにしても、ウォルター・アイザックソンがそうした人物ばかりを選んで評伝にしているのはなぜなのか。彼は決して彼らの天才性を真っ向から崇め奉っているわけではない。読み進めているうちに、マニュアルを無視し、社会の軌道から外れ、時には自らを壊しつつも、後世に語り継がれる何かを生み出す者たちの神秘性を著者と一緒に容赦無く解体しているような気持ちになる。
私は過去にアイザックソンが著したジョブズの評伝全2巻分を漫画化したが、原作を読んだ直後に感じたのは、アイザックソンのジョブズに対するあくまで沈着冷静な俯瞰の目線だった。尋常ではない生き方を辿った人物の解釈に挑む興奮が筆致に現れる気配もあるが、やはりアイザックソンにとってのジョブズは、自分とは相いれない未知なる観察対象だったのではないかという印象が残った。
ウォルター・アイザックソンはジョブズやレオナルドとは違って、ハーバードやオックスフォードといった、要は世間における最高水準の学府の学位を取得した、いわゆる現代社会においてのエリート中のエリートである。そんな彼からしてみれば、非嫡出子として生まれ、生みの親による愛情を経験しないまま育ち、しかも決してハイクオリティな教育を受けてきたわけでもなく、むしろ社会では問題児扱いを受けてきたような人物が、世界にその名を残していくであろうイノベーターとなりえた理由を分析したくなるのは自然の摂理なのかもしれない。
敷かれたレールの上を進まなかったことが、時に社会現象をもたらすような稀有な展開を導く、その謎のストラクチャーを知りたいと思うのは彼だけではないだろう。どんなに勤勉を貫いても、成功に導いてくれるはずのマニュアルを忠実にこなしても、それが計画通りの成績や結果を与えてくれるわけではないという辛辣な事実を明白に顕示してくるのが、こうした天才たちの存在だ。そして、そんな彼らと向き合っているうちにアイザックソンが得た天才の定義の一つが、科学と芸術、技術と人文とのクロッシングという要素である。
レオナルド・ダ・ヴィンチについてはこれまでにも実にたくさんの文献が出ているし、その特異な生き方は映画やドラマにとっても格好のネタとなってきた。しかしアイザックソンはレオナルドに特化した研究者でもなければ、美術史の専門家でもない。本書はレオナルドの残した膨大な量の自筆ノートをもとに、出生から時系列に沿ってその人生が綴られているが、ところどころに他者の視点によるレオナルド分析に対して個人的な見解が介入する。
心理学者フロイトによるレオナルドの分析が不適当だと思われるその理由を、自筆ノートのドイツ語翻訳の質の低さにあるとし、さらにこの誤った精神分析によってその後のおかしなレオナルドのイメージが作り上げられてしまったと指摘する。それからまたしばらく読み進めていくと、オークションに出品され話題となった『美しき姫君』という作品をレオナルド作だと主張する美術収集家のエピソードに焦点が当てられる。レオナルドという天才が後世の人間にいかなる影響を及ぼす存在であったのか、アイザックソンの分析は500年の時を経て残された自筆ノートの言葉からだけではなく、レオナルドを取り巻く様々な人々の解釈からこの人物像を浮き彫りにしようとしている。『美しき姫君』の作者を巡るあらゆる解析を踏まえて、アイザックソンはレオナルドという人物の位置付けを芸術と科学の交差点に固定させていくのである。
かつて私がフィレンツェのアカデミアで絵画を学んでいたころ、課題として幾つかのルネサンス時代の作品の模写を手がけたことがあったが、ボッティチェリの人物像が細い輪郭で縁取られているのに対し、レオナルドの絵には輪郭線をぼやけさせるスフマート技法が用いられていることを知ったのもその時だった。レオナルドのこの新しい試みによってそれまでの輪郭線式絵画は旧式という見方をされるようになるが、アイザックソンはこのテクニックこそレオナルドの芸術と科学、現実と空想、経験と神秘という境界線が分割できない、彼ならではの画法だと捉えている。『美しき姫君』の作者がレオナルドであることの真偽についての論争を要に、読者はレオナルドならではの自然科学的な審美眼をアイザックソンの指摘によって確認するのである。そして、アイザックソンはそうした作品に潜んでいるビジネス的有用性からも、更にレオナルドという人物を象っていく。
「自然の物体には輪郭がない」「物体の境界線の厚みは、目には見えない。だから画家たちよ、物体を線で囲うな」とレオナルドは自らのノートにも記すほど、絵画における線と背景に拘っていた。だとすると、くっきりと輪郭線の引かれた『美しき姫君』の画面から見つかった指紋がレオナルド自身のものと立証されたところで、売りものに対する策略的な工作の疑念を払拭することはできない。実際この世にはレオナルドが描いたのではないかとされる作品は何点もあるし、数年前、やはりレオナルド作とされる『サルバドール・ムンディ』というキリストの顔が描かれた作品が、どこかの金持ちによって510億円で落札されたことが話題になった。レオナルド自身にしてみれば、なぜ500年後の世界でも自分の絵が高額で取引されたり、自分についての書籍が出版されたりするのか理解に苦しむかもしれないが、成功という希望的観測を糧に生きていきたい人々にとって、彼のような存在は必要不可欠なのである。中には、天才と呼ばれたレオナルドと同じ人間であるという自覚だけで、明日を生きる勇気を持つ人だっているだろう。宗教の教祖とは言わないが、人に縋られる立場という意味ではこうした天才たちの立場も同質だと思う。
アイザックソンはこの本の巻末で、レオナルドは凡人には想像できないような傑出した才能に恵まれていたわけではなく、彼に学び、少しでも彼に近づく努力ができるとして、彼の人となりから得られるヒントをハウツー本さながら項目ごとに分けて並べているが、このページに行き着いた時は少しばかり驚いた。
「飽くなき好奇心を持つ」「子供のように不思議に思う気持ちを保つ」「脱線をする」「熱に浮かされる」「先延ばしにする」「紙にメモを取る」「謎のまま受け入れる」など、レオナルドが無意識に身につけてしまったこうした要素を、意図的に自分のものにすることができるのかどうか、私にはわからない。大人になってからいきなり脱線したり先延ばしすることを心がけよう、と言われて実践できる人が果たしてどれだけいるのだろうか。努力次第ということだろうか。それでもレオナルドのような天才になりたいと思う人がいるのであれば、レオナルドと同じ表現者という立場として、私はここにもうひとこと付け加えたい。
メモに「私には一人の友もいない」と書き記したレオナルドの感性と知的欲求を突き動かしていたのは、何よりもこの孤独感である。溢れる想像力と創造性を駆使して縦横無尽に生きる人間は、時には自分自身の味方にさえなってくれない孤独と常に向き合っている。そんな孤独を心底から体感できた人であれば、この本の締めくくりにあるように、誰にとってもなんの役にも立たないことだとしても、無心にキツツキの舌を描写してみたくなるレオナルドの気持ちが少しは理解できるようになるのかもしれない。そんなことを考えさせられる読後感だった。