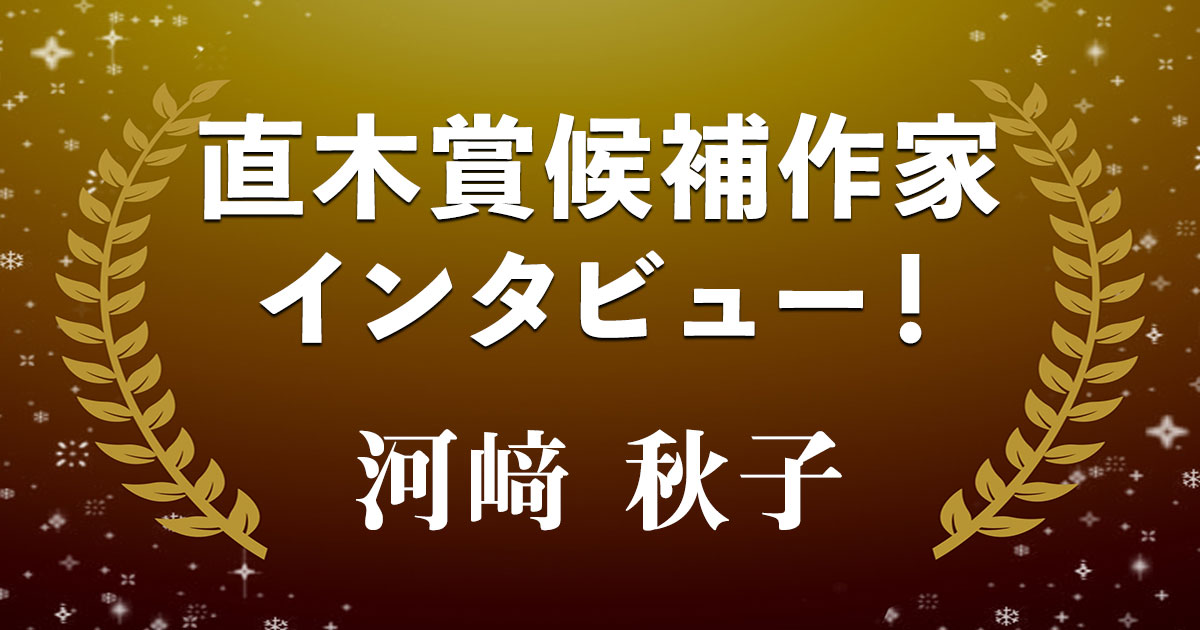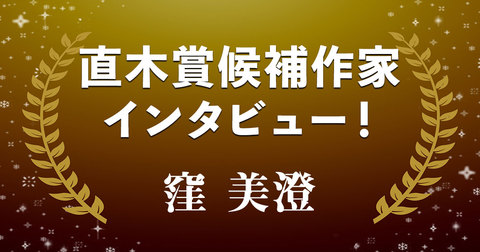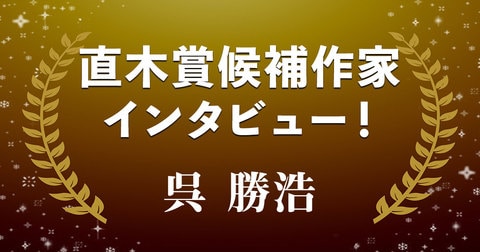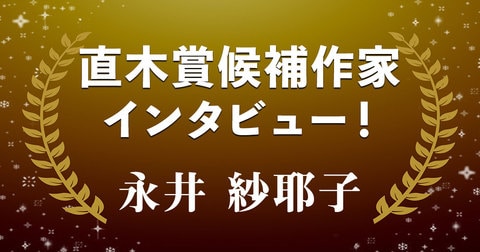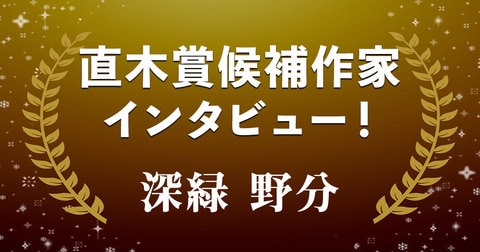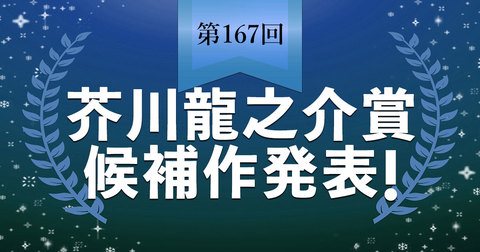雪の極端に少ない、冷えきった空気。海から吹きつける強い風――。
「せめて、湯たんぽとか……」
廊下の隅で寝る十歳の少女が、寒さに身体を震わせる『絞め殺しの樹』幕開けの舞台は、昭和十年、冬の根室。
なかば売られるように、新潟から根室に連れてこられたミサエは、畜産業を営む元屯田兵の一家、吉岡家に引き取られ、牛馬の世話に、家事に、奴隷さながらこき使われる運命を辿る。
「母の実家が根室で酪農をやっていたんです。私自身、根室の隣の別海町で生まれ育って、緬羊(めんよう)の飼育・出荷の仕事をしてきましたから、馴染みのある風土を描いたともいえますね」
元士族というプライドに固執し“他人に厳しく身内に甘い”吉岡家での生活、頼る人のない土地での日々は、ミサエにとって差別と意地悪に満ちた、耐えがたいものだった。
「泥の中からどんな蓮の花が咲くのか」――これは本書の構想時から、河﨑さんが考えていたことだという。
「書いていて非常に重い話ではありました。もちろん大まかな話の流れは最初に決めているのですが、連載中、毎回の原稿を書くたび、自分がミサエに苦しみを与えているというより、自分もまたミサエと一緒に苦しみを追体験している気持ちになるんです。彼女にとってあまりにつらい“ある場面”を書く時は、私も体調を崩しました」
札幌で働きながら学び、戦後、保健婦として自立したミサエには、束の間の安息と充実もあった。しかし夫婦関係と育児に悩み、折々に理不尽にさらされ、ついに家庭を失ってしまう彼女の人生は果たして幸せだったか? 美しい花を咲かせたと言えるのか? これら問いの答えは、第二部で物語のバトンを受け継ぐミサエの息子・雄介の生き方が示唆しているように思える。
雄介もまた、親の代から続く因縁と悪意に苦悩しつつ、それでも人生の選択肢を得るため勉強に励み、大学へ進む。次第に母のことを知り、理解し、ついに悪意に対して毅然と対峙する雄介が、その果てに下した“人生の決断”は、本書最大の読みどころだろう。
「彼の選択は、ある種の“意地”であり、悪意への“復讐”でもあるのかなとも思いますが、ミサエや雄介の人生に伴走して読んで下さった方に、この先、雄介はたぶんこんなふうに生きていくのだろう、と思いを馳せてもらえたなら、作者として万々歳かなと」
河﨑さんは最後にこう言い添えた。
「フィクションとして、根室をかなり過酷な土地のように描きましたが、実際の根室は食べものの美味しい、鄙(ひな)びたいいところなんですよ(笑)」

河﨑秋子(かわさきあきこ)
1979年生まれ。2014年『颶風の王』で三浦綾子文学賞、19年『肉弾』で大藪春彦賞、20年『土に贖う』で新田次郎文学賞を受賞。他著に『鳩護』。
第167回直木三十五賞選考会は2022年7月20日(水)に行われ、当日発表されます。