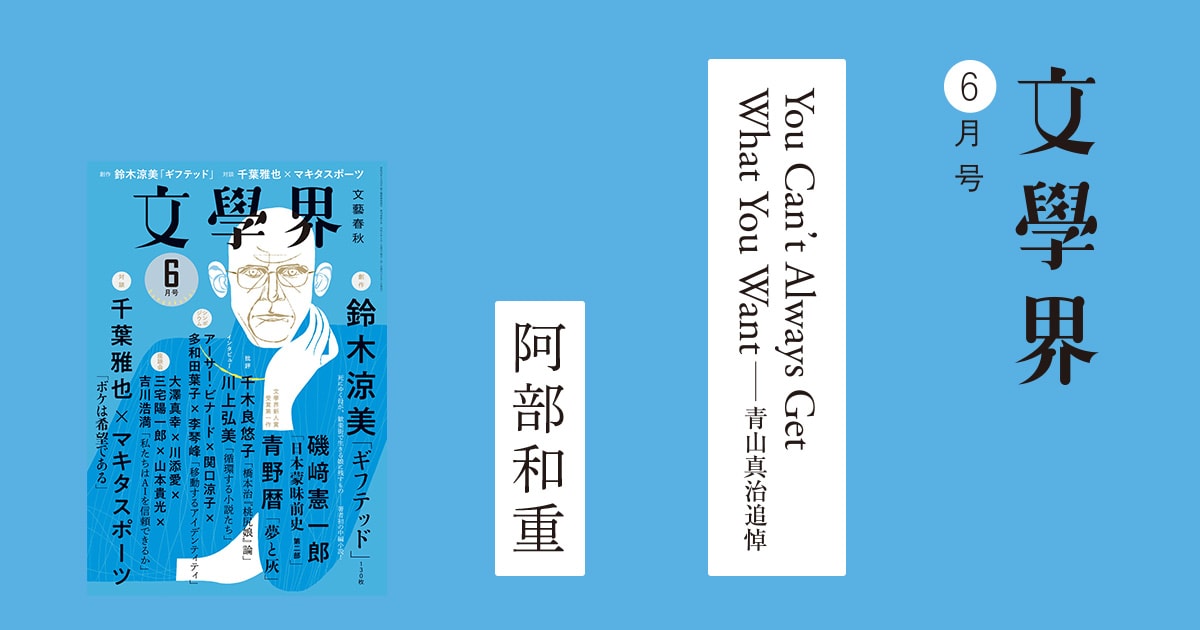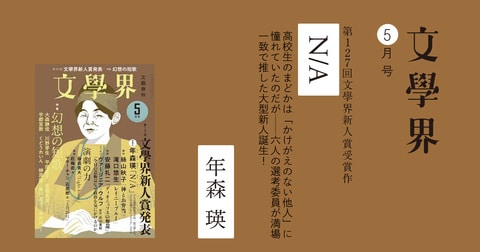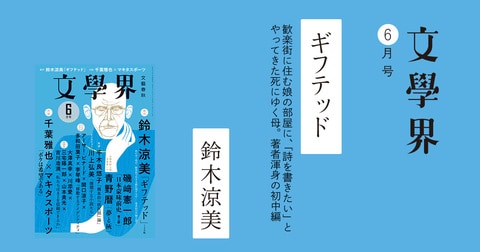青山さんと最初に会った場所は『Helpless』の試写会場だった気がする。同作の初公開日は一九九六年七月二七日とされているから、その数カ月前、四月か五月あたりか。だとすると、わたしの年齢は二七歳、監督は三一歳。鑑賞後は数人で会食という流れだった。
ひきあわせてくれたのは、アテネ·フランセ文化センターのキュレーターや安井豊の筆名で批評活動をされていた当時の安井豊作さんだった――アテネの映画上映によく通っていたわたしは、九四年のデビュー直後から『カイエ·デュ·シネマ·ジャポン』の編集委員に誘っていただくなど、安井さんにはたいへんお世話になった。数年後に映画監督となり脚本家としても活躍する同年の井土紀州さんとアテネで知りあったのもおなじ時期だった。
おふたりとの会話に頻繁に登場する最重要人物が青山さんだった。中上健次への深い傾倒もその頃に聞き、初作発表をひかえた新人映画作家に対する期待感が強く伝わってくる話に刺激も受けた。おかげでわたしの頭には、初対面もまだの相手の人物像がさらさらと素描されていったが、しかし実際に会ってみると、そんな想像は一瞬で消しとんだ。三一歳の青山真治はなにもかもはねかえす岩壁みたいな存在感を放ち、とにかくとっつきにくかった。この男となかよくなることはまずなさそうだとわたしは思うばかりだった。
のちに結局なかよくなれたのかどうかといえば、それはわからない。新宿ゴールデン街コミュニティーとは無縁の下戸たるわたしは、当然ながら愉快な飲み友関係など構築できない。腹を割ってふたりで語らう機会はおろか、長電話好きの青山さんと受話器ごしにおしゃべりしたことすら、案外かぞえる程度しかなかったのではないか。せっかく声をかけてもらったのに、わたしが不義理な対応をしてしまったことも二、三度あった。
あるいは、『青山真治と阿部和重と中原昌也のシネコン!』の鼎談収録や『エリ·エリ·レマ·サバクタニ』の撮影現場に密着させてもらえたりした二〇〇〇年代のなかばの時期、集中的に一緒にすごしすぎたのかもしれないとも思うが、いずれにせよ、その後わたしは年々だれとも会わなくなっていったため、青山さんと顔をあわせることも減ってしまった。
にもかかわらず、そういうわたしを青山さんが気にかけてくれているとはっきり感じられることがたびたびあった。たいていは酔っぱらっていたとはいえ、人間関係のもつれを心配し、仲をとりもつ電話をかけてくれたりしたこともあった。多忙のなかわたしの結婚パーティーにもきてくれて、相変わらずの泥酔ぶりではあったものの、帰り際に「よかったよかった」とくりかえし言ってもらえたときの情景はいつでも脳裏に呼びだせる。
対面機会がすっかりなくなった近年は、もっぱらTwitterを追うだけになってしまった。SNSなんてもんは基本クソだなと思いつつ利用しているわたしは、青山さんのアカウントは欠かさずチェックしていた。するとたまに、首をかしげたくなる投稿が目についたり、なんでこんなしょうもない陰謀論なんかリツイートしちゃうのよと諫めたくなることなどもあったが、かといってこちらからリプを送ったりもしなかった。電話でもかければよかったわけだが、それのみのために連絡するのも変な意味がつきそうだ。青山さんのほうでもわたしに対し思うところはあったかもしれない。が、その声ももう聞けないのだ。
青山さんとのあいだでいわゆる見解の相違というやつはいろいろな面に認められたが、じかに伝えあった事柄もあれば、そうでないのもある。ダルデンヌ兄弟監督作『息子のまなざし』の評価をめぐる不一致などは、現在も活字で確認できるはずだ。
二五年ほどのつきあいを今あらためて振りかえれば、緊張感だけはとぎれずつづいていたようにも思う。見解や嗜好性から行動原理にいたるまで、相違点は多々あったものの、創作上の志向面でおおきくかさなる部分があり、新人時代よりたがいを意識せざるをえなかった気がする――少なくとも、わたし自身はそうだった。それは「中上健次以後」をいかに実践するかというまことに重大な課題だ。
青山さんの北九州三部作とわたしの神町三部作は、その課題への回答として世に送りだされている。九二年、偉大な作家の早世にリアルタイムで直面し、それから数年後、プロとしての創作活動を開始した青山さんとわたしは、むろんふたりで申しあわせるようなことはいっさいなく、自分たち世代にとってそうするのがあたりまえというふうに、「ポスト中上」の可能性を模索していった。小説はともかく、映画での具現化を果たした青山真治には称賛しかない。しかしまさか、当の映画作家が中上健次の没後三〇年という年にあまりにも早い最期をむかえるとは考えてもみなかったし、そんな宿命などいらなかった。
最後に、実現しなかったひとつの企画について打ちあかしておきたい。九九年に、青山さんはわたしの小説の映画化を検討してくれたことがあった。「無情の世界」という短篇だ。プロデューサーとの顔あわせの会食に呼んでもらったり、監督自身がまとめたプロットの内容について電話で長々と意見交換したり、一時的には着実な進展があったものの、残念ながら制作会社の都合で頓挫してしまった。実際に撮られていたらどんな作品になっていたかと想像してしまう。『EUREKA ユリイカ』が発表されたのは、その翌年だった。
(初出:「文學界」2022年6月号)