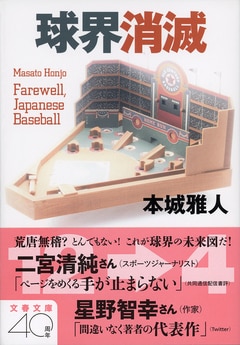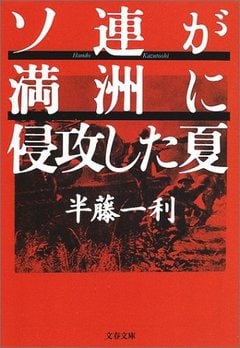2009年、松本清張賞の候補となった『ノーバディノウズ』でデビュー。以来、年3冊ペースで作品を上梓してきた著者の最新刊は、競馬の騎手を主人公にした渾身の書き下ろしミステリーだ。
「今回の作品では、究極のところにいながら、さらに負荷がかかった人間を主人公にしようと思いました。仕事をしていれば誰しも追い詰められるような時はあります。でももっと、命ギリギリの闘いをしている主人公を考えて浮かんだのがスポーツ選手――まずカーレーサー、次がボクサー、そして競馬のジョッキーでした。
いずれも死と隣り合わせの競技で、トレーニングや減量に追われ、精神状態は極限に追い詰められている。そこでさらにもうひとつトラブルに直面したら、彼はどんな行動を起こすのか――それを人間ドラマ的なミステリーで描きたいと思ったんです」
主人公の飯倉元春は45歳のベテランジョッキー。若くして頂点に立ちながら、馬主と決裂し低迷する。30代で復活するも、レース中の死亡事故をきっかけに再びどん底に落ち、いまようやく久々のGⅠレース勝利を飾る。
「僕はスポーツ紙の記者として長い間、現場で取材をしていましたが、長く続けている選手が一流、というのがまず一番に来ます。たとえば、若くて大活躍している選手のことをファンやメディアが持ち上げると、それを横で見ている一流選手の目は冷めている。野球のピッチャーなら1回手術をしてから、競馬のジョッキーなら1回大怪我してから、そこからどうなるかだな、と言うんです。
別に彼らは若い芽をつぶそうとしているのではなく、彼らにはそれがリアルな選手人生なんです。生き残っている選手はみな、一度はそういう苦しさを経験したうえで、いまも現役でいる。
ということは、プロ選手の魅力は落ちぶれてから這い上がってくるところにあるのではないか。才能だけではなく、努力や工夫をし、生活習慣を変え、いままで好きにやっていたことをすべて封印して、戦いの場に戻ってくる――カムバックする姿に我々は心を打たれているんですね。
元春は2回挫折を味わって這い上がり、そこでまた苦難が待ち受けている。それを彼がどう乗り越えるのか、彼の生き様を描いてみたいと思いました」
復活を遂げた元春だが10年以上、減量に苦しんでいる。まともな食事を摂るのはレース終了後の日曜夜から火曜日まで。それも炭水化物は避け、塩分も極力減らす。水曜日以降は炭酸水で空腹を紛らわしながらサウナに入り、100グラムでも落とそうとする壮絶なものだ。その姿は圧倒的なリアリティーで迫ってくる。
「具体的に誰かをモデルにしたということはありません。ただ武豊騎手からお父さん(故邦彦氏。元騎手、調教師)が減量に苦労していて、白いご飯を食べるのを見たことがなかった、という話を聞いていたし、ほかの現役騎手からもどうやって減量するか聞きました。一番衝撃を受けたのは、水曜日以降は食事をやめ、水分だけでコントロールしている騎手でした。昔はフラフラになってレースを終えて、点滴を打ったり、風呂に飛び込んで桶で水を飲んだ、なんていう人もいたそうです」
物語の終盤、追い込まれた元春は究極の選択を迫られる。そして迎えた結末は、衝撃的だ。
「最後はこのエンディングを読者に嫌われてもいい、と覚悟を決めました。読者に嫌われる怖さとの闘いだったけど、これしかなかった。物語をきれいな方向に寄せていくと、それまで積み上げてきたリアリズムが全部崩れてしまうと思ったんです」
記者経験を活かしてスポーツに材を取った作品でデビューしたが、その後、新聞記者が活躍する社会派エンターテインメントが話題となり、また最近では医療小説にチャレンジするなど、テーマの幅が広がっている。
「デビュー4作目くらいまではスポーツミステリーを書いていましたが、その後いろいろな編集者と仕事をしているうちに、もっと間口の広いテーマを勧められたり、新聞記者小説で賞を受賞したこともあって、スポーツミステリーからは遠のいていました。同じジャンルばかり書いていては縮小再生産になってしまうし、まったく知らない世界を書くことで、フレッシュさは保っていたと思う。
ただ同時に、どうして日本ではスポーツ小説はメジャーにならないのだろうと、ずっと思っていました。別にスポーツ好きな人が本を読まない、なんていうことはないのに。
でも振り返ってみて、ひょっとしたら振り切っていなかったのかな、と反省したんです。単にスポーツを題材にしても、それなら実際に試合を見たほうが面白いと思われるだろうから、ミステリーを絡めて書いていたんですが、それだけでは弱かった。だから今回は、競馬に関する部分はとことんリアリズムを突き詰めようと思いました。そこを振り切って書けば、絶対に読みたいと思う読者はいるはずだと、強い気持ちをもって臨みました。途中からは本人になり切った感覚で書いていましたね」
原点に戻るようにしてスポーツミステリーを書き終え、今後目指していく方向とは。
「スポーツ紙の記者というのは、本来エンタメ性が高いんですよ。戦争報道とスポーツ報道は違って、極論すればスポーツ報道は世の中になくてもいいものです。でも僕はずっと、そういうところで読者を楽しませようと思っていました。作家になったのも、読者に楽しんでもらいたいと思ってのことです。
だからこれからも、エンタメ性は絶対に損ないたくない。自分の書いたものに自己満足するのではなく、エンタメ作家は読者が喜んでくれて完結するものと思っています。
自分はこれからも、毎晩、寝る前に本を読んでる人が、ああ面白かった、と言って閉じられる本を書いていきたいですね」