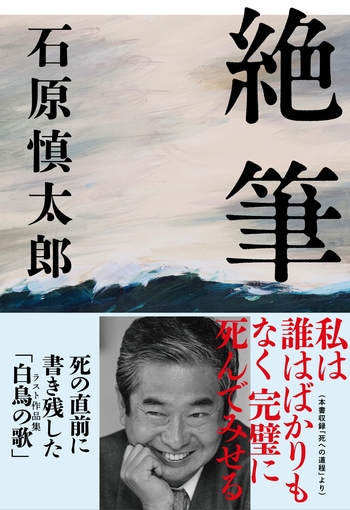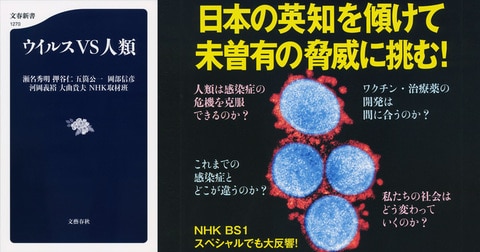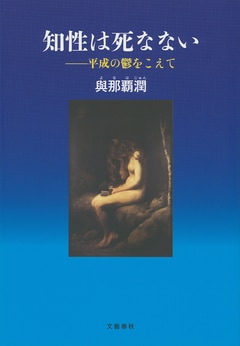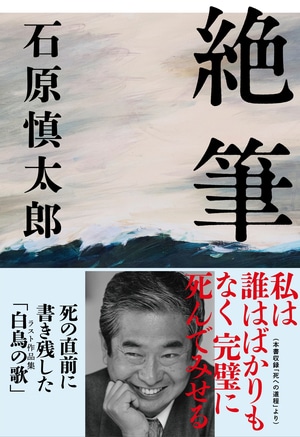
今しばし死までの時間あるごとくこの世にあはれ花の咲く駅
亡くなる五日前に父を訪ねた際、この歌人・小中英之の歌で始まる上田閑照(しずてる)の随筆『折々の思想』のプロローグを朗読してあげた際に「こういう良いエッセイとは何処で出会うの?」と聞かれたのが父との最後の会話になりました。本来は上田さんのような京都学派は父の柄ではなかったと思いますが、このテキストを題材に、父が元気でいた頃と変わらずに生と死の境界について、いろいろと話してみたいと思い一月ほど前から枕元に置いておいたものでした。父は病床で最期に何を見て何を感じていたのでしょうか。
亡くなってから葬儀までの間に、ものを取りに父の書斎に入ると、テーブルの上に乱雑に積まれている本の中に、哲学者の柄谷行人の『柄谷行人発言集 対話篇』が目にとまり、意外な取り合せに興味を持ちました。柄谷さんといえば護憲派で「左翼」を自認している方ですから、改憲を主張した父とは相容れないイメージがあります。付箋がついている頁をめくると父との対談(一九八九年)が載っていて驚きました。中で柄谷氏が「(石原の当時の新作)『生還』には『末期の目』がない。日本の美学の伝統から言えば必ず『末期の目』に映ったものは美しいとなる。しかし『生還』では絶対に生き返ろうとしてるでしょう」と評価しているのを読み、思わず膝を打ちました。たしかに病気再発が判明する半年ほど前に書かれたエッセイの中で、父は「晩節において当然対峙を強いられる『死』という『最後の未知』に臆することなく、自ら踏み込んで迎え撃つという姿勢こそが己を失うことなく『最後の未来』を迎えるに違いない」と結んでおります。それが石原慎太郎の生き方でした。同時に「俺はもうじきに死ぬ!」まだ元気に飛び回っていた頃から、己の健康に神経質で度々そんなふうに騒いでいた父に対して、「それなら十年がかりで看取ってやるよ」と私は軽口で返しておりました。当たり前のように大きな存在であり続けた父が老いていき、やがては迎える父の死に対して、息子として、またひとりのアーティストとして、その一部分を共有したいと望んでいたのかもしれません。元気な頃は晩酌をしながら、闘病生活に入った後は病床で、よくそのような話をしたものです。
政治家として、また「太陽の季節」で芥川賞を受賞した「太陽族」作家として広く認知されていた父ですが、では実際にどのような小説を書いていたのかは意外に知られていないのではないでしょうか。そして父は若い頃より「死」という主題に惹かれ続けていました。もとは「戦場へ行き遅れてしまった子供たち」からの視点だったのでしょうか、俯瞰した眼差しから本当に様々なかたちの死について書いていますが、晩年、特に大病を患った後は、小説のテーマとしての興味から更に踏み込んで、死を自分自身のものとして、より身近に感じるようになっていったような気がします。

父がよく引用していたのが若い頃に親交のあった太平洋戦争下で大蔵大臣を務めた賀屋興宣(かや・おきのり)氏が晩年に己の死について語り残した言葉です。「死ぬとね、その後は私一人で暗く遠い道をとぼとぼ歩いて行くんですよ。そうすると自分を悼んでくれた親戚や友人なんかもみんな私のことを忘れてしまって、私自身もそのうちに私自身のことを忘れてしまうんですよ。死ぬことはいかにもつまらない、だから私は死にたくないですな」父は何度もこの賀屋氏の話をしておりました。「死ねば自分が死んだという意識も含めて全く何もありませんよ、だから死ぬのはつまらない」「虚無は虚無として厳然と実在する」いつのまにか父は自分が作ったアフォリズムの傑作だと半ば得意げに繰り返し言っておりました。
晩年の父は死後の世界や輪廻転生はないと繰り返し否定していました。但し、超越者や超越的なるものの存在は否定しておりません。本人は、かつて「巷の神々」という著作の取材を通して人智を超えた能力を持つ何人もの人間に会ったからと述べておりますが、果たしてどうだったのでしょう。「Somebody up there likes me」とよく口にしていましたが、これはポール・ニューマン主演の映画『傷だらけの栄光』の原題からの引用になります。実在したボクサーの伝記映画で、刑務所あがりの不良少年がチャンピオンになりあがるまでの生涯が描かれたサクセスストーリーのようです。父は実際に「自分は選ばれた人間だという自負はあったよ」と申しておりました。
死後の世界は信じないと言っていた父ですが、数年前に実家で酒を酌み交わしながら、私が参加していた東日本大震災の被災地におけるプロジェクトを通して見聞きしたことについて話をしていた際に、現地の心霊現象の話に並々ならぬ興味を示しました。実際に東北学院大学の学生が被災地に於ける心霊現象体験の話をリサーチしたものをとりまとめた『呼び覚まされる 霊性の震災学』という本が出版された際には、その情報を提供した私より早く取り寄せて読み終えてしまったくらいです。この本に触発されて書かれた作品が本書に収められている「北へ」です。会話の中で父は「もし俺が死んだ後、おまえが困っていたら、必ず俺は幽霊になって現れてやるからな」と言ってくれました。父らしくない珍しいことを言い出すなと思いながら、息子としてはそれなりに感動していたのですが、後にいたるところで「死んだら虚無だけだ。死後の世界は存在しない」と述べているものですから、「オイ親父、あの時のセリフは何だったんだよ」と少なからずガッカリした覚えがあります。それにしても超越した存在を肯定し、不可知なるものに興味を隠さない父でしたが、強烈な自我、自意識故に結局はそれらに身を委ねる事はありませんでした。

親交の厚かった精神科医の斎藤環氏によると「五~八歳くらいの子供の天真爛漫さのまま大人となった」と分析されている父ですが、更に戦後の高度経済成長期「日本の青春時代」と自分の青春時代が重なり、正に「時代と寝た男」と評されるようになった故か、老齢になってまで、青年らしさを失うことが無かったように思います。晩年に常に枕元に置いて愛読していたジャンケレヴィッチ著の『死』には「老衰は死に向かっての育成だ」と書かれているようですが、父はそれを肯定しつつも自分の肉体の衰えに対してイライラしていました。私としては年相応にもう少し良い具合に枯れて行くことを密かに期待しておりましたが、もちろん息子の思いなんぞに応えてくれる父ではありません。ある時、イギリス人の映像作家デレク・ジャーマンの写真集『ガーデン』のような仕事を父と一緒にできないかと思い、父に持ちかけた事もあります。ジャーマンはHIVに感染してから、ロンドンの家を引き払い、イギリス最果ての村に移住した。そこで庭いじりをしながら余生を暮らし八年後にこの世を去りました。そのときの暮らしをまとめた『ガーデン』は一部で大変な評判になりました。社会風俗から離れて、情念のない穏やかな暮らしをしながら、もしジャーマンのように彼岸から穏やかに世界を見つめ直すような眼差しを持ち得たならば、作家・石原慎太郎はどのような創造活動をするのだろうと興味があり、プロデュース出来ないかと探ってみたのです。やはり私は父が末期の目を持つことを期待していたのかもしれません。いずれにせよ、それは私の思い込みであり、老いと真っ向から闘っている父にはとりつくしまもございませんでした。
亡くなる前の二年もの間は母の手術、入院などもあり父は随分と寂しい思いをしていたと思います。そして膵臓癌の早期発見、治療、肋骨・尾骶骨の骨折、脳梗塞の手術、膵臓癌の再発、闘病生活を経て父が亡くなり、一月後には母が亡くなるというあっという間の日々でした。リハビリ施設にいたことも多く、コロナ禍の中、今までの様に父と酒を酌み交わしながら話をする機会も減ってしまったことが悔やまれます。そしてこの父の本当に最後の短篇集の解説を書く事になり、最晩年の短篇数点をまとめて読む機会を得て、今までの父の作品とはどこか異なるイメージを抱きました。絶筆となったエッセイ「死への道程」以外は「死」が直接のテーマになっていないということは確かにあります。しかし過去に似たようなテーマの短篇もある中で、やはり明らかに何か違う。より身近に死と向かい合いながら生活しているうちに、父の中で何かしら小さくない変化があったのでしょうか。

冒頭に記した父と最後に読んだテキストの中で上田閑照は、この歌について「大切なのは、私たちの世界が『この世』と感じられ、その感じに、同時に、『この世』ならざる、死に逝くことによってのみ往くことのできる『いずく』が感じられていることである」と述べています。そして更に与謝野晶子の歌「いずくにか帰る日近きここちしてこの世のものの懐かしきころ」を引用して「晶子の存在は既に『この世』と『いずく』と両方にわたっており、そのとき、現生において交わり係る『この世のもの』が死まで透き通って、それまでとは違った深みからの親しさにおいて経験されている」と述べています。
現実の病床で死と向き合う事は意識家の父にとって自我を失うという最大の恐怖を伴うしんどい闘いであったろうと思います。葛藤していたし、度々弱音を吐く事もありました。しかし、本書に収められている小説を読んでいると、石原慎太郎という作家の中の無意識が感じとった死までの時間は、たしかに透き通っていたのではないかと思わせるものがあります。未熟な私は意識的に父に末期の目を求めてしまいましたが、今になって病床で父が語った「ノスタルジーしか感じない。只只懐かしい」という言葉が少し理解できた様な気がいたします。父は最後にそれぞれの境遇を超えて共有されるような、生や存在そのものに対する懐かしさのような領域を描いていたのではないでしょうか。父は往き、もはやこういった話をする機会は失われました。幽霊になって出て来てくれる趣味もなさそうです。しかし、著作を引っ張り出して読んでみればいつでも父を感じることができるのは本当にありがたい。今は父の作品と共に「この世」と「いずく」の境界を私なりに見つめていければと思っています。