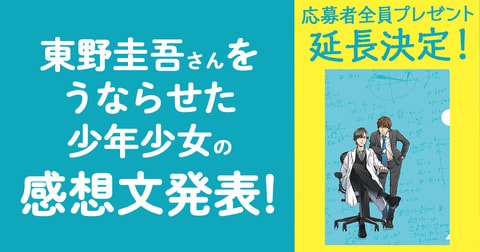著者のライフワークである〈矢吹駆〉シリーズの第7作『煉獄の時』が刊行された。シリーズ開始当初から熱狂的な読者に支持されるが、新作刊行は実に11年ぶり。大改稿に至る事情と、新作に対する著者の想いとは――。

「これまでも雑誌連載が終わっている小説を手直しするのに時間がかかったことは何度かあるけれど、今回ほど大変だったことはないです。本当に完成できるのかどうか分からなかったし、やめてしまおうかと思ったこともありました。某作家には、シリーズ6作目の次は8作目にして、これは欠番にすればいいのではないか、と唆されたこともあった(笑)。でもそういうわけには行かないので、何とか完成させられて、ホッとしました」
シリーズ前作『吸血鬼と精神分析』が刊行されたのは2011年。また本作の雑誌連載が完結したのは2010年だった。改稿に費やした年月は10年を超え、しかも雑誌連載時とは犯人が変わるという事態になった。
「10年前に体調を崩して60代の前半はほとんど小説の執筆はできなかったので、実質の作業時間は5年くらいです。コツコツ直してはいたけどこのままではいつまでたっても完成しないので、一昨年、思い切って他の仕事をすべて休んで集中して、一応去年の春には物語全体の結構が出来上がりました。
雑誌連載時と犯人が変わったのは、取材の深まりと関係があります。シリーズ第4作の『哲学者の密室』でホロコーストを取り上げたんですが、今回はその問題をもう一度語り直すことになりました。ナチス占領下のパリでユダヤ人の迫害があり、それが深いところで事件の動機になった、と作り替えた。すると、連載では脇役だった人物が中心的な扱いになり、作中での立ち位置も変わって、大幅に加筆することになったんです。
そしてここからがいちばん大変だったんですが、普通の小説だと単に書き直せばいいのだけれど、本格ミステリだと伏線などを全部張り直して、破綻や矛盾がないか読み直さなければならない。本格ミステリとしての結構を崩さずに小説を書き直すというのは、本当に大仕事でした」
本作は「現在I」「過去」「現在II」の3部構成になっている。現在の舞台は1978年6月。パリ大学の女子学生ナディアは、著名な作家のシスモンディに友人の矢吹駆を紹介する。シスモンディのパートナーであり、戦後フランス思想家の頂点に立つクレールが、彼女にあてた手紙が消失した謎を駆に解き明かしてほしいというのだ。その後、彼らはセーヌ川に係留中の船で全裸の女性の首なし屍体を発見するに至り、事件の調査のために大学の指導教授のもとを訪ねる。すると教授は若き日の友人、イヴォン・デュ・ラブナンのことを語り始めた――。
ここから始まる過去編は、第2次大戦前夜のパリを舞台にした歴史小説風でもあり、革命と恋愛に身を投じる青年たちの群像劇でもあり、本格ミステリとは違う読み味がある。
「『哲学者の密室』でも第2次大戦中を描きましたが、あの作品は時間の幅として短期間で、回想場面はあるとしても空間的には強制収容所内だけでした。でも第2次大戦前の1930年代は非常に特殊な時代です。ナチスが台頭し、スペイン内戦が起こり、右翼と左翼が街頭で衝突しているというのはパリでもベルリンでもあった。今回はもっと長期間で登場人物も多く、そうした時代の奥を描きたかったんです。
そして何よりいま、いろいろな点で時代は30年代を反復している気がします。最も顕著なのが今回のウクライナ戦争です。1938年のミュンヘン会談では、ナチスの要求に対して英仏が宥和的な姿勢を示したことで、結果的に第2次大戦を招いた。その過程を過去編で書きましたが、いま、ウクライナ侵攻ではミュンヘン協定を引き合いに出した、ロシアの要求を呑んでしまったら戦争が広がっていくという議論があって、シンクロしていると感じます。過去の話を書いているのに、いまに対応するところがたくさんある。
改稿を続けていたこの10年間を通して30年代の反復をたびたび感じ、30年代はどういう時代であったかを描いたことで、謎の背景の提示にとどまらない小説になったかもしれません」
〈矢吹駆シリーズ〉の第1作にして著者デビュー作である『バイバイ、エンジェル』が刊行されたのが79年。当初からシリーズは全10作を予定しており、シリーズ全体を通して一種の教養小説としての側面もある。
「『バイバイ、エンジェル』を書き始めた時、20世紀青年の運命を描くというモチーフがありました。念頭にあったのは連合赤軍事件ですが、ただ普通の小説で連合赤軍事件を書こうと思ったら、あの事件そのものがファンタスティックなのでリアリズム小説ではうまくいかず、ミステリにした。また小説を書くためには自分の溢れる思いを突き放して対象化する必要があり、語り手を女性にしたり外国人にした。そうして初めて、人に読んでもらえる出来になったかと思います。
その時から、20世紀――戦争と革命の時代を生きた青年の話を書こうと思っていました。19世紀はフランスでいえばナポレオン戦争が終わった平穏無事な時代で、スタンダールやバルザックがいた。ロシアではドストエフスキーというように、19世紀の作家たちはその時代の青年のことを書いている。それが念頭にあって、では自分は20世紀青年を描こうとしたんです」
刊行を待ちわびていたシリーズ当初からの読者もいるが、80年代以降の生まれの若い読者からの反響も大きい。
「20世紀青年にとって20世紀は問題だけど、21世紀の若い人たちにとってどう読まれるのか、正直なところよく分かりませんでした。だから若い読者が面白いと言ってくれるのは素直に嬉しいです。
いまの若者には、イヴォンみたいな20世紀青年はずいぶん遠い存在に感じられると思います。たとえば我々が若い時は、とにかくカッコいい車に乗ってスピードを出す、という速度への欲望が共有されていた。20世紀の思想は、根本ではそういう20世紀青年の気分を土台にして哲学的に精錬していったというところがある。しかしそのベースのところ――速度や極限への欲望とか――が変質しているとしたら、20世紀青年の運命を小説として描いてどこまで面白いと思ってもらえるか、分からない。
ただし、自分は19世紀文学であるスタンダールもドストエフスキーも面白いと思って読んだわけだから、初めから諦めることもないだろう、書くだけでも書こうと」
長編10作からなる連作だが、もちろんシリーズ未読、『煉獄の時』が初めてという読者でもぜひ手にとってほしい。
「一話完結の探偵小説として書かれているので、単体の探偵小説として読んでいただく分にはなんの問題もないです。事件の謎と解決として十分読めるはず。
主題部分も、前作のことを知っておいた方がより面白いとは思うけれど、たとえば今回はウクライナ戦争の問題が1930年代の反復であるという読み方ができるし、そういう読み方、楽しみ方ができるのではないかと思っています」