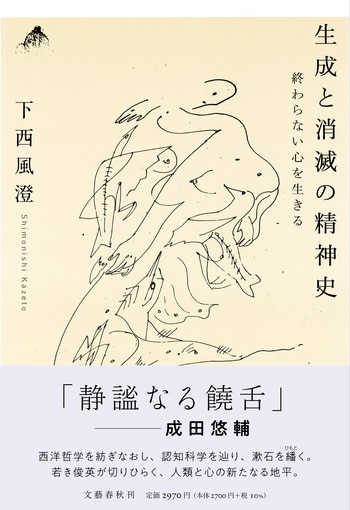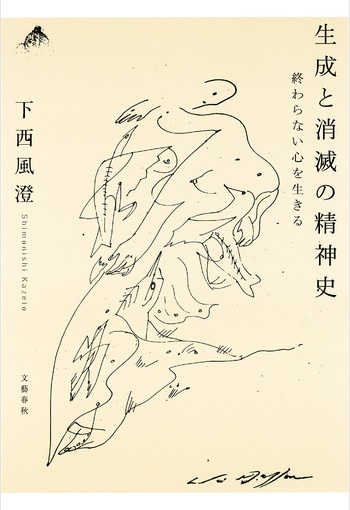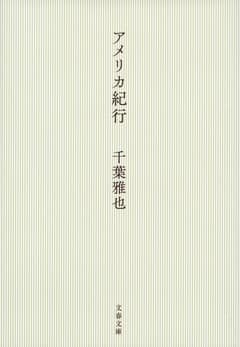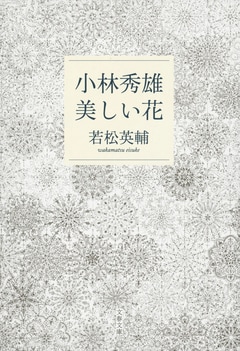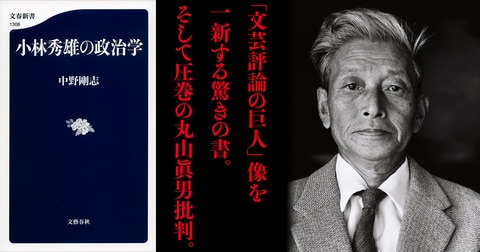人類は「心」をどのように捉えてきたのか? 下西風澄さんは著書『生成と消滅の精神史――終わらない心を生きる』において、西洋哲学、認知科学に、夏目漱石まで横断しながら、人類と心の3000年の歴史を描き出します。本書の刊行を記念して、序章の冒頭を公開します。
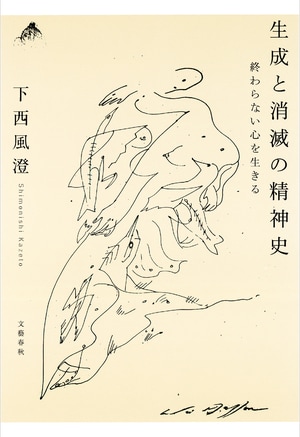
心の自明性――フーコーの考古学
本書は、心はどこまで自明か? という視点で書かれている。心の自明性を問うということは、心などそもそも存在しないのではないかという地点にまで遡って考えることでもあり、心が存在するとしたらいかなる根拠のために存在するのかを考えることでもある。また、心が自明ではなくなんらかの理由で存在しているとしても、そこに理由や要因があるならば、私たちはその要因によっては、まったく別の心を持った可能性もあったのではないか、あるいはまったく別の心を持つことも可能なのではないかということも考えることになる。実際、近年の人類が「人工知能」と言って人間とはまったく別の素材と設計によって意識を構築しようとしていることを考えれば、少なくとも人類は意識が必ずしも自然発生的で一回きりのものではなく、なんらかの意志とアイディアによって構築可能な存在であると考えているはずである。そこで本書は「心とは一つの発明だったのだ(one of the inventions)」という立場を取ってみようと思う。
かつて、フランスの哲学者ミシェル・フーコー(Michel Foucault, 1926-1984.)は『言葉と物』のなかで、「人間」はたかだが二〇〇年たらず前に生まれたのだと言って思想界を騒がせた。フーコーにとって人間とは、単なる生物学的な存在ではない。あらゆる生物種のうちの一つとして人間=ホモ・サピエンスが存在するのではない。「人間」は、ある特定の時代の特定の知識形態と制度が生み出した特定の存在の在り方なのだ。逆に言えば、私たちの持つ知識の形態や生きる環境、制度に支えられた存在としての人間は、その知識や制度が終わるとともに消えてしまう。実際フーコーは、一八世紀末に誕生した「人間」は、その背景にあった制度の撤退とともに消滅すると考え、「人間の終焉」を予告した。
フーコーの危惧した人間の終焉は、現代において、おそらくは彼の予想を大幅に超えて、まったく別のラディカルなかたちで訪れようとしている。ロボティクス研究の発展は人間固有の身体を奪い、人工知能の知的能力は人間のそれを凌駕し、神経科学は脳内に侵襲し、分子生物学は遺伝子をハックする。人間という存在は、物質のレベルではもはやオリジナリティを喪失している。これら技術発展による人間観の変容は「ポスト・ヒューマン」という名で新たな哲学潮流をも生み出している。人間という存在がその固有のアイデンティティを失ってしまうのか、あるいはそれでも人間の固有性は続くのか、それは分からない。それでも本書がフーコーから学ぶことは、人間という存在は自明に存在するのではなく、あくまでも可塑的でテンポラルな(仮初めの)存在であるということだ。しかしまた同時に、フーコーは人間の可塑性を落胆しているのではない。むしろ「人間」が消え去ってしまうことに、希望すら見出している。
それにしても、人間は最近の発明にかかわるものであり、二世紀とたっていない一形象、われわれの知のたんなる折り目にすぎず、知がさらに新しい形態を見いだしさえすれば、早晩消えさるものだと考えることは、何とふかい慰めであり力づけであろうか。(*1 )
人間が、あるいは人間の心が、ひとつの偶然的で仮設的なモデルにすぎないとすれば、それはあるタイプの人間にとっては自分の心を支える本質の瓦解する恐怖かもしれないが、あるタイプの人間には自分の心が肯定されうる別の世界線を想像することのできる「ふかい慰め」になるだろう。
本書はフーコーに同意する。人間や心は、与えられた自明な存在ではないし、必然的で本質的な存在でもない。また、唯一で決定的でもないし、変容不可能でもないし理想へと収束もしない。あらゆる歴史があり得たように、あらゆる人間とあらゆる心があり得た。本書はそういう視点に立つ。フーコーが人間という存在をひとつの「発明」としてその起源を歴史のなかから「考古学的」に発掘したように、本書は心あるいは意識(*2 )という存在をひとつの「発明」であると考えた上で、その創造と更新の歴史を辿ってみようと考えている。
フーコーの人間の発明論における重要な点は、それが自然発生的に生じたのではないということだ。「十八世紀以前に、《人間》というものは実在しなかった(*3 )」と言うフーコー。一九世紀頃を境に、言語、経済、政治、宗教など様々な知と制度の変化が起こったことが人間の誕生の契機ではあるが、あくまでフーコーはこの新たに誕生した「人間」は「知」が「みずからの手でこしらえあげた〔fabriquée(*4 )〕」ものだと考えている。この点を見逃してはならない。複雑で膨大な歴史の過程のなかで生み出された人間の誕生には、明らかに人間の意志、ある生物が自らを人間として成立させんとする欲望が働いている。だからこそ本書は、単に歴史的な事実を確認するのではなく、その歴史的な言説の背後に働いている「心」という存在をみずからこしらえようとする欲望や否応なき衝動を取り出すことを目指している。
人間は発明された。いや、正確にはフーコーがフランス語で語ったまま「l’homme n’est qu’une invention recente(*5 )」と言うべきだろう。なぜなら「人間(*6 )」という日本語によって名指される存在も、またべつの発明だからである。フーコーにとっては人間(l’homme)を発明したのは、一八世紀末のヨーロッパという特定の時代の特定の地域の知的な枠組みと制度なのだ。事実、日本においてフランス語のl’hommeや英語のhumanという言葉の訳語が「人間」として定着したのはそう古くない。明治以前の日本人はふつう人間のことを「ひと」と言っていた。大正時代から昭和初期にさえも「人間」という語は一般的ではなく、「Man」も「人」と訳されることが多かった。「間(あいだ)」という字をここに付け加え、「人−間」という関係性を前提とした概念を構築し、普及させたのは、和辻哲郎や三木清といった哲学者らの仕事によってである。とりわけ和辻は『人間の学としての倫理学』のなかで、そもそも「人間(じんかん)」という言葉は「人」を意味していなかったのだと分析している。それまで「人間」という言葉は「よのなか」や「世間」を意味し、西欧語のhomo、manなどは「人」と訳されることが多かった。これは漢字の本国である中国でも同じである。李白の「別有天地非人間」、蘇軾の「人間行路難」など、漢詩における「人間」の使用も本来は生物としての人ではなく、「人間社会」のことを表す言葉であった。しかし和辻は、日本で使用されることとなった「人」という語はさらに不思議な言葉だと言う。「“ひと”の物を盗る」と言えば「他人」を意味し、「“ひと”を馬鹿にするな」と言えば「自分」を、「“ひと”は言う」といえば「世間」を意味する。和辻はこの多義的な意味を持つ「人」という概念を弁証して「人間は単に「人の間」であるのみならず、自、他、世人であるところの人の間なのである(*7 )」と言って「人間」という新たな存在を創造しようとしたのだ。
和辻の、関係性を重視した人間概念には、ドイツの哲学者ハイデガーのもとで学んだ経歴も影響を及ぼしている。しばしば指摘されるように、単独者として生きるハイデガー的な人間(現−存在)を批判的に乗り越えるために、和辻にはハイデガーの時間的に規定される人間存在を、風土という空間的な環境に依拠する人間存在として規定し直そうとする目論見があった。重要なことは、人間という存在は時代や環境を超えた普遍的な存在ではなく、私たちがいかに人間を捉えるのかという視線や思想によってこしらえあげられた存在であるという観点である。その観点から見れば、人間という文化的な存在だけではなく、「意識」という自然科学の対象にさえなる存在も、その概念形成や視線やイメージの形成の過程のなかで形作られていると考えることができる。
本書はこれから、その時代や環境、言語などの複雑な背景のなかから誕生した心という存在の形成過程を、あるいはその成立する条件を、それぞれの時代の哲学者の思想を通じて見ていこうと考えている。
註
(*1) Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Gallimard, 1966, p. 15.(ミシェル・フーコー『言葉と物――人文科学の考古学』渡辺一民・佐々木明訳、新潮社、一九七四年、二二頁。)
(*2) 本書では「心」「意識」「精神」「魂」などという語を使ってその思想的系譜を辿っていく。学問的にはこれらの語・概念そのものの区別や使用法、関係性そのものが重要となるが、本書では細かい差異の検討は基本的には行わずに、むしろ心や意識と呼ばれるものの総体やイメージを辿ることを優先する。各論において、特にその術語の概念が重要な意義を持つ場合に限ってその含意を検討していく。
(*3) Ibid., p. 319.(前掲書、三二八頁。)
(*4 )Ibid.(同前、同頁。)
(*5 )Ibid., p. 15.
(*6 )坂部恵によれば、中国語の「人間」は「永遠の輪廻のうちにあって、魂が滞留するひとつの段階」を示す仏教用語「manussaloka」を翻訳したものである。(坂部恵『鏡のなかの日本語──その思考の種々相』筑摩書房、一九八九年、五九頁。)
(*7 )和辻哲郎『人間の学としての倫理学』岩波文庫、二〇〇七年、二二頁。
この続きは本書でお読みください。