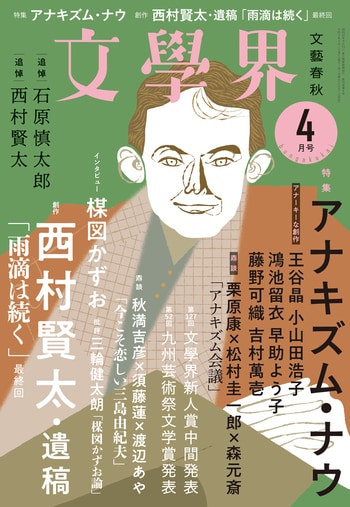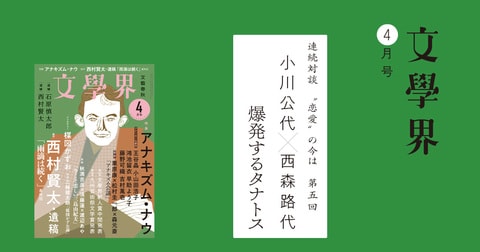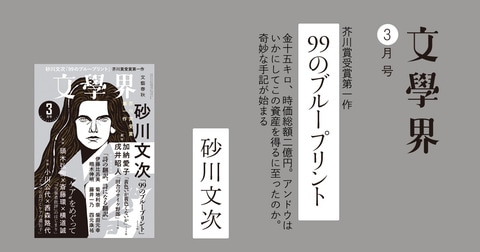アナキズムとはどのような考えなのか。なぜいま注目されているのか。今日のアナキズムを日本に広めた三人が語る、相互扶助の思想とその展望。
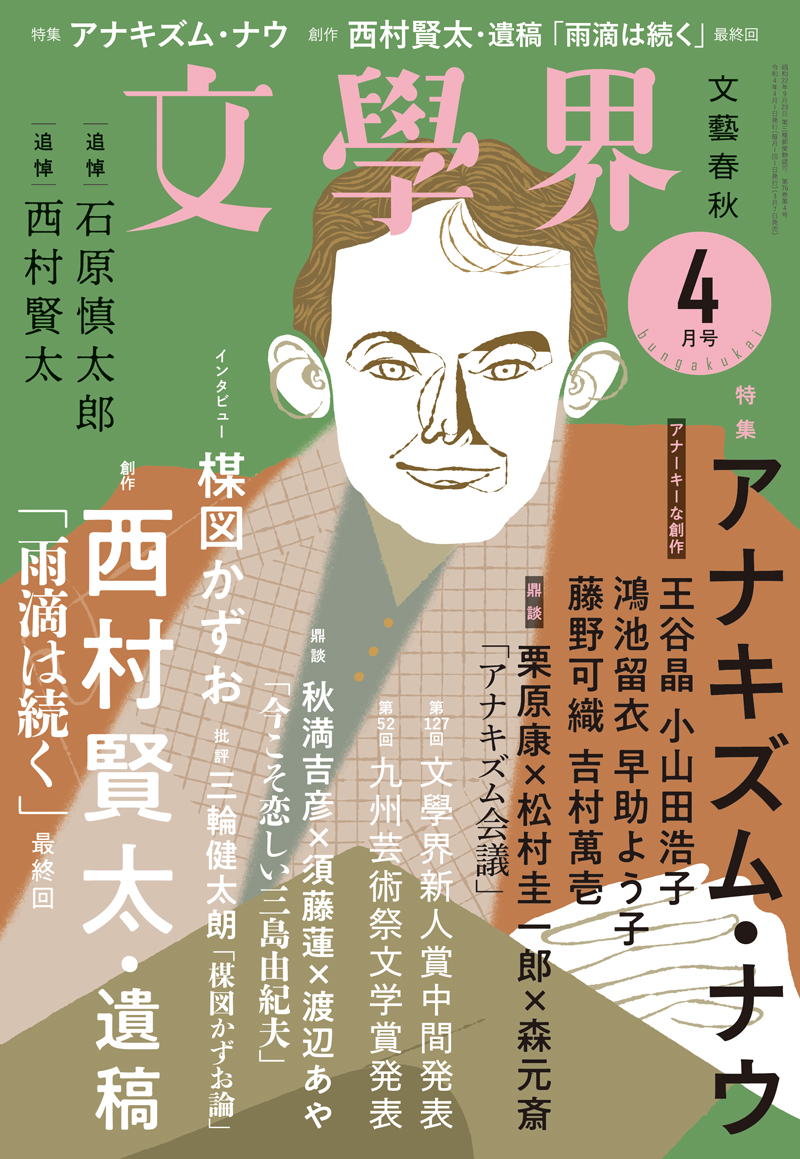
■大杉栄の衝撃
――本日は、お三方のアナキズムとの関わり方、そして近年注目の集まるこの思想の魅力について談義していただき、最終的に、それを今この国でどう実践し得るのか、というところにまで踏み込んでいければと思います。
栗原 僕は、大杉栄という大正時代のアナキストを研究しています。彼に関心を持ったのは高校生のころ。将来をみすえて進学、就職……などと言われてがんじがらめになっていたときに、彼の本を読んだらいろいろと腑に落ちたんです。将来をみすえた自分なんてものは一回全部脱ぎ捨ててしまっていいぞ、ゼロになって好き放題やっちまえ、みたいな思想に衝撃を受けて。僕は全然不良でも何でもなかったんですけど、学校からの「言うこと聞け」という圧に対して「クソくらえ」とずっと思っていた子供だったので、それがしぜんとアナキズムと重なったんでしょうね。
実際に運動に参加したのは、大学院生のころ、二〇〇三年からです。一九九〇年代後半から世界的に盛り上がりを見せていたグローバル・ジャスティス運動に関わりました。ちょうど新自由主義がガンガン来ていて、日本では小泉政権。雇用の非正規化が進んでいて、僕も研究者志望だったけど、自分も含めて非常勤講師で食っていくしかない、その仕事すらないかもしれないという状況でした。政府は非正規化が進めば「自由になります」と言ってたけど、新自由主義の「自由」は大企業トップの自由です。カネもうけのためなら露骨な搾取も首切りもなんでもあり。法的に国内で許されなければ海外でやる。ようするに金持ちのやりたい放題。トップダウンで上から決められたら問答無用、こっちは何も言えずに強制される。それが世界レベルで展開されていた。一パーセントの金持ちによる金持ちのための資本主義です。クソですね。そんな世界はもうたくさんというのが、グローバル・ジャスティス運動です。だからデモ一つ組むにしても意識的にトップダウンが拒否される。政党や指導者の命令に従うのではない。自分たちのことは自分たちでやる。運動の原理は「自己組織化」と「水平性」。アナキストを名のっていなくても、みんなアナキズム的な原理を前提にしていました。
そんなときに出会ったのが、アメリカの人類学者でアナキストのデヴィッド・グレーバーの文章です。当時、イギリスの政治・経済誌『New Left Review』に発表された「新しいアナキストたちThe New Anarchists」を読んだら、運動の新しい局面を「新しいアナキズム」と名づけていて「おおっ」って。僕ら三人とも、グレーバーには影響を受けていると思うので、またあとでじっくりお話ししましょう。
■深夜のドンキのアナキスト
森 僕の場合も、栗原さんと同じように、アナキズム的なものへの関心の萌芽は、高校生の頃だったように思います。でも、アナキズム関連の本を読んだ、とかではなくて、それを地でいくような体験を通じて出会っていった感じかなと。自分は東京の西の方の生まれで、貧しい母子家庭で育ったのですが、まわりにも似た境遇のヤツらがたくさんいました。で、みんなで夜な夜な府中の甲州街道沿いにあるドン・キホーテにワラワラと集まっては、「今日何する?」みたいな感じでやっていた。そこはたまり場であると同時に、割りのいいバイトを紹介してもらったり、いろいろな生活の知恵をみんなで共有する場でもあった。今から考えてみると、アナキズムにおいて重要なテーマの一つである「相互扶助」的な空間でもあったように思います。
その後に大学に入って、そういう場所や関係性に何か言葉を与えたいと思った時に、哲学がそうした役割を担ってくれるのでは、とぼんやりと思い、ジル・ドゥルーズを経由してアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドに行き着きます。卒論も修論も博論も全部ホワイトヘッドです。でも大学院に進むと、いろんなものを去勢されて、政治的な発言を一切慎み、学会論文を査読に通すためだけに生きていかなければならなくなる。それに途中で我慢ができなくなってしまい、一方で、密かにピョートル・クロポトキンやミハイル・バクーニンといったアナキストたちの本を読むようになった。そこからアナキズムと彼らが志向した相互扶助みたいな考え方を発見していくことになります。
それから間もなく、ホワイトヘッドの「のちの展開」にも気が付き始めました。例えば、同時代だとブライアン・マッスミという、ドゥルーズ/ガタリを英訳していった人だったり、フランスならダニエル・コルソンみたいな人が、ホワイトヘッドとアナキズムを一緒に語っていたりした。自分の中では、ホワイトヘッドはアナキズムのような社会思想と全然関係ないものだと思っていたのが、そういった哲学者たちが先陣を切って一緒に論じていることに驚き、刺激を受けました。と同時に、日本にも鶴見俊輔という、ホワイトヘッドとアナキストを一緒に論じた先人がいることを発見し、自分もこういうラインでやれるんじゃないか、と。鶴見は必ずしもアナキストを自称してはいないのですが、アナキズム的に思考していくことが非常に多い人で。上意下達的なものに対し、必ずそこからズレていこうとする。そうした振る舞い――何かが固定しそうになると途端にズレていく在り方を、鶴見は「反射」と言いました。高校時代を振り返ってみると、これはまさに自分たちが無意識的にやってきたことなんじゃないか、と気づいた。例えば、夜ドンキにたむろっている時、ヤクザや半グレみたいな怖いお兄さんたちがやってくると、瞬時に「マズイ!」と判断してサーッと散っていくような反応ですね。そういう生活の知恵、直観的な判断みたいなものと通ずるものがあるな、って。
とまあ、そうやって思索を深めていく中で出会ったのが、先ほど栗原さんが触れられたグレーバーの著作だったりします。
■人類学と「国家」
松村 私が思想としてのアナキズムを勉強し始めたのはごく最近で、二〇一七年頃、お二人の本がきっかけでした。森さんの『アナキズム入門』とか、栗原さんの『アナキズム 一丸となってバラバラに生きろ』ですね。最近でこそ『くらしのアナキズム』なんて本を書いていますが、それまではことさらアナキズムを自分の研究主題に据えたことはありませんでした。ただ、グレーバーの本と出会ったのは二〇〇五年頃です。当時、私は大学院生で、読書会で「ものの価値を考える」みたいなテーマから、グレーバーの『Toward an Anthropological Theory of Value』を読みました。この本にはアナキズム的な要素はあまりないんですが、人類学の理論としてすごく衝撃を受けた。その後、二〇〇六年に京都大学でグレーバーを呼んでシンポジウムを開催する機会がありました。それと同時期に、彼の『アナーキスト人類学のための断章』の翻訳が出た。その日本語版に彼が寄稿した「まだ見ぬ日本の読者へ」という序文がよくて、その中にマダガスカルの事例が出てきます。人々は、ほとんど政府がない状態だったにもかかわらず、みんな普通に生きてきた、と。かの地に滞在していたグレーバーは、そこがじつは無政府状態にあることに半年くらい気がつかなかった。そのエピソードが一九九八年から通ってきたエチオピアの村の人々の姿と重なりました。アフリカは社会も国家も非常に不安定で、しょっちゅう体制が変わる。外国に植民地にされたかと思えば解放され、社会主義革命が起きて軍部の独裁政権が始まったかと思ったら反政府軍が集結して追い出したり。言うなれば、「国家」が全然確固としたものとして存在していないわけです。だから、人々はそんなものに頼ろうという発想はほぼなくて、淡々と自分たちで自分たちの生活をやっている。その姿がグレーバーのいう「アナキズム」とつながるのか、というのはとても新鮮に思えました。エチオピアの人たちのそうした姿をずっと見続ける中で、「最後は国家が何とかしてくれる」と信じて疑わない日本とは対照的だな、と気づいた。そこから「国家がどうあろうと、何とか暮らしていくためにはどうしたらいいのか」という問いが生まれ、人類学を通して国家という存在を捉え直す、という試みが始まりました。
くりはら・やすし●政治学者。1979年生まれ。著書に『村に火をつけ、白痴になれ 伊藤野枝伝』『執念深い貧乏性』『サボる哲学 労働の未来から逃散せよ』など。
まつむら・けいいちろう●文化人類学者・岡山大学准教授。1975年生まれ。著書に『うしろめたさの人類学』『はみだしの人類学 ともに生きる方法』『くらしのアナキズム』など。
もり・もとなお●哲学者・長崎大学准教授。1983年生まれ。著書に『アナキズム入門』『国道3号線 抵抗の民衆史』『もう革命しかないもんね』など。
構成●辻本力
この続きは、「文學界」4月号に全文掲載されています。