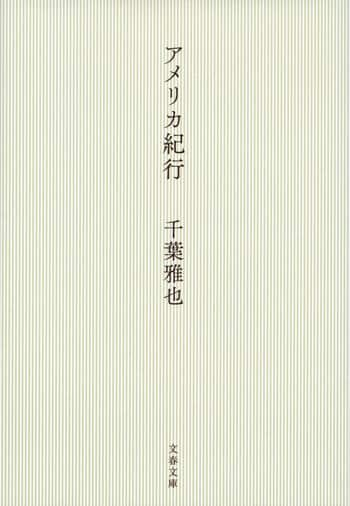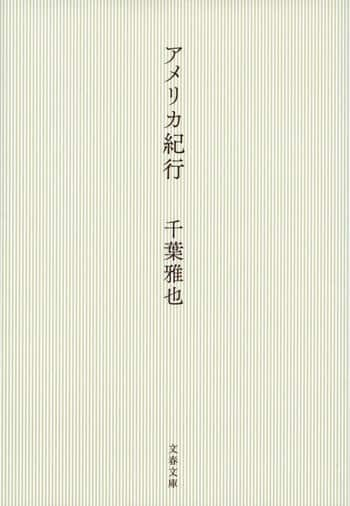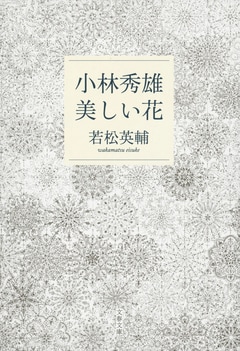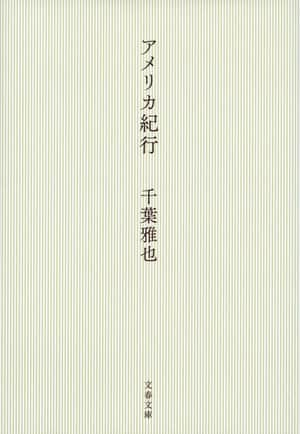
題名に、ちょっとした違和感を感じた。これは「紀行」か。いや、たしかに、外国に出て異質な経験に向かい合ってはいる。ハーバードの研究機関を拠点にした千葉雅也の四か月のアメリカ滞在は、実直に語られている。観察は繊細だし、積極的に動いた。フロリダへも飛んだ。ロスにも飛んだ。ドイツの学術会議にも参加して、マルクス・ガブリエルなどとも話してきた。
だったら、どこが「紀行」っぽくないんだろう。そう感じるのは、単に私が「前」の時代を生きてきたからにすぎないのか。
最初に読んだアメリカ紀行が、私の場合、小田実の『何でも見てやろう』(一九六一)で、小田の行き先が奇しくも同じ場所だった。そこに「ライシャワー日本研究所」はなく、代わりにライシャワー教授がいた。駐日米大使赴任前の知日派リベラルの先生に、小田は異論をぶつける。そしてハーバードをこぼれ落ちるようにして、例えばニューヨークのゲイ・カップルのアパートに向かう。カルチャーが衝撃(ショック)として存在した当時、それにぶつかっていくには小田実の厚顔を必要とした。そして厚顔による語りは、おのずと話が大きくなった。冒険(ピカレスク)や風刺(サタイア)と親和的なスタイルに。感動と批判が増幅される方向に。
そういうタイプの「紀行」は、グローバル化の進んだ地球では成り立たなくなった、というだけのことなのか。いや、それだけでは説明にならない。
ここにも文化摩擦はあるのだが、摩擦の界面が、人と社会の間ではない。もっと微妙でセンシティブ。感覚と環境の間が擦れるというべきか。紀行者の肌、舌、耳で「差異」として集められた情報が読者に届く。帯電した空気、シューズの履き心地、飲むコーヒーの酸味の具合、ガランとした倉庫地帯を走る「シャーシャーと紙を裂くような車の音」。
驚きや危険がないわけではない。大学の北側に良好な住処(すみか)を得る前、著者はロクスベリーに一時的な間借りをした。さらりと書かれているが、ボストンの南西に入り込んだこの近くは結構やばい、黒人たちのネイバーフッドだったところ。小説でもドキュメンタリーでもこの地名は、歴史の街ボストンのエリート市民の居住区と対蹠的に使われてきた。
千葉雅也のロクスベリーに、そのような「意味の絡み」は不要である。Airbnb をタップして、タクシーに乗り込めば、それなりの居心地で住めてしまうのだから。家主はトリニダード・トバゴから移民してきたオヤジさんで、ゲイ・カップルとして養子を育てた。息子は軍人になって日本に駐屯。日本の写真を見せられる。多重なマイノリティーと、多重なエリートが、かくも自然に接続する。それが「何でもなく」書かれているところに、今の時代の倫理がある。
その倫理は否定形の形を取る。彼のデビュー本の書名は「動きすぎてはいけない」だったが、この本も、いろいろな「ない」によって制御されている。まず、始まりと終わりを設け“ない”。すんなり始まる最初のページは、散歩中たまたま覗き込んだ教会の中で、ここにささやかな文化摩擦が待っていた。
アメリカは日本のように地縁や職場で自然とまとまる社会ではない。個として動く人々が「フレンズ」の関係をなしながら、相互の信頼を支えとする。新たな友との出会いにおいては、だから力一杯握手をし、明示的に微笑む。名前を聞き合い、名前で呼び合う。著者はそんな人たちの「温かい人間ぶりに」その場を「押し出され」てしまった。
「人間ぶり」という表現が斬新だ。「人間性」ではない。性格としてではなく、動詞由来の「ぶり」をもって人を語る。人間を be 動詞によって粗大に確定するのではなく、常に「生成変化」(becoming)に向けての微細な「ぶり=shaking」を内包する存在として見る。この視線はドゥルーズ的というべきなのか。