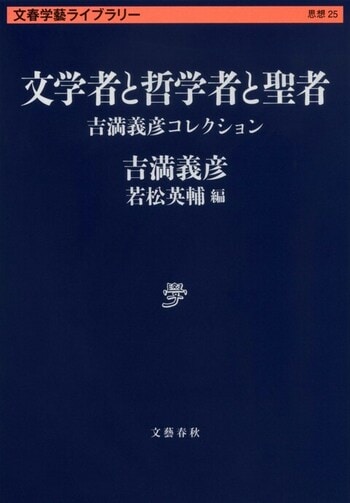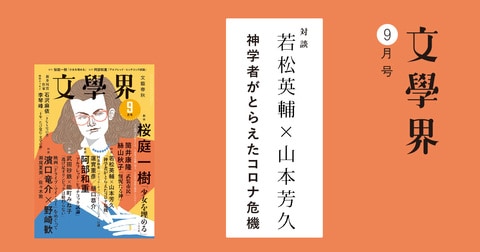詩人は真の神の詩人となるときまことに預言者となるでしょう。それは霊の眼によって世紀の魂を透視し、使徒たちの心を燃やす苦悩を美しく照らし出すところの星々の輝きとなるでありましょう。
(吉満義彦「リルケにおける詩人の悲劇性」)
本書の題名にもなっている「文学者と哲学者と聖者」という言葉は、吉満義彦(一九〇四~一九四五)の理想と共に、彼自身の生の軌跡を端的に表現している。吉満は、近代日本屈指の哲学者であるだけでなく、その魂に詩人を宿した優れた批評精神の持主であり、聖性を求めて止まない一個の求道者でもあった。だが、完全な文学者、哲学者がいないように完全な聖者もまた、存在しない。人に許されているのはどこまでもその道を歩むことである。吉満はこう記している。
われわれすべては芸術家たり哲学者たることはできないが、われわれはすべて人間として聖者の愛の勧告と祈りに従って愛を、しかり神の愛における兄弟への愛を実践することが、これを努めることが許されている (「文学者と哲学者と聖者」)
彼の哲学と文学、そして信仰の核にあったのは「愛」だった。彼にとって「愛」とは、人間の心情の昂ぶりではなく、不可視な姿をして存在している「神」そのものにほかならなかった。その姿を可能な限り純化しようと試みること、そこに彼の生涯は費やされた。
誰のなかにも内なる哲学者がいて、内なる芸術家がいる。そして、意識しないところに内なる求道者が眠っている。吉満はそうした伏在する存在に向って言葉を紡ぎ続けた。吉満にとっての哲学は、哲学研究者やそれを愛好する者のためのものではなかった。すべての人に必要な叡知の糧、それが、彼が信じた真の哲学のありようだった。
このことは吉満義彦をどのように認識するかという問題とも無関係ではない。彼との邂逅を熱い言葉で語ったのは、いわゆる哲学者たちではなかった。加藤周一や小松茂、渡辺秀のように『全集』に解説を寄せた人物は別にしてもフランス文学者の渡辺一夫、批評家の越知保夫、そしてもっとも頻度高く語ったのが遠藤周作だった。哲学者井筒俊彦は例外で、遠藤周作との対談「文学と思想の深層」で、遠藤が「私たち当時キリスト教の学生が影響を受けた思想家は、岩下壮一、それから吉満義彦先生ですね」と語ると井筒は「そうです、私もこのお二人の著書はよく読みました」と応じている。遠藤を文学の道に導いたのも吉満だった。あるとき、遠藤を堀辰雄に紹介する。このことは遠藤の基点となっただけでなく、近代日本精神史の岐路にもなった。
吉満義彦は、文学と哲学と信仰が一つになる、そうした場所で生き続けた稀有なる魂だった。「詩とロゴス」のなかで吉満は、自身にとっての哲学、あるいは哲学者をめぐって印象深い言葉を残している。「私は一個の小さな哲学者(フィロゾーフ)にすぎない」と書いたあと、彼はこう続けている。
これは自惚れで言うのではない。自分の立場を謙遜に告白するのである。哲学者はものを普遍的原理から見るのが仕事である。しかるに芸術家はものを個別的に表現することを、創作することを目的とする。
哲学的視座が必須なものであることを疑わない。しかし、それだけでは不十分だというのである。哲学者の知性と理性はいつも、芸術家の感性、そして求道者の霊性とのつながりのなかにあらねばならない。同じ文章で吉満は、哲学的精神は芸術的精神と共鳴するとき、その本来のはたらきをなすという。
そもそも芸術と言い哲学と言い、人間の最緊張において営まれる精神の活動は、「人間」が人間の「現実」地盤に根ざしこれから出発して人間を「超越」する営みにほかならない。真のリアリズムはむしろ現象されない人間の「現実」を、それ故超現実的な実在なるものを顕現する努力であらねばならない。
彼にとって哲学も、文学を含めた芸術も、信仰の道もまた、人間の生とは何かという問題を探究する道程に終わるものではなかった。それは眼前の現実だけでなく、「人間の『現実』地盤に根ざしこれから出発して人間を『超越』する営み」でなくてはならなかった。
先の一節にもあったが「実在」は吉満義彦を読む重要な鍵語(キーターム)の一つである。彼にとっての「実在」あるいは「実在なるもの」とは、世にいう社会的現実ではない。それを超え出るもう一つの世界からの光に照らされている状態を指す。
漢字学者・中国文学者の白川静によると「存在」とは、時間的に「ある」ことを意味する「存」と空間的に「ある」、「在」が一つになった言葉だという。吉満義彦がいう「実在」は、その境域を超えてくる。