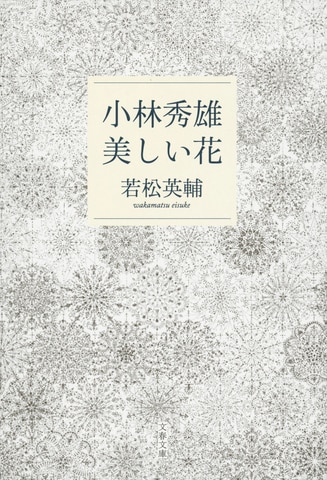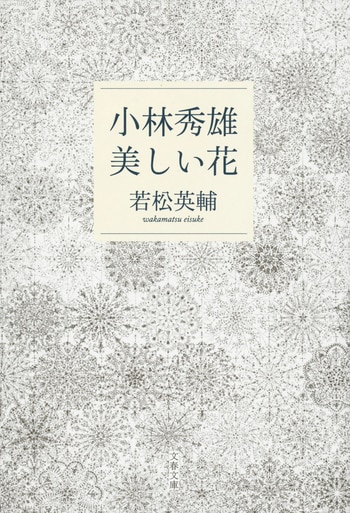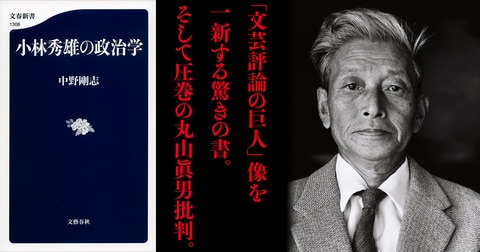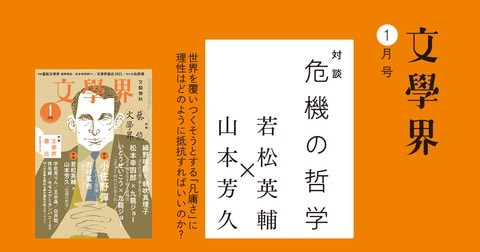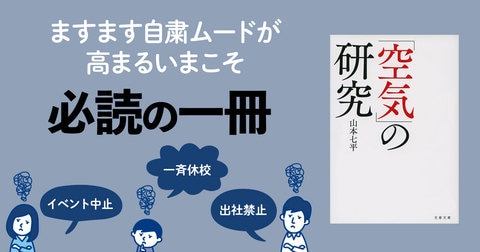本書には著者自ら本書の小林秀雄論の独自性とその意義、そして執筆の背景を丁寧に語った「序章」と「あとがき」がある。そこでここではこうした鮮烈な小林論を生み出す若松英輔氏のカトリック批評家としての精神的土壌をめぐって解説したい。
「文學界」で二年間連載され単行本化された六百頁を超える若松氏の小林秀雄論を読む――それは長い神秘の夜の旅ともいえる体験――を終えてその余韻の中で想い起されたのは、若松氏が慶応義塾大学の学生だった二十二歳の時の処女作「文士たちの遺言」だった。中村光夫、小林秀雄、正宗白鳥を論じ、「三田文学」(一九九一年春季号)の学生懸賞論文で佳作に入選し掲載された批評だ。私はその頃、遠藤周作と共に日本人の心情でキリスト教を捉えなおす課題に生涯をかけていた井上洋治神父がその目的で創設した「風(プネウマ)の家」の活動を手伝い、機関誌「風(プネウマ)」を発行していたが、そこで井上神父が青年たちにバトンを渡したいと始めた勉強会に若松氏も集っていた。若松氏の受賞を喜びながら、自分の書くべき使命を見出した若者の熱い思いがみなぎった原石のような文章を読んだ時の感動が今も蘇ってくる。その後、氏は会社勤めをするようになって、「風(プネウマ)」三九号(一九九五年一二月)に「越知保夫―生きるということ」を寄稿してもらったのが唯一で、十数年の空白があったが、それは自分に使命として与えられたテーマを深く深く掘り下げ続けた時であったろう。そして、地下の水脈とつながり一気に泉が湧き出るように、「三田文学」(二〇〇七年春季号)で新人賞を受賞し発表された「越知保夫とその時代 求道の文学」を皮切りに批評活動が本格的に始まる。「文士たちの遺言」以来、その受賞作も、それをさらに充実させた氏の批評家としての原点となる著書『神秘の夜の旅』も、そしてこの大著『小林秀雄 美しい花』まで若松氏が一貫して自分のうちなるテーマを深く掘り続けてきたその一筋の持続の営為に対して感動と敬意の念を禁じ得ない。
本書の「あとがき」には、「書きながら片時も忘れることがなかったのは越知保夫」「彼こそ、この短くない旅の導師」とあり、本書は越知保夫に捧げられている。若松氏がカトリック批評家の越知と出会わなければ、本書は生まれなかった、さらに言えば今日のような形で活躍する批評家若松英輔も生まれなかったことは確かだろう。
若松氏を越知に出会わせたのは、井上神父の精神的自叙伝『余白の旅 思索のあと』だ。若松氏は近著『読書のちから』の中で、「人生を変える一冊は確かに存在する」と述べ『余白の旅』を取り上げ、著者に十九歳で出会って以来、「私の無二の師になった」と語る。井上神父が同書で越知を論じた部分は、若松英輔編『小林秀雄 越知保夫全作品』に転載され、巻末の「小伝 越知保夫」の中で、岩下壮一に始まる近代日本のカトリシズムの精神史として、岩下に続く、リルケ、ドストエフスキー、小林秀雄といった文学者をよく解したカトリック哲学者吉満義彦、吉満を最初に受容した批評家越知保夫、その越知を継承、展開した批評家で作家の遠藤周作と宗教的実践家の井上洋治と続く血脈を語る。ここには、それらの血脈を継ぐカトリック批評家としての自らの位置を自覚し、その使命を果たすべき覚悟がうかがえる。その使命の一つの大きな結実としての小林秀雄論であるゆえに、多くの小林論がある中で、本書の鮮烈さが際立つのではなかろうか。