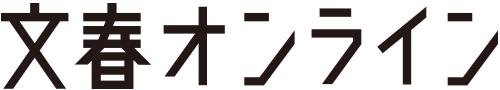M-1決勝で“さざ波の笑い”しか起きず…「日本全国の前でスベってるのと同じ」ある人気コンビを襲った“漫才の恐怖” から続く
いまや年末の風物詩である「M-1グランプリ」。一夜にして富と人気を手にすることができるこのビッグイベントに、「ちゃっちゃっと優勝して、天下を獲ったるわい」と乗り込んだコンビがいる。2002年から9年連続で決勝に進出し、「ミスターM-1」「M-1の申し子」と呼ばれた笑い飯である。
ここでは、笑い飯、千鳥、フットボールアワーなどの現役芸人やスタッフの証言をもとに、漫才とM-1の20年を活写した中村計氏のノンフィクション『笑い神 M-1、その純情と狂気』(文藝春秋)から一部を抜粋してお届けする。(全2回の2回目/1回目から続く)

◆◆◆
プラス・マイナスのネタに会場中が爆笑
本番前、プラス・マイナスの岩橋良昌は、一方的に注意事項をまくし立てるのが常だった。それも延々だ。相方の兼光タカシは、それをやり過ごすかのように、いつもうつむきながら黙って聞いていた。
「性格上、あいつは言わずにおれんのはわかるんで。『やってるやん』って言ったら、『やってへんやろ』って言い返されるだけ。もう、もめるんが嫌なんで、いっつも黙ってます」
そんな岩橋が、2018年、M-1グランプリ決勝の最後の一枠をかけた敗者復活戦のときだけは「無」になれた。静かな自信は兼光にも伝播していた。
「なぜだかわからないんですけど、出ていく前から、『ウケんのやろな』と思えた。あのときは、怖いものなしでしたね」
岩橋は、あるときはチアガールに扮し、あるときはピッチャーに扮し、そのたびに大爆笑をかっさらった。
「一種のトランス状態に入ってましたね。謎の力が出てた。あとで映像、見返したんですけど、動きキレキレでしたね。迷いがなくなったら、人間、あんなことになりますね」
兼光の「イチバンバンバンバンバン……、センターターターターターター……」という野球場の場内アナウンスのモノマネは、屋外だったこともあり、私の心は一瞬にして神宮球場へ連れ去られた。
プラス・マイナスのネタは、声と動きが大きく、設定はシンプル。この日、初めて最初から最後まで、プレス用の最後列まで言葉とストーリーが届き、会場中が爆笑に包まれた。
岩橋が体が千切れんばかりの勢いで手足を上げたり下げたりするシーンはあまりのバカバカしさに、私も取材者の立場を忘れ、腹をよじって笑い転げた。
いい大人が、あらん限りの熱量で、道化を演じる。その姿には生きることの喜びと悲しみが凝縮されていた。笑いながら、涙が込み上げてきた。まさに笑いの神が舞い降りたかのような3分間だった。

視聴者投票の結果、敗者復活戦の勝者に選ばれたのは…
ところが──。
彼らは敗れる。会場にいれば明白だった。全16組中、笑いの量、質ともに、プラス・マイナスがダントツだった。しかし、延べ200万人による視聴者投票の結果、選ばれたのは、もっと知名度が高く、もっと人気のある若手コンビ、ミキだった。
視聴者投票は人気投票になりやすい。全国的にほぼ無名で、人気とも縁がないプラス・マイナスが、約1万800票差で2位に食い込んだだけでも大健闘と言えた。
敗者復活戦の勝者が読み上げられた瞬間、岩橋は、組んでいた両腕をほどき、両手を膝の上においた。白いスーツの上に黒いパーカーを羽織った巨漢が、魂の抜け殻のようになっていた。
「ああ、終わった、と。M-1は、僕らに最後まで厳しかったなと。正直、『今度こそ、俺らが主役になれた』と思ったんですけど」
事前の打ち合わせでは、落選した場合、2人で「ぶぅーっ!」と息を吹き、後ろにそっくり返る予定だった。
「僕ら芸人やから、親が死んでも笑かさなあかん。せやのに、あんときはショック過ぎて、ただただ凹んでしまいましたね」
一方、相方の兼光は苦笑いを浮かべ、呆然と立ち尽くしていた。
「岩橋が何にもしないんで、俺、ほんならどうしようと思って、普通にしてました。ただ、このままほっといたら泣いてまうわと思って、こらえてましたね」
芸人は普段、舞台上では道化師であり続ける。その仮面をいとも簡単に剥いでしまうのがM-1という舞台だった。
「M-1で勝つよりも、笑い飯に認めて欲しかった」
2018年のM-1後、私はこの日のプラス・マイナスのことを『週刊文春』誌上で2週にわたり「敗者たちのM-1グランプリ プラス・マイナス『奇跡の3分』」という記事にまとめた。
その取材中、関西で青春時代を過ごした芸人の口から、何度も聞いた言葉があった。
「M-1で勝つよりも、笑い飯に認めて欲しかった」
笑い飯──。
わらいめし、と読む。
短髪で、尖った鼻の哲夫。長髪で、ギョロ目の西田幸治。
変なネタをする、アヤシげな、あの2人か。

取材をする前まで、私の笑い飯に対する認識はその程度だった。
それにしても意外だった。
〇〇に認めて欲しい。それまで、このブランクに入りうる人物は、この世界ではただ1人だけだと思っていた。笑いの神、ダウンタウンの松本人志である。
だが、違った。
2000年にコンビを結成した笑い飯は2002年から2010年まで、9年連続でM-1の決勝ラウンドに進出している。「容赦ない」と言われるM-1予選の選考において、空前絶後の記録である。
そして、出場資格の関係で最後の挑戦となった2010年に悲願の優勝を遂げた。M-1の最初の10年は笑い飯の歴史でもあった、そう言われるゆえんである。
「ミスターM-1」、または「M-1の申し子」と呼ばれる笑い飯は、M-1が生んだ最大のスターコンビと言っていいだろう。
プラス・マイナスの記事を書き終えた後、『週刊文春』の編集者から「M-1ものの長期連載を」と頼まれたとき、真っ先に過(よぎ)ったのが笑い飯の存在だった。
笑い飯を中心に据え、M-1の最初の10年を振り返れば「M-1とは何か」「漫才とは何か」、ひいては「笑いとは何か」の答えは、自ずと浮かび上がるのではないかと思った。
元アジアンの馬場園梓は笑い飯を「神」と評した
2021年秋から2022年春まで、22回にわたって『週刊文春』誌上で連載された「笑い神 M-1、その純情と狂気」は、こうして誕生した。この本は、その連載原稿に加筆・修正を加えたものである。
女性コンビとして2005年、初めてM-1決勝に出場した元アジアンの馬場園梓は、まだ笑い飯が無名だった頃から「この人らが売れんかったら、誰が売れんねん」と思っていたという。アジアンは久々の実力派女性コンビだったが、2021年に惜しまれながらも解散している。
「神なんですよ、ホントに。初めてネタを見たとき、『あ、すごい人に今、会ってるかもしれない』って思いましたから。お茶の間を温かい笑いで包もうという感じではなく、自分の中の完成された作品を、すごい角度からぶつけてくる。こんな人ら、おるんや、と。芸人って、普通は徐々におもしろくなっていくもんじゃないですか。でも、あの2人は最初っからほぼ完成されていた。完璧と完璧なんです。
だから、一般人の方に降りてきてくれるだけでいい。われわれは一段ずつ登っていく作業なんですけど。もう、そこが決定的に違うんです。ただね、西田さんは一般の人にも通じるようにかみ砕いてくれるけど、哲夫さんはかみ砕かないんです。脳の中身を、そのままさらけ出してくることがある。だから、時折、わけわからないときもあるんですけどね。あの人、ホント、頭おかしいんで」

千鳥の大悟が神妙な面持ちでいった言葉
笑いの神は、笑い飯の他にもまだいた。「笑い飯に認めて欲しかった」という言葉は、時折、「笑い飯と千鳥に認めて欲しかった」に膨らんだ。
レギュラー番組10本を持つ千鳥は、吉本興業切っての売れっ子コンビだ。今や、ダウンタウンの後継者とさえ言われている。その千鳥にとって、笑い飯は、この世界における「師匠」であり、「兄弟」だった。そして、ときに「教祖」でもあった。
笑い飯が結成される前から彼らと付き合いがある千鳥の悪童面の方、大悟は、神妙な面持ちでこう言った。
「今でも哲夫さんにおもろないと言われるのが、いっちゃん怖いですから」
──落ち込みますか。
「うん。誰に言われるより」
笑い飯は桁違いの狂人
笑い飯がまだ何者でもなかった頃、ともに大阪で青春時代を過ごした元芸人の水上雄一は、現在、マッサージ師の資格を取得し、大阪市内にクリニックを開業している。仕事は順調だという。所帯を持ち、小さな子どももいる。
そんな水上の言葉が心にしみた。
「笑い飯さんとおるときが、いちばん楽しかった。芸人を辞めて10年以上経ちますけど、この10年で笑った回数よりも、あの人たちとおった1時間、2時間の方が笑ってたと思います。あんだけ必死に考えて、あんだけ笑って。苦痛なんだけど、楽しかった。おかしいですよね。笑うために真剣に悩むって」

おかしい。でも、ピュアだ。
M-1において、光り輝くネタは、いわば一粒の砂金だ。何百回、何千回と川の砂を皿で掬(すく)い、ほんの一握りの人間だけが見つけることができる。
M-1のために生み出される何千組の、おそらく何万というネタは、毎年、誰にも知られぬままゴミ同然に破棄されていく。人を笑わせることのできないネタほど、世の中で無用なものはない。M-1とは、ネタの壮大な墓場でもあった。
にもかかわらず、漫才師たちは毎年、そこへ向かった。
彼ら、彼女らは、例外なく愚かだった。もっと言えば、狂っていた。しかし、それゆえに、直視できないほどの眩(まぶ)しさを放ってもいた。
そんな中に、桁違いの狂人で、桁違いの恒星があった。
それが、笑い飯だった。