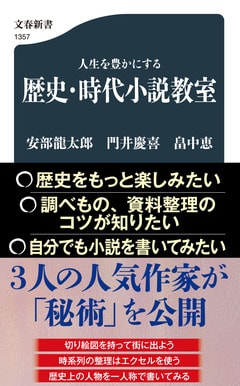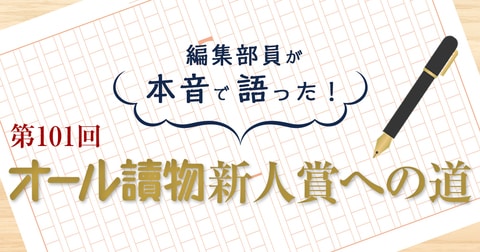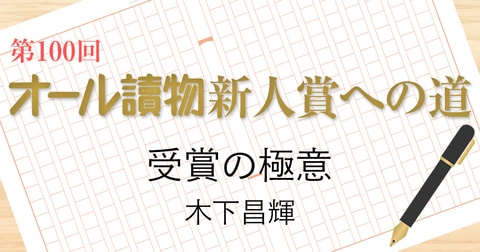四
数日続いた秋雨が上がって、澄んだ青空が目に染みる。天気が良くなったおかげか、咲兵衛の気鬱も少々晴れた。長雨で傷んだ菊がないかと見回っていると、かめが風呂敷包みを抱えて帰ってきた。麴町に住まっている叔母のお梅を訪ねに行ったのだが、ひどく疲れた顔をしている。
縁台に腰を下ろしたかめは、風呂敷包みを脇に置くと溜息をついた。
「佐倉様と蓬助ちゃん、おまえ様の見立てどおり知り合いでした」
亭主の咲兵衛が、蓬の花の一件で蓬助に会いたがっている――そう話を切り出して、かめは穏田村の住まいを叔母から教えてもらった。話のついでに、蓬助には親身になってくれる人はいないのかと尋ねてみたという。
「癪を病んで通っていたお侍が、弟のように可愛がってくれていた。どこの御家中の方かは知らないけれど、たしか佐倉兵馬という名だったと、叔母は申しておりました」
「やっぱりそうか。だけど、佐倉様が四谷屋敷の侍だとは、明かしていないだろうな」
「絶対に申しません。この話には続きがあるんです。ですから、たとえ叔母であっても、佐倉様の御身分を明かさないほうがいいと思ったんです」
かめは花畑を見回した。誰もいないが、声を潜める。
「今年の春になって、橘庵さんの御妻女が、『あの佐倉という侍に出入りを断って、蓬助を他所に預けてほしい』って、言い出したそうです。御妻女が言うには……」
かめの声がますます低くなる。よく聞き取ろうと、咲兵衛は耳を寄せた。
「二人が物陰で『懇(ねんご)ろ』にしているのを見た、って」
「えっ」
かめは花畑に目を転じて、小さく首を振った。
「でも、お梅叔母さんは、蓬助ちゃんを追い出すための言い掛かりだって怒ってました。ねえ、おまえ様。懇ろって、何でしょうね」
「そりゃ、おまえ……懇ろだろう」
承知はしているが、二人とも「男色」という言葉が喉につかえて出なかった。今の世の中、男同士で睦み合っても別段珍しくもない。江戸城下のそこかしこで、様子ありげな男二人が肩を寄せて、道行きを楽しんでいる。見交わす眼の力強さで、それとわかるのだ。男女の間には培えない強く深い結びつきを良しとする、美男子同士なら、端から眺めても景色がいいと、数寄者たちは持て囃(はや)す。だが年端のいかぬ他人様の子に手を出すのは、さすがに人の道から外れよう。
「きっと、言い掛かりですよね」
かめは、そう言って俯いた。実直な好男子に見えた兵馬が、実は子ども相手に男色を嗜(たしな)んでいたらしいと知って、相当堪えたようだった。
しょんぼりと沈むかめを見て、咲兵衛は申し訳なく思った。河童を見たと言い出せぬまま女房を利用して、挙げ句の果てに傷付けてしまった。もうこれ以上、小狡(こずる)い真似はしたくない。
「明日、穏田村に行ってくるよ。真実はどうあれ、蓬助という子に罪は……ないだろう」
血に塗(まみ)れて川縁に立っていた河童が蓬助だったら、やはり兵馬の死に関わっているのだろうか。だが、疑念ばかりを重ねても埒(らち)があかない。あの面差しは瞼に焼き付いている。顔を見ればわかるはずだ。
翌朝起きると、かめはいつもの朗らかな女房に戻っていた。二人分の弁当を作って、お梅から託された蓬助への土産と一緒に風呂敷包みにする。それを咲兵衛に手渡して、笑顔を見せてくれた。
「蓬の花を見つけたら摘んでお行きなさいな。それから、川っ縁の道を行くのですから、お早めにお帰りくださいませ」
「わかってるよ。お守りの寛永通宝も、ちゃんとここにあるから」
懐の上をぽんと叩いて、咲兵衛は素直に頷いた。
四谷屋敷を出た咲兵衛は、日差しに目を細めながら歩き出した。蓬助に会ったら、まず蓬の話から始めよう。賢い子と聞いているが、初対面で心を開いてくれるだろうか。いきなり立ち入った話をしたところで、正直に打ち明けてくれるとは思えない。
考え事をしながら歩くうちに、千駄ヶ谷観音坂下の橋まで来た。真っ青な秋空の下、田圃には人が出て稲刈りの真っ最中だ。人の往来も賑やかで、先日の不気味な気配は微塵もない。橋の手前から川沿いに進むと、咲兵衛は対岸を眺めた。兵馬が斃(たお)れていたと覚しき所は、そこだけ草が刈られていた。咲兵衛は手を合わせて、兵馬の冥福を祈った。瞼を閉じると、河童と遭遇したあの時の光景がありありと浮かぶ。
咲兵衛は川沿いに続く道を眺めた。穏田村までは、あと半里ほど歩かねばならない。道の先に真実が待っているのだろうか。それが受け入れがたいものであっても、先へ進むためには通らねばならぬ道がある。ここまで来たら、もう引き返せない。
小川を右手に見ながら、道は浅い谷の間を抜けていく。咲兵衛は藪に目を配って、子どもの身の丈ほどに伸びた蓬を見つけた。葉群れの間から、赤茶に泡立つ長い花穂が立ち上がっている。
葉も付けておかないと、蓬の花だとわかるまい。咲兵衛は繁り重なる蓬を搔き分けて、具合のいい茎を探りながら苦笑いを浮かべた。そういえば、兵馬が教えてくれた。伸び放題の蓬葉のように雑念多き心模様を「蓬の心」というのだと。
「今のおれの心、そのまんまだな」と、咲兵衛は勢いよく鎌を当てた。
その百姓家は蓬助の生みの母の親戚筋で、穏田村の外れにあった。母屋の土間にいた無愛想な老婆が、怪訝(けげん)な目をこちらに向ける。咲兵衛は突然の訪問を詫びてから、蓬助に会いに来たと告げた。顔をしかめた老婆は、顎で戸外を指した。
「さっき田圃から帰ってきて、納屋に入っていったよ。稲刈りで忙しいのに怠けてばっかり。何を考えてんだか、魔物みたいな目をして睨み付けてくる。薄気味悪い子だよ」
咲兵衛が振り向くと、今しがた通ってきた前庭の片隅に納屋が見えた。用が済んだら田圃に戻るよう言ってくれと、老婆は吐き捨てるように言った。
咲兵衛は前庭を横切って、納屋の戸口まで来ると、軽く咳払いしてから声を掛けた。
「四谷で花作りをしております咲兵衛と申します。お梅さんの使いで参りました」
しばらく待ったが、返事がない。咲兵衛は、そっと引戸を開けた。農具を収めた土間の奥に一畳ほどの板敷きがあり、ぼさぼさの髪を紐で束ねた後ろ姿が見える。
「蓬助さんかい」
壁際の文机に頰杖を突いていた少年が、ゆっくりと振り向いた。
黒目がちの瞳がじっと咲兵衛を捉える。底知れぬ眼力には、覚えがあった。前髪の上にある丸い中剃りが河童の皿に見えなくもない――ああ、この子だ。間違いない。
「小父(おじ)さん」
物怖じしない声が返った。
「前にも会ったよね。千駄ヶ谷の川っ縁で。おったまげた顔で逃げていった」
無邪気な笑顔が目に飛び込む。どう話を進めようかと思案していた咲兵衛は、一気に肩の力が抜けた。河童と見間違えるほど異様な姿をしていたのに、それを隠し立てする気は全くないらしい。いったい、どういうつもりなのだ。
戸惑ううちに蓬助の顔から笑みが消えて、また挑むような眼差しを向けてきた。咲兵衛は用心しながら、蓬助に近づいた。
「あの時は情けねえ格好を晒しちまったな」
と、照れ笑いを浮かべて見せたが、蓬助の瞳は、こちらの真意を探るようにじっと動かない。息苦しくなった咲兵衛は、腕に抱えた蓬の束に目を落とした。
「蓬の花を摘んできたよ。もしかしたら、見たいんじゃないかと思ってね」
「これが」
目を丸くして、蓬助が身を乗り出す。途端に、あどけない童の顔になった。
「葉っぱが似てるから、菊のような花が咲くのかと思ってた」
蓬助は花房を手に乗せて、小豆色の細かな花や、丸い蕾の感触を確かめている。その指先が花茎から葉に移り、固い茎をたどっていく。瞬きもせず、医者が見立てをするような熱心な眼差しだ。
「茎が木の枝のように固くなってる。花の周りの葉っぱは、ぎざぎざがなくて蓬に見えない。でも、やっぱり草餅の匂いがする」
「いったん覚えれば、草むらでもすぐに見つけられるよ」
「それは人に摘まれずに、秋まで生き延びた蓬だね」
まあそうだがと頷いて、咲兵衛は背負ってきた風呂敷包みを開いた。お梅から託された綿入れに、蓬助が嬉しそうに袖を通す。蓬助には少し大きいかなと微笑んだ咲兵衛は、ふと文机に置かれた土器(かわらけ)に目が留まった。黒砂利のようなものが一摑み盛ってある。形も大きさも朝顔の種に似ているが、妙に黒光りしていた。
「これは、何だ」
咲兵衛が土器に手を伸ばすと、蓬助はくるりと向きを変えて袖で遮った。
「勇気の種だよ」
「……勇気の種って。そりゃ、何だ。ちょっと見せてくれ。おれは花作りだ。知らねえ種があるのなら、覚えておきたい」
覗き込もうとした咲兵衛に、蓬助は腹の内を探るような鋭い目を向けた。
「小父さんは、兵馬様を知ってるよね。蓬に花が咲くかどうか、花作りの咲兵衛に訊いてみるって兵馬様が言ってた。だから、きっと知り合いなんだ」
すべてを見通すような空恐ろしい眼差し。姑息な言は通用しそうもない。咲兵衛は腹をくくった。
「ああ、そうだ。知り合いだよ。佐倉様はあの川っ縁で亡くなった。癪の発作で頓死ということになったが……おまえは、子細を知っているな」
一気に核心へと踏み込む。だが蓬助は、まるで懐かしいものを見たかのように微笑んだ。
「何で笑うんだ」
「だって、小父さん、正直なんだもん。兵馬様と同じだ。御家のために私事を言わぬのが武士の生き方だけど、おまえといる時だけは本心で語れる。そう言って、いつだって兵馬様は、おれには正直だった。他人には言えぬ本音も打ち明けてくれたし、おれを誰よりも大事にしてくれた。だから、それに応えたくて、おれは兵馬様と生きるも死ぬも一緒だと誓ったんだ」
「おまえと佐倉様は、その……恋仲だったのか」
蓬助がこくんと頷く。咲兵衛は感情を押し殺して畳みかけた。
「あの川っ縁にいたおまえは、尋常な姿じゃなかった。正直に言うよ。おれは、おまえが佐倉様に手を下したんじゃないかと疑っていた。でも、そんなに大切な人を傷つけるはずがねえよな。佐倉様は、自らお腹を召されたんだよな」
そうであってくれ――すがるように訊くと、蓬助の目に優しい光が宿った。
「気掛かりを溜め込んで、小父さんの身体にも砂が溜まるといけないよ」
「そりゃまた、どういう意味だ。おまえの言うことは、さっぱりわからん」
首をかしげた咲兵衛を、蓬助は大人びた顔で見上げた。
「男の身体には、砂が溜まりやすいと言われてるんだ。昔、癪に苦しむ石工が蒟蒻(こんにゃく)を食べて、身体に溜まった砂を払って本復したって話がある。それから『蒟蒻は砂っ払い』って言うようになったんだよ。砂のうちに払えればいいけど、溜まりすぎた砂は石に育つ。その証拠に、秀吉公の家来が癪に苦しんで腹を裂いたら、拳ほどの亀みたいな石が出たんだって。これは父上から聞いた話だけど、おれは兵馬様にも話して聞かせたんだ」
蓬助は言葉を切って、俯いた。
「あの日、兵馬様はいつもよりも具合が悪くて。本当に、このまま死んじゃうんじゃないかってくらい苦しんで。でも、おれには、どうすることもできなくて……ただ抱き合って、温めてあげることしかできなかった。兵馬様の鼓動が耳いっぱいに響いて、まだ大丈夫、まだ死なないって心の中で繰り返してた。しばらくしたら、兵馬様は右の脇腹を押さえて、『ここにしこりがある。きっと、おまえの言った石があるんだ。今から腹を切る。だから、本当に石があるかどうか、確かめてくれ』って言い出したんだ。『良い医者になるなら、見識を深めろ』って言った。おれは止めようと思った。思ったけど、もう一人の自分が、人の腹の中で育つ石を見たがっていた。迷っているうちに、兵馬様は腹を切って……早く石を出せって。おれは気力を振り絞った。腹の中を探って、固くなった臓物を摑んだ」
瞳を潤ませて、蓬助は右手を見つめた。
「あったよ、本当に石があるって言ったら、兵馬様の顔が、すうっと楽になった。しばらく時が止まったみたいになって、急に震えが止まらなくなっちゃった。おれは、しっかりしなきゃって気合を入れて、石の入った腸を切り取った。その時、川の向こうにいた小父さんと目が合ったんだ」
咲兵衛が走り去った後、切り取った腸を大きな葉っぱに包んで、身体を洗って着物を着た。この納屋に帰り着いて腸の中を改めると、果たして黒い砂利石が出てきたという。
咲兵衛は、土器の黒石から目が離せなくなった。
「これが、佐倉様の腹から出た石なのか」
人の腹から、こんな石が出るとは――凍り付いた咲兵衛に背を向けて、蓬助は土器に顔を寄せた。
「おれと兵馬様は義兄弟の契りを結んだ。兵馬様が死んだら、おれも生きてはいないと誓った。なのに、おれは意気地がなくて、すぐに後を追えなかった」
「そんなことを佐倉様は望んでねえぞ。良い医者になれって言ったんだろう」
「ここで畑仕事を手伝っていても、医者にはなれないよ。きっと立派な医者になるって、亡き父上にも約束したのに」
しゅんと項垂(うなだ)れた蓬助の肩に、咲兵衛は手を置いた。
「確かに、ここじゃ医者の修業はできないが、おまえには明日がいっぱいあるだろうが。望みを捨てずに精進すれば、必ず良い目が出るものだぞ。おまえは聡いから、必ず医者になれるはずだ。おれも力を貸すよ。だから、元気を出せ」
気休めに並べた言葉ではない。咲兵衛は、本気で蓬助のために尽力しようと、この時決心した。その思いが伝わったのか、蓬助はようやく顔を上げた。
「ありがとう、小父さん。そうだね……力を出さないといけないんだよね」
壁を見つめて頷いた蓬助は、土器から黒い粒を一つ摘まみ上げた。そのまま、ためらいもなく口に入れる。ごくりと飲み下す音に、咲兵衛は血の気が引いた。
「おい、そんなもの食うなよ」
「兵馬様の身体から出た石を無下にできるものか。これを飲むと心が奮う。おれの中に勇気が育つ。だからこれは勇気の種なんだ」
陰りの消えた蓬助の顔を見て、咲兵衛は溜息をついた。不遇なこの子が前向きになれるなら、腹の石を食らうのも大目に見てやるべきだろう。
「明日に向かう勇気が出るなら、止めはしないがなあ。とりあえず、ちゃんと飯も食え」
咲兵衛は、かめが拵えた弁当を手渡した。味噌を塗りつけ、こんがりと焼いた握り飯だ。
蓬助は握り飯を頰張ると、ぱっと目を瞠った。
「美味しい」そう何度も呟いて、飯粒を付けた口元をほころばせた。
五
往きは重かった咲兵衛の足取りも、帰りには軽やかに弾んだ。
「ほら見ろ。河童なんて、いなかっただろう」と呟いて、うーんと唸る。そもそも、そう思い込んだのは、誰あろう自分ではないか。
まったく不甲斐ねえな――歩きながら咲兵衛は、ぽんと頭を叩いて顔をしかめた。
川縁で裸の蓬助を見た時、肝が据わっていれば目を背けなかった。眼をひんむいてよく見れば、ただの子どもだと気付いただろう。真実を見極めもせずに、幻影に怯えた自分が情けない。
物の怪は現世(うつしよ)にいるんじゃねえ。人の心の弱みに棲(す)み着くんだ――咲兵衛は青く澄み渡る大空を見上げて頷いた。もっと精進して、頼り甲斐のある男にならなけりゃ。女房のためにも、寄る辺ない蓬助のためにも。
午刻(ひるどき)を過ぎて咲兵衛が小屋に戻ると、かめは土間続きの板の間で洗濯物を畳んでいた。土産の綿入れや、途中で摘んでいった蓬の花に蓬助が喜んでいたと、咲兵衛は当たり障りのない話から語って聞かせた。
かめは俯いたまま、ぼそりと訊いた。
「それで……佐倉様とは、懇ろだったのですか」
「うん、いや……兄弟のように仲良しだったって」
「それなら、佐倉様が亡くなったと知って、がっかりしたでしょう」
「……そうだな」
咲兵衛は余計な事実を伝えずに言葉を濁した。
兵馬と義兄弟の契りを結んだと大人びた口調で語った蓬助は、迷いのなさ故に、かえって子どもらしく見えた。だが、佐倉兵馬の本音はどうだったのだろう。無垢な少年を己の愛欲に巻き込んで、悔いていたのではないか。腹を切ったのは病の苦しみのせいばかりではなかろう。一切を清算して蓬助には明日を生きてほしいと、あの世の兵馬も望んでいるはずだ。
畳みかけた野良着に綻びを見つけたのか、かめが針箱に手を伸ばす。
「どんなお子さんだったのですか」
「癖はあるけど、いい子だよ。込み入った事情を抱えて育ったせいか、こちらの腹の底まで見透かすような目をする。それが可愛げないとも言えるが」
蓬の花を手に取った蓬助を見た時、咲兵衛にはわかったのだ。あの鋭い目つきは威嚇(いかく)とは違う。物の真を見極めようとする真摯な眼差しなのだと。
かめは糸先を舐めて、針の穴を狙う。だが、なかなか通せないでいる。
「親ならどんな子でも可愛がるというのに。実の親がいないのは気の毒ですね。その上、兄のように慕った人にまで死なれて」
目を細めて針に糸を通したかめが、ようやく顔を上げて微笑んだ。
「また会いに行ってあげなさいな」
「うん、そうするよ。その時は、また握り飯を作ってくれ。今まで食べた握り飯の中で一番美味しかった、御馳走様って、あの子が言ってたよ」
「あら、嬉しい」かめの笑顔が、とびきり輝いた。
月が変わって、九月になった。
叔母のお梅が、杖にすがって花畑の小屋にやって来た。
「蓬助ちゃんが、死んだよう」
咲兵衛夫婦の顔を見た刹那、お梅はそう泣き叫んだ。ここへ来るまでに力を使い果たしたのか、手にした杖をほうり出して縁台に倒れ込む。寝耳に水の知らせに、咲兵衛は棒立ちになった。
「おまえ様、叔母さんを起こしてあげて」
かめに尻を叩かれて、咲兵衛はおろおろと手を差し出した。お梅を引っ張り起こす間に、かめが茶碗に水を汲んでくる。それを飲ませてもらった叔母は、胸を叩いて息を整えた。
「叔母さん、何があったの。蓬助ちゃんが死んだって」
「それが……私にも、さっぱりわからなくて。さっき橘庵先生の次男坊が使いに来てね。いきなり『蓬助が死んだので、穏田村へ遺骨を引き取りに行ってくださいますか。母がうちに入れるのは嫌だと言っているので、然るべき納骨先が決まるまでお梅さんの所で預かってください』って、金子(きんす)をぽんと置いてね。『後は、よろしくお願いします』って、さっさと帰っちまった」
お梅の話を聞いて、かめが声を張り上げた。
「何で、そんなに冷たいんですか」
「あそこの家族はね、蓬助ちゃんが御隠居様の子じゃないって疑ってるんだ。七十過ぎた年寄りが、お灸を据えたぐらいで子どもを授かるはずがないって。でもね、私は側にいたから知っているよ。蓬助ちゃんは間違いなく御隠居様の子だよ。あの子は何も悪くないのに、いつだって居場所がなかった。お骨になってまで、こんなに邪険にされるなんて」
お梅は涙を拭うと、咲兵衛が縁台に立てかけておいた杖を握った。
「息子が仕事で明後日まで帰ってこないから、頼める者がいなくってね。早く迎えに行ってやらなきゃと思って、家を飛び出してきたんだけどさ。勤めを辞めてから急に足腰が弱っちまって。でも、すぐに行ってやりたいんだよ。たとえ骨になっても、もうこれ以上、あの子に寂しい思いをさせたくない。咲兵衛さん、穏田村に行く道を教えてくれませんか。あっちの方には、行ったことがなくってねえ」
「ここから一里もあるのに、その足じゃ無理ですよ」
叔母を押しとどめて、かめが咲兵衛を振り向いた。
「おまえ様が迎えに行ってやってくださいな。それで、何があったのか、その家の者に直に訊いてきてちょうだい。犬猫の子じゃあるまいし、死んだの一言で済まされる話じゃないでしょう」
かめの瞳が潤んでいる。咲兵衛は、女房の涙を見たくなかった。
「わかった。おれに任せてくれ」
咲兵衛は屋敷から走り出た。蓬助の身に何が起きたのか、この目で確かめなければ――。
一里の道を駆けに駆けて、咲兵衛は穏田村の百姓家に飛び込んだ。先日、顔を合わせた老婆が、囲炉裏端からこちらを見た。相も変わらず目つきが険しい。
「蓬助が亡くなったと聞いたもので……」
咲兵衛が丁重に切り出したのを遮って、老婆の声が尖る。
「あんたが取りに来たのか。骨壺は納屋だよ。持っていってくれ」
預かっていた子どもが死んだというのに、随分とぶっきらぼうな言い方だ。咲兵衛は土間に踏み入って、老婆の横顔を睨み付けた。
「あんなに元気だった子が、なぜ死んだんですか」
自在鉤に下げた鍋に水を差した老婆は、柄杓(ひしゃく)の先を前庭に向けた。
「そこで勝手に死んだんだよ。どこに隠してたんだか、脇差しを持ち出して」
四日前の朝だったという。素っ裸で髪を振り乱した蓬助が、抜き身の脇差しを手に納屋から出てきた。呆然とする家の者を睨(ね)めつけると、刀の切っ先を喉元に当てて、そのまま前のめりに倒れた。手の施しようもなかったそうだ。
「気味が悪い子だったけど、やっぱり魔物に取り憑かれていたんだ。すぐに岡本さんに知らせたが、この村で弔ってくれって銭だけ寄越した。だけど嫌なこった。あんな気持ち悪い死に方をした子を、村の墓場には金輪際入れるもんか。寄越した銭で火葬にしたから、骨を引き取りに来いって、今朝方また使いを出したんだよ」
咲兵衛はふつふつと怒りがたぎった。岡本家の冷淡さもさることながら、この老婆が放つ茨(いばら)のような刺々しい言葉にも腹が立つ。
だが、この婆さんは強がりを言っているだけで、本音は怖がっているのだ――と、咲兵衛は睨んだ。
老婆は、蓬助が魔物に取り憑かれていたと言い切った。きっと、この世ならぬものの存在を信じているに違いない。村の墓場には入れたくないと意地を張るのは、近くに葬ると祟られるとでも思っているのだろう。そんなふうに怯えるのは、心のどこかに弱みがあるからだ。もしかしたら、邪険に扱った蓬助に、後ろめたさがあるのではないか。そうか。それなら、もっと恐れればいい。
「迷惑を掛けてすまなかったな。だが、死んだ者を粗末に扱うのはよくない。骨になっても、魂は見てるもんだよ。ところで、あんた。河童を知ってるかい」
不審そうに振り向いた老婆が、微かに頷いた。
「どんな奴か、聞いたことはあるだろう。なりは小童だが、素っ裸で髪はぼさぼさ。人の腸を食らうから、身体中が血塗れで」
咲兵衛の視線の先が、誘うように前庭へ向く。
「不幸な死に方をした人の子は、河童に生まれ変わって、仕返しをするって言うぜ」
「お、脅すのか」
老婆の声が裏返った。
「信じる信じないは、あんたの勝手だがね。まあ、当面は気を付けるこった。うっかりすると、尻の穴から腸を引き抜かれるぜ。ごぼっとな」
ひいっと悲鳴を漏らして、老婆が尻を押さえる。咲兵衛は目を背けて、母屋を出た。
前庭に騒動の痕跡は残っていない。だが咲兵衛の脳裏には、異様な風体で命を絶った蓬助の有様が、最初に川岸で見た姿と重なって鮮やかに浮かんだ。
自害に使った脇差しは、兵馬の物だろう。形見として、ずっと隠し持っていたのに違いない。だがどうして、素裸で死に臨むのか。
問いながら納屋の戸を開ける。初めてここを訪ねた時のように、文机に頰杖を突いた蓬助が振り返ってくれたら――だが、壁際の文机には、素焼きの骨壺が置いてあるだけだった。その傍らに、土器が一枚。兵馬の腸から出たという黒い砂利石は、もう残っていなかった。
勇気の種だと、蓬助は言った。
兵馬様が死んだら、おれも生きてはいないと誓ったのに、意気地がなくてすぐに後を追えなかった。これを飲むと心が奮う。おれの中に勇気が育つ。だからこれは、勇気の種だ、と。
「その勇気は、生きるためのもんじゃなかったんだな。逝き遅れた時を埋めるために、あの時と同じ格好で死んだっていうのか」
蓬助の真意に思い至らなかった情けなさに、咲兵衛は机を叩いた。
「頼りにしていた佐倉様を亡くしたばかりだったのに、独りにするんじゃなかった。おまえの本心を見ずに、手前勝手な思いやりに浮かれてた間抜けなおれを許してくれ」
咲兵衛は骨壺を両手で引き寄せて、撫でさすりながら手拭いで包んだ。
「さあ、一緒に行こう」
物言わぬ蓬助に語りかけながら、咲兵衛は納屋を出た。
陽の傾きかけた小川沿いの道に、人影はない。千駄ヶ谷で兵馬と会うために、蓬助はこの道を駆けていったのだろう。その幻の後ろ姿を追うように、咲兵衛は歩いていく。
道の先に観音坂下の橋が見えた。咲兵衛は対岸の草むらに目を向けた。
あの日よりも夕日が眩しい。
「佐倉様が待っているよ」
咲兵衛は骨壺を開けて、遺灰を一つまみ取った。向こう岸に面影を追いつつ、手を開いて白い灰を風に乗せる。蓬助の生きた象徴(しるし)が、川霧のように流れて消えた。