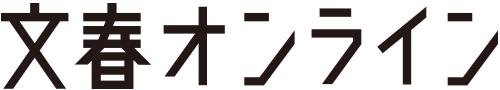『情熱大陸』(MBS・TBS系)や『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ系)など、数々のドキュメンタリー番組を手掛けてきた、映像作家の大島新氏。そんな彼が『ドキュメンタリーの舞台裏』(文藝春秋)を上梓した。
ここでは、同書より一部を抜粋して紹介。大島氏は、フジテレビ時代に“過剰演出”を経験。複雑な思いを抱きながら番組を制作していたのだが——。(全2回の1回目/2回目に続く)

◆◆◆
なぜフジテレビを辞めたのか
時間を少し巻き戻します。入社4年目、1998年に、ゴールデンタイムの情報バラエティの仕事をするようになってから、テレビの仕事そのものはともかく、自分が「テレビ局の社員」でいることは難しいかも知れないな、という思いが日に日に強くなっていきました。その理由は、私が世の中の少数派である、ということに尽きます。好きなことや興味があることはマイナーなジャンルが多く、大ヒットドラマやバラエティには、ほとんど関心が持てませんでした。(付け加えると、選挙で自分が投票した人は勝ったためしがありませんでした)
マスメディアであり、営利企業でもある民放テレビ局は、多くの人に観てもらわなければ商売あがったりです。高給を得ている社員ならばなおさら、会社の売り上げにも貢献しなければなりません。それならば、深夜のドキュメンタリーよりも、ゴールデンの情報バラエティで役に立つことが重要です。
担当した番組が週刊誌に「やらせ疑惑」と取り上げられる
私が担当した金曜20時放送の情報バラエティ番組『ウォンテッド‼』(1998年4月~1999年3月)には、苦い思い出があります。同番組はもともと1週間の出来事を振り返る生放送の情報番組として始まったのですが、視聴率が振るわなかったために企画内容が変わり、途中から生放送ではなく収録の番組になりました。
そしてある時期から、世の中の様々なダメな人や悪い人を取材し、その本人をスタジオに呼んで(顔はわからないようにすりガラス越しの出演)、ご意見番の芸能人が叱りつける、という内容に変わっていきました。企画の内容は番組の上層部が決めていて、私たち若手スタッフはその方針に従うだけでしたが、おそらく視聴率対策だったのだと思います。
今の基準ならば、コンプライアンス的に問題あり、とされてもおかしくないような番組でした。やがて番組は過激化していき、週刊誌には「やらせ疑惑」の記事が載りました。スタジオ収録はフジテレビ社内班が担当していましたが、VTRは外部の制作会社が取材して納品することもありました。
局のプロデューサーの要望に応えるために、取材現場で無理が生じた可能性は否定できません。バラエティの基準ならば「演出」の範囲に入る手法だったのかも知れませんが、私には少なくとも「誇張」に思えましたし、ものによっては「捏造」に近い表現もあったのではないかと思います。
作りたかった人物ドキュメンタリーと真逆の仕事をこなす日々
私自身が取材したVTRの中にも、編集で「盛りに盛って」放送し、電話による抗議や苦情が寄せられたこともありました。今なら、同番組は毎週のようにSNS上で炎上騒ぎになっていたでしょう。それでも、いや、だからこそ、視聴率は向上していきました。チーフプロデューサーは、抗議や苦情に動揺する若手を鼓舞するためだったのでしょうか、「“悪名は無名に勝る”と言うんだよ」と、番組の方向性の正しさを説いていました。
私が作りたかった人物ドキュメンタリーは「世の中には知られざるすごい人がいる」とか、「こんなにかっこいい生き方がある」といった方向、つまりポジティブに人間を捉えることでした。そして放送によって、観た人の心が前を向く方向に動いたり、何かの行動のきっかけになるようなドキュメンタリーを作りたい、と思っていたのです。
ところが、やっていることは真逆でした。「世の中にはこんなに悪い奴がいる」とか、「こんなにダメな人間を懲らしめてやる」といったことを世に伝える番組のスタッフとして、寝る暇もないほどに働いていたのです。こんなことが我が身に降りかかったのは、自分が会社員だからでした。それでも、いつかまたドキュメンタリーを作るチャンスは来ると信じて、何とか日々の仕事をこなしていました。

コンペで選ばれていた企画がボツに
「あの企画を君にやらせることは出来なくなった」
退社の引き金は、FNSドキュメンタリー大賞という枠で、私の企画が一度は通ったのに、紆余曲折を経てボツになったことでした。FNSドキュメンタリー大賞とは、フジテレビ系列の全国のテレビ局(28局)が、年に1本ドキュメンタリーを出品し、審査を行って大賞や特別賞を決めるという試みで、今も続いています。放送は深夜ですが、作り手にとっては候補作に選ばれるだけでも栄誉なことです。
フジテレビでは、若手を中心に企画のコンペがありました。1999年のフジテレビの候補作には、私が提出したあるマイノリティ集団の若者たちを追う企画が選ばれ、取材のGOサインが出ました。ところがその決定のわずか2日後に、当時の部長に「あの企画を君にやらせることは出来なくなった」と告げられたのです。
理由は、打ち切りが決まっていた『ウォンテッド‼』の後継番組のスタッフとして必要だから、ということでした。それも、ロケのディレクターではなく、3週に1本回ってくるスタジオの演出を担当させたい、という話でした。
新番組のスタートは1999年の4月でしたので、私は入社5年目。そのキャリアでゴールデンタイムのスタジオ演出を担当するのは、「抜擢」と言われてもおかしくないポジションでした。しかしそれは、ドキュメンタリー制作を断念することと引き換えでした。
民放キー局の現状は充分わかっていた
部長には「もう大島は深夜で何か月もかけてドキュメンタリーを作るようなポジションではなく、ゴールデンのレギュラーで会社に貢献してほしい」と言われました。加えて、テレビ局員に必要な経済感覚の話も出ました。平たく言えば、深夜のドキュメンタリーは給料に見合っていない、ということです。
この時私は、部長が言っていることは正しく、ドキュメンタリーを作りたいと思っている私がこの会社にいる方が間違っている、と感じました。
実はその時までの4年間で、民放キー局のそうした現状は充分わかっていたのです。ドキュメンタリーを現場のディレクターとして作れるのは、若い時期の「経験値」として、せいぜい2~3本で、その後は違う形で会社に貢献しなければならない。
日常的にドキュメンタリーに携わるとしたら、プロデューサーになるしかなく、実際に現場で取材して制作を担当するのは制作会社のスタッフやフリーのディレクターでした。
今でも『ザ・ノンフィクション』や『情熱大陸』は、局内で制作しているのは1割程度、9割がたは外部制作です。(NHKと、民放でも地方局は事情が異なり、キャリアを積んでもディレクターを続ける人もいます)

森達也監督『A』の衝撃
レギュラー枠の局のプロデューサーは、企画の選定や番組のクオリティ管理など、重要な役割を務めますが、現場で取材をするわけではありません。
そして私は4年間で、制作会社所属やフリーの立場で、ドキュメンタリーを作り続けている何人もの先輩ディレクターたちの活躍を見てきました。映像ディレクターの中村裕さんもそうでしたし、約20年後に『ぼけますから、よろしくお願いします。』でご一緒することになる信友(のぶとも)直子さんもその1人でした。
そうした先輩ディレクターたちの仕事の中で、私にとって決定的だったのは、1998年に公開された森達也監督のドキュメンタリー映画『A』でした。当時のBOX東中野(現在のポレポレ東中野)で『A』を観たときの衝撃は忘れられません。大げさでなく、上映後に椅子から立ち上がれないほどでした。
入社した1995年から、テレビ局の内部でオウム報道の洪水の中にいた者として、オウム真理教を独自の視点で描いたことはとにかく驚きでした。教団の内側に入って撮った森さんのカメラには、たくさんの報道陣の姿が映っていました。
私はオウム取材の現場には行っていませんでしたが、スクリーンに映し出された報道陣を見て「これはおれだ」と思わずにいられませんでした。『A』については別の章で詳しく記しますが、私はフジテレビにいる限り、こうしたドキュメンタリーを作ることはできない、と思わずにはいられませんでした。
会社に辞意を伝えた翌日に、妻の妊娠が発覚
私自身のマイナー志向、会社の経済の論理、外部のディレクターの眩しい活躍……。様々な要素が絡み合って、もう辞めようと決心しました。あとはタイミングでした。新番組が既に進行していたのと、短い期間とは言えたくさんの方にお世話になったので、気持ちを伝える時間も必要と考えました。ちなみに妻は「あんたの好きにしたらええわ」(香川県出身の讃岐弁です)と大らかなものでした。
そうこうするうちに、新番組が視聴率不振で2クール(6か月)を待たずして8月で打ち切り、ということが決まりました。もうこのタイミングしかない、と思い、そのことが決まった6月末に部長に辞意を伝えました。6月末は、ちょうど会社の人事異動のタイミングでもあったからです。番組が終わる8月の半ばまでは仕事をまっとうし、退社の日は8月31日に決まりました。

劇的だったのは、会社に辞意を伝えた翌日に、妻から「妊娠したで」と言われたことです。あまりのタイミングに、喜びととまどいが相半ばしました。
多くの人に「ドキュメンタリーは食べていくのが大変だぞ」と言われていたのですが、夫婦共働き(当時妻は広告デザイン事務所に勤めていました)なら何とかなるだろう、くらいに軽く考えていたのです。ですから、妻の妊娠が先にわかっていれば、躊躇したかもしれません。
でもその順番だったので、退社の決断も間違っていないのだろう、と思い直しました。ありがたいことに熱心に慰留してくれる人もいましたが、気持ちは変わりませんでした。私は誕生日が9月なのですが、30歳になる2週間前の1999年8月31日に、フジテレビを辞めました。
映像作家・大島新が明かす、秋元康が『情熱大陸』の取材で見せた“本当の顔”「秋元さんに良い印象を持っていなかったが…」 へ続く