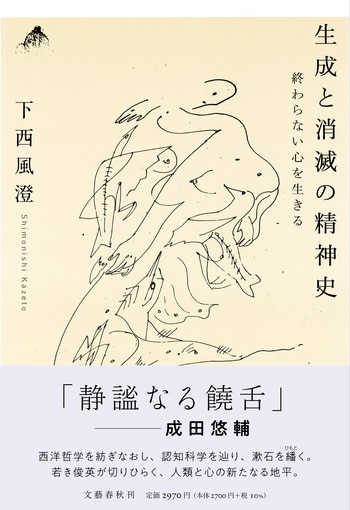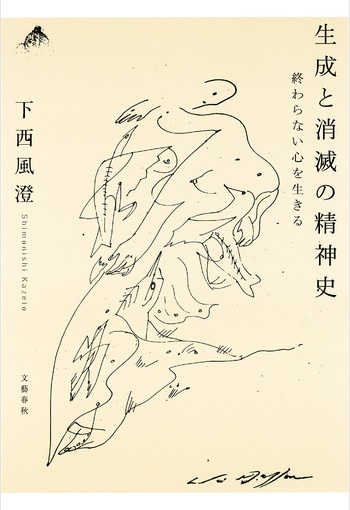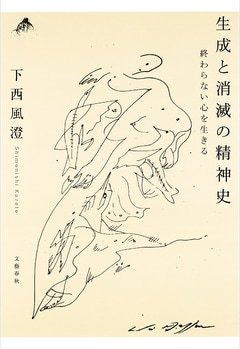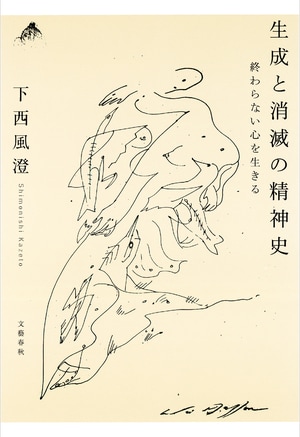
心の三千年史を考察した『生成と消滅の精神史』を上梓した下西氏と心と脳の問題を探究してきた山本氏・吉川氏が、AIやインターネットに翻弄される心の行方を語り合った。
■「心」は発明された
山本 今日は下西風澄さんの新著『生成と消滅の精神史 終わらない心を生きる』(小社刊)をめぐって下西さんに、吉川浩満くんと私の二人でお話を聞きたいと思います。まだお読みになっていない方もいるかと思いますので、はじめにこの本の全体像をお伝えしましょう。本書のテーマは「心」です。ただし、一口に「心」と言っても、いつでもどこでも同じように捉えられてきたわけではない。歴史的に変化してきたものです。下西さんはその変遷について、「第I部 西洋編」では主に哲学の歴史から、画期となる部分を取り出して精密に読解する。なぜ哲学かといえば、近代に心理学などが登場する以前、人間の心や精神について検討していたのは哲学だったからです。また、「第II部 日本編」では、日本の古代から近代に至る心の捉え方を、これまたポイントを押さえて案内してくれます。そういうわけで、本書を読むと、日頃は自明に思えるかもしれない心の見え方が変わると思います。
では、先に吉川くんから感想をいただいて、それから下西さんのお話をうかがいたいと思います。
吉川 序章で下西さんが表明するのは、ミシェル・フーコーの「人間の発明」に準えて、心もまた「発明」されたものとして見るということです。つまり、心が普遍的にいつでもどこでも存在するものとは考えない。だから問われるのは、その本質とは何か? ではなく、それはどのようなものと考えられ、語られてきたのか? ということになります。そして、その「発明」について、従来の哲学的な論証のスタイルではなく、メタファーとイメージの変化を追うスタイルでやっていくのだ、というモットーが示される。読みながら思い起こしたのは、レベッカ・ソルニットの『ウォークス 歩くことの精神史』(左右社)です。あちらはソルニットが「歩くこと」をめぐって、比喩的な意味で歴史のなかを歩き回る本です。この本では、下西さんが「心」のイメージとメタファーをめぐって、下西さんなりの道筋で、西洋と日本の歴史のなかを歩き回ったんだな、という感想を私は持ちました。
山本 重要なポイントを指摘していただきました。心には直に知覚できるような形がないので、言葉で捉えるにも譬え話をするしかないんですよね。その譬え方の変遷に下西さんは注目されていると言ってもよいかもしれません。下西さんは、大学院で哲学を研究されたとうかがっています。本書に結実することになるテーマについては、以前から温めてきたのでしょうか。
下西 そうですね。もともと僕は大学院の博士課程にいて、心――自然科学の領域では意識――について哲学的に考えるとともに科学的に考える研究に取り組んでいました。そのなかで、どうしてもこれは歴史性の問題として考えなければならないと思い始めました。先ほど吉川さんにもおっしゃっていただきましたが、私たちが「心」として思い描いてきたものは、時代や場所によって異なるのだから、心の「本質」や「本性」を探究するのではなく、私たちは心をどのようなものとして、あるいはどうあるべきものとして、考えてきたのかを考察しなければならないと。普通は百年、二百年ぐらいを遡ってみるのでしょうが、僕は執念と無謀で三千年ぐらいを遡り、歴史的に見ていくことにしました。その出発点には、現代では心には、あまりに過剰な仕事が担わされているのではないか、という直感がありました。心は外界の溢れかえる情報を適確に処理し、自分の感情や身体を統御し、合理的に真偽や善悪を判断し、意思決定をすることを常に求められています。僕の本で書いたように、すでにソクラテスが心をそのような仕事を担うものとして発明していたのですが、現代にあっては、心に求められる仕事の量が増え、その精度も高くなっている。現代人はみんな文字の読み書きができて、高度な思考能力を備えていて当然と思われていますし、インターネットと常に接続していて、膨大な量の情報が入ってきます。そのような環境では、心の仕事は増える一方です。つまり、現代の技術的・社会的な環境が、私たちに心の過剰な能力を要求する一方で、私たちの意識はそれに対応しきれていないのではないか。でも、心にここまで過剰な仕事が背負わされていなかった時代も当然あったはずで、その時代まで遡ってみることで、心について一から考え直す作業が必要なのではないか。心が過剰な仕事を荷下ろしできる道筋はないか。そんな問題意識から出発しました。
山本 物書きの立場から見ても、これだけの文献を集め読み解き、これだけの文章を書くのは尋常なことではありません。一見さほど分厚くないように見えますが、実際には五百ページ以上ある。書いている途中で逃げたくなりませんでしたか(笑)。
下西 逃げたかったです(笑)。実は、さらに二章分の原稿がありまして。書いてはみたものの、本の主旨がわかりづらくなるので削ったんです。
山本 なんと! そのお話もぜひ後で聞かせてください。この本は書き下ろしですが、どんなふうに書き進められたのでしょう。
下西 大学院の博士課程で研究している時代は、論文を書くのと同時に詩を書いたりと、いろんなことをやっていたんですが、その間も十年ぐらいこういうことをずうっと考えていました。当然それは大学院の研究スタイルには合わなかったですし、論文の形にならないようなことばっかりを考えたかったので、博士課程をやめてから執筆を始めました。ですから、実際の執筆期間は五年ぐらいです。家にひきこもりながら、月に一、二回ぐらいしか人と会わずに延々と何かを読んで何かを書く、みたいな洞穴生活を続けて、五年ぶりに顔を上げたのが、今、という感じです(笑)。
山本 内容もさることながら、書き方もなかなか聞いたことのないスタイルですね。本全体の構成は、書き始める前に固めてからとりかかりましたか。
下西 最初に目次を作る作業に一年ぐらいかけました。まず大まかな流れを作り、それに沿うように書いていきました。第I部では、古代ギリシャのホメロス、ソクラテスから始まり、デカルト、カントといった近代の哲学者を経由して、フッサールやハイデガーといった二〇世紀の哲学者に至ります。そこまでは普通だと思うのですが、その先の認知科学の時代に入ったところで、フランシスコ・ヴァレラという二〇世紀後半を生きたチリ出身の神経生物学者を論じ始めます。ここが難しかった。超大物哲学者たちの後によくわからないチリの変な科学者を入れるというのは、だいぶ無理をしていますからね(笑)。そこを自然に見せるための工夫をだいぶ凝らしましたが、意外とみなさん自然に読んでくださったみたいで、よかったなと思っています。
■西洋編と日本編にした理由
山本 さて、改めて内容についてうかがって参りましょう。本書の第I部は西洋編でした。古代ギリシャのホメロスでは、現代とはかなり違ったかたちで心が捉えられていた。下西さんの表現をお借りすると「特定の場所をもた」ず、風のように「世界に遍在して分散されたもの」だった。それに対して紀元前五世紀から四世紀頃のソクラテスになると、心はひとつの統一体として捉えられるようになる。しかも心は肉体を管理する働きをもつと考えられます。
では心にはどのような機能が備わっているか。これが探究すべき課題となる。このご本ではデカルトとパスカルの例を検討した後で、ひとつの頂点のような存在としてカントが登場する。カントにおける心は、感性や悟性、構想力といったファンクションから成る。ただし、そうした機能には限界もあることをカントは指摘している。面白いことに下西さんは、カントによる心の捉え方をコンピュータに喩えていて、これは腑に落ちる論じ方だと思いました。
あとはこのモデルがどんどん精緻になっていく、というストーリーかと思えば、話は思わぬほうへ進みます。現象学を提唱したフッサールや彼に学んだハイデガーの議論では、カントで輪郭がくっきりしたように見えた心が、むしろ形を失って環境のなかに綻んでゆく過程が描かれます。さらにはヴァレラやメルロ=ポンティを参照して、身体を通じて環境(世界)とやりとりをするものとして心が捉えられるに至る。
そこから第II部の日本編に繋がっていきますね。日本では西洋のようにカチッとした概念で心を把握するというのとはまた違うあり方があった。『万葉集』や『古今和歌集』などの詩歌にあらわれる心、あるいは近代において心を文学と科学のあいだで捉えようとした夏目漱石の話も出てきます。まずお聞きしたいのは、なぜこの「西洋編」と「日本編」の二部構成になったのか、ということです。
下西 心の歴史を語るうえで、歴史には複数の時間が流れているという考えを強調したかったからです。本のなかでも触れていますが、西洋では一本の線で歴史がつながっているという価値観が非常に強いですよね。
山本 ヨーロッパのキリスト教的な時間の感覚によれば、神の一手目によって宇宙が始まり、そこから終末へと向かっていく、一本の時間の流れがあります。
下西 西洋編だけでは、どこか一点に僕たちは向かうというような歴史観を反復してしまうんじゃないか。そこに日本編をぶつけるというヘンなことをすることで、歴史の流れを複数化する。あらゆる場所で、あらゆる速度で、あらゆる時間が流れている、という感覚をわかりやすく再構築したかったんです。
吉川 その構成はすごく重要だったと思います。心という、あるんだかないんだかわからないものを相手にすると、すぐに思考が抽象化してしまって、つい単線的なものの見方になってしまうところがありますからね。西洋に対置するものとして日本が選ばれ、日本における心や意識の変遷が紡がれていくことで、ものの見方が複数化する。今回の本であれば、日本だったけれども、他の可能性がいくつもあるはずで、それはこの本を通して、読者がいろいろ見出していくところかな、と思います。
山本 私はこういうとき、つい「中国ではこう、インドではこう、アフリカではこう」と博物学的に並べたくなります。でも、下西さんの目的に照らせば、そうする必要はない。西洋的な心の捉え方の変遷に対して、日本の例を脇に置けば、それで十分複線化できる。読者はこの本を中心に置いて、そこに自分の経験や知識を並べていくという楽しみ方もできますね。
吉川 例えば、心理学を専門に勉強している人だったら、心理学の歴史におけるその人なりの『生成と消滅の精神史』ができると思うんですよね。そういうふうにして、この本を出発点にいろんなことが考えられる。
下西 この本を読んでくださった方から、「フロイトはいないの?」とか「精神分析系はどうなっているの?」という感想をもらいました。それもやったほうがいいのかなぁという思いにも、ちょっとなったんですが、そうすると、僕は生涯かけて永遠にこの本を書き継いで書き足して、全二十巻ぐらいのものを書かなければならなくなる(笑)。あくまでこの本は、心の歴史の一つのサンプルなんですよね。恣意的と言ってもいいような、僕個人が見たかった歴史です。でも、そこにはまた、別の必然性があるんですが……。