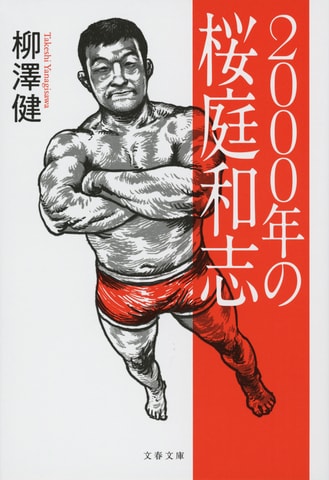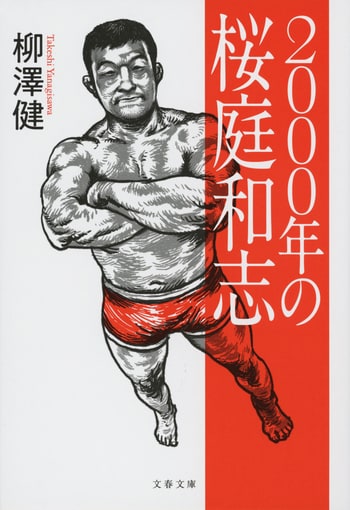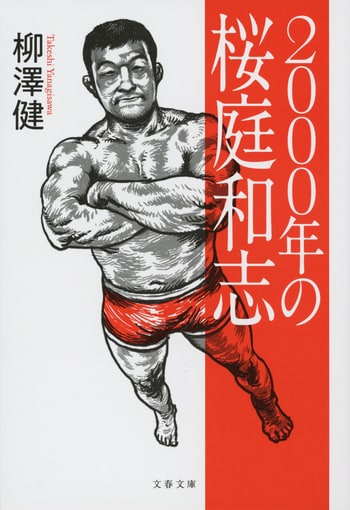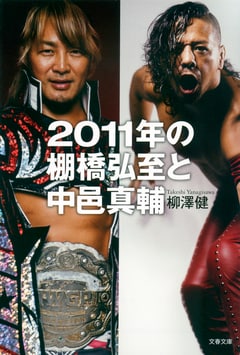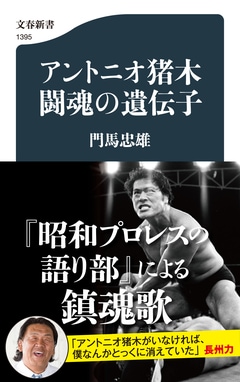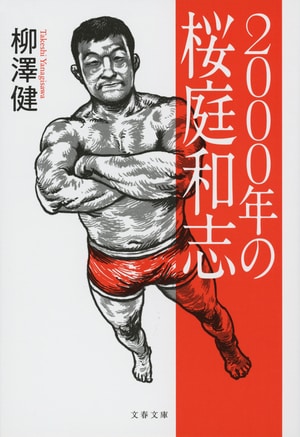
本書は文藝春秋から上梓された『1976年のアントニオ猪木』、『1984年のUWF』に続くプロレス格闘技三部作の最終巻『2000年の桜庭和志』の文庫化である。
2007年に出版された『1976年のアントニオ猪木』は、文藝春秋で『スポーツ・グラフィック ナンバー』の社員編集者であった柳澤健がフリーとなり、47歳にして作家デビューを果たした作品だ。
1998年4月の猪木引退試合以来、熱心な猪木信者であるボクは『アントニオ猪木自伝』(新潮文庫)を大量に買い込み、ホテルへ泊まるたびに引き出しの『聖書』とすり替えるという急進的な布教活動に励んでいたのだが、『1976年のアントニオ猪木』の登場は猪木信者にとっての『新約聖書』を思わせるほど衝撃的で、ボクにとっては生涯のベストノンフィクションとなった。
『1976年のアントニオ猪木』は、猪木が70年代に闘った一連の異種格闘技戦のファーストシーズンである「1976年」に開催された4試合に焦点を当てている。
猪木はなぜ、純然たるプロレスを離れて格闘技路線に走ったのか? その根本的動機とは終生の敵であるジャイアント馬場を打倒するためだった。そのため「プロレスとは最強のキングオブスポーツだ!」「いつ何時、誰の挑戦でも受ける!」という教義=猪木イズムを掲げ、仮想敵、外敵をプロレスのリングで迎え撃つという構図を作り上げた。
〈2月・ミュンヘン五輪、柔道無差別級と重量級の優勝者・ウィリエム・ルスカ戦〉
〈6月・プロボクシング世界ヘビー級チャンピオン・モハメッド・アリ戦〉
〈10月・アメリカで活躍中の韓国人プロレスラー・パク・ソンナン戦〉
〈12月・パキスタンで最も有名な英雄でプロレスラー・アクラム・ペールワン戦〉
普通の書き手ならば、誰もがボクシング現役ヘビー級世界王者・モハメッド・アリ戦が行われた6月の「格闘技世界一決定戦」を本筋にすることだろう。なにしろ、世界格闘技史の特異点として、今なお内外で再評価されている一戦なのだから。しかし、柳澤は違った。アリ戦だけではなくアリ戦前後の海外試合の舞台裏を、アメリカ、韓国、オランダ、そしてパキスタンにまで足を延ばして、関係者に徹底取材したのだ。
猪木はプロレスをリアルファイトと思い込んでいた世界最強の柔道王のルスカには契約書通りにプロレスを履行させ、異国、東京での負け役を強いることに成功した。
次にモハメッド・アリとの世紀の一戦は、エキシビションと思って来日したアリ陣営に対し、猪木ひとりだけが最後までリアルファイトに固執した。ルールは試合当日まで紛糾し、リング上では「猪木―アリ状態」と呼ばれる退屈な膠着状態が続き、15Rを経て消化不良の引き分けに終わる。当時は世紀の大凡戦、茶番劇として世界で嘲笑され、しかも10億円を超える莫大な借金を背負う羽目に陥った。
韓国遠征では、プロレスのつもりで挑んできた格下の韓国のプロレス王、パク・ソンナンに、猪木が負け役になるという筋書きを拒否。掟破りのガチンコ(リアルファイト)を仕掛け、相手の目に指を入れるほどの死闘の末に勝利。結局、エースを木端微塵に潰された韓国プロレス界は崩壊に追い込まれてしまう。
観光気分で妻・倍賞美津子と訪れたパキスタン遠征では、逆に地元の英雄・ペールワンから急遽リアルファイトを挑まれることとなった。猪木は実力で大きく上回るにもかかわらず、再び相手の目に指を入れる反則技まで繰り出し、相手に噛みつかれると、ついに腕を脱臼させるという凄惨な試合の末に勝利を収めた――。
オランダと日本のプロレス界を結ぶ柔道界の猛者、ルスカ、ヘーシンク、ドールマンの三竦みの人間関係、日本の力道山時代を彷彿させる官民一体となった韓国プロレス史の変遷、まるでアラビアンナイトの怪人かのようなパキスタンのプロレス一族の流転など、現地取材はそれぞれが各国の比較文化論として一冊の本になるほど濃密だ。
共通するのは「自国開催の選手が勝つ」というプロレスの不文律を猪木が破棄したことだ。
本来、プロレスとは、肉体の強靭さや華麗な技を競い合いながらも、勝敗だけは予め決められている、ただし選ばれしプロフェッショナルによる命懸けのショービジネスなのだ。
この前提のなか、ルスカ戦を除く1976年の3試合だけが、長い猪木の現役生活のなかでリアルファイトであったと著者は断言する――。
『1976年のアントニオ猪木』は、村松友視の著書『私、プロレスの味方です』(1980)という始発駅から旅立ち、井上義啓編集長の『週刊ファイト』、ターザン山本編集長の『週刊プロレス』と乗り継いで「活字プロレス」という巨大な幻想空間の中を、車窓に聳え立つ猪木山脈、いや蜃気楼を追い続けた昭和のプロレス者にとっては因果鉄道の終着駅でもあった。
中央公論社で文学誌の編集者であり、後の直木賞作家となる村松友視が文藝の香り漂う演劇論的手法で、その虚像の輪郭を作った猪木という名のイリュージョン。その幻想をライターのキャリアの初期に『ぱふ』という雑誌名のファンタジーの匂い漂うマンガ批評誌の編集者であった柳澤健が『ナンバー』編集部に転じ、調査報道に徹し、地を這う取材を経てルポライティングという手法で幻想の実像を検証してみせたのだ。
それは「底が丸見えの底なし沼」「虚実の被膜」「闘いのメビウスの輪」などなど……修辞を練り尽くし、メタファーを駆使して、勝負論だけは曖昧模糊にしてきた活字プロレスの向こう側だった。
最強は短い、人生は長い――。裸一貫で世界を渡り歩き、現役を退いても虚像も実像も世間に晒して、あらゆる毀誉褒貶に受け身を取り、リアルもフェイクも織り交ぜながら人生の力比べを続けるプロレスラーの儚さ、そして強さに我々は惹きつけられるのだ。
単行本出版後、文庫版の『完本 1976年のアントニオ猪木』(2009)では、ボーナストラックとして猪木本人が著者のインタビューに応じている。猪木は単行本執筆時には取材依頼を受けることはなかったのだが……。
さて、百戦錬磨のプロレスラーは気鋭のルポライターにどう対峙したのだろうか――。
その後、ボクは著者と面識を得たが、会うたびに「次回作には前田日明を!」というリクエストをぶつけたから、2017年に刊行された『1984年のUWF』は、ボクにとって待望久しい作品だった。
だが、タイトルは個人名ではなく団体名のUWF。UWFの中心人物は前田日明だが、著者はUWF関係者のなかで前田にだけはあえて話を聞かないまま、この作品を完成させた。もちろん雑誌連載時から論議を呼んだのは言うまでもない。著者曰く、「UWF史は今までに前田が語ってきた前田史観で確立してきたから、そこは避けて描く」と。この人物ルポライティングの手法は、かつてゲイ・タリーズが描いたフランク・シナトラやデイヴィッド・ハルバースタムが描いたマイケル・ジョーダンなどニュージャーナリズムのジャンルを切り開いてきた成功例はあるのだが……。前田は無類の読書家として知られ、強烈なエゴイズムと誇り高きダンディズムが共存する名うての論客だ。かつて沢木耕太郎、村松友視をこき下ろした過去もあるだけに著者のその大胆不敵さに驚いた(ちなみにボクは前田の兵隊〈マニア〉なのでこの作品は、私見では反前田史観過ぎるところがあるのも前田の名誉のためにあえて付記しておきたい)。
『1984年のUWF』は「プロレスは最強の格闘技である」との教義を最初に猪木に授けたプロレスの神様・カール・ゴッチの逸話から始まる。このゴッチ直伝の猪木イズムに最も影響を受けたのは佐山聡だった。結論として、佐山聡は猪木を越えるプロレスの天才であり、そして格闘家としても日本の総合格闘技のプロ化の先端を走っていた。ただし、長年に渡って正当な評価を得ることはなかったのだが……。
1981年に新日本プロレスに登場したタイガーマスク(佐山聡)は、たちまち4次元殺法で日本中を熱狂させたが、わずか2年4カ月で引退。その佐山がスーパータイガーとして復帰したリングこそが旗揚げ間もない「1984年のUWF」=「第一次UWF」であった。若き前田日明をエースとする猪木の使徒(弟子)たちが旗揚げした新団体は教祖・猪木に「捨てられて」迷走していたが、佐山が考え出した脱プロレスの先鋭的なルール、格闘技を重視した過激なスタイルによって一部に熱狂的なファンを生んだ。だがまもなく、すでにシューティング(のちの修斗)を構想してプロレスの完全格闘技化を目指す佐山と、選手およびスタッフの生活、団体の運営を最優先する前田との対立がリング上でも表面化する。やがて佐山が団体離脱すると、資金繰りに行き詰まり一度は母体・新日本に吸収されたものの、1988年、再び新生UWFとして旗揚げし、格闘プロレスを謳って一躍大ブームを作り出す。ところが1991年、人気絶頂時に団体は内部分裂、三派に分かれて歩むことになる。U系団体はそれぞれに「最強」を標榜した。だが1993年にUFC、K−1、パンクラスが誕生したことでマット界全域の相転移が起こり、フェイズは一気に変わった。「最強」の最前線にブラジルのグレイシー柔術が名乗りを上げると、猪木の使徒たちは実力の証明を迫られる。髙田延彦vsヒクソン戦のためPRIDEが誕生、やがてMMA(総合格闘技)=真剣勝負が隆盛を誇るようになる。猪木の直弟子である髙田がヒクソンに連敗、船木誠勝もヒクソンに敗れた。プロレスラーは次々と格闘技の生贄となったのだが、世界の格闘技シーンをリードし、興行の人気を支え続けたのが日本のプロレスラーであることも紛れもない事実であった。やがてプロレスを引退した、アントニオ猪木も髙田延彦も前田日明も総合格闘技団体のアイコンとなり、リング上の要職をつとめるようになる。
PRIDEで「元気ですか‼ 123ダー‼」と御託宣を唱えるだけで、会場に大熱狂を呼びおこす猪木は、プロレスと格闘技という、本来、異教の教義と競技を串刺しにする、新時代のコロシアムを司祭するシャーマンそのものであった。
Uの時代――。ファンはこの小さな団体の見果てぬ夢に想いを馳せ、共同幻想に酔った。ボクが上京した年が1981年、以降、旧、新生、分裂後のU系団体には足繁く通い、ファン同士、『週刊プロレス』を握り締め、熱く議論を闘わせたものだ。約束の地を求め、傷つけ合いながら集合離散の挫折を繰り返す若武者たちの姿の虜になったからだ。
この一冊は佐山聡の弟子で柔術家の中井祐樹の最後の言葉で締めくくられる。
「日本の格闘技はプロレスから生まれた。(中略)過去を否定するべきではないと思います」
虎のマスクを被り、グローブを嵌めた悲運の天才・佐山聡の表紙を手に取るたびに、感傷的な気分に浸る――。
そして三部作の最後が2020年に出版された『2000年の桜庭和志』。本書である。
荒涼たるプロレスの大地に現れた新たなる救世主の物語だから、三部作で一番作風が明るい。だが、そもそも「プロレスは最強の格闘技」という猪木イズムの十字架をUWFインターナショナルの桜庭和志が背負うとは、専門筋でも想定外だったと思う。
UWFインターナショナルでは前座レスラーに過ぎなかった桜庭が、一際輝き出すのは1997年の12月のアルティメットジャパン大会である。この日、代役で出場し、レフリーの誤審もありつつ優勝した桜庭がリングで発した「プロレスラーは本当は強いんです!」は今なおプロレス史に残る名言として語り継がれている。しかし、その最終証明でもあるホイス・グレイシー戦に至るまでには3年の月日と9試合の無敗街道が必要だった。その間、体重差を無視した理不尽なマッチメイクも拒まず、無差別級でリアルに勝ち続けることがどれほど奇跡的なことであったか、本書で仔細に辿れば自明だろう。
しかし、なぜ、日本人ファイターで桜庭だけがいち早くMMAファイターとして仕上っていたのか? じつは桜庭のバックグラウンドはプロレスばかりではなかった。
学生時代のアマチュアレスリング/プロレス道場でカール・ゴッチ由来のサブミッション/Uインターでのムエタイのキック/出稽古に来たエンセン井上から学んだブラジリアン柔術/桜庭はこれらを組み合わせて自分のファイティングスタイルをほぼ独力で構築した。しかも、桜庭が「僕はアスリートであると同時にプロレスラーです」と語るように、格闘家として勝負に結果を出すだけでなく、プロレスラーの矜持で、対観客を意識して魅せる試合を毎回、披露することで世界でも他に類のない総合ファイターになったのである。
猪木の第二の故郷ブラジルから来航し、日本の格闘技界の黒船となったグレイシー柔術は、元を正せば日本を起源とする武道である。1951年、ブラジル遠征に訪れた柔道の鬼・木村政彦のキムラロック(後の桜庭の必勝技)で御大・エリオ・グレイシーが敗れた、その手痛い教訓がグレイシーたちの柔術をさらに進化させた。猪木一家がブラジルに移住する6年前のことである。20世紀半ばに日本発祥の柔術をブラジルで発展させた一族が、20世紀末にブラジル移民である猪木のプロレスの弟子たちをリングで葬り続けた。この因果がなければ、ここまで文脈のある大河ドラマは生まれなかったであろう。半世紀を経て因果は巡るのだ。
グレイシーはルールの押しつけや銭ゲバ交渉ぶりで日本では憎まれ役にもなっていたのだが、著者は、セルフディフェンスという哲学、地球の裏側で密かに発展を遂げた秘伝の武道の歴史を丁寧に紐解き、自らも柔術道場に入門し、いにしえの誇り高き剣豪一門を描くかのように深い敬意を払っている。
桜庭もホイスも、それぞれが一門の若大将として、実力で舞台の主役となったのだ。
当時、ボクは「SRS」という格闘技番組のレギュラー出演者だったおかげで、幸いにもPRIDEのほぼ全試合をリングサイドで生観戦することができた。ボクの史上最高のベストバウトも2000年の桜庭vs ホイス一択だ。トーナメントにも関わらず、この試合だけ特例で15分×無制限ラウンドルールが採用され、実際に我々もカブトならぬオシメを締めて試合を見守った。グレイシー・トレイン vs 桜庭マシーン軍団のファンタスティック過ぎる入場のプロレス的圧倒的高揚感から魂を鷲掴みにされ、計107分、いつ果てることのない射精中絶が続く官能的な緊張感、背後には歴史的格闘ロマンを秘めた美しき運命の一騎打ちは史上最高の一大スペクタクルであった。
試合中には幾度も「猪木―アリ状態」が出現した。寝た猪木と立ったアリが対峙するという見慣れぬ状態を観客は退屈とみなしてブーイングを浴びせ、メディアは膠着だと酷評した。だがボクの目の前では、「猪木―アリ状態」のホイスと桜庭が東京ドームを興奮のるつぼに叩き込んでいるのだ。1976年から綿々と流れる総合格闘技の変遷、MMAの技術の向上、そこへ挑み続けた選手たちの試行錯誤の姿が頭の中に次々に浮かび、想い出が波のように押し寄せてきた。
本書を読めば、あの歴史的な試合の興奮を追体験できるだろう。
2000年代のPRIDEは格闘技の中心地である日本に、世界中から最強の戦士を集め、世界に向けて発信するという世界最高のプロモーションであった。
そして、このPRIDEという異種格闘技戦の源流、大河の一滴となったのはあの日のアントニオ猪木であり、過渡期のバトンを繋いだのが在りし日のUWFの戦士たちだ。
プロレスのリングでリアルファイトを望んだアントニオ猪木。リアルファイトのリングで観客に向けてのプロレスを提供した桜庭和志。ともに時代を超えリスペクトされる勇者であるのは間違いない。
2023年、54歳を迎えた桜庭和志は、今も現役のプロレスラーとして戦っている。
本書でも紹介された桜庭が考案した寝技イベントのグラップリング大会「QUINTET」は、今年9月に5年ぶりに開催が決まり、桜庭の長男の出場が発表された。大会のスーパーバイザーに就任したのは前田日明だった。
日本のプロレス格闘技は旧世代から新世代へと確実に受け継がれていく。
2022年10月1日、アントニオ猪木の訃報が世界を巡った。
柳澤健が書き綴った三部作には「アントニオ猪木」というモチーフとテーマが鎮魂歌のように繰り返されている。
時代を経て書物で追体験する読者にとって、猪木の残した膨大な功績のなかのひとつは「2007年の柳澤健」というノンフィクション・ライターを生み出したことだ。