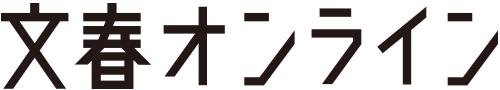〈「薩摩武者を率いた四兄弟」の命知らずな三男が…豊臣秀吉を激怒させ、首を狙われた末に用いた「最期の策」とは〉から続く
戦国小説集『化かしもの 戦国謀将奇譚』の著者・簑輪諒が、小説の舞台裏を戦国コラムで案内する連載の第7回です。(全7回の7回目/前回を読む)
◆◆◆
慶長19年(1614)、天下人・徳川家康は全国の大名の軍勢を率い、徳川幕府に従わぬ最後の抵抗勢力である、大坂城の豊臣氏を攻めた。世にいう、「大坂の陣」である。
豊臣方は必死に抗戦したが、翌慶長20年(1615)、滅亡。以後、250年以上にわたって、江戸時代という泰平の世が続いていく。
秋田藩・佐竹家の重臣、戸村義国(とむらよしくに)は、この大坂の陣の緒戦である「今福の戦い」で大いに活躍し、将軍・徳川秀忠から直々に武功を褒賞され、感状(戦功を讃える賞状)と青江次直の刀を下賜(かし)された。
それから30年後――正保2年(1645)、55歳になっていた義国のもとへ、奇妙な書状が届けられる。
差出人の名は、桑名藩・久松松平家の家臣、高松久重(たかまつひさしげ)。かつて、今福の戦いにおいて豊臣方として、戸村たち佐竹勢と戦った男だという。

高松久重の依頼
高松久重は天正15年(1587)の生まれで、戸村より4歳年上にあたる。彼はもともと讃岐(香川県)の大名・生駒氏に仕えていたが、朋輩と諍(いさか)いを起こして出奔し、豊臣方に身を投じて大坂の陣に参加した。
戦後、豊臣方の「大坂牢人」は厳しい残党狩りにあったが、やがて幕府から牢人赦免の達しが出ると、高松も再仕官。いくつかの主家を渡り歩いた末、最終的に桑名藩に落ちついた。
そんな高松が、一面識もない戸村に尋ねたのは、簡単に言えば
「今福の戦いにおける私の働きを、覚えておられるでしょうか」
という話であった。
「かつて、私は豊臣方の木村重成(きむらしげなり)殿の部隊に属し、今福の戦いにおいて佐竹勢と槍を合わせました。
そのときの様子や、己の働きのほどを、別紙の『覚書』に記しましたので、はなはだ恐れ多きことながら、是非とも戸村殿に内容をご確認頂き、間違いがないかどうか、吟味して頂きとうございます。
そうして己が働きを、しかと子孫に伝えたいのです」
高松はすでに59歳。生きているうちに、自分の武功を確かな形で記録しておきたいと考えても、おかしくない齢だ。彼にとっては、直に戦場で戦った相手であり、その武名を天下に知られる戸村義国は、証人としてこれ以上ない人物だったのだろう。
そして戸村も、その思いを汲(く)んだのか、顔も知らない相手からの、この唐突な依頼を引き受けた。
「大坂の陣」を戦国最後の戦いとするならば、戸村も高松も、戦乱の時代を知る最後の世代である。敵味方に属して争った間柄とはいえ、同じ時代を生き、同じ戦場を駆けた高松に対して、戸村は同志に近い思いを抱いたのかもしれない。
岡山藩の感状騒ぎ
しかし、実のところ、高松が戸村に『覚書』の確認を依頼したのは、子孫に語り残すことだけが理由ではなかった可能性がある。
というのも、この依頼の前年――正保元年(1644)、岡山藩・池田家で、大坂の陣での武功を巡って、ある騒動が起こった。そして、高松は間接的ながら、この騒動に関わっていたのだ。
この頃、岡山藩では、藩士たちの経歴書(家中書上)の編纂事業が行われていた。その報告過程において、三人の藩士が論争を起こしたのだ。
彼らはいずれも、かつて木村重成隊に属し、豊臣方として大坂の陣を戦った、元大坂牢人であり、論争の種となったのも、大坂の陣の際の武功についてだった。
この論争は、岡山藩の家老たちが詮議することになり、元牢人たちに対しては、大坂の陣当時の感状を提出するように命じられた。
ところが、どうしたわけか、三人のうちの一人――斎藤加右衛門という男は、感状を紛失してしまっていたらしく、慌てて偽物をこしらえて藩当局に提出した。その偽物は、文面もおかしければ花押も違い、なにより発給者の木村重成の名を、間違えて「乗重」と書いているようなお粗末なものであった。
捏造が発覚した斎藤は所領を没収され、永蟄居(終身刑)に処された。
かつて、木村重成隊に属していた高松久重は、斎藤ら三人とは旧知の仲であったため、詮議の過程で岡山藩から、参考証人として問い合わせがあった。
後日、事の顛末を知った高松は、戦慄したのではないか。
戦国の世にあっては、感状は栄誉の象徴であり、再仕官の機会を得るためにも重要であった。だが、たとえどれほど立派な経歴を掲げて仕官したところで、その後の働きが期待外れであれば、家中で立身し、地位を保つことなど出来るはずもない。肝要なのはあくまでも、仕官してからの武功だった。
しかし、今は違う。譜代の重臣ならいざ知らず、身一つで仕官した牢人上がりにとって、新たな武功を立てる機会などなくなった泰平の世にあっては、過去の事績の価値はなによりも重い。そのような時代になったのだと、高松は実感せざるを得なかっただろう。
家名と身代を守るためには、感状だけに縋(すが)るのでは心もとない。もっと確かな証明が欲しい。……斎藤加右衛門の一件から、高松はそのように考え、戸村義国に己の働きの確認を願い出たのではないだろうか。

主張と食い違い
高松と戸村は、直に会うことはなく、互いに書状を送り合って記憶をすり合わせた。そうして、高松が数名の牢人衆と共に、戸村の手勢と槍合わせしたことを確認した。
その一方で、二人の間では、一つの相違点が生まれていた。
「当時の私(高松)は、黒い甲冑に黒羅紗の羽織という装いで、敵と一番に槍合わせをした。これまでの話によれば、その相手は戸村殿だったと思われる。このこと、覚えておられないか」
一番槍、しかも相手が高名な戸村義国となれば、これほどの栄誉はない。高松はなんとしても、この点を証明したいと思っただろう。
戸村の返答は、次のようなものだった。
「確かにあのとき、木村隊に黒具足の武者がいて、私はこの御仁と槍合わせをした。……だが、その黒具足の武者は、右手に槍を、左手に采配を持って下知し、背には白黒段々の旗を差していた」
白黒段々の旗は、木村隊の「番指物(ばんさしもの)」である。番指物は、小姓衆や馬廻衆など特定の役職の者たちが差す、揃いの旗指物だ。
つまり、
「自分が槍合わせをした武者は、高松のような牢人衆ではなく、大将・木村重成の直臣であったのだろう」
と、戸村は言っているのだった。
高松はその後も食い下がり、返信で、
「番指物を差す身分の者が、采配で指揮をすることはあり得ませぬ」
などと、暗に戸村の見間違い・記憶違いを示唆し、遠回しに訂正を求めたが、戸村は譲らず、
「たしかに番指物を差す者が、普通、采配を振るうことはない。だが、采配自体は武者なら必ず所持しているもので、この有無をもって、黒具足の武者が高松殿であったと断ずることはできない」
と、あくまでも己の主張を曲げなかった。
戸村にしてみれば、
「戦場で旗指物の有無を見誤るなどというのは、敵味方の区別がつかないと言うも同じである。たとえ30年前のことであっても、記憶違いなどあり得ない」
と言いたかったのだろう。結局、両者の主張は平行線を辿り、やがてこの奇妙な往復書簡は終わった。
戸村の頑固さに、高松は辟易(へきえき)しただろう。しかしほんの少しは、そのことを喜ぶ気持ちもあったのではないか。
自分が命を賭けて戦い、敗れたのは、たやすく言葉を曲げ、武功を粉飾するような下らぬ敵将ではなかった。ここまで交わした書簡は、そのことを雄弁に物語っていた。
こうして高松久重は、武功の証明にはいささか心もとない文書と、子孫に語り伝えるべき、新たな思い出を手に入れた。
「黒具足の武者」の正体
ちなみに、紀州藩主・徳川頼宣の言行を記した『大君言行録(南竜言行録)』によれば、戸村が戦った黒具足の武者の正体は、「木村隊の物頭・佐久間蔵人」であったらしい。
佐久間は、「今福の戦い」の翌年、「若江の戦い」で井伊直孝の部隊と戦い、井伊家臣・正木舎人(重次)に討ち取られた人物である(『寛政譜』井伊氏)。
同書の記述が正しいとすれば、高松も戸村も、すでにこの世にいない人物に振り回されていたことになる。
おかしみさえ感じさせるような真相だが、この奇妙な往復書簡の結末には、かえって相応しいかもしれない。
参考:堀智博『大坂落人高松久重の仕官活動とその背景 : 戸村義国との往復書簡を題材として』(『共立女子大学文芸学部紀要』第62集 収録)2016