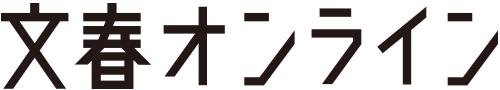〈「彼は美しい贈り物を携えた者だけに会見を許した」…織田信長の心をつかみとれ! 戦国武将たちの“贈り物合戦”〉から続く
戦国小説集『化かしもの 戦国謀将奇譚』の著者・簑輪諒が、小説の舞台裏を戦国コラムで案内する連載の第5回です。(全7回の5回目/前回を読む)
◆◆◆

宮部善浄坊継潤(みやべぜんじょうぼうけいじゅん)は、豊臣秀吉に仕えた勇将だ。
彼は武将であると同時に僧侶でもあり、頭を丸めて法衣を着込んだ、いわゆる法師武者であった。ちなみに、後世の史書では「善祥坊」と書かれることが多いものの、『竹生島奉加帳』に残る本人の署名は「善浄坊」であり、表記としてはこちらが正しいようだ。
譜代の家臣を持たない成り上がりの秀吉にとって、継潤は古参の重臣と言っていい。本記事では、そんな彼と秀吉との出会いについて書いていきたい。
山門出身の武辺者
継潤は、近江(滋賀県)の豪族・土肥氏の八男と伝わる。彼は同国の湯次(ゆすぎ)神社の社僧・宮部清潤(せいじゅん)の養子となり、やがて比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)に上って僧侶の修行に励んだ。
『真書太閤記』によれば、継潤は僧侶でありながら武芸を好み、兵書の研究にいそしんだというが、後年の武将としての活躍を考えれば、いかにもありそうな話だ。叡山時代の彼についての史料は少ないが、よほど武張った荒法師であったのだろう。
やがて継潤は、修行が十分成ったということで、叡山を降りて宮部氏を継いだ。
実は宮部氏は、ただの僧侶ではない。同氏は室町幕府の重鎮・伊勢氏の被官で、下湯次庄における庄司(荘園の管理者)だったとされる。
しかし、「応仁の乱」以降、幕府の権威は失墜し、荘園の多くは、各地の大名・国衆(領主)によって好き勝手に横領されていた。
「わしが同じことをして、なにが悪い」
あるいは継潤は、そう考えたのかもしれない。
彼は、伊勢氏から管理を任されていた下湯次庄を横領し、宮部城と名付けた城砦を築いて防備を固め、兵を率い、近隣の勢力と領地を奪い合うようになった。いかに乱世とはいえ、仮にも僧籍にある者とは思えない所業だが、以来、継潤は武将としての才能を開花させていった。
『武家事紀』によれば、土地を巡っての合戦の最中、継潤は富永新兵衛という弓の名手と一騎打ちになったが、彼は富永の放った矢を、槍で三度も打ち落としたという。
その武名は、近江国内でよほど鳴り響いていたのだろう。やがて継潤は、北近江を支配する浅井長政(あざいながまさ)に招かれ、仕えることとなった。継潤は持ち前の武勇によって、浅井家中で頭角を現していき、敵対する勢力からは、
――宮部の城主善祥坊は、武勇勝(すぐ)れて、浅井一味の諸将の最も心悪(こころにく)き者(『真書太閤記』)
などと評されたという。
浅井家の盾として
以前のコラムでも紹介したように、浅井長政は信長と敵対し、元亀元年(1570)6月、「姉川の戦い」で織田軍に挑むも、敗れた。
この戦いののち、信長は浅井方の横山城を奪い、城番として木下秀吉(豊臣秀吉)を置いた。横山城は、浅井氏の本拠・小谷(おだに)城から9kmほどしか離れていない。浅井長政としては、喉元に刃を突きつけられた思いがしただろう。
だが、秀吉には目障りな敵がいた。小谷城と横山城の中間に位置する宮部城を守り、盾のように立ちふさがる、宮部継潤である。
元亀2年(1571)10月、秀吉は大胆にも、その継潤に調略をしかけた。――織田方に、寝返れというのである。
継潤にしてみれば、悪い冗談としか思えなかっただろう。なるほど、たしかに信長は、「姉川の戦い」で見事に勝利した。しかし、その後の戦局は、むしろ織田方にとって不利が続いている。
浅井氏は姉川で敗れたとはいえ、十分に余力を残していたし、朝倉氏、石山本願寺、三好三人衆といった諸勢力と連携して信長を包囲し、各地で織田方の拠点を脅かした。
昨年12月、信長は将軍・足利義昭の仲介によって浅井・朝倉方と和睦し、やっとの思いで窮地を脱した。姉川での快勝からたった半年の時点で、信長はそこまで追い詰められていたのだ。
そして、将軍にすがりついて結んだこの和睦も、ほどなくして破れ、信長は再び、四方の敵の防戦に回るはめに陥っていた。
織田方は、明らかに窮していた。そして、継潤にとってもう一つ、無視できないことがあった。先月――9月12日、信長は継潤の古巣である、比叡山延暦寺を焼き討ちし、虐殺を行っているのである。つまり継潤にとっては、信長は仇も同然であり、そんな自分を口説き落として織田方に引き込もうなどとは、正気の沙汰とは思えなかっただろう。
秀吉の交渉
『浅井三代記』によれば、秀吉は次のように継潤を説いたという。
「貴殿がこの城で本望を遂げたところで、そんなものは“九牛の一毛”に過ぎませぬぞ」
九牛の一毛とは、「多くの牛の中の一本の毛」のことで、「多数の中の一部、取るに足らないもの」を意味する故事だ。秀吉がこの種の漢語に詳しいとは思えないから、あらかじめ古典に通じた家臣か禅僧にでも尋ねて、用意していた言葉なのかもしれない。
この言葉は、中国初の通史『史記』を編んだ司馬遷(しばせん)が、友人に送った書状に由来する。
司馬遷はかつて、敗将・李陵を弁護したことから帝の怒りを買って投獄され、死刑を免(まぬが)れるために宮刑(去勢刑)を選び、宦官(かんがん)となった。
司馬遷は、書状の中で語る。
「刑に服し、潔(いさぎよ)く死んだところで、世の人々は、節義を通したなどと讃(たた)えてはくれません。所詮、私のような小人の死など、多くの牛の中の、一本の毛を失うようなものです。虫けらが野垂(のた)れ死ぬのと、なんの違いがありましょう」

そのような死よりも、彼は大願である『史記』の完成のため、当時の士大夫にとって死以上の屈辱とされた宮刑を受け入れ、生きることを選んだのだった。
「この小城を死ぬまで守り続けるのが、お主が生涯をかけてやりたいことか? それで、まことに本望なのか?」
秀吉は、継潤にそう言いたかったのではないか。
さらに想像を広げ、小説風に綴(つづ)るのなら、秀吉は次のようなことを言って、こんこんと継潤を説得したかもしれない。
「お主には、この言葉の意味を察するだけの教養がある。己一個の意地と槍働きにしか興味のない、木っ端武者どもとは違うはずだ。そのことを、この秀吉も、そして我が主君・信長様も、十分に理解しておられる」
「それに比べて、浅井長政はどうだ。いまも最前線で、織田方と対峙し続けるお主に、どれほど報いたのだ。これまでの武功に見合うだけの身分に引き上げてくれたり、新たな城や領地を与えてくれたのか。……なにもあるまい。譜代の家臣でもない、山法師崩れのお主を厚遇などしてしまえば、重臣たちの不興を買い、人心を失って孤立しかねないと、長政は恐れているのだろう」
「だが、信長様は違う。あのお方は、左様なことを恐れはせぬ。卑賎に生まれ、草履取りに過ぎなかったこの秀吉が、一手の大将となり、最も重要な城を任されているのがなによりの証よ。……のう、継潤よ。お主は、古典も兵書もろくに知らず、武芸においても己より劣る、愚かな譜代衆の盾として、ろくな褒美もなく使い潰されるのが望みか。そうして九牛の一毛の如く、なにごとも為さず、誰にも知られぬまま、ありふれた木っ端武者として死んでいくのが本望か」
「司馬遷は、節義を通して潔く死ぬよりも、『史記』を編むという大望のため、汚辱にまみれて生きることを選んだぞ。お主はどうするのだ、善浄坊継潤」
実際の秀吉が、どのような言葉を用いて交渉したのか、詳しいことはわからない。しかし、少なくとも、普通なら到底あり得ぬような裏切りを、決断させるに足るものだったのは確かである。
その後、継潤は城ごと織田方に寝返り、その証として浅井方の国友城を攻撃した。浅井家中の衝撃は、いかばかりであっただろう。
横山城から宮部城というラインを手に入れた信長は、元亀3年(1572)、その延長線上に虎御前山(とらごぜやま)城を築く。小谷城はすぐ目の前で、いつでも攻め掛かれる位置である。いよいよ追い詰められた浅井氏は、その後も抵抗を続けたものの、この翌年、ついに滅亡した。
ところで、継潤は、秀吉の甥の秀次を、一時的に養子にしていたことがある(後年、秀次が三好氏の養子になった際に解消)。この養子入りについて、一説には、継潤を寝返らせるために秀吉から持ち掛け、実質的な人質として秀次を預けたのではないかともいう(小和田哲男『豊臣秀次 「殺生関白」の悲劇』)。
「日本無双」の荒法師
そののちも、継潤は秀吉の家臣として活躍を続けた。
秀吉が大規模な兵糧攻めを行った「鳥取城の戦い」では、支城の雁金山城を攻め落として敵方の補給路を分断し、九州征伐の際の「根白坂の戦い」では、敵の島津軍の猛攻を最前線で防ぎ切り、その働きぶりを秀吉から「日本無双」と讃えられた。
信長の死後、天下人となった秀吉によって、継潤は鳥取5万970石を領する大名となった。秀吉は、この古参の重臣の働きに、十分に報いてみせたといえる。
参考:黒田惟信編『東浅井郡志』第3巻 1927