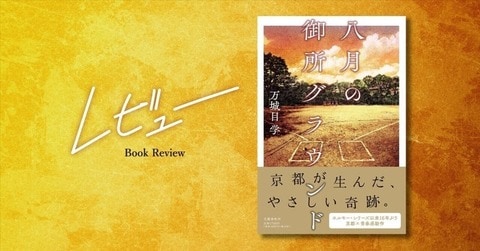第15回
ハンバーグ人生劇場①
〜立志編〜
子どもの頃、ハンバーグは大好物でした。晩ごはんはハンバーグよ、と母親から告げられると、心の中でガッツポーズです。そして僕は、お手伝いのために腕まくりもします。我が家のハンバーグは、ハイカラ志向だった母親のこだわりか、塊のナツメグを摺りおろして入れるのがお約束でした。そのナツメグを摺りおろす係が僕だったのです。
ナツメグは、グラタンやコロッケ、ミートオムレツなどにも使われており、僕にとってまさしく「ご馳走の香り」でした。硬いナツメグを小さなおろし金で摺りおろすのはなかなか難儀でしたが、そんなご馳走の香りに包まれるひとときは、なかなか悪くないものでもありました。しかもそれが後に、大好物であるハンバーグという形をとって現れるわけです。お手伝いを拒む理由は何ひとつありません。
そんなある日、ハンバーグの食卓を囲みながら、父親がこんな蘊蓄を聞かせてくれたことがありました。曰く、日本は肉が高いから、ハンバーグにも玉ねぎやらパン粉やらでカサ増しをするようになったのだ、と。しかしそのおかげで日本のハンバーグはふんわりジューシーでおいしい料理になった。外国のハンバーグはほぼ肉だけなので、かえっておいしくない……。
へー、なるほど、と僕はいたく感心しました。さらに父親は、
「だから日本のハンバーグは世界一おいしいわけだが、その中でも特においしいのが我が家のハンバーグなのだ」
と、妻へのリップサービス含めてうまいことまとめました。やればできる男です。
父親はそう言いましたが、僕にとっては「もっとおいしいハンバーグ」がありました。それが洋食レストランのハンバーグです。ハンバーグそのものは家のそれと似たようなものだったと思います。しかしその表面には、格子状の香ばしく美しい焼き目が付けられていました。そしてそのこと以上に僕を魅了したのがソースです。昭和の時代ですから、それはもちろんデミグラスソース。
家でのハンバーグのソースは、ハンバーグを焼いた後のフライパンに、酒、トマトケチャップやウスターソースなどいくつかの調味料を加えて煮詰められたものでした。甘酸っぱくて、それ自体にハンバーグそのものの残り香もあり、それはそれでおいしいものではありましたが、レストランのデミグラスソースはそれを確かに凌駕するものだったのです。
特に甘いわけでも酸っぱいわけでもないのに、それはとことん深い味がしました。何と何を混ぜたらそんな味になるのか、さっぱりわかりませんでした。そしてそこにははっきりと苦味もありました。これぞオトナの味だ、と子どもの僕は興奮したものです。
時は過ぎ、大学生になって一人暮らしを始めると、そういうレストランのハンバーグとは縁遠くなりました。その代わり身近になったのは、学生食堂のハンバーグです。レストランには山高帽のコックさんがいましたが、学生食堂にいるのはねじり鉢巻のおっちゃんです。下宿の近所にあったそんな食堂のハンバーグに、僕は衝撃を受けました。
それは子どもの握り拳くらいの大きさがあり、しかも一人前で2個。ボリュームは申し分ないものでした。しかし格子状の焼き目なんて付いていなくて、知っているハンバーグよりなんだか色が淡いのです。当然ナイフとフォークなんてありませんから、それを箸で一口分切り取ります。なるほどそれは、箸で難なく切断可能な柔らかさでした。
柔らかさが第一の衝撃だったとするならば、第二の衝撃はその切断面でした。「ハンバーグとは肉料理である」という常識を覆すが如く、その断面はややクリーム色がかった白っぽい色だったのです。最初は間違ってコロッケが配膳されてしまったのかと思いました。しかしその表面にはパン粉がまぶされた形跡も、揚げてある気配もありませんでした。ハンバーグであることは間違いないようです。訝しみながらその一切れを頬張った時に、僕は察しました。これは肉以外の材料を徹底的に増すことで巨大化を実現した、未知の料理なのだ、と。
かつて父親から聞いた蘊蓄の記憶が蘇ります。「日本は肉が高いから混ぜ物でカサ増しをするようになったのだ」。確かにそのハンバーグを名乗る未知の料理は、その方向性をひたすらに突き詰めたもののようでした。さすがに肉が全く入っていないわけではないようでしたが、どうもその主原料はむしろパン粉と玉ねぎであるようでした。
肉の味が薄いのを補うかのように、全面にかかっているソースの味は、極めて濃いものでした。と言ってもそれはほぼトマトケチャップそのものであり、そこに醤油なのかソースなのか何かしらが少々混ぜ込まれているようでした。色味だけはデミグラスソースに似ていないこともありませんでしたが、もちろん別物です。
散々こき下ろすようなことを書き連ねてしまいましたが、実はその不思議なハンバーグは、僕の心をガッシリと捉えました。ふんわり、と言うか、味も食感も頼りないそれでしたが、甘酸っぱくなおかつしょっぱいソースを伴った時、そこにミラクルが生まれたのです。そのミラクルは、ソースのしょっぱさに慄きつつ、慌てて掻き込んだ白ごはんと邂逅することで完全体となりました。巨大な2個の「謎ハンバーグ」は、学生食堂にお約束の気前良い丼ぶり飯と共に、あっという間に胃の腑に収まり、青春の荒ぶる胃袋を難なく鎮めてくれました。
以来僕は、その店に定期的に通い続け、そこではほぼそれしか注文しなかったのです。僕は相変わらず、それをハンバーグと認めるのに些かの抵抗感がありましたので、それを心の中で「学生ハンバーグ」と命名し、ハンバーグとはまた別の素晴らしい食べ物と位置付けることにしました。
それはそれとして、僕は当時の自炊生活の中で、ひとつの発明を成し遂げました。その頃僕は狭い下宿のキッチンで、イタリア料理、なかんずくパスタを作るのに凝っていました。外食すると高いイタリア料理も、自らの技術を向上させて自作すれば安く済ませることができる、という地に足のついた理由もありました。そして同時に「それを振る舞うという名目があれば、女子を自宅に誘引するための完璧な言い訳が成立するのではないか」という、サイテーの、しかしある意味、青少年として健全この上ない目論見もあったのです。
そんな話はいいとして、僕はある時、当時すでに有名シェフであった落合務さんのレシピに基づき「ミートソース」にチャレンジしていました。そのレシピが特徴的だったのは、「先ず最初にひき肉をフライパンに押し付け、それをハンバーグのように両面しっかり焼き付ける」という工程が指示されていたことです。リビドー、もとい向上心に忠実に、僕はその指示を律儀に守って、ひき肉をしっかり両面焼きました。
こんがりと焼けたそれを、何の気なしに一口味見してみました。その瞬間、脳内で何かがスパークしました。
「う……うまいっ!」
その「ハンバーグのような何か」は、思えばお馴染みの「パン粉主体の学生ハンバーグ」には決定的に欠けているファクターを、過剰なまでに補完するものでした。そしてそれは同時に、「ステーキ」という、貧乏学生には最も縁遠いご馳走への見果てぬ希求を、ほぼ満たしてくれるものでもありました。
結局僕はそこでミートソース作成を中断し、心の中で落合務先生に謝罪と共に感謝の辞を捧げ、それを皿に移し、塩胡椒だけをふったものをそのまま貪り食べてしまいました。向上心もリビドーも、青春の荒ぶる食欲の前には案外無力だったということかもしれません。
この「ひき肉を押し付けて焼いただけのハンバーグのようなステーキのような何か」は、そうやって僕の定番自炊料理となりました。長らくそれは、関西で俗にいう「よそで言うたらアカン料理」であり続けましたが、ある時僕はそれに「学生ステーキ」という名称を与え、堂々と公言することになるのです。
しかしそれはまた別の物語。いつかお話ししましょう。
・②風雲編はこちら
・③望郷編はこちら

稲田俊輔(いなだ・しゅんすけ)
料理人・飲食店プロデューサー。京都大学卒業後、飲料メーカー勤務を経て円相フードサービス設立に参加。2011年に東京駅 八重洲地下街に南インド料理店「エリックサウス」を開店。現在は全店のメニュー監修やレシピ開発を中心に、業態開発や店舗プロデュースを手掛ける。
ジャンルを問わず何にでも喰いつく変態料理人、またナチュラルボーン食いしん坊として、Twitter(@inadashunsuke)等でも精力的に発信。『おいしいもので できている』『飲食店の本当にスゴい人々』『ミニマル料理:最小限の材料で最大のおいしさを手に入れる現代のレシピ85』『「エリックサウス」稲田俊輔のおいしい理由。インドカレーのきほん、完全レシピ』『食いしん坊のお悩み相談』など著書多数。
人気作家の作品&インタビューがもりだくさん♪ 「WEB別冊文藝春秋」はこちら