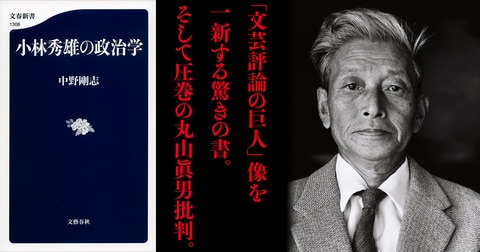一 乳児と検閲
一方、母はといえば、その「お話」の意味するところを、いうまでもなく十二分に理解していたに違いない。それはもとより禁止もなければ、検閲も存在しない世界である。無論私は、この頃のことを何一つ覚えてはいない。しかし、他の乳児たち同様に、自分にもかつてはそういう世界が確実に在ったのは、まぎれもない事実なのである。(一三五頁。傍点は引用者、以下同じ)
『幼年時代』第二回の右の一節は、異様である。
この原稿を自宅で掲載誌の編集者に渡した一九九九年七月二一日、江藤淳は浴槽で手首を切り、亡くなる。遺書を除けば、批評家の文字どおりの絶筆となった文章だ。
「お話」にカッコが附されているとおり、書かれているのは江藤が生後二か月のとき、生母に甘えて言葉ならざる声を発していたという、それだけの話である。読者の誰もが通過した自明の季節について、わざわざ「他の乳児たち」と比較し、そこには「検閲」がなかったとまで述べる人の感性は、ふつうではない。
もちろん江藤の著書になじんだ人なら、一九八一年の『落葉の掃き寄せ 敗戦・占領・検閲と文学』に前後して発表された、多数の「検閲研究」を想起するだろう(八九年に単行本となる『閉された言語空間』も、連載開始は八二年)。中学・高校生だった青春期にGHQによる占領を迎え、当時は「言葉が奪われていた」事実に後から気づいた文学者が、そのショックを乳児期の描写にまで遡らせて叙述している。そう解するのも不可能ではない。
もし江藤を通じて「戦後史を綴る」だけでよいなら、そうした読解もそれなりには妥当で、なにより政治的に安全かもしれない。だが併録された『妻と私』とともに読むとき、私の目には江藤の言う「検閲」が、限られた時期に特定の勢力が行った単なる史実としての挿話を超えて、人が生きる際の困難を象徴する一語として浮かびあがる。
二 告知と責任
『妻と私』は、一九九八年の一一月に慶子夫人を失った江藤が、翌九九年の『文藝春秋』五月号に寄せた手記だ。本人が述べるように「これほど短期間にこれほど大きな反響を生んだものは、ほかに一つもない」(一〇八頁)ほどの評判を博し、七月に単行本となる。しかし同月に江藤が自死を遂げたため、追悼特集を組んだ『文藝春秋』の九月号ではもういちど掲載されている。いわば一年のあいだに三度刊行されるほど、『妻と私』は同時代の読者を揺さぶる文章だった。
なにが、そこまでの反響を呼び起こしたのか。ひとつには江藤が得ていた知名度と権威だが、それだけではありえない。当時は一九九七年夏にわが国初の臓器移植法が成立した直後で、人の死をめぐる「自己決定権」の当否が、TVを含むマスメディアで激論された記憶が生々しかった。拙著『平成史 昨日の世界のすべて』(文藝春秋)に記したように、それはポスト冷戦期にあれほど輝いて見えた自由と自立の理想が、翳りを帯び失速してゆく前触れでもあった。
『妻と私』で、医師から妻が末期がんの状態にあると知らされた江藤は、こう書く。
医者は、当の本人には「脳内出血」だといっているのだ。そして、家族には本当の病名を告げて、家族からそれを患者に「告知」せよという。……これは患者にとってはもちろん、家族にとっても残酷きわまる方法ではないか。しかも、「告知」の責任だけを負わされて、患者を救うことのできない家族にいたっては、あまりに惨めというほかないではないか。(二七―二八頁)
「いくら現代の流行であるにせよ、このからくりには容易に同調できない」(二八頁)と憤る江藤は、妻に対して告知はしないと決める。そもそも「不必要な苦痛を味わわずに、静かに眠るがごとく逝きたい」(三五頁)というのが、夫妻で長年話しあった理想の臨終だからだ。しかし病院長と高校時代から友人だったのは妻の方で、医療の知識で劣ると自認する夫には、彼女に病名を隠しきる自信が持てない。だからターミナルケアの鎮痛剤を「新薬の抗生剤だ」と偽って与えたときも、「医学知識に詳しい家内が『新薬』の性質に気付いていないとも思われなかった」(七〇頁)。
小林秀雄亡き後(一九八三年没)、文壇を代表する保守派となって久しい江藤だが、その本領はマッチョイズムにはない。むしろ敗戦以降、日本ではいかに威厳ある家父長なる存在が不可能になり、夫が妻を守れなくなったかが、六七年刊行の主著『成熟と喪失』の主題だった(とくに、その小島信夫『抱擁家族』論)。
だが、まさか自身がかつて評論した対象と同じ役柄を、より無力な形で演じさせられ、その過程を散文に記し公表することになろうとは。いわば批評家が作中人物に化けて小説に紛れ込んでしまう、メタフィクションめいた事態がリアルに起きた。『妻と私』はその困難を体験者の目で綴った、類書のない当事者研究でもある。
三 批評と沈黙
そもそも批評とは、なんだろう。それは世界の自明性が壊れてしまった後で、作品(=批評の対象)に感じる「意味」を媒介とすることで、他者との関係を作りなおそうとする試みだと思う。
鑑賞した百人が百人、同じように抱くだろう感想を書いた文章を、批評とは呼ばない。それは単に自明なものをなぞるに過ぎない。一方で「こんな独創的な解釈ができるのは私だけだ」と批評家が誇るとき、実は彼(ないし彼女)こそが、他者にもその解釈を共有してほしいと――つまり自分が感じとった「意味」は、批評の読者にも理解されうるはずだと信じている。そうでなければ、わざわざ批評として文字にする必要はない。
江藤にとっての慶子夫人は、おそらく批評を通じて最も繋がりたい相手であり、同志であり、そして厄介な他者だった。
死別へと向かう『妻と私』の不穏な予感は、「はじめてアメリカに留学したとき、……家内の顎が突然はずれたことがある。そのように家内には、予想もできない不思議なことがときどき起った」(二一頁)と記されることで始まる。一九六五年に刊行された『アメリカと私』の冒頭にある、ファンにはよく知られた挿話を指すものだ。同書と、その後日談である「日本と私」とを並べて読むとき、本書の背景をなす恩讐ともにある夫妻の旅路が、痛々しくも鮮やかに姿を現す。
江藤淳が慶大の同期生だった三浦慶子と結婚したのは、大学院に在学中の一九五七年。戦後世代を代表する批評家として名を上げた後、六二年にロックフェラー財団のプログラムでプリンストンに招かれるが、ロサンゼルスでいきなり夫人が体調を崩す。なんとしても医療費を支給させるべく、財団相手に奮闘した体験を皮切りとして米国風の自主自立の精神を体得してゆく過程が、『アメリカと私』の主旋律をなす。
六四年の帰国後を綴る「日本と私」の初回によれば、帰路に欧州を経由した際にも慶子夫人は腹痛で入院し、江藤は旅程をキャンセルしている。『アメリカと私』と同じ『朝日ジャーナル』誌に六七年から連載されたものの、盟友だった山川方夫の事故死(六五年)を描いたところで中絶し、単行本にはならなかった。書籍に入るのは江藤の没後、福田和也氏の編んだ『江藤淳コレクション2 エセー』が初である。
「日本と私」はアメリカ風の個人主義になじんで帰朝した夫妻が、日本社会へと再適応できず葛藤する苦労話であり、その象徴として慶子夫人はじんましんに悩まされる。江藤は妻をかばいながら新居を探すものの、ついに「何年ぶりか」で彼女を殴ってしまう。映画鑑賞の後、江藤としては妻の疲弊ぶりを見てディナーを諦めたのに、慶子夫人が「疲れているのは本当は自分ではなくて私〔=江藤〕のほうであり、そういう私を自分が支えているのだとでもいうように」振る舞ったからという、率直に言って褒められない理由だ。
しかしこの身勝手で暴君的な夫は、なにをそこまで会食に求めていたのか。その告白は、卓越した批評家の筆になるものだけに、いまもひどく突き刺さる。
いわばそれはおたがいが一生懸命に生きているということを、ちょっとわきから眺め直してみるような行事だ。そこからみると夫も妻もおたがいに孤独な人間だが、夫は妻が、妻は夫がそうであることを知っていて黙っているので、この孤独にはあまりとげとげしたところがない。……
「まあ、なかなかよくやっているね」
その言葉はもちろん相手の耳には聴えない。聴えないが、だいたいそんなことをいっていることがおたがいにわかっているので、ふたりのあいだの沈黙には本当は言葉が充満している。(『江藤淳コレクション2 エセー』ちくま学芸文庫、四五五頁)
夫妻がともに「孤独な人間」だとさらりと書いているが、これが単に性格の問題を指すのではないことは、連載の中途、自身と慶子夫人の生い立ちを赤裸々に描く箇所から知れる。江藤は母親の結核のために実家から隔離されて育ち、葬儀のために「治ったよ」と嘘を吐かれて呼び戻された際には、「なぜか私は母が死んだことを完全に理解していた」。三浦家は家長が満州勤務の官吏だったことから、敗戦時は平壌で劣悪な収容所に入れられ、脱走して九死に一生を得たものの「小学生だった家内は毎日お葬式ゴッコをして遊んでいた」(同書、三六六・四一七頁)。
時代を考えれば大卒どうしのカップルというだけで知的な夫婦だし、実際に慶子夫人は夫の著作をイラストでも支える才女だった(『妻と私と三匹の犬たち』河出文庫)。しかし穏和な幼少期を奪われて育った二人の目には、戦後日本の社会はどこまでも壊れて見える。その違和感を言葉にすることで生き延びようと健筆をふるう批評家が、心底ではいかに言葉や批評なしでも安堵できる沈黙を欲していたか。
――生前は未刊に終わった「日本と私」で、江藤はそれこそを吐露していた。
四 自死と共存
慶子は、無言で語っていた。あらゆることにかかわらず、自分が幸せだったということを。告知せずにいたことを含めて、私のすべてを赦すということを。……その無言の会話が、いったい何分、いや何十分つづいたのか、私は覚えていない。そこには不思議に涙はなく、限りなく深い充足感だけがあった。(七八頁)
『妻と私』にこう記される、臨死状態に入った妻に寄り添う経験の際、江藤がかねて切望した「沈黙」に身を浸していたことはあきらかだろう。そうした状況で人が味わう独特の時間の感覚は、同書では「日常的な時間」に対する「生と死の時間」と名指され(初出は六六頁)、繰り返し登場する。しかし介護に疲労し敗血症に陥りつつあった江藤は、いつしかそれは単に「死の時間」でしかないのではと慄き、言葉を喪失する体験への誘惑と抵抗とのあいだを揺れ動くことになる。
「私のすべてを赦す」なる表現に込められた謝罪の対象は、まさか往年の殴打のみではないだろう。病名を告知しないという決断をはじめとして、人は他者を気遣いながら生きようとするとき、どうしても擬態しなければならない虚偽を抱え込む。四歳で母を喪った際、父親に吐かれた「治ったよ」との嘘がまさにそれだが、いまや江藤は夫であり家長である者として、生き続けるかぎりで嘘を吐く側に立たねばならない。
生きるとはその意味で、みずからの真情に対し不断に加えられ続ける「検閲」との格闘であり、だからその検閲は実は、敗戦とも占領とも関係がない。そうした検閲なしに生きることを許されるのは、そもそも内面を言語にする力を持たない乳幼児の段階のみだが、しかし江藤の場合、それは母の死によって断ち切られてしまう。
だから『妻と私』の脱稿後に書き起こされた『幼年時代』の冒頭で、江藤が亡くした妻と母を重ねるのは偶然ではない。人は言語なしに、批評なしに他者と生きてゆくことは、ほんとうにできないのか。検閲不在の境地が死ではなく、生につながる回路を、中途で断ち切られた自身の幼少期を復元することで探してみたい――。
それが妻と最期の時間をともに過ごした、江藤に浮かんだ一念だったと思う。
すでに諸賢の指摘のあるとおり、『幼年時代』の文章はどこかおかしい。誰の目にも江藤の自伝として映ることを前提にしながら、両親は江上堯・寛子(正しくは江頭隆・廣子)、本人は敦夫(正しくは淳夫)と、微妙に名前を変えている。「日本と私」の頓挫後に連載を始めた『一族再会』(単行本は一九七三年)と同一の主題で、そちらではすべて実名で著したのだから、いまさらプライバシーを気にするのも変だ。
おそらく江藤は、批評ではなく創作として、「死の時間」に抗いながら検閲なしの世界を描き出すことができると示したかったのではないか。かつて精神的な自伝を「永いあいだ、私は自分が生れたときの光景を見たことがあると言い張っていた」と書き始めた作家は、戦後日本の現実の中で、真情を偽らずにすむ生き方を求めて果たせず、自死に至った(三島由紀夫『仮面の告白』一九四九年)。
批評家として出立した江藤は、そうした無理をせず、むしろいかに自分には乳児期の記憶がないかを強調しつつ筆を進める。そして歴史家の手つきで、亡き母の残した手紙を筆写し、幼少期に自分から奪われた可能性の復元に努めようとする。
中絶未完となった第二回の終幕は、この生き続けようとする江藤の試みを損なった元凶をあまりにもあからさまにして、傷口を覗く心地がする。つい先日も本人の責任で妻に病気を告知せよと迫った、あの酷薄な自己決定の論理が、戦前に母を追い詰めた存在として再び姿を現す。
母はその点で、あまりにも素直であった。つまり、「不行届」は努力によって行き届かせることができると、確信し過ぎているようなところがあった。(一五七頁)
書くという営為によって、自然らしい正しさを失った敗戦後の時代を生き延びた批評家は最後、この場所から先を書き継げずに、命を絶った。
だがその敗北は、必然なのだろうか。
批評とは異なる形で、言葉にすら頼らずに、すべてが壊れて見える世界を他者とともに持ちこたえてゆく方法は、ほんとうにないのだろうか。
おそらくは生涯で初めて、書き続ける必要はなく「私たちは、ただ一緒にいた。一緒にいることが、何よりも大切なのであった」(六七頁)という境地を知った『妻と私』の体験に、他の形で活かされる可能性は、なかったのか――。
その問いが本書を読み終えるごと、いつまでも私の中に響いてやまない。