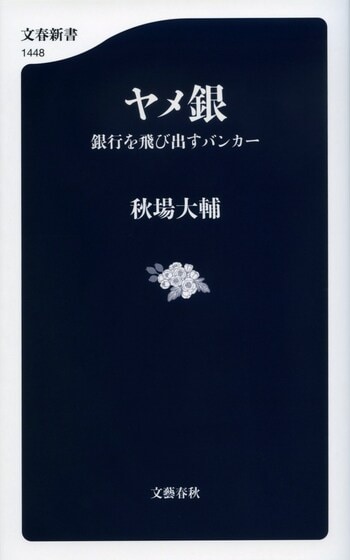一九八九年十二月二十九日、日経平均株価は終値で三万八千九百十五円八十七銭と当時の史上最高値を付けた。年が明けて株価は急落したが、世間のほとんどが株価の調整は一過性のものと考え、資産効果に酔いしれた。筆者が大学を卒業して就職したのは九〇年四月。世間がバブルを謳歌していた真っ最中だった。
三十年以上前の狂乱は今でも仲間うちの会話で話題になる。あの頃の人の浮かれた映像をテレビで観ることもたまにある。そのさなかに社会人になったのだから、筆者は正真正銘の「バブル世代」である。もっとも当時の嘘のような本当の話や映像を観たり聞いたりしても、どうも他人事に思えてしまう自分がいるのも事実だ。
確かに街で「ボティコン」(もはや死語だが、ボディラインを強調したワンピース)を着た女性が通り過ぎると振り返って凝視した記憶はある。しかし臆病が災いし、ボディコンの女性たちが夜な夜な踊っていたというディスコ(これまた死語だが)というところへ行ったことがない。当然ながら東京・六本木辺りの交差点で一万円札を振りかざしてタクシーを止めた経験もない。だから「バブル世代」と言われてもピンとこないのである。
自分にとって「バブルな記憶」ってなんだろう。そんなことを思って記憶を辿ってみたが、思い出したのはキラキラした話ではなく、むしろ苦い過去だった。
「新聞社で働くことになればプライベートな時間なんてほとんどないに違いない。一緒に旅行へ行くなんて機会もないだろう。奮発して海外へ遊びに行くか?」。父のそんな一言がきっかけとなり、家族で香港旅行に出かけたのは八九年十一月だった。
初日夜のことだ。夕食を食べるため、わりと豪華なホテルの中にある中華料理の店に入り、メニューを見た。たまたま目に留まったアワビの煮込みは「時価」と書かれていた。英語を喋れない父が「値段を聞け」と言うので給仕係に尋ねると、当時の日本円換算で一万八千円と言った。大きさは一口サイズの饅頭くらい。さすがに高すぎると思っていると、傍にいた父が「じゃあ四個だな」と言った。
高級食材とはいえ一個一万八千円もするはずはない。今にして思えば完全にぼったくられているわけだが、当時は家族全員の金銭感覚がマヒしていた。家族で「やはり高級店の味は違うな」などと分かったような口をきき、それぞれ恍惚の表情を見せながら胃袋に収めた覚えがある。
さて、異常だった時代のこうした思い出を人に話していると面白いことに気づく。バブルの思い出として香港の中華料理屋の話をしても聞き手はさして笑わず、むしろ小さなアワビ四個に七万円超を払った世間知らずぶりにあきれる。
多くの人にとって当時の金満エピソードは耳タコなのだ。逆に興味を持たれるのがバブルの頃の就活事情。当時の学生にしてみれば身の回りで起きた当たり前の出来事だったが、多くの人には珍しいらしい。
あの頃の就活は四年生の八月が解禁だったが、学生は四月くらいからざわついた。そこで筆者が所属していたゼミの指導教授は新学期早々に学生と個別に面談する機会を設けてくれた。ありていに言えば進路相談だったわけだが、全員のヒアリングを終えた後の授業でこんなことを言った。
「これから就活が本格化するから、君たちの話を個別に聞いたけれど、勉強不足にほとほとあきれたよ。希望する職種を聞いたら、ほぼ全員が金融と言うじゃないか。そもそも金融といったって幅が広い。銀行もあれば証券会社や保険会社だってある。その絞り込みもできていないのか。諸君が言う金融、中でも都市銀行や長期信用銀行は難関中の難関だ。売り手市場だからといって甘く見てはいかん」
普段はアカデミアにどっぷり。世俗的なことを言っても全く興味を示さないような指導者だったので、学生の就活に踏み込んで発言したことはとりわけ印象的だった。
あの発言をいまだに覚えている理由がもう一つある。就活の結果だ。教授が難関中の難関といった大手銀行から同期十七人のほとんどが内定をもらい、うち九人が実際に就職した。むろん同期が抜きんでて優秀だったからそうした結果だった可能性がないわけではないが、おそらく違う。バブルのころの銀行の採用活動は異常で、ハードルが低かったのだろう。
筆者は週刊文春で二〇二〇年六月から七月にかけて「ヤメ銀~銀行マンは絶滅するのか」を、二〇二一年四月から六月にかけて「ヤメ銀~絶滅時代のバンカーたちへ」を執筆した。それはこんな動機から始まった。
我々は世間が浮かれまくっていた時期に就職した。しかし、ほどなくしてバブルは崩壊、中でも銀行は不良債権処理に追われ、その後、大再編を経験した。就職先に銀行を選んだ仲間たちは就職時に想定した銀行像やバンカー像と、就職後の現実に大きなギャップを抱えたに違いない。
銀行に入った仲間の多くが第一線からは退いたいま、銀行とはどんなところだったのか、バンカー人生は楽しかったのかを聞いてみたい。もう銀行から離れた「ヤメ銀」なのだから本当の心の内を話すのではないか。そんなことを考えた。
もっとも仲間の話だけで記事を書くわけにはいかない。いくつもの伝手を頼って取材を始めると、話を聞くことになったヤメ銀の年齢は結果的に二十代から八十代と幅広く、同世代ばかりではなかった。そのせいか、どのインタビューでも聞いた「あなたにとって銀行はどんなところだったんですか」「バンカーとはどんな生き物ですか」といった質問への答えは肯定的なものもあれば、極端に否定的なものもあり、結論を得ることがなかった。
連載が終わった。しばらくして持ち上がった「連載をベースに新書を作らないか」という話はありがたかったが、反面、困った誘いでもあった。結局分からずじまいだった「銀行とは何か?」「バンカーとは何者か」にそれなりの答えを出さなければならないけれど、それが骨の折れる作業と思えたからだ。
すっきりしない日々が続いたが、ある日のこと、ぼんやりとした光が差し込んだ。当時大学三年生だった親戚に就職のアドバイスを求められ、くだんのバブルの頃の就活エピソードを話した時のことだ。
当時、就職先としての銀行は「難関中の難関」と言われたが、ゼミの同期の内定率は一〇〇%で、仲間の半分以上が実際に就職した。バブルの頃の就活は異常だった……。この話を聞いた親戚は、内定率一〇〇%や半数が実際に銀行へ入ったことではなく、同期が判で押したように銀行を志望したことに目を丸くした。
ほぼ全員が「希望する職種は銀行」と即答した筆者の世代にとって、銀行は入ってしまえば一生安泰な企業社会の頂点。バンカーはビジネスの世界で一目置かれる職業だった。しかし猫も杓子も希望する就職先は銀行という時代はもはや昔話。今では銀行が大学生の人気就職先ランキングの上位から滑り落ちることも珍しくなくなっている。そうした変化があるからこそ、親戚は銀行志望者の多さに驚いたのだ。
そこで二つの考えが頭に浮かんだ。
銀行やそこで働くバンカーはかつてと今とで大きく変わった。幅広い世代に「銀行とは何か」「バンカーとはどんな生き物か」を尋ねても答えが収斂しなかったのは当たり前である。ここは考え方を改めて「銀行とは何か」や「バンカーとはどんな生き物か」に答えを求めず、銀行やバンカーがどんな変遷を遂げたかを辿ってみたらどうだろうか。
もう一つはこうだ。
世の中には銀行の変遷を辿った「銀行史」は山ほどある。しかし「バンカー史」はない。そうであれば時代ごとのバンカーの自画像を浮き彫りにし、変化の軌跡が環境変化に相応しいものだったのかを検証することには意味があるに違いない。
本書はそんな試行錯誤を経て書き上げたものなので、週刊文春での連載とは趣がだいぶ違う。登場するエピソード等は連載時と同じでも、かなりの部分で分析が当時と異なる。
二〇二三年三月末時点でバンカーは二十六万四千人超(全国百十行の職員数、全国銀行協会調べ)にのぼるという。この中にはバンカーを続けようとしている人、どう続けるか悩んでいる人、バンカーを辞めようとしている人がいる。これとは別にバンカーになろうとしている人がいて、バンカーを辞めた人もいる。立場の異なるそれぞれの人にとって本書の分析が今後の行動を考えるきっかけの一つになれば幸いに思う。(文中敬称略)
「はじめに」より