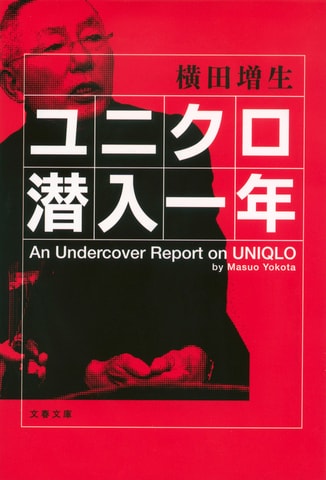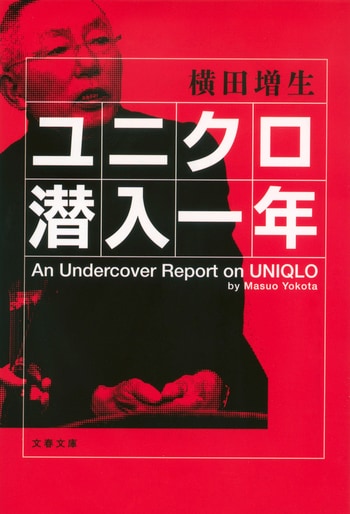ユニクロ社長・柳井正氏は、自社がブラック企業と批判されていることにたいして、「限りなくホワイトに近いグレー企業」と余裕をみせて答えている。完全なホワイトではない、とは謙遜かそれともホンネなのか。
「悪口を言っているのは僕と会ったことがない人がほとんど。会社見学をしてもらって、あるいは社員やアルバイトとしてうちの会社で働いてもらって、どういう企業なのかをぜひ体験してもらいたいですね」
挑発的である。この作品『ユニクロ潜入一年』がユニークなのは、前著『ユニクロ帝国の光と影』を出版して名誉毀損で訴えられ、損害賠償(二億二千万円!)、さらに出版差し止め処分を請求された文藝春秋と、訴えられなかった著者とが手を携え、地裁、高裁、最高裁と争ってユニクロの訴えを退けたあと、追撃の一冊として出版されたことにある。
これは、著者が柳井社長の挑発に乗ったかたちで、ユニクロのいくつかの販売店にアルバイトとして入職、さらにかつて働いていた労働者に取材して書いた、冷静沈着な一書である。サービス残業の恒常化などを自己体験で確認、柳井氏に叩き返した証拠であり、完璧な「勝訴」の記録である。
売り上げ額を誇るような大企業が、言論にたいして「フェイク」と声高に主張して、「スラップ」(恫喝訴訟)を構える典型的な事例である。しかし、企業は社会的存在であって、「コンプライアンス」(法令遵守)ばかりか、内外の批判を謙虚に受け止めて改革し、時代にあわせていかないかぎり生き残れない。いまの時代は内部の批判者としての労働組合が無力化し、経営者が社内民主主義を自己点検する志向が弱まっている。
企業経営は内外の批判に対応し、時代のニーズに合わせるのが賢明なはずだ。社内では箝口令を敷き、外部の批判にたいしては威丈高に高額な賠償請求を振りかざす。批判者を恫喝するのは、経営者の狭量を示して美しくない。世界から注目されているユニクロが、「巨大な柳井商店」の流儀のままでいるのか、企業内言論の自由を確立し、働くものを大事にする大らかな社風で、世界に迎え入れられるのか、その問いかけとしてこの本は貴重である。
本書を読んで意表を衝かれる想いがしたのは、年間売り上げ八七二九億円、純利益五二八億円、従業員五万二八三九人。世界に冠たる大企業が、つねにアルバイターを募集し続けるほど、人手不足が常態化している現状である。販売をささえているのは、主婦と学生、短時間勤務のアルバイターたち。五十過ぎの著者でも即決採用、翌日出勤で迎え入れられるほどに、労働者が払底している。
ユニクロは世界にむけて店舗を展開しているのだが、あたかも広大無辺の戦場をとりとめもない傭兵でカバーしていて、さほどの不安感をもっていない。それが流通業界に不案内なわたしをまず驚嘆させた。