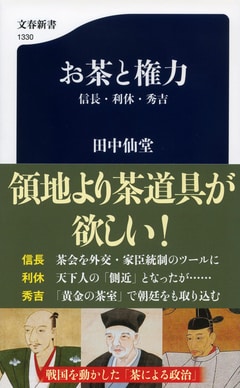『茶の湯の冒険 「日日是好日」から広がるしあわせ』は不思議な一冊だ。
読む者によって、さまざまに色合いをかえる。いや、同じ読み手であっても、その時おかれた状況によって、まるで違う読み物となるのではないだろうか。
わたしは、『茶の湯の冒険』と改題される前の単行本『青嵐の庭にすわる』を数日の日を挟んで、三回読んだ。最初の一回目は、解説を引き受けたならば自分なりに読みこなさねばとの気負いと共にページをめくった。が、そんな情動はすぐに失せて、いつの間にか、ただ一読者として作品の中にのめり込んでいた。ほんとうに、心身が共にずぶずぶと沈んでいく、あるいは呑み込まれていくような感覚だった。二度目は、もう少し己を律し、冷静に読み解く心構えで向き合った。すると、一読目では気がつかなかった騒めきが立ち上ってきたのだ。
風音、雨音、足音、撮影機材の音、喚声、笑声、大声、囁き、胸の鼓動、人の動き回る気配、感情の起伏……ある時はリアルな物音として、ある時は人の内にある幻に似た音として、一冊の本の中から様々に流れ出してくる。さらに、そこに、茶人としての作者が捉えた音や香りや色合いが混ざり込む。
松籟、白木の三方に載せられた小さな米俵の金色、着物の華やかな色と柄、朱塗りの盃、雪の庭の静寂、濃茶の香り……。実にさまざまなものが絡まり合い、うねり合って、読み手に迫ってくる。静寂を内包した騒めきが確かに伝わってくるのだ。
そこには人がいた。
監督や俳優を始めとする映画の撮影スタッフが、お茶の道に携わる人々が、そして、作者自身がいた。作者の森下さんは、自分を含めて「日日是好日」という映画に関わる人たちに飽くことのない好奇心を抱き、じっくりと冷静に眺めたかと思うと、相手の持つ魅力に理屈でなく引き込まれて心を揺らせる。
それは、“樹木希林”という稀代の役者に対してだけではない。黒木華さんや多部未華子さんら実力派の人気俳優に対してだけでも、異彩を放つ大森立嗣監督に対してだけでもなかった。森下さんの眼差しと心と筆は、あらゆる“人”に向いているのだ。
原作者でありながら茶道指導者の役目を担いスタッフの一人となった森下さんは撮影現場を目の当たりにして、驚きと感嘆の日々を送ることになる。
樹木希林さんの演技と生き方はむろんのこと、多くの技術者たちの仕事の一つ一つに森下さんは真っすぐに驚き、真っすぐに感嘆する。
こんなことができるなんて。
こんなことまで表現するなんて。
ここまでやるのか。ここまでやれてしまうのか。
すごい、すごい、すごい。映画の撮影現場ってすごい。
『茶の湯の冒険』の一節一節から、森下さんの興奮が響いてくるようだ。
映画原作の『日日是好日』の中に、十五歳の少女ひとみちゃんが登場する。茶道に憧れ、森下さんの師、武田先生に弟子入りしてきたのだ。そのひとみちゃんが茶道に関わるあらゆるものに、生き生きと反応する様が、撮影現場に触れた森下さんの瑞々しい態度と重なる。少なくとも、わたしには、重なって感じられた。『茶の湯の冒険』は、森下さんの内から溢れる少女のときめきを伝えてくれるのだ。
それは、作家森下典子の筆の力があってこそ伝わってくるものでもある。過剰でも過小でもなく、身の内や外に生じたものを淡々と的確に、しかし、どこにもなく誰にも真似できない文体で表す。森下典子の文章は自在で自由でありながら、独自の規律があり、優美かと思えば、わたしたちの日常の言葉にするりと寄り添う。
これは、茶道に似ている……のだろうか。
と、わたしは胸の内で呟いた。
わたしは茶道とは無縁の、ペットボトルのお茶をラッパ飲みするような人間である。それでも『茶の湯の冒険』や『日日是好日』を読んでいると、茶道が一部の選ばれた人たちの稽古事ではなく、わたしたちの日々の暮らしと細やかに結びついていると思えるのだ。己を解放すること、楽に息をすること、自然の理に身を置くこと、他者を知ること、一日一日を生きていくこと。そんなところに繋がっているのだと。
森下典子の文章もそうだった。
少女のときめきを書き切るためには、大人の思索と書き続けることで生まれる底光りする文体がいる。大切な茶席に、選び抜かれ、磨き抜かれた道具がいるように。
そして眼もいる。
対象を熱を込めて、しかし、冷静に見つめる眼だ。これも、少女は持ち得ない大人のものだった。『茶の湯の冒険』の内で、森下典子によって描き出される人々は誰もがプロだ。樹木希林さんは、一際見事なプロ中のプロの仕事を見せてくれた。森下典子の筆は、そのすごさを丁重に丁重に表す。森下さん個人が圧倒される様も余すところなく書き上げる。けれど、そこに留まらない。樹木希林という、あまりに大きな光に眼を眩ませることなく、他のスタッフのプロ振りもきちんと捉えているのだ。
結果『茶の湯の冒険』は、見事なお仕事エッセイになった。
俳優、監督、プロデューサー、大道具、小道具、音響、照明、衣装……、何十人もの仕事師たちへの賛歌となりえたのだ。それが、作家森下典子の為した、プロの仕事である。
三度目の話をしよう。
三度目、『茶の湯の冒険』を読み終えたとき、騒めきは遠のいていた。
かわりに、しんと静まり返った寂しさ、寂寥に近い情が心を満たしていく。
怖いほどの静かさだった。
それがなぜなのか、わたしには確とは摑めない。
樹木希林さんが亡くなられたからなのか、映画の撮影が終わりを迎えたからなのか、他に理由があるのか、掴めないのだ。
掴めているのは、ここまで静かで穏やかな寂しさを初めて味わったことだけだ。
そこまで思いを巡らせ、『茶の湯の冒険』というタイトルの意味が分かった気がした(飽くまで、あさのが勝手にわかった気になっているだけかも)。
この本は心を未知の世界に誘ってしまう。これまで知らなかった、触れてもいなかった世界、ここではないどこかに連れていくのだ。
日常に添いながら遥か高みに引き上げ、遥か高みに導きながら、必ずわたしたちの日々に戻ってくる。けれど、その日常はこの一冊を知らなかったころの日常とは微妙に違っている。
この変化を冒険と呼ばずして何と呼べばいいのか。
茶を点てるとき、人の身体は大きく動かなくても心は新たな世界を進んでいるのだろうか。うーん、やはりわたしには答えが出せない。
この先、森下典子の作家としての冒険に目を凝らさねばならない。そこだけは、確信している。