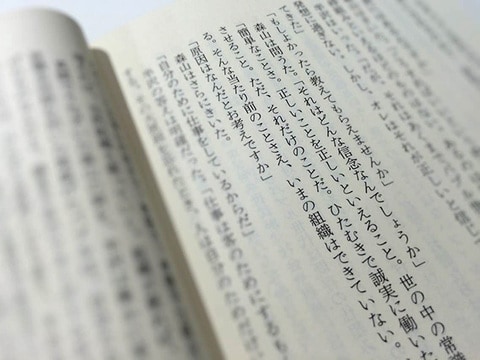4月13日からスタートのドラマ『花咲舞が黙ってない』。
今田美桜が演じる花咲舞が、大手銀行を舞台に不正を見逃さず、弱い立場の人たちのために立ちあがる痛快インターテインメントだ。
放送を記念して、池井戸潤の原作『花咲舞が黙ってない』(中公文庫/講談社文庫)と『不祥事』(講談社文庫/実業之日本社文庫)に収録されている、文庫解説を全文公開する。(全3回の第1回)

二十世紀末の銀行を描く
珍しい――というか池井戸潤にとって初めてのことである。自身の原作によるTVドラマのタイトルを後追いで採用したのは。
二〇〇四年に刊行された連作短篇集『不祥事』は、一四年、『花咲舞が黙ってない』というタイトルでTVドラマ化された。原作『不祥事』には、“花咲舞が黙ってない”という短篇は収録されていないのだが、講談社文庫で刊行された際の帯のコピーが“花咲舞が黙っていない”であった。TVドラマのタイトルは、これを参考にして『花咲舞が黙ってない』に決められたそうだ。そして今回、池井戸潤はそれを『不祥事』の続篇となる書籍のタイトルに採用したのだ(これまでの池井戸潤原作のTVドラマは、あの『半沢直樹』と、『銀行狐』収録の短篇を単発でドラマ化した『覗く女』を除くと、原作のタイトルを採用していた)。
なので、TVドラマ『花咲舞が黙ってない』のファンが、原作である『不祥事』を読まぬまま、この本書を書店で手にするケースも少なからず生じるだろう。もちろんそれでも愉しめる小説なので全く構わないのだが、念のため、ここでTVドラマの原作の紹介をしておくとしよう。
『不祥事』は、独立した魅力を持つ八つの短篇からなる一冊であり、しかも、八篇を連ねて、東京第一銀行のなかに潜んでいた“闇”を炙りだすという作りとなっていた。その『不祥事』の第一話「激戦区」で、花咲舞と上司の相馬健はコンビを組んで臨店指導グループとしての活躍を開始するのである。
最初に登場するのは相馬だ。かつては大店で融資係として活躍していた彼は、赤坂支店に異動になる際に課長代理に昇格した。次のポストは融資本部間違いなしといわれていたが、赤坂支店で副支店長と衝突し、次の転勤で営業課に回された。それから五年、相馬は屈辱の日々を送ることになった。支店長からはバカにされ、副支店長に嫌みをいわれ、出世競争から落ちこぼれた。だが、二ヶ月前に本部調査役に収まることができたのだ。職級としては、課長代理も調査役も同じなのだが、東京駅前の銀行本店十階の自分のデスクから八重洲の街並みを見下ろす気分はなかなかのものだった。
相馬の調査役としての主な仕事は、営業課の事務処理に問題を抱える支店を個別に指導し、解決に導くことである。その彼に、初めて部下が付くことになった。それが入行五年目の花咲舞である。代々木支店時代にもやはり相馬のもとで働いていた舞は、ひどいはねっ返りで上司を上司とも思わない行員だった。その彼女が、再び相馬のもとにやってくることになったのである。相馬の口をついて出たのは、花咲という名前ではなく、「狂咲」(くるいざき)という当時の呼び名だった……。

こうした具合に再会した二人は、自由が丘支店での誤払い事案を皮切りに、数々の問題の真相を究明していった。その姿を描いた『不祥事』が刊行されたのは二〇〇四年のこと。続篇である本書『花咲舞が黙ってない』の刊行は二〇一七年だ。続篇刊行までに十三年もの年月が経過しているが、作中の時代設定は本書も二十世紀末目前であり、『不祥事』と連続している(臨店指導グループのフロアは十階から四階に移動したようだ)。もちろん、本書は、『不祥事』刊行当時の読者にも、TVドラマをきっかけに『不祥事』を読んだ読者にも、あるいはTVドラマを観ただけの読者にも、素直に愉しんで戴けるように書かれている。さらにいえば、本書からまず読んでも全く問題はない。
さて、東京第一銀行を蝕む“闇”は、本作に至っても姿を変えて存続しており、今回は、さらに上層部の姿勢が問われる展開となっている。というのも、東京第一銀行そのものの存在を揺るがしかねない巨額の赤字が現実のものとして迫ってきていたからである。大口取引先のハヤブサ建設が破綻し、二千億円もの不良債権を抱え込んでしまったのだ。
二十世紀末といえば、一九九七年に上場ゼネコンの東海興業が破綻するなど、大手を含むゼネコンが会社更生法適用を申請したり、あるいは、債務免除で生き延びたりしてきた時代だ。そうした動きと連動するように、金融業界においても、北海道拓殖銀行や山一証券が破綻し(九七年)、翌年には日本長期信用銀行と日本債券信用銀行も破綻(九八年)した。生き残った企業においても、九九年には第一勧業銀行と富士銀行に日本興業銀行を加えた三行がみずほフィナンシャルグループの設立に動き出すなど再編が始まり、“銀行に入れば一生安泰”といわれていた時代は終わりを迎えようとしていた。この『花咲舞が黙ってない』は、そんな時代の物語である。
七つの短篇
第一話「たそがれ研修」は、いかにもそんな時代らしいシーンで幕を開ける。ハヤブサ建設の破綻に伴い、“東京第一銀行、空前の大幅赤字予想”なる見出しが経済新聞の金融面を飾った日のこと、自分たちのボーナスへのダメージを嘆いていた舞と相馬たちの上司である芝崎次長が研修から帰ってきた。シニア管理職研修、いわゆる“たそがれ研修”であり、数十年必死に銀行のために働いてきた管理職が、銀行に頼らずに第二の人生を切り拓くことを求められる研修である。三人ともモチベーションが下がるなか、芝崎は、舞と相馬の臨店指導グループに新たな指示を下した。赤坂支店での顧客情報漏洩疑惑の調査だ……。この短篇、ミステリとしては舞の発想の転換が冴えている。ちょっとした偶然の後押しもあるが、それにより新たな視点での調査を行うことができて、真相へと到達できるのだ。そしてその真相が明らかになるシーンが、また印象的だ。犯人が心情を吐露するのだが、本人はそれこそ激白したつもりであっても、視野が根本的に狭いことが読み手に伝わってくる。井の中の蛙の激白なのだ。その犯人が舞に一喝される姿の滑稽な悲哀が、深く心に残る。
続く第二話で花咲舞と相馬は、事務ミスを連発する現場の様子を窺いに、銀座支店へと赴く。直近で発生していたのは、小切手取引に固有の事務処理に関するミスだった。それによって、ある会社から取引先への振り込みが予定通りに行えない事態が発生してしまったのだ……。この問題に関する原因究明やその後の対処について臨店指導グループの二人が探ることになるのだが、ここでもやはり花咲舞の着眼点が冴えている。ある記載事項(それは単なる英数字の列に過ぎないのだが)に気付き、それが意味する“不自然さ”を見抜くのだ。こうした花咲舞の推理の経路を愉しめる「汚れた水に棲む魚」は、同時に、本書を貫く大きなテーマが具体的に顔を出し始める一篇でもある。鍵を握る人物は、頭取の牧野治、企画部長の紀本平八、そして紀本の懐刀と呼ばれる切れ者、企画部の昇仙峡玲子調査役だ。彼等が――具体的には昇仙峡玲子が企画部特命担当として――東京第一銀行のため、手段を問わずに動き始めるのである。
第三話「湯けむりの攻防」の舞台は、九州の別府だ。老舗旅館の白鷺亭において臨店指導グループの二人は、天然鮎塩焼き、キスの天ぷら、ヒラメ薄造り、豊後牛のステーキなどなど、最高の料理を堪能する。臨店先の別府支店の計らいでもあったが、白鷺亭側にも二人をもてなす理由があった。別府の町おこしに協力して欲しいというのだ。白鷺亭が旗振り役となって別府全体を守り立てるべく融資を申し入れているが、なかなか話が進まず、打開に向けて力添えをしてもらえないかという期待だった……。この第三話は、ミステリとしての謎解きではなく、銀行の能力が試される様を重視した一篇となっている。適切な融資判断を行えるか、だ。そしてその積み重ねが、銀行そのものの力であることを、かなり衝撃的な形で読者は――そして花咲舞も相馬も――知ることになる。
物語の折り返し点となる第四話「暴走」は、新宿駅東口繁華街で車が暴走し、三十人超の重軽傷者を出した事件で始まる。“世の中への不満”を動機として述べた運転手の男が、暴走に先だって東京第一銀行四谷支店でローンを断られていたことが判明する。マスコミから何か言われる前に、銀行としての手続きに問題がなかったことを確認するために四谷支店を訪れた花咲舞と相馬は、さしあたり問題ではないものの、気になる書類を発見する。そしてさらに深く調査を進めた舞と相馬は、ある悩ましい真実に到達してしまう……。これもまた銀行としての力量が試される一篇だ。
こうして東京第一銀行のなかにギスギスとした空気が充満していく様子が浮き彫りにされていくなか、第五話「神保町奇譚」は、一服の清涼剤として機能している。寿司屋を訪れた舞と相馬は、同席した一人客の女性が、亡くなって五年になる娘の通帳に、死後も動きがあったと話すのを耳にする。舞たちは、その口座が自行のものではないながらも、謎の解明に協力する。そして見えてきた真実――なんとも素敵な短篇小説である。人物、謎、舞台。小説を構成する要素が、適材適所に配置されていて、実によい。
その素敵な余韻がまだ読み手の心に残るうちに始まる第六話「エリア51」。このあたりまでくると、窮地に陥った東京第一銀行をめぐる大きな物語としての色彩が濃くなってくる。この第六話の冒頭では、東京第一銀行がメーンバンクを務める東東デンキに巨額粉飾の疑惑があるとの報道が流れる。それはそれで銀行にさらに数千億円の痛手をもたらすのだが、舞と相馬は、もっと重大な情報を偶然入手してしまった。そして銀行の危機意識と臨店指導グループの正義が軋む……。
物語はそのまま最終話「小さき者の戦い」へとなだれ込む。この最終第七話は、実は全体の七分の一ではなく、五分の一以上を占めるという、ボリュームたっぷりの作品である。ここでは、第六話で臨店指導グループに生じた大きな変化から新たな謎が掘り起こされ、そして第六話で提示された情報をさらに深掘りする形で、東京第一銀行を巡る大きな物語に一つの決着が示されている。また、あえてこの解説では筆を控えてきたが、昇仙峡玲子など、本書のそこここで顔を出してきた面々も、しっかりと活躍している。『花咲舞が黙ってない』のラストを飾るに相応しい重みのある一篇なのだ。
全七話を読み終えると、この『花咲舞が黙ってない』が、TVドラマのテンポのよさを保ち、花咲舞の啖呵の痛快さも維持しつつ、それだけではない深みを備えた小説に仕上がっていることを体感するだろう。ひとりひとりが確かな存在感を持ち、それぞれに自分なりの人生を重ねてきた面々が集い、互いに影響を及ぼし合って、この物語は完成しているのである。フィクションの痛快さと、フィクションだからこそ描きうる苦いリアリティを極めて高い次元で両立させた一冊なのである。
TVドラマと新聞連載
この花咲舞の新作は、読売新聞の二〇一六年一月十七日から十月十日にかけて連載された。今年(一七年)の五月に刊行された『アキラとあきら』は、〇六年から〇九年にかけての雑誌連載に相当手を入れてから発表されたが、新聞連載からさほど間を置かずに刊行された本書『花咲舞が黙ってない』は、ほぼ連載時のままだという。
とはいえ、新聞連載の段階では、当初の構想と異なる展開もあった。連載の途中で、新聞社からもっと続けて欲しいという要請があり、それに応えて終盤の大きな闇に費やす枚数を増やしたのだという。予定にない延長だったとはいえ、『花咲舞が黙ってない』の完成度や充実度という観点でいえば、結果的にはありがたい要請だったといえよう。
連載に際して池井戸潤は、読者が朝刊で毎日続けて愉しめるものにすべく、軽く読めるものを意識したそうだ。主人公も、それなりに世間の認知を得たキャラクターがよかろうと考えた。また、純然たる長篇にしてしまうと、連載途中でついて行けなくなる読者が出てくる可能性があることも気にしたという。そうした考慮の結果、一四年、一五年と二度にわたってTVドラマ化された花咲舞を主人公とする連作短篇集という枠組みが決まったのである。であるが故に、執筆時にはTVドラマのテイストも意識した。池井戸潤は具体的に役者をイメージすることはせずに書いたというが、おそらく、多くの読者は脳裏に杏をはじめとするあの俳優陣を浮かべつつ読み、しかも全く違和感を覚えないだろう。つまりは、ドラマの視聴者が朝刊の連載小説にすんなりと入り込めるということだ。ちなみに、花咲舞の父(大杉漣演じる幸三)が営む居酒屋「花咲」は、ドラマでは重要な役割を果たしており、レシピ本が出されるほどであったが、本書には登場していない。残念といえば残念だが、第三話の別府や第五話の寿司屋など、魅力的な飲食シーンはこちらにも登場しており、読者としては十分な満足を得られるだろう。
連作短篇集という形式についていえば、池井戸潤はこれまでにも『銀行総務特命』(〇二年)や『仇敵』(〇三年)など、いくつも発表してきている。そうしたなかで、著者本人が節目の作品と位置付けているのが、『シャイロックの子供たち』(〇六年)だ。この作品は、登場人物のそれぞれに著者として心を寄せて、それに基づいて物語を動かすという作劇法に池井戸潤が到達した一冊である(一話ごとに視点人物を交替させてその人物をくっきりと描きつつ、それらの短篇が全体で一つの物語を構成するかたちで書かれていた)。『シャイロックの子供たち』以降のすべての池井戸作品は、この作劇法で生み出されてきており、本作も例外ではない。そうした観点で舞や相馬以外の登場人物の心にも目を配って読んでみて戴きたい。必ずや発見があるはずだ。
そうそう、『花咲舞が黙ってない』は、書籍としては十三年ぶりの続篇になるが、花咲舞が主役の中篇が単独で電子書籍として販売されていることも紹介しておこう。二〇一〇年十一月から翌年六月にかけて『ニッキン』(日本金融通信社)に連載された「犬にきいてみろ」だ(つまりはTVドラマ放映前の一作)。ある人物の不正を暴こうと花咲舞が奮闘する作品だ。独立した作品ならではの花咲舞の弾けっぷりと、ユニークでとぼけた結末が愉しめるミステリであり、読み逃す手はない。
もう一つの大きな物語
本書は東京第一銀行を主人公とする物語でもある。過去の不適切な行為の積み重ねと、その問題への不適切な対応の積み重ねによって歪みきった東京第一銀行が、巨額の赤字によっていよいよ追い込まれた際、いかに振る舞うか。それを読ませる作品でもあるのだ。
そこにはトップダウンの取り組みもあれば、花咲舞たちのボトムアップの改善もある。いずれも推進は容易ではないし、上層部と現場でベクトルが一致するとも限らない。それでも座して死を待つのではなく、行動する人々がここにいる。誰の判断や手段を支持するかは読み手次第だろうが、前述のように、その判断や手段にはその人の人生が投影されており、それぞれに懸命である。
それらの登場人物のなかで特に注目して戴きたいのが、企画部長として昇仙峡玲子を操る紀本平八だ(『不祥事』に神戸支店の副支店長として紀本肇なる人物が登場しているが、それとは別人で無関係)。彼は、この『花咲舞が黙ってない』とほぼ同時に文庫版が書店に並び始める『銀翼のイカロス』という《半沢直樹》シリーズ第四弾にも顔を出している。本書と『銀翼のイカロス』をあわせて読むと、紀本というバンカーの約二十年が見えてくるのだ。彼の生き方を、半沢直樹の勤める東京中央銀行の中野渡頭取や、あるいは、紀本の上役であり、花咲舞や相馬たちの東京第一銀行のトップでもある牧野治頭取などのバンカー人生と比較してみるのも一興。ちなみに作中の時代設定としては、本書の方が過去を描いているが、『銀翼のイカロス』を先に読んでも愉しみは些かも減じられないのでご安心を。
この『花咲舞が黙ってない』は、現時点では、さらなる続篇が書かれる予定はないそうだ。少々寂しくもあるが、それはそれとして、十三年ぶりの新刊として書店に並ぶことは、まずなにより喜ばしい。その内容が圧倒的に充実したものであったから、喜びはなおさらだ。
2017年9月
(むらかみ・たかし 書評家)