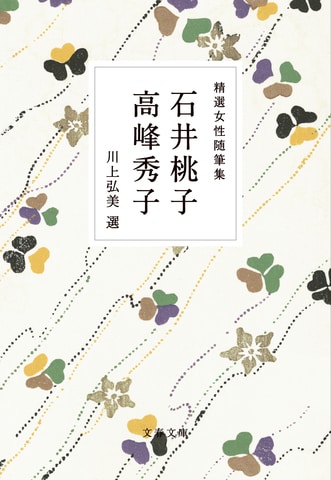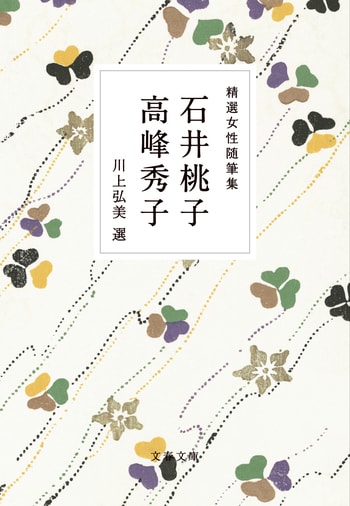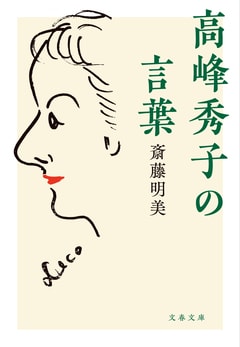石井桃子は、幼年期を回想した『幼ものがたり』を《子どもの館》一九七七年四月号から翌年の五月号まで連載し、一九八一年に福音館書店から刊行した。
「まえがき」にはこう書いてある。〈幼い子どもの心に残ったものであるから、あるところはきれぎれであり、また、いまとなっては、真偽の保証もできないようなものだが、それを承知で、私はこれを書きとめておこうと思いたった〉。
私たちはこういう幼年期の回想記をいくつか持っている。『幼ものがたり』刊行の三〇年前に、幸田文が『みそつかす』を上梓した。『みそつかす』のさらに三〇年前には、中勘助の『銀の匙(さじ)』が単行本化された。
『幼ものがたり』の「まえがき」には、当時彼女の一家が住んでいた旧浦和宿の家の間取図が描いてある。〈井戸〉〈鳥小屋〉〈外便所〉〈ウサギ小屋〉〈かまど〉〈大釜〉などの具体的な位置が示してあって興味深い。
『幼ものがたり』は全部で約七〇篇の断章から構成されていて、主題別に章立てされている。本書の第一章「『幼ものがたり』より」はそのうちの二六篇を収録している。本巻での掲載順は変わっていない。
最初の「『どっちがすき?』」から「ねずみ」までの四篇は、冒頭の「早い記憶」の章から採られている。ここで石井桃子は意識の海面から、自分のいちばん古い記憶にむかって錨を下ろしていく。
錨が海底に届いたところで、こんどは家族のことへと話題が進む。「祖母」から「もっこに揺られて」までの一二篇は「身近な人びと」と題された章から。
これは明治末年のことだから、この言葉で私たちが考えるような核家族ではもちろんない。〈まあちゃん〉のような、ひとことでは位置づけにくい関係の人――まあちゃんは、父のいとこだということが〈大きくなるにつれ、いつとはなしにわかって〉くる――が同居している、もう少し大きくて流動的な共同体なのだ。
長い時間を生きていない子どもにとって、家族という概念はまだ「時間」のなかでとらえられていない。家族とはなによりまず関係だ。そして他人ではあっても、どこか自分というものの空間的な延長としての性質を持っているものなのだ。
つづいて、「雪の日」「夏の遊び」「指」の三篇は「四季折々」という章から採られた。季節とは、循環して繰り返す時間だ。世界各地の神話を創り出したこういう時間のことを、カイロス的時間と呼ぶ。時間のカイロス的な側面は、年中行事や季節感によって区切られる。この三篇は、雛祭を題材とした石井桃子の童話『三月ひなのつき』(一九六三)と併せて読むものなのかもしれない。
自分を中心とする空間としての家族、循環するカイロス的な時間、いずれも自己意識の文脈に依存した直示(ダイクシス)的・転換子(シフター)的な認識のありようだった。直示とか転換子とかいうのは、「私」「あなた」「いま」「きのう」「むかし」「来年」といった、発話者の立場によって指すものが変わる表現のことだ。
『幼ものがたり』のフラグメントの配列は、こういった直示的世界から、地図的な空間把握および年表的な時間把握へと進んでいく。「Kちゃん」から「遠い隣」までの四篇は「近所かいわい」という章に収められたものだ。〈田中さん〉の家とか〈伊勢屋〉といった固有名は、発話者の立場から独立して対象を指し示すためのものだ。つまり、転換子的な世界認識から、固有名による世界認識へと、ここで変化している。
最後の三篇は「明治の終り」という章から。ここにあるのはカイロス的時間ではもはやない。繰り返さずに一直線に進み、ニュースや歴史といった形で外から指示される、クロノス的な時間である。
『幼ものがたり』の語りの手際は、たんに焦点がくっきりしているというのではない。石井桃子の文章は、記憶の曖昧さを曖昧さのままに提示できる。さらに今回改めて読んでみて、章立てが律儀なまでにシステマティックであることに驚いた。明晰で、幼い心が世界を把握していく段階を再構成するかのようだ。この明晰さがこの人の文章の味わいなのではないか。
石井桃子の創作や文章から編んだ選集『石井桃子集』全七巻が、一九九八年から九九年にかけて岩波書店から刊行された。第三巻までが創作(絵本テクストを含む)、第四巻が先述『幼ものがたり』、第五巻が『新編 子どもの図書館』、第六巻が『児童文学の旅』、第七巻がオリジナル編集の『エッセイ集』となっている。最新作だった長篇小説『幻の朱(あか)い実』(一九九四)は収録されていない。
『石井桃子集』の功績はとりわけ、彼女の業績のなかでもっと言及されていいはずの小説『迷子の天使』を第三巻に収録したことと、第七巻でエッセイをまとめて読めるようにしたことだと思う。
第七巻は一九五一年から半世紀近くにわたって書いてきた文章六一篇を収録し、書き下ろし一篇を加えたものだった。本書第二章はここから六篇を選んでいる。
石井桃子の多面的な活動のひとつとして、児童書にかんする施設や運動体の運営がある。白林少年館、家庭文庫研究会、かつら文庫、東京子ども図書館などである。こういった活動のなかから中川李枝子文・大村(山脇)百合子画の『いやいやえん』も登場した。「生きているということ」は、自ら設立した東京子ども図書館の《おしらせ》二〇号(一九七九年一月)に掲載したもの。
石井桃子の創作でもっとも有名な『ノンちゃん雲に乗る』は戦後に登場した「戦時下文学」である。そのあたりの事情は「自作再見『ノンちゃん雲に乗る』」で回想されている。《朝日新聞》一九九一年九月二二日に掲載された。
石井桃子は戦後、児童文学研究者としてたびたび英語圏を訪れた。移動すること、人と出会うことについてどう考えていたか、「ひとり旅」(角川書店《俳句》一九七六年一月)と「ヘレン=T」(《びわの実学校》一九八四年五月)で彼女は少しだけ教えてくれている。
「太宰さん」(岩波書店《文庫》一九五七年六月)と「井伏さんとドリトル先生」(筑摩書房『井伏鱒二全集』第一二巻月報、一九九八年一一月)は、このふたりの小説家との交流を回想したもの。石井桃子と太宰治の縁については、井伏鱒二の随筆「をんなごころ」にも違う角度から書かれている。
犬養道子の回想記『花々と星々と』『ある歴史の娘』に、若いころの石井桃子が登場する。祖父・犬養毅が菊池寛を介して蔵書整理のために雇った、日本女子大出の海老茶袴(えびちゃばかま)の女性だ。「クマのプーさん」シリーズ日本語訳のきっかけは、西園寺公一(きんかず)が『プー横丁にたった家』の原書を幼い道子の弟・康彦にクリスマスプレゼントとして贈ったのを、石井桃子が道子たちに訳して聞かせていたことだったという。
石井桃子は児童文学の研究者であって、同時に実作者として童話や絵本の創作も残した。
かなり年長の読者であれば、映画化された『ノンちゃん雲に乗る』の作者としての石井桃子を真っ先に思い浮かべるかもしれない。それより下の世代になると、たぶん、幼時に本の表紙の「石井桃子訳」というか「やく いしい ももこ」という表記によって、世のなかに翻訳というものが存在することを知ったのではないか。
石井桃子は「うさこちゃん」(ナインチェ、英語圏ではミッフィー)やプーさんやピーターラビットといったシリーズものを翻訳し、エリナー・ファージョンをはじめとする重要な作家たちを紹介した。また編集者・プロデューサーとして、『ドリトル先生』を井伏鱒二に、『星の王子さま』を内藤濯(あろう)に、『たのしい川邊』を中野好夫に訳させた(中野訳は抄訳、のちの石井自身による全訳が『たのしい川べ』)。岩波少年文庫の創刊にかかわった。
だから彼女は児童文学翻訳史上最大の重要人物として記憶されているのだけれど、とはいえこの人は「大人の作家」なのだ。
幼年期を回想した『幼ものがたり』において、回想する語り手である〈私〉と回想される主人公である〈私〉とがだらしなく一体化する箇所は一ページとして存在しない。両者はいつもきっぱりと、フェアに分かれている。
石井桃子はいつでも、大人の態度で文章を書く。彼女のエッセイの読者は、それを読みながら、大人であることが自分に求められていると気づくのだった。