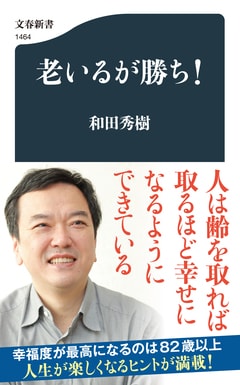〈「私の反論がカットされていた。これが編集というものかと」田嶋陽子が90年代の『TVタックル』で繰り広げた“戦い”のウラ側〉から続く
「日本でいちばん有名なフェミニスト」として、長年テレビ番組などのメディアで活躍してきた田嶋陽子さん(83)。近年、SNSを中心にフェミニズムへの関心が高まるにつれ、その功績を再評価する動きも出てきています。
ここでは、そんな田嶋さんが9月20日に上梓した『わたしリセット』より一部を抜粋して紹介。90年代、『ビートたけしのTVタックル』で男性出演者と激しい議論を交わしていたことで、仲間であるはずのフェミニストからも嫌われても、田嶋さんがテレビに出続けた理由とは――。(全4回の3回目/最初から読む)

◆◆◆
スカートをはいたら「ひざ頭をキチンとつけなさい」
私がはじめてテレビに出たのは、NHK教育テレビの『英語会話Ⅱ』です。イギリス留学から戻ってきたときに紹介され、1985年から3年間、講師を務めました。
衣装は自分で全部用意していましたが、3年もやっていると着るものがなくなります。だから、昔まだ「女らしくしなきゃ」と頑張っていたときにはいていたスカートを引っ張りだしてきた。そしたら、視聴者からものすごく達筆の手紙が届きました。そこには「女性なんだから、ひざ頭をキチンとつけなさい。足を開いているのを見ると、同じ女性として恥ずかしい」と書かれていました。やむなく、スカートをはいて出演するときは、スカートのなかで太ももを革のベルトで縛りつけるようになりました。
でも、トーク番組や討論番組では、精神が集中できないのが嫌なので、スカートをはきませんでした。人間はここ一番と踏ん張ると、男であろうと女であろうと、ひざ頭は開いてしまうからです。「女らしさ」の強制は、健康で自然な状態を抑圧する。だから、女は精神的にも肉体的にも二重に不利になるのです。
『英語会話Ⅱ』で私のファンになってくれた人もいましたが、私がバラエティ番組に出はじめると、その人たちも離れていきました。そのころは、男の人はほとんど全員が私のことが大嫌いでしたけど、女の人も半分くらいは私を嫌いだったと思います。当時は、ほとんどの女の人がフェミニストになりたくなかった。男社会に嫌われたら、女の人は生きていけないから。心のなかに不満を抱えていても、構造としての女性差別があるなんて思えないし、思いたくもない。だから、私が言いたい放題言うと、不安になったのでしょう。
男たちはそこに目をつけて、女同士を戦わせようとしてきました。『TVタックル』でも「女の敵は女」という企画で、男たちが見ている前で女たちを討論させようとしたことがあります。でも、私はそれに乗りませんでした。あれでは闘犬と同じですから、すごく卑怯だと思います。
たったひとりのフェミニズム運動
私がバカにされたり笑われたりしたのは、一つには「権利を主張する女なんて、ブスで結婚もできない女」という世間のイメージにぴったりだったからかもしれません。でも、私はそんなことではビクともしません。「そのうち、あんたたちが泣きべそかくよ」と思っていました。今まさにそうなっているでしょう。
テレビでバカにされながらも頑張れたのは、私が大学教授という立場だったからです。社会的にいえば、下手な男より地位が上だと思われていたから、少しは耳を傾けてもらえることもあった。みんなは大学教授の女をいじめるのが、うれしくてしょうがなかったでしょうが。もし、私に肩書きがなく、普通のサラリーウーマンだったら、すぐにつぶされていたと思います。少なくともこんなに長く続いていません。
私に捨てるものが何もなかったことも大きかったですね。テレビに出たときはもう50歳を目の前にして、カメの甲羅みたいなものが身についていましたから、叩かれても叩かれても大丈夫でした。もしあれが30代だったら、耐えられなかったと思います。
でも、残念だったのは、仲間であるはずの女性たちからサポートしてもらえなかったことです。とくにフェミニストたちは、本当に私のことを嫌いましたね。あのころのフェミニストは左翼系の人が多くて、反近代主義が盛んでしたから、テレビを超軽蔑していました。私がテレビに出るようになると、「フェミニズムを笑いものにした」とか「フェミニズムが誤解される」といった批判が聞こえてきました。私がお笑い番組に出てバカにされる姿は、見ていて耐えられなかったみたいです。
面と向かって「フェミニズムのことをもっとちゃんと言わなきゃダメじゃない」と言われたこともあります。でも、「あなたを紹介するから、代わりに出てよ」と言ったら、「私はダメよ」だって。その後、実際にテレビに出たフェミニストもいましたが、周りの出演者からワッと言われると何も反論できませんでした。NHKならいいけど、お笑い番組に対応できる人はいなかったですよ。
私は自分が正しいと信じていましたし、批判してくるフェミニストたちには「じゃあ、あんたたち、私のように体を張ってみなさいよ」と思っていました。今から考えれば、たったひとりのフェミニズム運動だったと思います。
私はみんなで集まって旗をもってやるような運動はペースが合わなかったから、私がひとりでできるフェミニズムの運動はこんなところかなとも思いました。テレビに出ることが、私にとってのたったひとりのデモ活動だったんですよ。結果的に、私の周囲からはフェミニストがいなくなりましたが、その代わり、街なかや手紙で一般の女の人たちが励ましてくれるようになりました。
背中を押してくれたのは駒尺喜美さんの言葉だった
それでも、もうテレビに出たくないと思ったことは何度もあります。そんなときに私の背中を押してくれたのが、法政大学の同僚で、ライフアーティストを名乗るフェミニストの駒尺喜美さんです。
駒尺さんは愚痴る私に「テレビは拡声器だよ」と言ってくれました。「せっかくのチャンスだからやめちゃいけない。学者が本を書いて出版しても1000部2000部しか売れないけど、テレビはもっとたくさんの人に届くよ」って。『TVタックル』は視聴率が20%を超えたこともあります。視聴率1%で100万人が見ていると言われていますから、単純計算で2000万人が見ていたことになる。
一方で、『タックル』の前に出ていたNHK教育テレビの『英語会話Ⅱ』の場合は、テキストの売れ具合からみても、5万人くらいしか見ていません。視聴者の数がぜんぜんちがいます。NHK教育テレビで女性の問題を扱ったこともありますが、NHKで真面目にフェミニズムを語っても、見る人は多くはありませんでした。昔は出演者が用意された原稿を読むだけでしたから、話している言葉も自分の言葉になっていませんでした。それでは誰だって退屈します。
こうして私は、フェミニズムの考え方は笑い飛ばしながらでもなんとか世間に伝えるしかないという結論にいたりました。何百年も続いてきた女性差別は、人々の文化や習慣や思想など、あらゆるところに霧雨のように染み込んでいます。ちょっとやそっとの理屈を並べたところで、誰も聞いてくれません。だから、たとえバカにされて笑われても、繰り返し話を聞いてもらうことが大切だと思いました。

テレビに出続けることに対する使命感みたいなものがありましたね。私は自分で育てた私なりのフェミニズムの考え方を伝えていくんだという意識が強かった。ケンカの相手はいつもおじさんでしたが、私はブラウン管の向こう側を意識していました。向こう側にいる女性たちに、もっと自由な生き方があることを伝えたかったのです。だから、おじさんたちに何を言われても怖くなかった。実際、私の話を聞いて、夫に食ってかかる女性が増えたらしく、男の人に恨まれましたね。
最初のころは、毎回あれも言おう、これも言おうと思って出るものの、共演者に邪魔されて思いどおりの発言が出来なくて悔しかった。でも、駒尺さんから「一度に全部言おうとするから辛い。大事なことを1回にひとつ。その代わり100回出たらいい」と言われました。
今から考えると、テレビはオファーがなければ出られないのだから、傲慢なのかもしれません。でも、結果的には何百回も出て、自分の考えを言い続けましたね。『TVタックル』には、12、3年出させていただいたでしょうか。