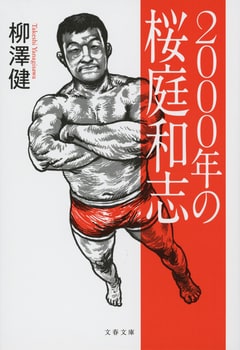80年代に「クラッシュ・ギャルズ」の一員として一世を風靡し、女子プロレスファンの女性たちを夢中にさせた長与千種。9月に配信されたNetflixドラマ『極悪女王』でもその活躍が描かれ、悪役レスラー・ダンプ松本の永遠のライバルとして視聴者たちの心を掴んだ。
ここでは、プロレスをテーマにした数々の著作を持つライター・柳澤健さんの『1985年のクラッシュ・ギャルズ』より一部を抜粋して紹介。長与千種の子ども時代と、小学5年生にして失った、あまりにも大きなものとは……。(全4回の1回目/続きを読む)
◆◆◆
長与千種の子ども時代
父親は千種を男として育てた。洋服も靴も鞄も青いものばかり。おもちゃはミニカーであり怪獣であった。
母親が初めて買ってくれたビニールの赤い靴のことを、千種は今でも覚えている。可愛いひまわりの絵が大好きだった。
しかし、赤い靴を履けば父親の機嫌が悪くなる。千種は赤い靴を靴箱の奥に隠し、時々出しては頬ずりして、再びしまい込んで青い靴を履いた。

小学校に入学する少し前、父親は黒いランドセルを、母親は赤いランドセルを買ってくれた。どちらも選べない千種は両方ともドブに捨て、改めて買ってもらったショルダーバッグを肩にかけて学校に行った。
バッグの中身はカラだった。教科書は学校に置いたままだったからだ。
母親の頑張りの甲斐あって、バーの経営は順調そのもの。「リヨン」の他に市内に6軒の店を出した。自宅の下の「リヨン」には従業員用の大きな黒板があり、父親はその黒板を使って小学校1年生の千種にかけ算や割り算、難しい漢字を教え込んだ。
「学校の先生は通りいっぺんのことしか教えない。みんなと同じことをやっていたら、同じ位置に留まるだけだ。みんなと同じことをするのは無駄だから遊んでこい。学校は遊びに行くところだ」
父親の言葉は絶対だった。
学校のテストは簡単すぎた。あっという間に解答用紙に答えを書いてしまい、後はずっとキョロキョロしていた。「先生からすれば、さぞかしクソ生意気なガキだったはず」と現在の長与千種は笑う。
成績はずっとオール5だった。だが、父親からは強い男の子であることを、母親からは可愛い女の子であることを求められて、千種の人格は必然的に引き裂かれていく。
「バーの子」と言われてバカにされた
幼稚園の頃は鳩小屋に入って寝てばかり。小学校では授業中にもかかわらず教室を抜け出して遊んでいた。母親は学校からしょっちゅう呼び出しをくらい、そのたびに頭を下げた。
赤ちゃんが使うおしゃぶりを小学校入学後も手放せなかった千種は、ついに小遣いを貯めて2つのおしゃぶりを買い、ヒモにつないで首から下げた。寝る時は口にひとつをくわえ、手にひとつを持った。お菓子ばかりを食べて栄養失調と診断されたこともあった。
幼い頃の母の記憶は白粉おしろいの匂いと結びついている。「リヨン」のママとして大勢のホステスを雇い、計7軒のバーやスナックを切り盛りする母は、いつも白粉の匂いをさせていたからだ。深夜、店から酔客を送り出してタクシーに乗せる母の姿を、千種は時々2階から見た。
母にしなだれかかる酔っ払いを許せない千種が、銀玉鉄砲で撃ち、唾を落とすと、気づいた母が2階に上がってきて、こっぴどく叱られた。
飲み屋街の子供たちは「バーの子」と言われてバカにされる。泣いている仲間を見つけると、持ち前の激しい気性が爆発して、仲間を引き連れて仕返しに行った。「みんなにバカにされるのなら、自分たちの遊び場を作ればいい」と考える千種は、すでに小さなコミュニティのリーダーだった。
弟が生まれ、女子プロレスと出会う
7歳の時に、弟の洋が生まれた。父親が狂喜する姿を見て千種は複雑な気持ちになった。長与家の長男はとても大切に扱われたからだ。七五三の祝いは、千種の時とは比較にならないほど派手にやった。洋の枕元には「めざまし」と称して寝起きに食べるお菓子が置かれた。小遣いも欲しいだけもらえた。千種が「どうして弟だけ?」と両親に聞いても「男とはそういうものだ」と言うばかり。納得できるはずもなかった。
小学4年生の春、千種は夜遅い時間にテレビでやっていた女子プロレスの試合を初めて見た。大きなマッハ文朱と太ったジャンボ宮本が戦っていた。
「女であること」「強いこと」「かっこいいこと」が、女子プロレスの中ではひとつになっていた。男にも女にもなりきれない10歳の少女が夢中になるのは当然だった。
まもなく大村に女子プロレスの興行がやってきた。初めて会場で観戦した千種は声も出ない。黙りこくったまま、ひたすら見つめるばかりだった。
空手に通い始めたのも同じ頃だ。
もともと千種は肺機能が弱く、頻繁に喘息の発作を起こして病院に担ぎ込まれて注射や点滴を受けた。中耳炎に何度もかかり、小児結核になったこともある。
身体の弱い下の娘のことを常に気にかけていた母親は、ある日、空手衣を着て裸足で町を走る子供の集団を見つけた。空手をやらせれば、千種も丈夫になるかもしれない。そう考えた母親は翌日道場に連れて行った。
空手は楽しかった。帯の色が変わっていくたびに、身体もどんどん強くなっていくのがわかった。
だが小学5年生の夏、一家に大事件が起こった。
千種がいつもの時間に学校から帰ってくると、家の中には何もなかった。テーブルも椅子も勉強机も布団も本棚も。
両親もいなかった。
朝、家を出る時にあったものが、すべて失われていた。

がらんどうになった暗い家の中を、ショルダーバッグをかけた10歳の少女はいつまでも眺めていた。
悲しいも悔しいもなかった。ただ、何か大きなものが自分から抜け落ちたような気分だった。
親戚の家をたらい回しにされる
店の経営状態は回復不能だった。狭い大村で商売の規模を広げすぎた上に、父が友人の借金の連帯保証人になり、逃げた友人の代わりに背負わされた。負債は5000万円に及び、店も家も抵当で取られた。両親は神戸に働きに行かなくてはならず、いつ大村に戻ってこられるかはまったくの未定。
このような事情を小学5年生の千種に話しても理解できないだろう。そう考えた両親は、何も言わずに千種を置いていったのだ。
姉はすでに名古屋で就職していたし、4歳の弟は母の姉に預けられていた。
何も知らない千種が玄関で立ち尽くしていると、母親の妹がやってきて言った。
「チコちゃん、今日からおばちゃんの家で暮らそう」
叔母の言葉に従う以外、千種にできることは何ひとつなかった。
新しい生活が始まった。
臨月だった叔母はまもなく出産した。赤ん坊は可愛かったし、叔母は優しくしてくれた。
風呂を沸かすのが千種の仕事だ。外にある風呂釜の焚き口に置いた石炭の下に割り箸を差し込み、紙に火をつけて団扇うちわで懸命にあおげば、やがて石炭に火が移る。少しずつ石炭が赤く輝き始めると、「これが家というものだ」という実感があった。
先に風呂に入った叔母に呼ばれると、千種は裸の赤ちゃんを大きな白いタオルにくるみ、だっこして、落とさないようにゆっくりと歩いて風呂場の叔母に渡す。
幸せだった。
だが、そんな幸せも長くは続かなかった。1年後、夫が関西にバーテンの職を見つけ、叔母の一家は大村を離れたからだ。
6年生になっていた千種は、今度は父の妹の家に預けられた。そこには3人の子供がいた。
唯一の救いだった女子プロのテレビ中継
初めて千種が家に入ると、一番上の男の子が千種を嫌な目で見た。その目は「邪魔者は出て行け」と言っていた。
最初は作ってもらえた弁当も、そのうちに「パンでも買って食べて」と金を渡された。成長期に入り、パンだけではとても足りなかったが「お前は本当によく食べる。父親から送られてくる生活費じゃ足りない」とイヤミを言われれば何も言い返せなかった。
牛乳代のことを口に出せない千種は、水道の水でパンを流し込んだ。
我慢できなくなると、千種はパン代を節約して神戸の両親の家に電話をかけた。
「もうイヤだ。早く迎えにきて!」
しかし、母親はすでに三宮近くの小さな飲み屋で働いており、簡単に帰ってこられる状況ではなかった。ひとりぼっちの千種は、布団の中で声を立てずに泣いた。
中学に行けば制服がある。制服のスカートをはくと、自分が女以外の何者でもないことを思い知らされた。まもなく初潮が訪れた。千種は叔母に言い出せぬまま、ひとりで薬局に行って生理用ナプキンを買った。屈辱だった。
孤独に苛さいなまれた千種は勉強はもちろん、喧嘩さえもできなくなった。心に大きな穴が空いてしまって何もする気が起こらず、他人と話すことが苦手になった。
千種にとって唯一の救いはテレビの女子プロレス中継だった。
この時ばかりは、気が狂ったように暴れてチャンネル権を死守した。テレビを抱きかかえ、額を画面にくっつけるようにしてビューティ・ペアを見る千種の横を、上の男の子が「キチガイ!」と吐き捨てながら通り過ぎた。
その言葉を聞いた千種は、心中密かに「その通りかもしれない」と思った。千種の腕にはカッターナイフで彫られた「女子プロレス」の文字があったからだ。
〈ライオネス飛鳥は「リングに上がった時の長与千種の目はふだんとは違っていた」と…落ちこぼれと王者が臨んだ“禁じ手ナシ”の試合の裏側〉へ続く