ゴリラ研究の第一人者・山極寿一さんが新著『老いの思考法』を上梓した。老いの日々を「寂しい」「苦しい」と感じる人も多いなかで、人生後半戦の捉え方が一変する画期的な一冊だ。現代社会でどう老いたらよいのか話を聞いた。
◆◆◆◆

長寿国だが“老いは邪魔もの”な日本
――今回なぜ初めて「老い」をテーマにした本を書かれたのでしょうか?
山極 僕が長年付き合ってきたゴリラたち――目をかけて記録をしてきたオスのシルバーバックたちが、ここ数年、老いの時を迎えて次々に亡くなっていったんですね。彼らが先に死んでいくのを見て、人間の進化史の中で、老いがどのような形で社会に貢献してきたのかを真面目に考えてみようと思ったんです。
もう一つはアフリカで付き合っていた調査隊の仲間たちが、もうほとんど亡くなってしまったこともあります。日本では人生100年時代なんて言われているけれど、アフリカの人たちは寿命が短い。先進国で老年期がどんどん延びているなかで、人間としてどういう生き方がまっとうなのか見つめ直したかった。日本では寿命こそ延びているものの、むしろ「老いは邪魔もの」で、その日々を楽しんでいない高齢者も多いですから。
――辛そうだったりイライラしたりしているお年寄りが多いですね。
山極 社会の片隅に追いやられているという不全感をもった方が多いのでしょう。でも、アフリカの僕が付き合ってきた高齢者の人たちは、老いの時間こそ短めだったけれど、みんなに尊敬されて、子どもたちにも慕われていました。そういう文化がかつて日本にもあったと思います。

日本の医療はとにかく寿命を延ばそうと、しゃかりきになって数値目標を追ってきました。ただ老いの期間を延ばすことにいそしみ、その時間の質を置き去りにしてしまった感が否めません。われわれの超高齢社会の実態は果たして世界に誇れるものなのか、根本から老いのあり方を見つめ直すときに来ているのではないでしょうか。
高齢者と子どもの時間の使い方はとてもよく似ています。生産性や効率性を考えずに、刻々と変化する自然に心身を合わせるような時間は幼少期と老年期に特徴的です。現代社会の性急な時間の使い方を考え直すきっかけを高齢者はつくり出せるし、自然のような予測できない変化に対処する知恵は、高齢者こそ次世代に伝えられる身体知です。
これからの時代はあらかじめ決められたことを知識で学ぶよりも、未知のものに適切に対処する学びのモデルが求められていると思います。老人が学びの場ではたせる役割は大きい。
進化の隣人・ゴリラは老いをめぐる学びの宝庫
――他の動物とは異なる、人間の老年期の意味とはなんでしょうか?
山極 動物の世界は、個体と環境がダイレクトに接しているので、個の生命力が弱くなると自ずと死に至ります。しかし、700万年の進化史において人間は「弱みを強みに変える」戦略を採用し、社会力を強化しました。
出産という命がけの大仕事を経験豊かな高齢者が支え、一度にたくさん産めない子どもをみんなで世話をする「共同保育」を始めたのです。たとえ介護やケアが必要でも、高齢者と一緒に生きることが、集団的に大きな力になった。シニア世代が子育てにコミットすることが、社会を発展させる原動力になってきたのです。
実は、進化の隣人であるゴリラは老いをめぐる学びの宝庫です。ゴリラのオスは歳をとると、背中が白銀色のシルバーバックになって実に美しくなりますが、彼らは歳をとっても群れを追い出されることなく、若い世代から慕われて暮らします。その秘密はオスの子育てにあるんです。

ゴリラの赤ちゃんは離乳したら母親の手を離れ、父親に預けられます。子どもたちは父親の周りで遊び、抱きついたり背中を滑り台にして遊ぶんですね。父親に育てられた息子たちは成長しても父親を邪険に扱いません。だから老いたシルバーバックは敬われ、死ぬまで群れのリーダーであり続けられるんです。
――育児をしたからこそ老年期も大切にされるというのは興味深いですね。
“よい老い方”3つの条件とは?
山極 ゴリラのオスが生涯リーダーであり続けられるのは、自分の力が衰えてもみんなが慕ってくれるからです。ボスのように力で押さえ付けるのではなく、みんなに担がれないとリーダーにはなれない。松下幸之助さんが言うリーダーの条件は、「愛嬌がある」「運が良さそうに見える」「背中で語る」の3つです。実はこれ、そのままよい老い方の条件とも言えると思います。
シルバーバックのもとに安心して子どもたちがよってきて遊ぶように、「愛嬌のある」お年寄りのもとに子どもは自然と惹きつけられます。「運が良さそう」とは、「この人についていったら何かいいことがありそう」と思わせるような、惜しみなくまわりに分け与える前向きな振る舞い。「これは俺のもの」という独占欲の強い人は、運が悪そうでしょ?(笑)。
そして「背中で語る」とは、その人のなかにある自信。それは長い年月を生き抜いてきた人生経験からにじみ出てくるものです。

老いたゴリラの背中が美しいのは、その自信が生涯消えないからです。ジャングルの深い闇を移動するときも、先頭に立つシルバーバックの背中が浮き上がり、群れを迷わせません。いちいち指図したり振り返ったりせずに、リーダーは背中で語るものなんですね。
こうした魅力は、よい老い方をした成熟の証しでもある。
――老いの理想的なモデルですね。
山極 ご高齢の方は、人間同士の付き合い方や、自然との向き合い方の知恵をもっていますし、さまざまな分野での身体知もある。そういうポテンシャルにもっと思いを拡げるべきだと思います。
例えば、高齢者のみなさんは、伝統的なお祭りのとき、どういう衣装やどういう礼儀作法が必要かを知っていますよね。なんでも自由にやるのではなく、昔からの型を踏まえることでより活気溢れるものになったりします。そういう文化的な知恵がもっと世の中に満ちていいと思う。
競争から一歩身を引いたところにある幸福な時間
――最後に、老いの心構えとして一番大切なことはなんでしょうか。
山極 それは、我欲を捨てること、他人を立てること。若い頃は、自分の成功や利益を一生懸命追いがちです。力が溢れているから、ある程度は仕方ない。でも高齢者は、体力も認知能力も落ちてくるなかで、みなの模範となる振る舞いをし、他者の「引き立て役」になることが大切です。
高齢者は主人公じゃない、サポート役になるのがさまざまな世代とうまくやる秘訣です。現役を引退したのに、会社員時代を引きずって上司風を吹かせてしまうような態度はもってのほか(笑)。とくにベビーブーマー世代の高齢者は自分たちが社会の中心だった時代の感覚を捨て、若い世代を立てて社会の土台づくりをする姿勢が肝心です。主役はあくまで若い人たち。
もともと日本には隠居制度という優れた知恵がありました。隠居は壮年期の競合し合う関係性から抜け出して、落ち着いた場所で、趣味に興じる。草花を愛で、碁や将棋をさしたり、詩を詠んだりして、ゆったりした時間を過ごす。競争から一歩身を引いたところで自然とともにある時間をもつことは、とても幸福なことです。
高齢者が、どうやって自然と付き合い、人間関係を楽しんだらいいかを示すことは若い人にとって学びのモデルとなります。「歳をとったらああなりたいな」と思われるような生き方をつくっていくのです。
本書には、僕が研究人生のなかで動物たちから教えられた老いの本質や、忘れがたき恩師たちの老い方の知恵を記しました。社会のなかで、老いというものを捉え直すきっかけになれば嬉しく思います。
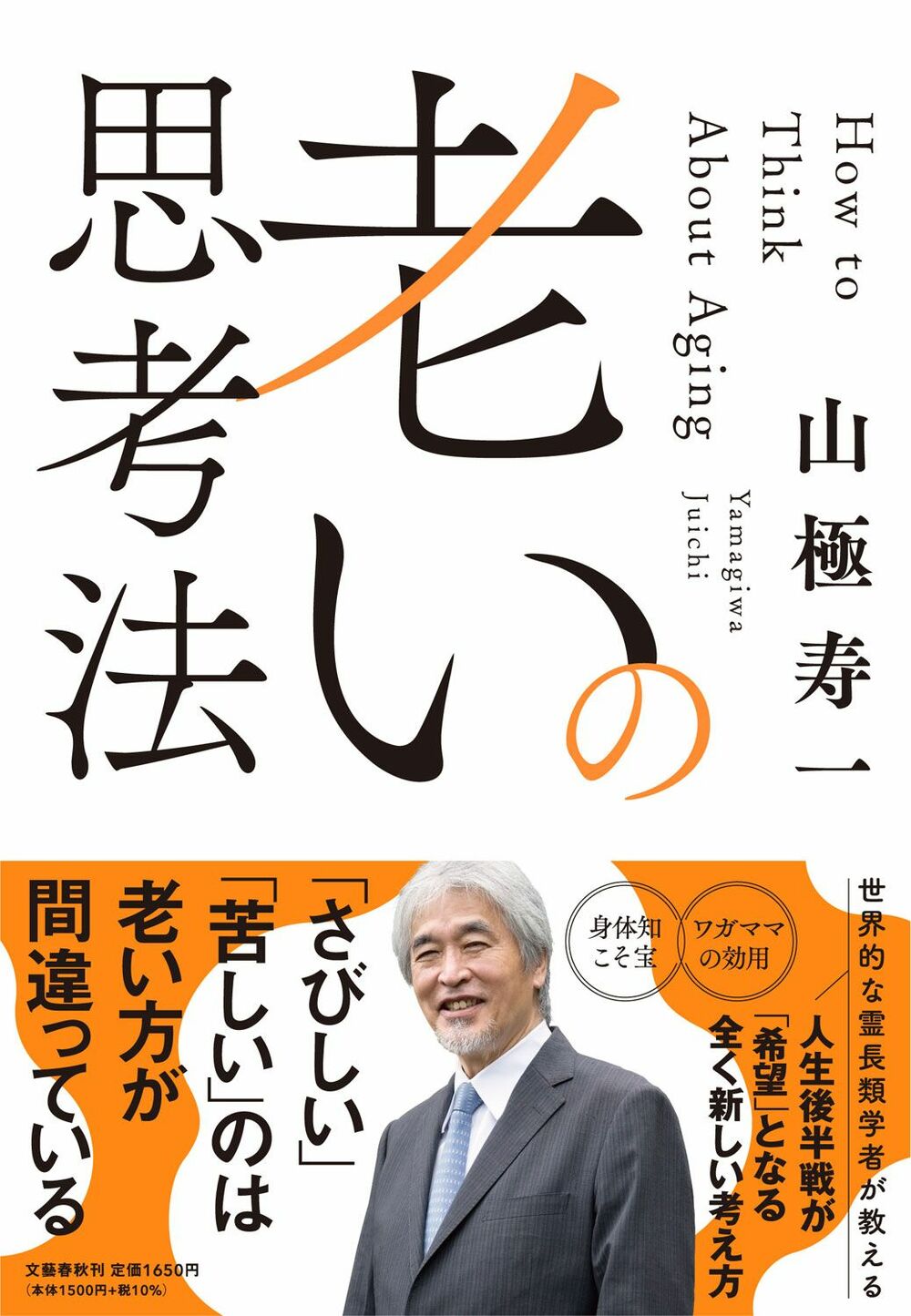
INFORMATIONアイコン
刊行記念トークイベント
4月3日(木)MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
「サル化する社会でどう老いるのか?」
山極寿一×内田樹
https://online.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70065-250403




















