かつてなく孤独を抱えた高齢者が多くいる社会で、人はどう老いの日々を過ごしたらよいのだろう? 話題の新著『老いの思考法』を上梓した、霊長類学者・山極寿一さんに訊く“老い方の知恵”。
◆◆◆◆

社交とは、“明確な目的を持たない遊び”
――年々、高齢者の独居率の割合も増え続けていますが、超高齢社会において寂しさや孤独を抱えるお年寄りが大勢いる現状をどうご覧になっていますか。
山極 これは僕があちこちで言ってるんだけど、日本社会から「社交」が消えつつあることに大きな問題があるんです。社交とは、“明確な目的を持たない遊び”を指します。その遊びの中で、互いに共感力を発揮しながら、コミュニケーションをとって交流する時間が人間には必要不可欠です。
一緒に詩を詠んだり、楽器を演奏したり、映画を鑑賞したりするのもいい。人と人とがリアルに交流することが大切なんですね。ところが今は趣味や好きなことをするさい、お金を払って一人で楽しんできて、一人で帰ってくることが多いでしょう。それはただのエンタメの消費であって、社交ではない。人々が交流することを中心にした楽しい場を社会のなかで再構築しなければならないと考えています。
――孤立したまま趣味の時間を楽しんできても、どこか満たされないものが残りそうですね。
山極 もちろん一人で楽しむ時間をすべて否定するわけではありませんが、本来、スポーツを楽しむのもコンサートに行くのも遊びの一環です。その時間を誰とも分かち合わず、一人で完結してしまうのは非常にもったいない。
その点、例えば「子ども食堂」は、食事を中心にした大変良い社交の場です。今や全国で1万箇所を突破しましたが、こうした地域支援の場にボランティアで参加することは、優れた交流の機会となるでしょう。地元のお祭りだってそう。準備に時間がかかるお祭りは、何ヶ月か前から計画をたて、関係各所さまざまな調整をし、催し物の練習をし、人々が協力しあって本番を迎える濃密な時間そのものです。
まわりを見ると、いまシニアの方々の同窓会が流行っているようですね。学生時代のクラスメイトとか、気の置けない仲間で集まって昔の思い出を語り合うのもとてもよい時間でしょう。さまざまな形で人と会う機会を積極的につくっていくのが豊かな老いの時間につながります。
――確かにそうですね。
すべての動物で一番遊びが得意な「人間」
山極 社交の根底にある「目的のない遊び」――これは本来人間の子どもがとても得意とするところです。霊長類で長く遊べるのはゴリラとチンパンジーですが、遊びは体が弱いほう、小さいほうがイニシアティブを握ります。つまり、強いほうが弱いほうに合わせて力を調整しながら、時間の流れをつくる必要がある。追いかけたり追いかけられたり、対等な力関係のなかで役割を交代してこそ遊びが成立します。
実は、すべての動物のなかで一番遊びが得意なのは人間なんです。歴史家ヨハン・ホイジンガが『ホモ・ルーデンス』で明らかにしたのは、人間の文化も政治も社会もすべて遊びから発展して作られたということ。遊びを通して、力を制御し、相手に対する思いやりや信頼関係も自然にはぐくまれていきます。それが人間の対等で自由な社会の発展へとつながっていった。

だから、社交は遊びであり、人間社会を基礎づけるものだという原点に立ち返る必要があります。高齢者がコミットできる社交の場が少ないし、もっと言えば、学校という場はもっと遊びを担うとよいと僕は思っています。文科省の作ったカリキュラムに沿って数値目標を追う教育のもと、今や不登校児が34万人もいます。無論、不登校の背景には複合的な要因がありますが、幼少期から遊びのなかで友達とどう付き合うかを身体で学ぶ機会が減っていることと無関係ではないように思います。
――ご著書のなかで、交流の場としての縁側的な空間を重視されていますね。
「立ち止まれない」街のストリート
山極 僕は昭和30年代に東京郊外の国立で育ちましたが、当時はどこもかしこも縁側だらけでした。ふらっと友達のうちにいって縁側でジュースをもらったり、そこで過ごす近所の老人たちの世間話に聞き耳を立てながら遊んでいたものです。
こうしたハーフパブリック・ハーフプライベートの中間領域が日本社会の中で極端に少なくなってしまった。街のなかを歩いてもほとんどベンチがない。公園ですら、あっても長くゆったりとは座れない排除ベンチだったりして、多様な人々が腰を下ろして自由に話ができるような場になっていません。街なかで偶発的な社交が生まれないのです。
江戸の城下町は人々が立ち止まってそこらへんでいくらでも世間話のできた空間だとしたら、いまの都市設計におけるストリートは基本的にさっさと通り抜けることが重視された設計になっている。
――たしかに「立ち止まるな」という圧を感じます(笑)。
山極 京都大学教授の広井良典さんが本に書いていますが、ドイツやフランスの街の多くは立ち止まれるように作られていて、街のいたるところにベンチが沢山あるんですね。人々が座って憩える街になっている。パリとかでもカフェのベンチが街路に出ていて老人たちが腰掛けているでしょう。

ヨーロッパではパティオと呼ばれる建物に囲まれた中庭も多く残っていて、老人たちがたむろしてゆっくり過ごしているんですね。日本の都市でもそんな縁側的なハーフパブリックな空間を増やして、憩える街にしないといけない。入るのに暗証番号がいるようなマンションばかりではご近所との自然な交流も生まれようがないでしょう。
――マンションは気密性が高いですしね。
植物的な時間と、そこから伝達できる知恵
山極 僕がアフリカで訪れた村々では、老人たちが家の前に椅子を置いて、ゆったりと座っています。通りすがりの若者や子どもたちが時々立ち止まって、彼らとちょっとおしゃべりをしては去っていく。子どもにも若者にもそれぞれの時間があるけれど、老人たちは止まっているから、植物的な時間がそこでは作り出されている。
僕はよく思うのですが、流動性の高い加速する時代だからこそ、その中で自然の時間に立ち返った植物的な時間、そこから伝達できる知恵というのは大きな意味をもちます。それができるのはまさに高齢者の特権です。
――本当に「立ち止まる時間」って大切ですよね。
山極 その点、都市の時間とはちがって、地方の田舎は道で立ち止まって気楽に話ができるし、みんな知り合いだから、互いにふらりと訪問して世間話をするような交流も生まれやすい。
地方の人口減少を嘆く声は多いけれど、社交がしやすい地域のポテンシャルをうまく利用して関係人口を増やしていくことが地方創生の鍵だと思います。効率を求めてお金やサービスを集中させるスマートシティを推進し、憩える街を潰すような政策には常々疑問をもっています。むしろ、環境省が掲げる地域循環共生圏の発想で、各地域はそれぞれ自立しながらも繋がりを深めていくほうが優れたアプローチだと思います。
いまは高齢者がいつまでも若くありたい、若者と同じように楽しみたいと思う人が多いけれど、違うんですよ。高齢者には高齢者なりの若い世代とはまた違う楽しみ方があるし、老いたなりの身体と知恵でしかできないことがある。立ち止まり、ゆったりとした時間のなかで、知恵を伝えていけるような生き方ができるんです。
本書には、老いをめぐる学知から人生経験で得た気づきまで、考え方のヒントを多く記しました。目まぐるしい社会において、ふと立ち止まって考えてみる“憩いの一冊”になることを願ってやみません。
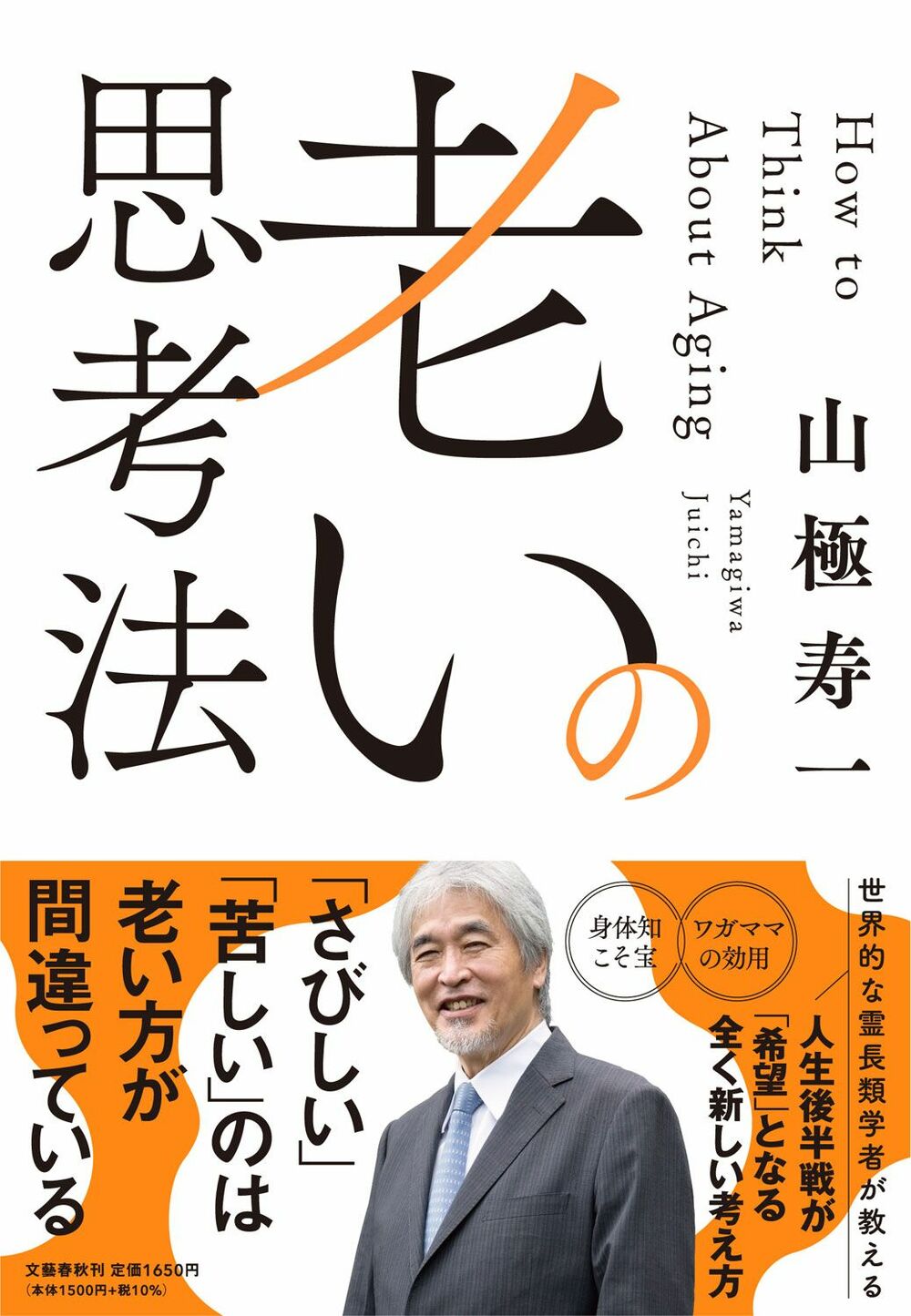
INFORMATIONアイコン
刊行記念トークイベント
4月3日(木)MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
「サル化する社会でどう老いるのか?」
山極寿一×内田樹
https://online.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70065-250403




















