藤井聡太棋士の師匠としても知られる杉本昌隆八段と、作家デビュー10周年を迎えた額賀澪さん。棋士と作家、一見すると異色の組み合わせのお二人の対談は、額賀さんによる「天才」をテーマにした連作短編集『天才望遠鏡』をきっかけに実現しました。

◆◆◆
「現実がストーリーを追い越してしまう」
――「星の盤側」では、登場人物の明智昴が14歳の誕生日にプロ入りし、藤井聡太棋士の最年少記録を塗り替えたという設定になっていますね。作中では、その天才中学生棋士・明智と“かつての”天才中学生棋士との対局が描かれます。杉本八段は、この作品をどのようにお読みになりましたか?
杉本:藤井くんはもちろん、ほかにも天才棋士が多く登場しますから、これが現実世界だったら(競争が激しすぎて)ちょっと嫌だなと思ってしまいました(笑)。登場人物に天才しかいないという意味では、実際よりも厳しい世界が描かれているな、と。
額賀:普段スポーツを題材に書くことも多いのですが、本当に現実との戦いなんです。小説のなかで「凄い記録」として書いたものが、1ヶ月後の日本選手権であっさり破られてしまったりしますよね。
杉本:ありますよね、そういうことって。
額賀:「星の盤側」を書いたのももう2年以上前になりますが、藤井七冠の快進撃が止まらず、内心、「小説を超えられてしまったらどうしよう」とドキドキしていました。
杉本:現実の将棋界では、藤井七冠の後は中学生棋士は出ていませんね。今回の小説のように彼の記録が更新された場合、さてどうするかと。現実がストーリーを追い越してしまうことはままありますから。
特に藤井七冠の活躍に関しては、よくそう言われていました。フィクションのようなストーリーを超えてしまう活躍をしている、と。
額賀:藤井七冠がプロ棋士になられてからの数年間、活躍を見るたびに「今、将棋の小説を書いてなくて良かったな」と思っていましたもん(笑)。
杉本:最年少記録を更新しながらタイトルを次々取っていき、とうとう全冠制覇なんてことになれば、フィクションの世界では「できすぎではないか」と厳しく突っ込まれそうです。
額賀:本当に書いていなくて良かったです(笑)。
藤井フィーバーと「天才」の生まれ方
――杉本八段の目から見て、小説で描かれる天才棋士と元天才棋士の関係性は、現実の将棋界にも通じるものがありましたか?
杉本:ええ。自分たちの世界も外からはきっとこう見られているんだろうなと思いましたし、実際、最近はちょっと活躍していないけれどご本人はどう思ってるのかな、などと思うことはありますね。
額賀:作中の天才棋士・明智昴が世間から持て囃されている様子は、やはり「藤井フィーバー」の頃を思い出しながら書きました。
杉本:「天才は、それを観測する人がいるからこそ成り立つもの」という書き方には「なるほど」と思いました。何か大きなことを達成する本人は、別に注目されたくて頑張っているわけではなくて、自分にとって楽しいことをやっていたいだけなんだけど、周りがそれを放っておかない。そういう存在があるからこそ、将棋に興味がなかった方にも関心を持ってもらえるわけですが。
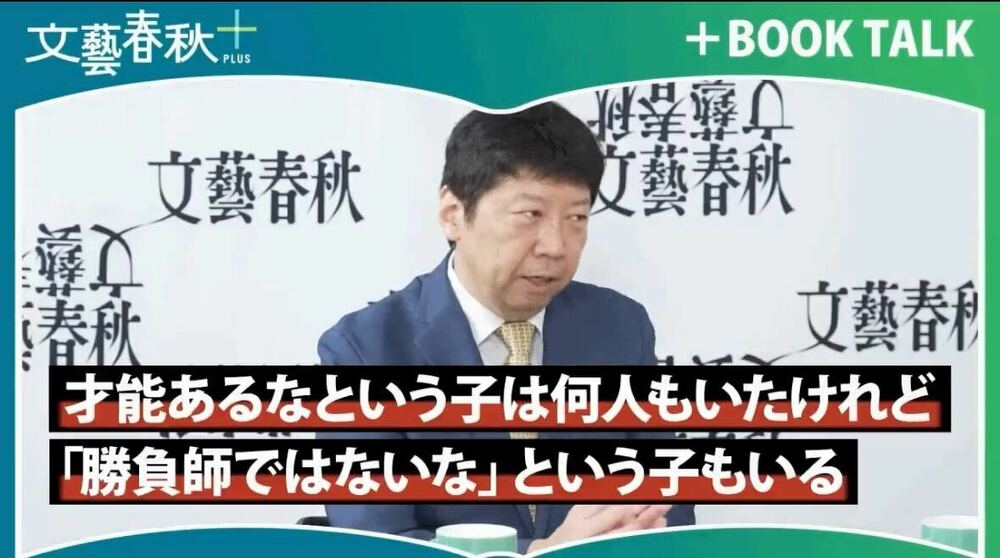
額賀:藤井フィーバーの中で一番印象に残っているのが、対局中の藤井棋士のお昼ご飯は何かという予想で盛り上がっていたことです。将棋会館の近くのお店にテレビ局の人が待機していて、注文が入るのを今か今かと待っている。空振りの可能性もあったと思うのですが、私が見ていた日はたまたまそこに注文が入り、店主の方がバイクで運んでいく後ろ姿をカメラがずっと追っていたんです。それを見たとき、「とんでもないことが起きている」と思いました。
杉本:あれはちょっとびっくりしましたね。でも、食べ物のネタって絶対外さないんです。将棋を指さない人はたくさんいるけど、ご飯を食べない人はいませんから。だから、テレビ局の人は自分たち棋士とは視点がまったく違うなと思いました。一般の人が食いつくのはどこかと考えたら、ご飯なんだなと。
世間が勝手に才能をジャッジして
――作中には「こうやって天才が天才として世間に受け入れられていく瞬間を、何度も見てきた」という言葉があります。杉本八段も、そうした瞬間を数多くご覧になってきたのではないでしょうか。
杉本:そうですね。ただ、どちらかといえば、受け入れられなかった天才の方をたくさん見てきたような気がします。将棋界では評価されていて実績も十分な棋士も、よほど何か分かりやすい活躍をしない限りはどうしても大きく取り上げてもらえません。まさに作中で描かれていましたが、みんな天才なのだけど、一般の方にまで知られる天才もいれば、そうじゃない天才もたくさんいるんですよね。
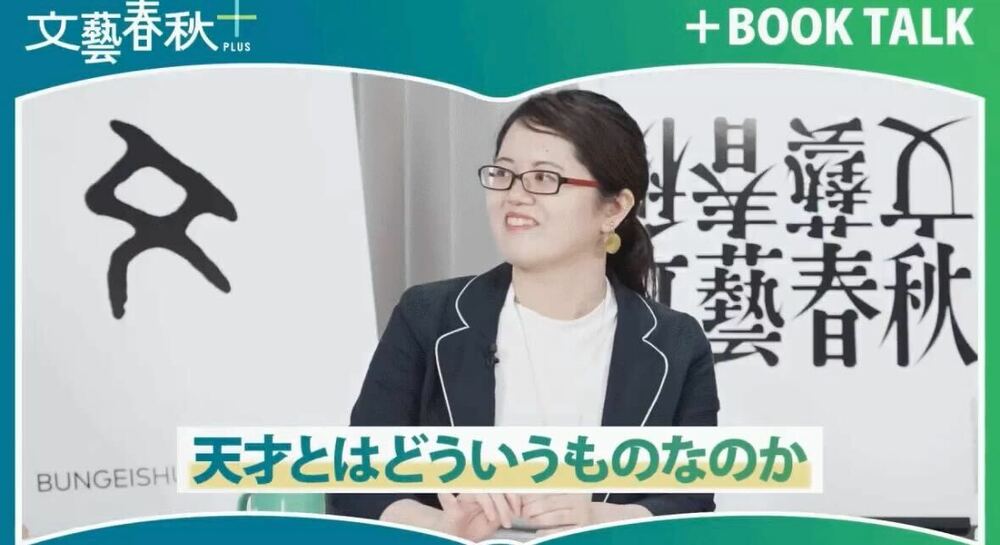
額賀:本当にそうですよね。小説家の世界でも、天才と言われながら売上や知名度の点であまり認知されていない人は大勢います。つくづく、天才とはその才能を「見る」側の認識で生まれるものなんだなということを、作品を書きながらも書き終えてからも思いますね。
杉本:本人が天才を名乗るわけじゃないですからね。その人の中ではそれが基準だから、自分に才能があるとか天才だとかは絶対思ってないんですよ。世間が「この人は天才なんだな」と判定する。
今回のお話で言えば、中学生棋士が天才として描かれていますけど、これが数ヶ月遅くて高校生だったら、また違いますよね。本人の才能は何も変わらないのに。
額賀:ある意味、世間が勝手なんですよね。勝手にジャッジして、「天才中学生棋士が生まれた!」となるか「高校生棋士はまあ、別に珍しくないか」みたいになるか。
杉本:この差って何だろうな、と思うことはあります。
勝負の世界では誰もが「丸裸」になる
――『天才望遠鏡』の中の「本当の天才は、戦いの場で丸裸になる」という言葉が杉本八段の心にも残ったと伺いました。
杉本:そうなんですよ。ちなみに、天才じゃない棋士でも丸裸になりますよ。自分も一応、丸裸になっています。物理的にじゃなくて、気持ちの上でですよ(笑)。対局の場ではやはり、おたがいにすべてをさらけ出してまっさらな状態で向き合いますから。

額賀:「星の盤側」を書き始めたとき、“スポーツ”としての将棋を書いてみようと思ったんです。主人公もスポーツカメラマンですし。
書いていくなかで、アスリートがすべてを剥ぎ捨てて勝負の一瞬に挑むのと同じものを、棋士の方に感じたんです。それで、このフレーズが出てきたんだと思います。
棋士に必要な3つの顔
――杉本八段のエッセイ『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』には、「棋士には『研究者』『勝負師』『芸術家』という3つの顔が必要」というお話が出てきますね。
杉本:谷川浩司十七世名人の言葉ですね。私がこれまで見てきた弟子たちの中でも、たとえば才能があっても勝負師ではないなと感じる子もいるんです。能力はすごく高いけれど、本番に弱いとか。逆に、どう見ても将棋の内容はまだまだなのだけど、実力以上に結果を出せる子もいる。それは「勝負師」なんでしょうね。
額賀さんも、「小説の才能」と「作家の才能」は別かもしれないというお話をされていましたよね。
額賀:面白い小説を書ける「小説の才能」と作家として生きていく「作家の才能」は、ベン図のように重なる部分とまったく重ならない部分があると思います。私たちは、出版社から仕事を依頼され、編集者など色々な方と一緒に1冊の本を作る個人事業主でもある。そう考えると、フリーランスとして最低限の社会的な振る舞いができるというのも「作家の才能」なんじゃないかと。
杉本:なるほど。私もエッセイを書くときに、自分の書きたいことと世の中に受け入れられることはきっと違うんだろうなと思うことはありますね。たとえば将棋の戦法などの細かい内容は書きやすいですが、あまりニッチなことは読者の方々には求められていないんだろうなと思います。
将棋に関しても、自分の指したい手というのがあるのですが、AIで分析させると明らかにマイナス評価が出ることがあります。それでも「いいからやるんだ」という人もいますが、対局相手もAIで分析できるから、そういう手は封じられてしまう。かといって、AIの示す手を真似しているだけでは自分の将棋が表現できなくなってしまいます。自分の個性は残しつつ結果を出さなければいけないというのは難しくもありますね。
AIをもう一人の相談相手に
――将棋界とAIの関係は、他のクリエイティブな分野にも参考になる点が多そうですね。
杉本:将棋の世界は、AIの参入が早い方だと思います。AIのいいところは自分のペースで使えたり、新しいものですから、将棋歴の違いにかかわらず同じように使えること。常に学習を続けているので、感覚が古くならないという利点もあります。ただ、本当にうまく付き合えているかどうかは棋士によるでしょうね。
額賀:出版界ではまだ、作家も編集者も「どうしたもんかね」となっている状態です。すでに使っている同業者によると、本文を書かせるのではなく、プロットの段階で、生身の編集者とは別にもう一人の“相談相手”として使っていたりするようです。
一方で、AIに頼りすぎると果たして誰の作品なのかという問題が出てきてしまう。だからみんなうまく手を出せずにいるんです。でも、いま伺った「AIはマイナス評価をしていても、自分の将棋にこだわってあえてその手を指すこともある」という例は、小説家がAIと付き合っていく上で一つの指針になるんじゃないかと感じました。
旋律のように勝負の手が浮かぶ
――最後に杉本八段にお伺いしたいのですが、「天才」とはどういうものでしょうか。
杉本:将棋の能力という見方をするならば、ある盤面を見たときにひらめくまでの時間の速さですかね。1秒で次の手が浮かぶ人と1分で浮かぶ人では、勝負の上で大きな差が出てきます。パッと見た時に「この最善手はこうでしょう」「ここが急所ですね」と気づく人は才能があるなと思います。
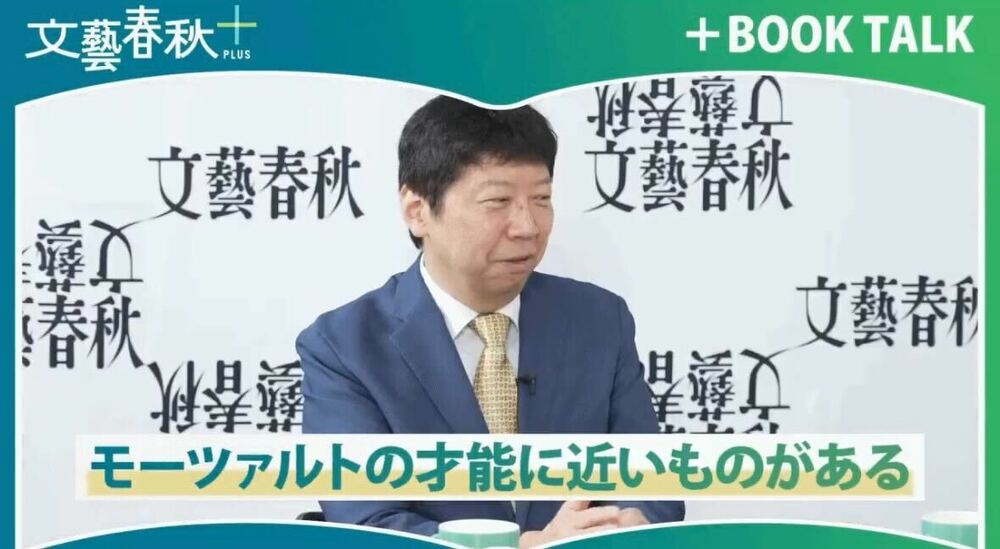
――藤井七冠も、そのスピードが非常に速いのですね。
杉本:ええ。特に詰め将棋――相手の玉を詰ませる手を思いつくまでがびっくりするくらい速くて。もう考えているというか、浮かんじゃうんですね、その最終形が。盤を見た瞬間に。これは才能で、努力だけでは多分たどり着けないんじゃないかなと思います。音楽でいうとモーツァルトの才能みたいなものに近いというのでしょうか。旋律が浮かんでくるんでしょうね。
盤上の勝負の世界に生きる者と、言葉の世界で創作を続ける者。それぞれの視点から語られる「天才」の実像や才能との向き合い方、さらにAI時代における小説と将棋の未来までたっぷり語り尽くされた対談の様子は、「文藝春秋PLUS」でご覧いただけます。
額賀澪さんの新刊小説『天才望遠鏡』、杉本昌隆八段の新刊エッセイ『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』は絶賛発売中です。























