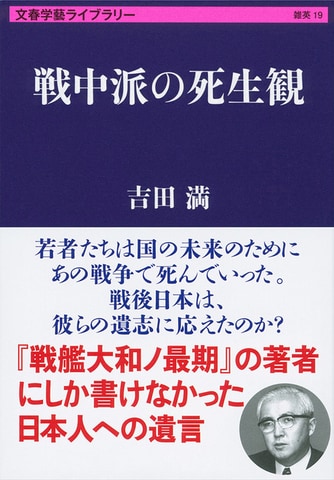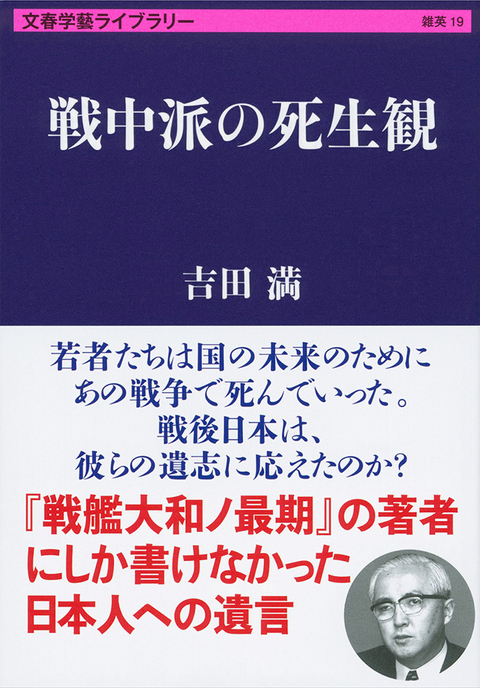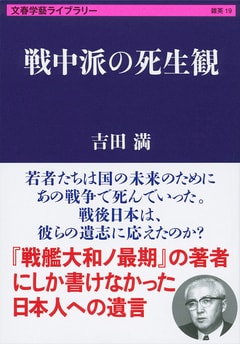「求道する文人の悲願(1)」より続く
戦中派の内心の真実
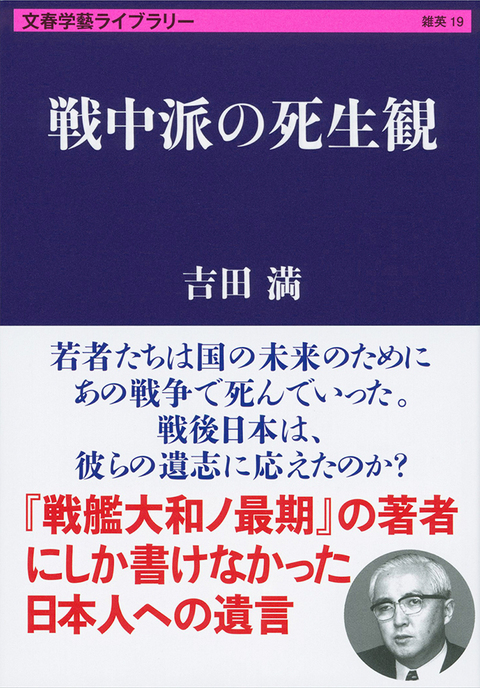
この作品を小林はのちに「正直な戦争経験談」と評した。当時小林は、青山二郎や画家梅原龍三郎と共に雑誌『創元』の刊行を準備していた。この創刊号に小林は『戦艦大和ノ最期』の掲載を考えていたのだった。だが、結果的にはGHQの検閲によって発表することを封じられることになる。
作品が広く読まれるようになるには幾多の試練を経なくてはならなかった。その道程は本書の「『戦艦大和ノ最期』をめぐって」に記されている。
発刊は一九四九(昭和二十四)年にひとまず書物のかたちになり、一九五二(昭和二十七)年に版が改められる。本書にも引かれているが、一九五二年版の「あとがき」に吉田は次のように書いた。少し長いが引いてみたい。『戦艦大和ノ最期』執筆当時の心境がうかがわれる。
「この作品の中に敵愾心(てきがいしん)とか、軍人魂とか、日本人の矜持(きょうじ)とかを強調する表現が、少なからず含まれていることは確かである。(略)この作品に私は、戦いの中の自分の姿をそのままに描こうとした。ともかくも第一線の兵科士官であった私が、この程度の血気に燃えていたからといって、別に不思議はない。我々にとって、戦陣の生活、出撃の体験は、この世の限りのものだったのである。若者が、最後の人生に、何とか生甲斐を見出そうと苦しみ、そこに何ものかを肯定しようとあがくことこそ、むしろ自然ではなかろうか。(略)
このような昂(たかぶ)りをも戦争肯定と非難する人は、それでは我々はどのように振舞うべきであったのかを、教えていただきたい。我々は一人残らず、召集を忌避して、死刑に処せらるべきだったのか。或いは、極めて怠惰な、無為な兵士となり、自分の責任を放擲(ほうてき)すべきであったのか。
戦争を否定するということは、現実に、どのような行為を意味するのかを教えていただきたい。単なる戦争憎悪は無力であり、むしろ当然過ぎて無意味である。誰が、この作品に描かれたような世界を、愛好し得よう──」(本書一一〇~一一一頁)
ここで述べられているのは戦争の讃美や追憶ではない。ただ、戦いと死に直面することを強いられた自身と同胞たちの内心の真実である。戦争に反意を表することすら許されなかった者たちの切迫した現実である。吉田は、彼が感じた時代の真実を文学の力を借りて言葉に刻んだ。ある人々は、眼前にある打ち消しがたい歴史に対峙する前に戦後の「新しい」価値観によってそれを断罪したのだった。
戦争を否定するのはよい。それはどこまでも否まれなくてはならない。だが、そこに連なることを強いられた者たちに裁きの刃が向けられるのを吉田は認めることができない。追い詰められながらも、どうにかして確かなものを見出そうとした営みを、戦争を断じるのと同様に裁くようなことを、どうしても受け入れることはできなかったのである。