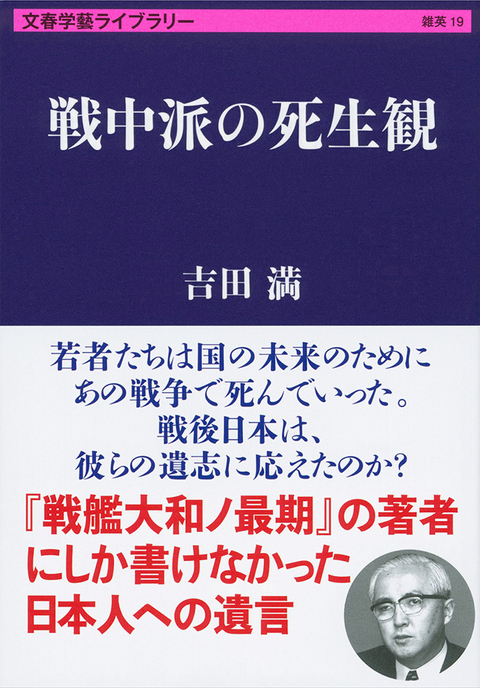戦中派とは
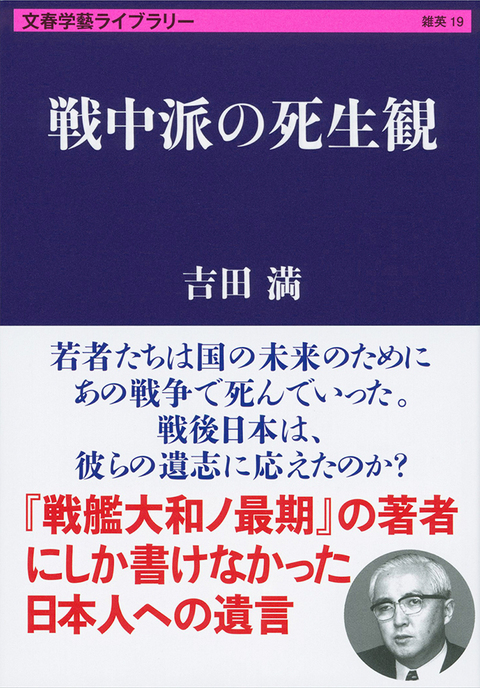
本書は吉田満の遺著である。同時にこの人物の本質にふれるための、格好の一冊でもある。さらに著者の小さな選集といった趣きもある。
表題にあるように著者は戦中派である。戦中派とは、戦争で亡くなった戦友の存在を傍らに感じながら生き続けることを宿命とする者の謂いだと吉田は、本書で幾度となく書いている。それを彼は「死者の身代りの世代」と呼び、「散華した仲間の代弁者として生き続けることによって、初めてその存在を認められる」(本書一三三頁)とも書いている。
また、彼は戦中派の精神をめぐってこう記してもいる。「われわれ戦中派世代は、青春の頂点において、『いかに死ぬか』という難問との対決を通してしか、『いかに生きるか』の課題の追求が許されなかった世代である。そしてその試練に、馬鹿正直にとりくんだ世代である」(「三島由紀夫の苦悩」本書八四~八五頁)。さらに吉田は同じ一文で林尹夫(ただお)の言葉を借りながらこう語った。
「おれは、よしんば殴られ、蹴とばされることがあっても、精神の王国だけは放すまい。それが今のおれにとり、唯一の修業であり、おれにとって過去と未来に一貫せる生き方を学ばせるものが、そこにあるのだ──と自分を鞭打とうとする愚直な世代である」(本書八五頁)
今日ではもう林尹夫の名前を知る人も少ないのではないだろうか。彼は一九四五年七月、四国沖上空で敵戦闘機と交戦し、戦死した。彼には没後二十二年を経て刊行された『わがいのち月明に燃ゆ』と題する遺稿集がある。林の言葉を吉田は、幾度となく、引いている。林だけでなく、何人もの戦死者の言葉が記されている。むしろ吉田は、他者によって語られた言葉を、自らの告白として引用している。彼はそれらを讃美しているのではない。ただ、けっして見過すまいという強い想いで向き合っている。彼にとって書くとは、単に自らの内心を表現することではなかった。むしろ、不可視な隣人となった死者との対話の記録だったのである。