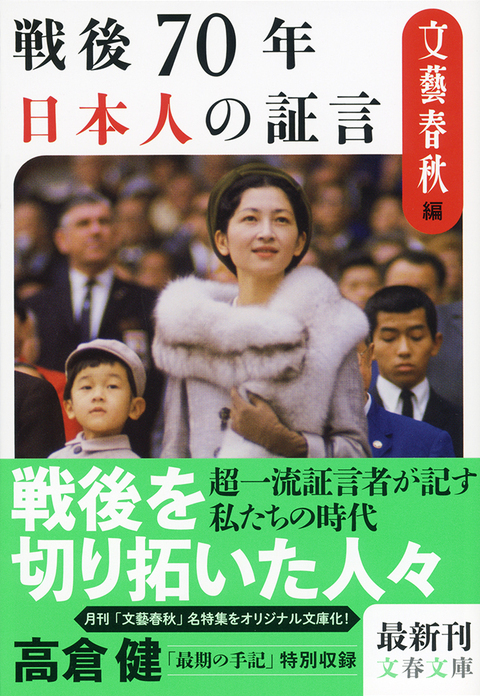明治三十四(一九〇一)年に官営製鉄所として操業開始以来、日本の鉄鋼業界を牽引してきた八幡製鉄所。高度経済成長を支え、ピーク時には十基の高炉が稼動した。当時の活気溢れる街の様子を、八幡市(現・北九州市)で生まれ育った作家・村田喜代子氏が振り返る。
幼い頃から周囲が人間ばっかりの所で育った。住んでいた家は八幡製鉄所の主力工場が結集した西門のそばだった。冬などは夜も明けやらぬ午前五時過ぎから、弁当箱を提げた職工がザクザクザクザクと門の中へ入って行く。六時も過ぎると今度は夜勤明けの職工が、これもザクザクザクザクと門から出て来る。
私は昭和二十年四月、敗戦の直前に生まれたが、戦後復興の大役を担った八幡製鉄所は従業員四万人前後もいただろうか。朝方まだ寝ている枕の下に、そんな西門界隈のざわめきが伝わってくる。工場は三交代制で、朝六時、昼二時、夜十時は職工たちで溢れる。門前の道筋には飲食店や角打ちの酒屋があった。
角打ちとは、一合升に注がれた酒を升の角に口をつけて飲むのである。酒は当然こぼれるので升の下には受け皿が付いていて、その小皿の酒をなめるのが先である。
母は再婚して近くの町で家を持ち、私は祖父母と暮らしていた。祖父は表具師で暇には自分の作った屏風に日本画などを描いて楽しんでいた。向かいに伯父の家があり、こちらは独身の職工のための下宿業を営んでいた。その家の従兄弟や娘婿たちも職工だった。
私は朝ご飯を食べて学校に行く。すると学校も大勢の子どもたちで一杯である。六十数人の生徒が教室にギュウギュウ詰めだ。近くに製鉄所の四階建て社員アパート群や社宅地区があり、子沢山の家々からランドセルを背負った子どもたちが吐き出されて来る。ちなみに昭和二十六年、八幡の桃園地区に建ち並んだ製鉄アパートは全戸、豪勢な水音を響かせる水洗トイレと、台所はダスト・シュート付きだ。
時は戦後のベビーブームで、外地から消耗して帰った男たちの家では、なぜか女の子がよく生まれたという。そういえば女の子が多かった気もしないではない。
マンモス小学校の運動会の朝は、遠く学校の上空が黄土色の霞に覆われた。一学年六十数人クラスが五、六組もあり、これに六学年を掛けると全校生徒数が出る。走り回る子どもたちのせいで運動場は砂塵の嵐だ。娯楽の少ない時代、町内の人々から親戚縁者、地方出身の若い職工も見に来て、場所がないと運動場の周囲の電柱に登る者も出た。