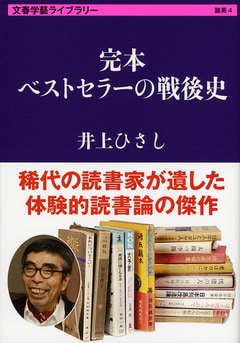5月12日、日本演劇界を代表する演出家・蜷川幸雄さんが亡くなりました。 「オール讀物」平成18年1月号に掲載された、演劇界の巨匠2名による対談を公開します。
「やっと会えましたね」
30年以上、日本の演劇界をリードしてきた両雄が、2005年秋「天保十二年のシェイクスピア」でついにタッグを組んだ。
古希を迎えた2人が初めて語り合う、創造の楽しさ、舞台の魅力。
前口上
俳優たちをのせた舞台と観客席とが向かい合い、その上とその四周に屋根と壁がある。これが演劇の基本財です。このとき演出家は、舞台の上のすべてに責任を持ちます。
まずなによりも、自分の全存在を賭けて作者より深く戯曲を読み込み、彼にしかできない方法で、人間と社会との関係を、つまり彼の「世界」を生き生きと構想します。このときの彼は疑いようもない芸術家です。
次に彼は、その「世界」をもとに俳優たちを選び、さらにその意味を装置や照明や衣裳や音楽や音響の専門家たちに伝えます。しかもこれらのすべてに「予算の範囲内で」という厳しい縛りがあります。このへんでは、彼は株式会社の経営者です。
稽古場は戦場になります。怯える俳優を励まし、はやる役者を抑えながら、彼はあらゆる方角に気を配っています。なにしろ現場には予想外の出来事が地雷のようにいたるところに埋まっていますからね。このような状況のもとで、彼は舞台でしか起こり得ない「演劇的時空間」を創り出し、自分の「世界」を実現しようと必死の努力をつづけます。ここでは、彼は部隊長であり斥候(せっこう)であり、傷ついて気後れした役者たちを看(み)る病院長にもなる。そして同時に、彼の脳裏には常に「観客からはどう見えるか」「どう聞こえるか」という声が響いていますから、観客の代表でもあります。一身にして芸術家と社長と部隊長と斥候と病院長と観客を兼ねなければならないのですから、演出家という仕事は、たいへんな力業(ちからわざ)です。
蜷川幸雄さん(1935―)は、この30年以上にわたって、傑出した舞台を次つぎに世に送り出してきた演出家で、その活躍は広く世界にまで及んでいます。たとえば、英国の名誉大英勲章を受けられたのも、シェイクスピアの本場のイギリス人が、「日本人がシェイクスピアをこんなふうに自分のものにしているのか」と感動したからでしょう。この意義は逆のことを考えてみれば、すぐわかります。
イギリス人の演出家がイギリスの俳優で近松を舞台にして日本に持ってきた。それを観た日本人が、「そうか、近松の本質はこうだったのか」と再発見して、それが外国人によってなされたことに感動する。蜷川さんはそのような仕事を成し遂げられたのです。
けれども、蜷川さんはこういった栄誉には関心がないようです。ただただ最高の職人を目指している。そうですね、「巨匠」という冠(かんむり)を絶えず拒否している巨匠でしょうか。その蜷川さんと今度初めて一緒に仕事をすることになりました。
(井上記)
蜷川 僕はいつも芝居が終わると腑抜けになるんですが、11月に「天保十二年のシェイクスピア」が終ってからは特にひどかった。この2週間、何年かぶりで、仕事をしていないんですよ。
井上 僕も、しばらく呆けたようになっていました。
蜷川 もう、体じゅうと脳髄を全部使わされた芝居でしたからね。で、しわくちゃになったというか、ボロきれのようになりまして。これじゃダメだと思って、部屋の掃除をして……。本を4分の1捨てて、ビデオも7割がた捨てて、身ぎれいにして、今日のこの対談で、おかげさまでようやく人間として再出発できました(笑)。
井上 こうやってきちんとお話をするのは、今日がはじめてですね。
蜷川 製作発表で、僕と井上さんが並んで写真におさまったとき、みんな、ありえない組み合わせだと思ったんじゃないでしょうか。
井上 歳も一つしか違いませんし、デビューの時期もほぼ同じ。蜷川さんがアングラ演劇から商業演劇に進出なさって、「ロミオとジュリエット」を演出した1974年は、たしかこの「天保十二年のシェイクスピア」の初演の年でした。

蜷川 演劇界というのは変なところで、居場所が違うと触れ合う機会があんまりないんですね。僕は当時、井上さんの「天保十二年~」の戯曲を読んで、面白い、やりたいと思ったんです。でも当時の僕にはいい役者が集められなかっただろうし、井上さんもはじめから西武劇場のために書かれていましたからね。
井上 蜷川さんがよく仕事をされていた劇作家の清水邦夫さんとは、NHK学校放送でずーっとご一緒していた。小学生向けのラジオドラマの台本を2人で週替わりで書いていたんですよ。
蜷川 ええっ。清水もかなりの遅筆なのに、そのお2人でよく穴が開かなかったですね(笑)。
井上 それが奇蹟的になにごともなかった。札つきの遅筆2人組に番組を任せたディレクターの蛮勇に改めて敬意を表したい(笑)。当時、清水さんは蜷川さんと組んで次々に話題作を発表していました。「真情あふるる軽薄さ」は1969年だったでしょうか。これはすごい事件でした。その舞台を観て、とてもショックを受けたのを覚えています。戯曲も凄いが演出も凄い、と体がふるえました。そしてそれから30年、ずっと同じ演劇界にいて、お名前と蜷川伝説を伺うのみでした。ですから、今回「天保十二年のシェイクスピア」でご一緒することになって、人生の黄昏もちょっと色濃くなったときに、ああ、やっと間に合ったな、と思いました。
蜷川 本当にそうですね。この歳になって、こういう芝居ができるとは……。
井上 初めて言葉を交わしたのが、2004年秋の文化功労者の授賞式の控え室。その時も、「よろしくお願いします」「(脚本を)直します」とそれだけ。打ち合わせもなし。脚本を3日で直すと生意気を言っていた割には、結局1ヶ月持ち歩いて手を入れていましたから、皆さんをずいぶんやきもきさせてしまいましたが。
蜷川 僕が最初に読んだ台本では「このたびは」と言って足袋を見せるという、言葉遊びから始まっていたのに、第2稿を読んだらそれが全部なくなっている。もうパニックになりました(笑)。
井上 いまどき「御礼モスリン上げます」とモスリン(メリンス)の着物を見せるなど、客席に伝わらないですよ(笑)。正直なところ、「天保~」はダメな戯曲と思っていました。初演の演出は出口典雄さんで、すぐれた才能の持ち主ですが、作品の出来が遅れた上にあまりにも長大すぎて、さすがの出口さんも腕の振るいようがなかった。だから今回のお話を頂いたときは意外でしたし、同時に、これが最後のチャンスだと思って、ずいぶん手を入れました。
特に、ト書きをどんどん削りました。下品なたとえですが、若い頃の戯曲は、結婚したての夫がいろいろ変な知識を仕入れて、ものすごい前戯をやる(笑)、そういう感じになっていた。
蜷川 アハハ。よくわかります。

井上 年のせいかどうか、そういう前戯がつまらなく思えて、削りに削って「農民合唱隊が歌う」とそっけなく始めました。あとはすべて蜷川さんにお任せしようと……。
それが蜷川さんの手にかかると、皆が半裸で肥桶を担いで、とどろくような大合唱に生まれ変わっていた。稽古場で最初のシーンを見たときは、驚いて、面白くて、腰を抜かしそうになりました。あの通し稽古はすごかったですね。自分が作者であることも忘れて唖然として観ていました。
蜷川 作者に見せるときが一番緊張するんですよ。できることなら来てほしくない、と願うくらい(笑)。
井上 そうでしょうね。
蜷川 だからあの時「面白かった」と言って頂いて、本当にほっとしました。役者たちも、井上さんがどこで笑ったとか、どこで笑わなかったとか、手を動かしたとか、演じながら全部見ていたんですよ。
井上 次々に繰り出されてくる色彩の組み合わせの面白さとか、役者さんたちの色気や熱気とか、大道具の出てくるスピードとか、芝居10本分くらいの手が使われていて、気がついたら4時間たっていました。自分の作品を通して、蜷川さんというのはすごい人なんだと改めて実感しました。
蜷川 僕は、何が嬉しかったかというと、生き返ったんです。井上さんの戯曲の言葉で。僕自身が蘇生した。井上さんはどうしてこんなに美しい言葉を書けるんだろう、どうやったら、こんなことが舞台の上で成り立つんだろう。この人の言葉を何とか自分のものにしたい……。三島由紀夫に対しても、寺山修司に対してもそうですが、その思いが、僕を芝居へと駆り立てているんだと思います。
「裸になるから、やらせて」
井上 沢竜二さんが歌いながら踊る、ふしぎな、でも懐かしいような場面、沢さん、大変だったとこぼしていましたけど(笑)、あの踊りには大衆演劇に半生を捧げた沢さんのすべてが入っている。涙が出ました。
蜷川 あれは、いいですよねえ。袂をスッと返したり、細かいテクニックがいろいろ入っているんですよ。
井上 もちろん他の役者さんたちも素晴らしかった。唐沢寿明さんの台詞の速度と正確さ、幕兵衛(まくべえ)をやった勝村政信さんの暗さ、篠原涼子さんの清潔さと伝法なところの使い分け、藤原竜也さんの輝き。
蜷川 大変だったんですよ。頑固者たちを一つ土俵に上げるのは(笑)。さっき言った沢竜二さんからは「僕、出たいんだけど」と電話がかかってくるし。白石加代子さん、きれいな役が好きなのに、老女の役をやらせちゃって、悪いなあ、今度何かの公演で借りを返そう、とか(笑)。そうこうするうちに、夏木マリさんからでっかい文字のファックスが入って、「私は長女じゃなくて次女をやりたい。次女はセックスシーンがあるから」と言ってきたり(笑)。
井上 長女役の高橋惠子さんの、御馳走を次々に食べながら口にモノが入ったままで、どんどんセリフを言う場面、あれ、よかったですねえ。でも、何を食べていたんですか。
蜷川 バナナとはんぺんです。もう、口がどんなになってもいいから、食べろ、食べろ、食べろと。これまでの人生で「舌打ち」さえしたことがなかったという女優さんが、太股に刺青入れて、本当に魅力的な悪女を演じてくれました。
井上 俳優によって、言葉を変えたりするんですか。
蜷川 藤原君はまだ若いから、何を言っても大丈夫という気持ちはありますね。例えば篠原さんは、スケジュールの都合で、2日ぐらい遅れて稽古に入ったんですよ。遅れて合流するときって、コンプレックスと、汽車が出ちゃったなあ、という焦りがあるものなんです。だから、篠原さんの最初の日は入口まで迎えに行って、一緒に喋りながら稽古場に入るようにした。それから、唐沢さんは大きな役ですから、あんまり大勢の前でダメ出ししないで、そばへ行く。で、毬谷友子はギューギュー追いつめた。自分で「裸になるから、やらせて」と言ったんだから、新しい毬谷に出会えなきゃしょうがない。裸になれ! って。
井上 いやー、僕らから見るともったいなくて。なにしろ矢代静一さんのお嬢さまのオッパイですからね(笑)。
蜷川 いつもの毬谷さんじゃ、僕は嫌だったわけです。彼女の「新しい自分」が欲しかった。でも初めはうまくいかなくて、「グラウンド1周して来い」と。「あんなに走らされたのは生まれて初めてだった」って言ってましたけど。でも、こういうのはすごく言い方が難しいんです。いったん「ヤだなあ、蜷川は」と思われてしまうと、もう空気がダメになっちゃうんですね。ことにこういう喜劇の場合、雰囲気を損なってしまうと致命的。「俺も気をつけるから、おまえらも気をつけろよ」って、みんなに正直に言ってました。
演出家と、非演出家の分かれ道
井上 蜷川伝説って、たくさんあるんでしょう。
蜷川 井上さんだって、「遅筆堂伝説」がたくさんあるじゃないですか(笑)。僕のは嘘も多いんですよ。
井上 ええ、この間、嘘を一つ発見しました。蜷川さんはすごく怖くて、稽古場では灰皿を投げたりテーブルをひっくりかえしたりするという伝説。僕もずーっと最近まで信じていたんですが、あれは実はたった1回か、2回。稽古場に大部屋の役者たちがサングラスをかけて、時代劇なのに浴衣も着ないで、スリッパ履きで現れて、しかも掃除用具で立ち回りをしたからなんですってね?
蜷川 僕、商業演劇で仕事を始めたときに、他人の金で仕事ができる人たちがすごくうらやましかったんです。コーヒーだって自分で淹れたことしかなかったのに、稽古場へ行くとコーヒーが出てくるんですよ、商業演劇って。それなのに座敷箒でフェンシングはないだろうと。だからね、その怒りをぶつけたんです。闘争だったですね。だって、誰も僕のこと演出家だって思っていないんだから。もちろん尊敬もされてないし、ギャラは中堅俳優とどっこいどっこいだし、そこから這い上がってきましたから。今でもリア王のように、頑なな石のような心を抱えています(笑)。
井上 俳優という、人に見られる職業から、演出家になって、意識はどういう風に変わりましたか。
蜷川 自分が演じなくてよくなったことは大きかった。演出家に転身したのは31くらいのときなんですが、すごく自由になったんですよ。
井上 役者をやっているときよりも?
蜷川 役者のときは自信がないからイライラしていたんだけど、演出家になったら「おい、みんな行くぞ」とか「おはよう」とか言ったりするのが恥ずかしくなくなった。「演出家」という役を演じていたのかもしれません。
井上 なるほど。演出家を演じているうちに、何かを投げたり、伝説が生まれた……。
蜷川 いや、あれは本気でした(笑)。でもね、商業演劇で仕事を始めて2本目の「リア王」で、僕は衝撃的なことを言われたんです。松本幸四郎さんがリア王で、財津一郎さんが道化。で、財津さんがある日、ちょこちょこっと寄ってきて、言ったんですよ。
「蜷川さん、蜷川さんがそうだって言ってるんじゃないんで、誤解しないで下さいね。でも僕、嘘で怒られると分かるんで、嘘で怒らないで下さい」
って(笑)。これはいいときに聞いた、油断しなくてよかったと思いました。
井上 僕は「きらめく星座」という自作で初めて演出をしたんですが、役者さんが理解不能なダメ出しをしてしまうんですね(笑)。「この稽古場には宝石が落ちていますから、それを拾いましょう」とか、言っている自分にもよくわからない。演出家と作家では言葉が違いますね。
蜷川 清水邦夫が演出をやっているのを後ろで見ていたことがあるんですが、「だから、世界に向かって叫ぶんだよっ」とか言って怒っているんです(笑)。客観的に見ているとね、通じないんですよ。
井上 通じませんね。
蜷川 おかしいんですけどね。
井上 具体的な指示を出さないといけない。フワッとした気取った表現では全然通じない。
蜷川 井上さんでも、演出家として作者として、怒鳴ったり、怒ったり、声を荒げるということはありましたか?