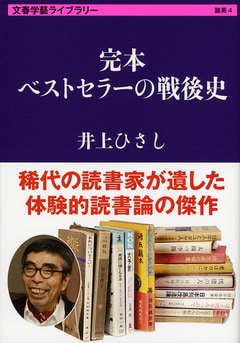井上 声が高くなって力が入るというのはありましたが(笑)。演出家としての僕は脚本を書いてもいるので、かなり立場は強いはずなんですが(笑)、稽古が進むにつれて、役者さんの方が、僕よりもぐーっと力を持ちはじめて、自分のやりたいことをやりだすわけです。それをなかなかとめられないんですね、僕の力では。ここが演出家と、非演出家の分かれ道ですね。紙の上ですと、消して書き直せば実現するんですが、舞台の上では、キャリアも誇りも技術もある、生身の俳優を説得しなければならない。そんなに素直に言うことを聞いてはくれません。つまり、ナメられるわけです(笑)。
僕はもう1本、「花よりタンゴ」でも演出をやったんですが、ハナ肇さんが、有り金取られて絶望するシーンで、ピアノの上を歩くと変な音がして面白いと言い張ってきかないんです。僕は楽器に足をかけるなんて絶対ダメだと思ったんだけど、いくら言っても負けてしまう。
蜷川 じゃあ、ハナさんは本番もピアノの上を歩いたんですか?
井上 歩きました。これで、ああ、演出は演出家に任せよう、と諦めがつきました(笑)。今の若い作家たちは、自分で演出もやる人が多いですが、やっぱり演劇の歴史の中で演出という仕事が俳優業や作家業から分かれたことには意味があるんだと思うんです。
蜷川 そうですよね。他人の想像力がかけ合わさるということが、自分で作・演出をしてしまうとなかなかない。
演出家の仕事で一番難しくて大変なのは、基本的なことですが、役者とのコミュニケーションなんです。僕の放った不用意な一言で、その時集まっているカンパニーがずたずたに壊れちゃったり、とげとげしくなったりすることがある。僕じゃなくて役者のワガママが原因の場合もあるんですよ。僕がその人の目をあんまり見なかったとか(笑)。大変ですが、そういうコミュニケートするエネルギーが持続して、うまくいったときは楽しいですねえ。
あと、僕の場合は何とかして戯曲の「言葉」に拮抗したいなあと思っている。今回も、印刷された上演台本のほかに、井上さんの手書きの修正が入った原稿をテーブルの上に置いているわけです。どこをどう直したか、たとえば「ね」を消して「と」にしたとか、そういうのがヒントになる。僕は台本の言葉は変えないで一字一句そのままやりたいので、役者にもすぐ「語尾を変えるな!」って言うし、飛躍しているところ、よくわからない部分はパズルを解いているみたいな感じです。たとえば井上さんの「ロミオ、ふわりと上へ上がる」なんてト書きがあると、どうやったらいいんだろう、と頭を抱えて悩むわけです。でもそこをリアルに変更してしまうよりも、工夫して本当に「ふわりと」ロミオが飛ぶと、客席からは大喝采が起きるんですよ。
井上 ご自分で脚本を書いたことはないんですか。
蜷川 井上さんも先ほどおっしゃってましたが、作家と演出家では言葉の選び方に関しての意識が全然違うんです。だから、作家の言葉に対する“畏れ”は常にありますね。僕は清水邦夫が初めて脚本を書いて直しているとき、同じホテルに泊まって寝ていたんですが、清水は「できないっ、できないっ。ダメだ、ダメだっ」て言いながら、ウウ~ッって部屋の中をグルグル走っている。僕はそこで起きられなくて、寝たふりをしていたんですが、そのとき、ああ、自分は文字に手出しをしちゃいけないと思いました。
井上 作家が演出家も兼ねるつもりで書いてしまうと、ひどい脚本になるんですよ。もちろんこれは僕の場合ですが。やたらとうるさいト書きばっかりで、いっそ小説にしてしまったほうがいいくらいです。チェーホフがやっぱりすごいと思うのは、ト書きのあの簡単さ(笑)。あれは考えに考えた末に残していますね。
蜷川 そうですね。僕は、シェイクスピアで嵐の中を走らされたあとにはなぜか、繊細な弦楽四重奏曲のようなチェーホフがやりたくなるんです。
書いているときが稽古場
井上 私には今、小説よりも芝居の方がずーっと面白いんです。小説は、読者がどこにいるのか分からない。かつては、反応があったんです。発表すると押し返してくるものが感じられた。このごろ、暗闇に石を投げているようで、誰も痛いとか、ハズレとか言ってくれない。
ところが、芝居には、観客がいる。しかも、時間を割いて、前売りを買ってくださって……そのとき、まだ脚本が出来ていないっていうのはほとんど詐欺です(笑)。それでも時間をかけて、交通費をかけて遠くからいらっしゃって、この人たちがつまらない芝居を観せられたときの顔というのはすごい(笑)。
蜷川 怨嗟の声が直接聞こえてきますからね。
井上 損したというより、もっと業が深いですね。芝居全体に不信感を抱き始める。自分はなにか大犯罪を犯してしまったんじゃないかと胃が縮こまる。そういうときは客席にいられなくて、遠くの照明室の隅っこからこわごわ見ている。
蜷川 僕も客席の一番後ろで、お客さんの反応を見ながら舞台を観ていますが、井上さんも結構、気になさるんですね。
井上 ええ、なにより気になります。ところが、これがいい芝居だったら正反対。金を払ってきてくださったお客さんがニコニコして、「ありがとうございます」なんて言ってくださるんですから。そういう一番正直な批評家がいるところで、一所懸命やるほうが楽しい。もっとも成功する芝居のときは、書き上げた瞬間に何となく直感はあるんです。
蜷川 へえ、そうなんですか。
井上 何も考えないときは成功ですね。「やったーっ」も「しまった!」もない。妙に澄んだ心境になります。そのままお寺に行けば高潔な大和尚になれそうな心境です。そして稽古が始まって、色んなパートで、同時進行でいろんな人がいろんな仕事をしているのが、初日が近づくにつれて、だんだんとね、ガチャーン、ガチャーンというふうにくっついてきて、舞台稽古のとき、それが全部くっついて生きはじめるわけですね。そのときの面白さといったらない。
蜷川 僕にとっての稽古場みたいなものですね。
井上 そうです、そうです。書いているときが私らの稽古場です。その前にいろんなものを集めたり、考えたり、組み合わせたり、何か1行いい台詞を書きたいとかね。そういうことをやっています。
蜷川 僕は構想のときよりも、稽古しているのが楽しい。初めは脚本(ホン)を読みきれていないんです。で、稽古場の最後の通しか、ゲネプロのとき、あっ、こういうものをつくりたかったんだ、とか、あっ、こういう作品だったんだ、というのが初めてわかるんですね。
井上 そこへ最後に観客の皆さんがガチャーンと入って、これがまたよかったときは、こんな幸せなことはないですね。その夢を追いながら、ここまで来てしまいました(笑)。この次も、とか、この次こそ、とか。それがエネルギーですね。
逆に、すごくうまく行っているように思っていても、なぜかフッとご飯が食べられなくなったり、ぷつっとここ(左後頭部に手をやって)に円形ハゲが出来たりすると、これは危険信号です。こういうときは、必ず先行き、この芝居はダメになる。
蜷川 どこかで詰まるんだ。
井上 最初の発想から間違えていた、ということが分かるんですよ。これが一番怖い。誰にも相談しちゃダメだっていうのも鉄則なんです。だって、自分のつくった世界を自分でどうにかできないというのは、これ、原理的におかしいわけですから。
蜷川 1日に何枚くらい書かれるんですか。
井上 調子のいいときは30枚くらい書きますよ。特に、もう、展開を読みきって、これしかない! という段階になると一気呵成にいくんですが、最初はやっぱり5枚、7枚、8枚、また5枚、10枚、3枚とか、そんな感じですね。小説はもっと自由ですから、連載でも、詰まると「まあ、余談だが」「それはさておき」「ところかわって」と緊急避難しておいて、どんどん違う話をしながら、やがて戻ると意外に解決がつくということもないではないのですが、芝居ではそうはいきません。芝居には演出家がいて、稽古場があって、スタッフ、キャストがいて、しかもお客がいる。そこで最初の1行を始めなければいけないときは、気合も入りますけど、難しいですね。そういうところ、本当にうまいと思うのはイプセンですね。
蜷川 あっ、そうですか。
井上 イプセンのあの入り方は、さりげなくたくさんの伏線を張りながら、それがちゃんと芝居になっている。まあ、「書き出しはイプセン」です(笑)。蜷川さんも「頭の3分で芝居は決まる」と仰っているでしょう。
蜷川 最近はそれほどでもありませんが、頭で劇の時間に入れてくれよ、という思いはありますね。子供の時から母親に連れられて、歌舞伎などを観ていたからかもしれませんが、幕開けで、ああっ!とドキドキするのが好きなんです。
井上 他にはどんなものをご覧になっていたんですか。
蜷川 子供のときは歌舞伎。それから、諏訪根自子さんという人のヴァイオリン・コンサートとか、巌本真理さん、藤原歌劇団に、斎田愛子さんという人がいて、彼女の「カルメン」だとか、貝谷八百子さんのバレエとか。地方の小学校しか出ていない母親が富山から東京に出てきて、僕を連れて歩いたんですね。自分の憧れていたものを息子にも見せたかったんでしょう。僕は終戦のとき小学校4年でしたから、その頃から、中学2年ぐらいまで。あの敗戦の混乱の中でも、焼け跡で、日比谷公会堂ではそういうレビューをやっていたし、帝国劇場だって、アメリカの映画がかかっていた。そういうものを普通に観に行けるくらい、庶民の女性もバイタリティがあったんですよ。とってもいい時代に僕は教育を受けたと思います。
井上 私がその頃住んでいたのは、山形県の小さな町で、劇場がひとつあって、ここで映画もやれば、実演もやるんです。大好きだったのは「ワンツー・パンチと青空楽団」という家族劇団で、これが3ヶ月にいっぺんぐらい回ってくるんですね。娘が歌を歌って、今考えると下手な歌ですけど、お兄ちゃんが太鼓を叩いて、お父さんがアコーディオンを弾いているような。その人たちが来ると、学校に行かずに朝からずっと、旅回りの一座の日常生活を見ていました。大人がみんなおひねりを投げるので、僕たちも夏だとスイカを畑から持っていってゴロゴロ転がしたり。あとは三流の歌舞伎とか、いろいろな出し物が来まして……やっぱり母親が芝居好きでした。母親の影響というのは強いですね。
怒りというエネルギー
蜷川 井上さん、劇評に激怒することなんてありませんか? 僕はしょっちゅうなんですが。
井上 あります。「ここをこうすれば」と、いいところを突いてくる批評には素直に脱帽しますが、実にくだらない、初歩的なことで文句をつけてこられると、激怒します。一晩たつと、まあ、しょうがないや、とは思いますが。
蜷川 そうですか。僕はもっとねちっこくてね。アングラやってた新宿時代、「蜷川の芝居を観ると、観客を意識しすぎていてゾッとさせられる」っていう批評があったんですよ(笑)。もう、頭に来て、よし、俺は一生、お客さんをゾッとさせてやろうと。そういうのをネチネチと根に持っていましてね。今でも暗闇からパチンコ玉撃ってやりたい奴はいくらでもいますよ(笑)。
井上 僕も「日本人のへそ」という芝居で、「大変面白いけど、思想がない」と書かれました(笑)。
蜷川 本当? それ、すごく失礼ですよね。
井上 それで、思想、思想ってなんだと思って、いろいろ思想関係の本を買いました(笑)。僕が芝居の世界に入ったのは、明日、食えるようにしたいというそれだけの理由でしたから、思想なんて関係なかった。今日、自分の力の中で一番いいものを出さないと、明日、食えないんじゃないかという強迫観念。それは僕の生い立ちや、僕らの世代とも関係があると思いますが。
浅草で、渥美清、谷幹一、長門勇、関敬六といった出世前の役者さんたちがめちゃくちゃおかしい芝居をしていた。ストリップを観に来たお客さんが、食べてる弁当を落っことすぐらい笑っていました。文芸部員として、舞台下手の袖でずーっと見ているんですけど、その時から、人間の心をつかんで、その心を揺すぶるくらい笑わせる芝居を書きたいと思い始めました。幸いラジオの仕事で、すぐれたディレクターたちに基礎訓練を受けて、小説も大好きですから小説も書いて、生活基盤をしっかりさせてから芝居を書こう、となっていったのです。
蜷川 僕の場合は、実家が洋服屋だったんですが、両親とも芸術に対する尊敬とか、パトロネージュの精神がある家だったんです。売れない画家の絵を買って援助してあげたり、学校の先生が来ると洋服を作ってあげたり、酒をふるまったり、そういう環境の中で育った。でも、そういう絵描きさんや学者さんたちが、売れたり偉くなったりすると、とたんに掌を返すように疎遠になってしまって、お礼状の一つも寄越さなくなる。それを見ていて「なんか、こいつら嫌だなあ」という気持ちがずっとあったんですね。
やさしくないと思うんですよ、人間に対して。僕の父や母がどれだけあの人たちを大事にしていたか。夜中でも、フラッと来ればお酒を用意してあげて、僕たち子供まで起こされて歓待したのに、偉くなったら素知らぬ顔かよ、と。
井上 よくわかります。正義って言うと大げさですけど、人の理とか、そういうことですよね。