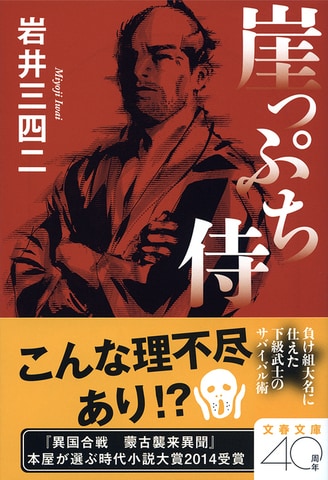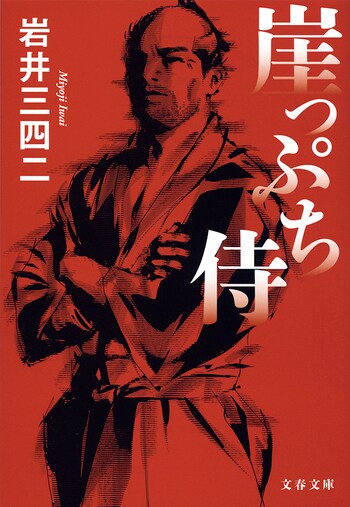田舎の小大名など天下を取ろうとしている秀吉から見れば、使い捨ての駒のひとつでしかないだろう。その小大名に仕える下級武士強右衛門のことなど考えられる筈もない。
変わりゆく時代のなかで、強右衛門の苦難が始まる。戦さでの戦いではない。生きのびるための暮しの戦いをしなければならない。
岩井三四二は、勇ましい戦さよりも、武士の暮しにこそ着目する。そこにこの小説の面白さがある。
小田原攻めから戻ってきた強右衛門に対し妻女は、父の七回忌の掛かりをどうするのか、長男を学問のため寺にやるとして寺への寄進をどうするのか、娘に新しい着物を作ってやりたいが、その掛かりをどうするのか、と内証の苦しさを訴える。「女房の目」である。
このあたり、現代の家庭とさして変らない。明治大正期の歴史家、内藤湖南が日本の歴史を振返って、こう言ったことはよく知られている。
「今の日本を知るためには古代史を研究する必要はない。応仁の乱以前はまあ外国の歴史のようなもの」
とすれば、応仁の乱後、この戦国末期の夫婦が現代の夫婦と似通っていてもおかしくはない。強右衛門は里見百人衆の一人。見てくれはいいが、しょせんは田舎の土着の武士。暮しは楽ではない。
岩井三四二は強右衛門の経済生活を丹念に描き込んでいる。面白いのは、強右衛門が「半農半士」であることだろう。普段は、農に就いていて、いったんことがあると士になる。この時代、武士の一般的なありかただったのではないか。
強右衛門は田の仕事さえ嫌わない。決していつも戦さで戦ってばかりいるわけではない。むしろ「半農」のほうが日常だろう。
加えて、強右衛門は船商売、廻船業もしている。小さな船を持っていて、領地でとれる米や薪を大きな町に売りにゆく。手広く商売をしているというより、そうしなければゆとりのある暮しが出来ないからだろう。
時代小説で、「半農半士」であり、船商売までしている武士が描かれるのは珍しいのではないか。そして、武士の実態とは、こういうものだったのではないか。「戦う武士」より「働く武士」である。しっかりと足が地に着いている。武士の魂だの忠義だの大仰なことを言いたて「死」を重んじる立派な侍より、暮しを大事にし「生」を重んじる強右衛門のほうに親しみを覚える。
強右衛門が「女房の目」という厳しく、リアルな生活者の考えを持つ妻女に頭が上がらないのも微笑ましい。武家社会の武張った家長とは違う。岩井三四二はキャラクターづくりがうまい。
さらに、農家の娘に、側女にしてくれと言い寄られ、さかんに「お屋敷と化粧料、お忘れなく」と釘をさされては、困り果てる姿もユーモラス。この娘、男の力などに負けない、したたかさを持っている。こういう強い娘が登場しているのも、「世の中が変わった」からなのだろう。