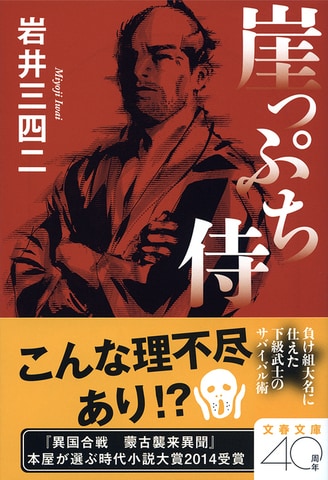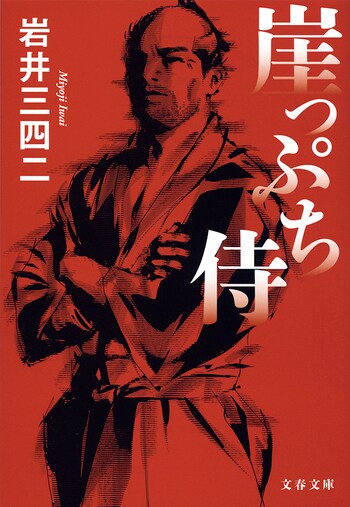安房の小藩は時の権力者に翻弄され続ける。秀吉の時代には、京にいる秀吉の意に従い、強右衛門は普請の手伝いに駆り出される。畚(もっこ)をかつぎ、鍬をふるう。そのために「人足」とまであなどられる。
「侍は主の浮沈で、自分の人生も変わってゆく」
関ヶ原の戦いでは運よく徳川方についたために、里見家は、実戦に参加しなかったにもかかわらず、戦いのあと、家康に取り立てられた。強右衛門の長男は、里見家のなかで要職に就いた。
小春日和のような日々が続く。しかし、変わりゆく世に平穏はない。家康周辺の権力争いの影響を受け、里見家も不幸に見舞われる。転封の憂き目に遭う。
お家存亡のときが来る。血気にはやる家臣たちは、館山城の明け渡しを拒否し、徳川家と戦うと息まく。
この時、強右衛門は「死」より「生」を重んじる「働く武士」として主戦派を抑える。
「籠城などしても無駄なこと。あの小田原城さえ落ちたぞ。ましてこんな小城、十日ともたぬわ。頭を冷やせ。無駄なことはやめておけ」
「戦う武士」なら負けるとわかっていて強権に向かってゆくだろう。武士らしく戦って死んでゆくだろう。それに対し、強右衛門は変わってゆく世の中をよく見ている。徳川家に刃向うことなど「無駄なこと」と醒めている。「働く武士」の真骨頂である。
もし強右衛門が「半農半士」ではなく、農も知らず、また船商売も知らない「戦う武士」だったら、主戦派に与したかもしれない。
しかし、強右衛門は戦い以上に、暮しを、生をよく知っていた。だから血の気の多い「戦う武士」に堂々と異を唱えた。みごとと言うべきだろう。
戦国の世が終わり、徳川の世になろうとしている。「戦う武士」はもう必要ではなくなってきている。秀吉の家臣に、佐古村の領地を検地されるという屈辱を受けた時、強右衛門は、世の中の変化を痛感した。
「世の中からは合戦がなくなり、平和になったようである。首をとって出世するなどは考えられなくなった。武勇を封印し、他国者と筆で戦うなど、半年前には誰が想像しただろうか」
強右衛門は「戦う武士」の時代ではなくなったことを知った。だからといって、新しい「筆」を持つ武士にもなりたくない。ではどうするか。
もともと「半農半士」である。士を捨てて農に帰ればいい。徳川の世はもう「半農半士」さえ許されないだろう。士農工商によって「半農半士」も過去のものになる。
そんな時代の流れにあって、強右衛門は最後、士を捨て、農に専念する決意をする。彼なりの時代への抗いであろうし、何よりも、「働く武士」として土に生きることが、かけがえのない自分の暮しだと思い定めたのだろう。強右衛門の老年を祝福せずにはいられない。