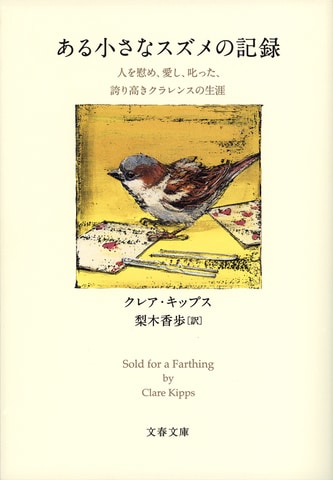
こちらもおすすめ
プレゼント
-
『妖の絆』誉田哲也・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募期間 2025/07/11~2025/07/18 賞品 『妖の絆』誉田哲也・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。
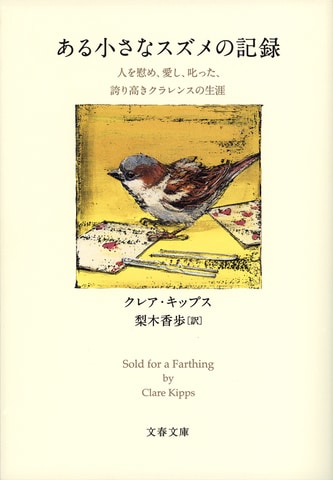

ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
| 応募期間 | 2025/07/11~2025/07/18 |
|---|---|
| 賞品 | 『妖の絆』誉田哲也・著 5名様 |
※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。