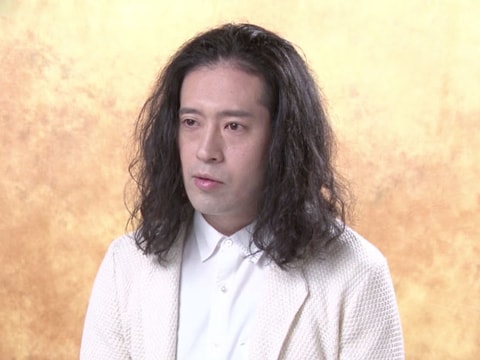二〇一五年、明石家(あかしや)さんまが還暦を迎えてBIG3はみな六十代以上となり、ダウンタウンも五十歳を過ぎた。私は、今もなお彼らの人気・実力は衰えていないと思っている。だが、いつの日か、私たちは彼らの晩年を目の当たりにしなければならない。それが引退という道なのか、人気の凋落という姿なのかは分からないし、彼ら自身も予想できないだろう。だが、率直に言って、私はその姿を見ることが怖い。その姿が、私にとって、胸を引き裂かれるほど辛いだろうということだけは、容易に予想できる。
昔のお笑い芸人について書こうと思ったのは、その不安を少しでも和らげるためだ。彼らの晩年の姿を見つめ、どのような最期を迎えたのかを知ることで、心構えをしておきたいのである。もちろん、それを知ったからと言って、不安が払拭される訳ではない。頭で理解したことと、心で感じることはいつも乖離(かいり)する。だが、それでも、歴史に学ぶことで、少しでも受け止める力を持っておきたいのである。その後にできるのは、なるべく先になるよう祈ることだけだ。
本書が、同じような不安を抱えるお笑いファンにとって、ささやかな一助になれば幸いである。
なお、本書では、取り上げる人物のことを一括して「お笑い芸人」として捉えている。これには異論もあるだろう。彼らは、「喜劇俳優」「芸人」「漫才師」「ヴォードヴィリアン」などを自称していた。歴史を振り返れば、「お笑い芸人」という言葉は、肯定的な言葉ではない。現代でも、伊東四朗(いとうしろう)は、「お笑い」ではなく「笑い」と言いたいと語っている。その理由は、「〈お笑い〉のあとにくっつくのは〈草〉で、お笑い草というのは何か程度が低」く感じられ、「信念を持ってる私にとって笑いをおとしめたくない」という思いからだという。(『キネマ旬報』平成二十三年十一月上旬号)
たしかに、笑いが蔑視されてきた歴史があるのは事実であり、それに対して喜劇人や芸人が戦ってきたことは尊重しなければならない。ただ、現在では、「お笑い」という言葉に対して、若い世代になるほど、蔑称の意味はないと思う。むしろ、カルチュア・ヒーローとして憧れの対象である。なので、本書では、笑いを目的としている芸能者というくらいの意味で、「お笑い芸人」を使っている。あえて一括りにしているのは、笑いを追求した人々の人生に共通する苦悩や葛藤を見たいからである。
本文中では、彼らが自称した「喜劇俳優」や「芸人」とともに、「お笑い芸人」という言葉も使っているが、私としては尊称のつもりなので、その点についてはご寛恕(かんじょ)いただきたい。
(「プロローグ」より)