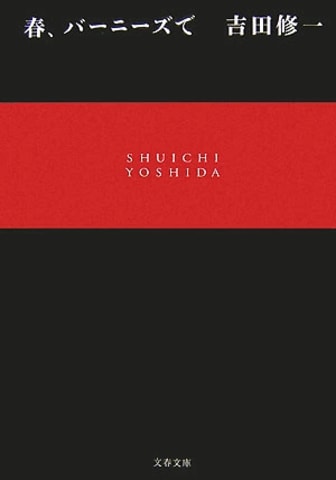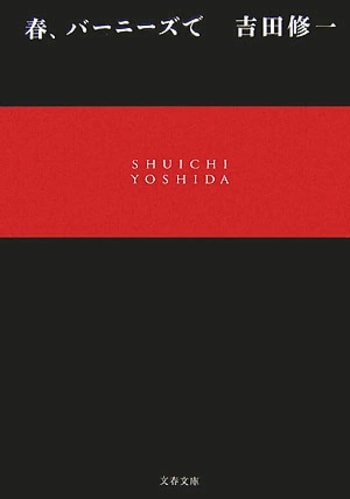都市のおとぎ話
――その最初の短篇「春、バーニーズで」では、筒井という妻も子もいる三十代の男が、「最後の息子」では閻魔ちゃんと呼ばれていたオカマのキャラクターと、新宿のバーニーズ・ニューヨークで十年ぶりにばったりと出会います。筒井の心境としては、閻魔ちゃんとの時間はすでに終わっていて、妻の瞳と妻の連れ子である文樹との時間のなかに現在では生きているわけですが……。
吉田 時間って、つながるじゃないですか。たとえば、ある人と会って一年、二年と過ぎれば、そこには二年分の時間があるわけです。そしてまた別の人と会えば、その人と流れる時間があると思うんですね。でも、別の時間のなかで暮らしていても、ふとしたはずみに、過去の時間とつながるような瞬間があったりすると思うんですね。
――この作品集には五つの作品が入っていますが、それぞれ独立した短篇小説でありながら、最初の四作は筒井を主人公にした物語でもあります。「春、バーニーズで」から始まり、筒井の住む聖蹟桜ヶ丘から新宿にむかう京王線の通勤電車で、マクドナルドで息子が話しかけた若い女性のことなどの想念が浮んでは消える「パパが電車をおりるころ」。会社の後輩に招待された結婚式のあと、ホテルの小さな部屋で妻と「おたがいにひとつだけ嘘をつこう」ということになる「夫婦の悪戯」。さらに会社にむかうつもりでいたのに衝動的に高速道路に入って北の方へむかう「パーキングエリア」……。ここには確かに「もうひとつの時間」が流れています。
吉田 これを書いているときに、ぼくが強く思うようになったのは、ドラマティックな出来事の起こる瞬間というものはドラマティックではないということでした。
たとえば、人生のなかでもドラマティックな瞬間ってあると思うんですよ。若いふたりにとっては結婚式ですよね。でも「夫婦の悪戯」は結婚式に参列している一組のカップルの一晩の話ですけど、この結婚式のときと、ふたりでホテルの部屋でなにげなく話していたときのことを比べて、十年後にどちらを覚えているか、比べられませんよね。むしろ、なにげなく話したことを意外と覚えていたりするものです。「パパが電車をおりるころ」では、文樹の本当の父親が家に迎えに来る瞬間が一番ドラマティックなんですが、十年後に印象深く残っているのは、その現場ではなくて、たとえば通勤電車のなかでああだこうだと考えていたことかもしれないですよね。ぼくとしては、東京という都市の、おとぎ話みたいなものを書きたいというイメージを持っていました。
――これは『春、バーニーズで』に限らず、吉田さんの小説に共通する特質ですが、それぞれの空気感がリアルに伝わってきます。たとえばマクドナルドで子どもが指をべとべとにしながらポテトを横にして食べているところ。サウナに行って、汗の雫が白木の床にぼとっと落ちる感じ……。
吉田 ぼくはサウナが好きなんですよ(笑)。しょっちゅう行ってるんで。
――たしかに水気のある場面が多いですね。プールとかお風呂とか。どうしてなのでしょうか?
吉田 浸っているのが好きなんですよ。なんか、自分の穢れた部分が出てくるような……気がするんですよ(笑)。