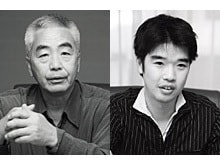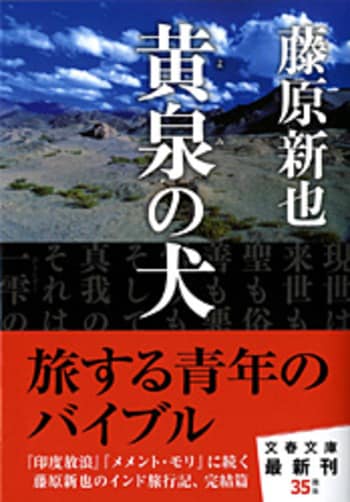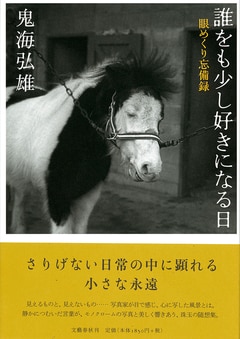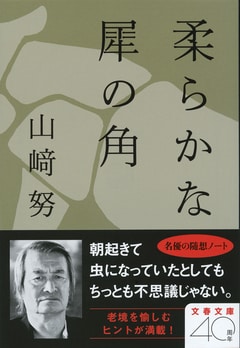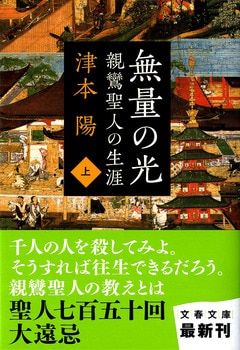〈瞑想ウイルス〉に侵される人々
稲泉 ところが、そこに異質な人たちが登場してくる。
藤原 そう。七〇年代の半ば辺りから、これはちょっと自分とは違うなと思える世代がインドにやってきた。それがずっと心に引っかかっていた。
稲泉 空中浮遊が出来ると称して信者を増やしているフランス人の青年とか、瞑想を続けるうちに幻聴に苛(さいな)まれ始め、少しずつ混乱していくYという人物とか。本書にはそうした人たちがたくさん登場します。それを〈瞑想ウイルス〉と名づけた藤原さんは、彼らとの出会いや対話からオウムの萌芽のようなものを感じ取っている。
藤原 インドにおける宗教という体制に、いともたやすく近づいて行ってしまう若者たち。瞑想していたらヒマラヤの頂上からエネルギーが立ちのぼっていると言ったり、お互いをホーリーネームで呼び合ったりする連中は、その頃からすでにたくさんいた。僕は彼らの姿を見ていて、いつも違和感を持っていた。オウムは九〇年代だけれど、自分との違いを強く感じた瞬間だったよね。
そういう誇大妄想って結局は保身なんだ。インドの現実というものはとてもハードだから、誇大妄想で逃げる。僕の旅はいかに素の自分、正気に戻るかという旅だった。それは必ずしもインドだけの話ではなく、日本のような管理社会にあっても同じで、ヴァーチャルな世界の中で正気の自分を維持していくのは非常に難しいことだよね。僕はインドという現実原則の強烈な場で自分を守るために宗教に逃げず何とか正気を守れたから、この管理機構がぐちゃぐちゃに張り巡らされた日本でも自分のスッピンさを保ち続けることができていると思っている。
捨てる不安、そして快感
稲泉 その意味で、藤原さんにとってあのインドの旅は今も原点なのですね。
藤原 そういう保身の感覚は、ここ十年の写真の世界なんかにも現れていると僕は思っている。ある自分の表現の方法論を見つけたら、それを壊すことなく踏襲していってしまう。快適な身の回りから飛び出ることがなく、自分の表現を壊せないところがあるよね、今の若い人たちには。J-POPなんかを聞いていても、二十代の歌手が昔の歌のカバー曲を歌ったりしているでしょ。僕らの時代は自分の方法論が見つかって表現したら、それをすぐに捨てて次に行くということがあたりまえだった。当然、捨てるのは不安だけれど、そこには快感もあるってことを彼らは知らない。
稲泉 ただ、実を言うと僕にはその保身の感覚というものを理解できてしまうところもあるんです。藤原さんの言う「捨てる不安」は理解できても、快感のほうには確かな実感を抱けない。よく言われるように、何かを壊して次に進もうとしても、すでに全てがやり尽くされているとあらかじめ思ってしまう、諦観みたいなものがあるからかもしれません。今の僕がインドに行っても、藤原さんの旅はできませんよね、たぶん。壊すものがあまりないように感じてしまうから。一方で壊したいという欲求だけは強くあって、だから壊してくれそうな人に魅力を感じてしまう。そしてそれが幻想に過ぎなかったと気付いても、いつのまにかその幻想を簡単には手放せなくなっている。
藤原 確かに一個の身体が旅をするという風景は七〇年代の半ばに終わってしまったし、新しいイノベーショナルな表現は過去にやられていて、難しいと思う。後はいかに方法を組み合わせるかということしか残っていない。でもね、それにしても何でそこまでしがみついているの、と思うことが本当に多いんだ。
稲泉 自分について考えてみると、そこはそこで何かに引き裂かれていくような感覚があるように思うんです。しがみついていないとそれこそ自分が消えるというか、細切れになっていってしまうというか。だからこそコンセプトを設定して、バラバラになりそうな自分を接着することの方に必死になっちゃう。
本書の印象的なシーンの一つに、『東京漂流』で「人間は犬に食われるほど自由だ」というキャプションを付けたあの一枚の写真をめぐる後日談がありますよね。このシーンに僕はとても胸を打たれたんです。野犬に襲われそうになった藤原さんが骨を持って犬たちと対峙して、最後は川に飛び込んで逃げる。その後でひょんなことから藤原さんは火葬の番をすることになるのだけれど、その際の火や灰や川の情景に強烈なリアリティが立ち上がってくる。そうした手触りのあるざらつくような現実に向かい合うことを、痛切に求めている自分に気付かされた思いがしました。
藤原 あのシーンを今まで書かなかったのは、あまりに滑稽すぎて恥かしかったからなんだけど、滑稽を突き抜けると恐しいリアリティが生まれた。書くということはやはりすごいことだと思った。
あの犬に襲われるシーンでも、その渦中でどんどん正気が生まれてきた。消えて行きつつある自分の正気が立ち上がってきて、その正気によっていかなるヴァーチャルな世界にも汚染されない自分ができあがっていく。そんな体験の一つだったと思っている。