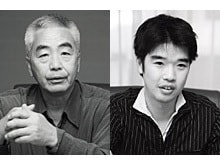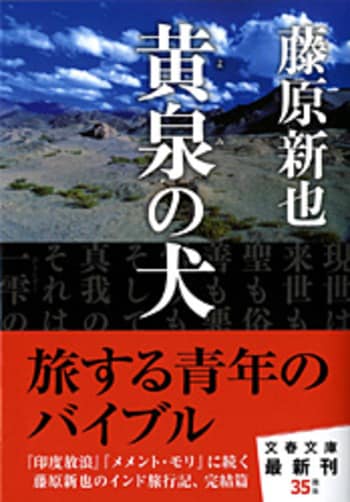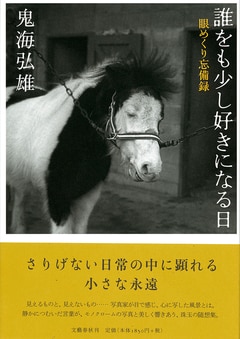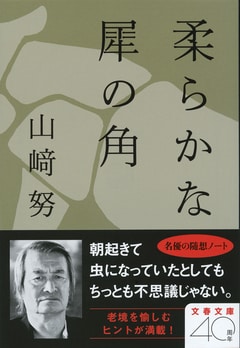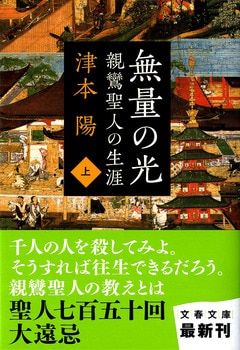都市は罰系を作らない
稲泉 本書の底流にはヴァーチャルな世界への批判が常にありますが、藤原さんはどのような意味でヴァーチャルという概念を捉えているのでしょうか?
藤原 例えば今はちょうど秋でしょ。すると、山に行けばキノコや栗や柿がある。里山の報酬というのがたくさんある。でもおいしいキノコもあれば毒キノコもあるし、栗には棘があるし、柿にも渋いものがある。必ず自然の中には報酬と罰とが共存しているものなんだ。つまり僕らが小さい時に自然の中で遊んだという体験は、報酬系と罰系が相まみえる世界に自分の身体を置いたということ。
バーチャルである都市は罰系をあえて作らない。いかに人間に快感を与えるかという考え方でできている。一番の象徴がコンビニエンスストアだよね。そこには報酬系しかない。その報酬系だけに生きている人間は身体のバランスが壊れていく。
稲泉 藤原さんが六〇年代に感じていたという“足音”は、まさにそれだったわけですね。実は僕はこの本を読んで、どうして自分が心を動かされたのかがうまく言葉にできなかったんです。でもいまの話を聞いて、本書に感じた迫力の正体が少し分かるような気がしてきました。自身の存在をめぐる危機感からインドに行った藤原さんが、旅の中で素の自分・正気の自分を獲得していく。一方でその周りに現れる人たち――空中浮遊やヒマラヤで光を見る人たち――は同じインドで正気を失っていく。その落差の間に浮かび上がってくる世界が本当にリアルなんです。藤原さんはインドにすぐ染まってしまう“オウム的な人々”を見つめながら、どんな気持を抱いていたのでしょう。不思議なのは、インドで同じ時間と場所を共有しているのに、藤原さんは全てに抗(あらが)い、彼らは染まっていく。そこにあった本質的な違いとはどのようなものだったのでしょうか?
藤原 世代の違いかもしれない。僕は四四年生まれなんだけど、数年後に生まれてくる団塊の世代との間に大きな断層みたいなものがある。いとも簡単に神がかる人に「そっちへ行っちゃいけないよ」と言いたかった。ただ、そこにはもう少し複雑な思いがあったんだ。僕はオウム事件の頃はコメントを差し控えていたのだけれど、軽々しく話せないという気持があった。というのも、ものすごく遠いのだけれど、ものすごく近くにオウムという存在を感じたから。この本の最後に極めて“オウム的”なYという人物が登場するけれど、その彼と僕は考えてみれば同じ時間と場所で向かい合っていたんだよね。オウム的な人間と僕は確かに全く違う存在なのに、でも一方では同じ空気を吸ってもいる。
稲泉 互いに矛盾している存在同士が響きあっていて、同時に成り立ちながらもすれ違ってもいて……。
藤原 そうした関係性をオウムに感じたんだよね。Y君に対しても「そっちに行っちゃいけないよ」という気分でいたのだけれど、実はそんな自分自身が同じ土壌の中にいる。その逃れようのなさがオウムにはあった。そしてそういった感覚は今のヴァーチャルな世界を生きている若い人間を描く上での、一つの基点にもなっているんじゃないかって思っている。