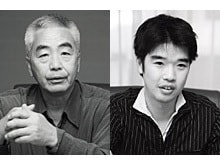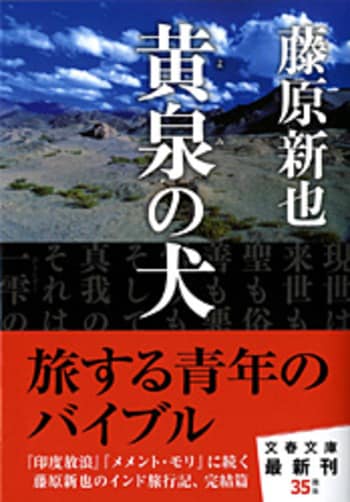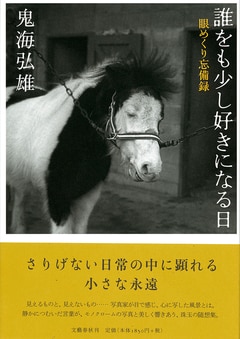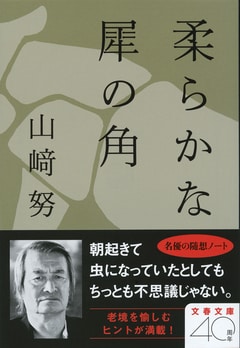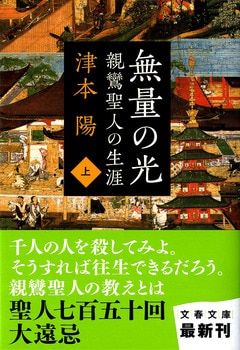『黄泉の犬』で二十代の旅を回想した藤原氏。 今の若者の旅との違いについて稲泉氏が訊く
稲泉 今回、『黄泉(よみ)の犬』の中で藤原さんは、二十代のときに旅したインドでの体験を下敷きにしながら、オウム真理教の深部に漂っていた若者たちの心性を描いています。『印度放浪』はもう三十年以上前の作品ですが、いまあらためてあの旅について書こうと思ったのは何故だったのでしょうか? 例えば僕がこの本を読んで引き込まれたのは、藤原さんが旅の中で出会った“オウム的なる人々”の姿が、時空を越えて当時の事件と奇妙に響き合っていくところだったのですが。
藤原 これは十一年前に「週刊プレイボーイ」でオウムについて書こうと始めた連載を大幅に改稿したものなのだけれど、途中で麻原彰晃の兄貴と会って話したところでトラブルがあったんだ。それで止む無く中断した後、こう考えた。オウム的な人のインドの旅を僕の旅と対峙させることで、今の若者のメンタリティみたいなものを描けるんじゃないか、って。というのも、当時の僕の旅と今の人の旅はかなり変わってきているな、という思いがその頃からあったから。
稲泉 変わってきている。

藤原 今の若い人たちは何かを成すために旅をしているでしょ。写真を撮ったり文章を書いたり、宗教的なものを取り入れるためだったり。コンセプトが先にくる旅を彼らはしている。
稲泉 自分に何かを上積みするために、何かの目的を持って旅をするという感覚ですね。対して藤原さんの旅は――。
藤原 僕の旅はむしろそういうものを一つ一つ壊していく旅だった。何しろ当時は自分の名前すら鬱陶しいと思っていたくらいだったしね。二十数年間を生きた自分がいて、日本という世間の中で生まれた価値観にがんじがらめになっている。でも、日本で培ってきた価値観や身体性が向こうの文化と衝突したときに、どんどん壊れていくんだ。最終的に自分がゼロに近づいていく、その感覚を僕は楽しんでいたんだね。

稲泉 そうした自分を壊したい、という感覚は藤原さんにとってどこから来たものなのでしょうか? 自分が見つからないみたいな感覚というか……。例えば、学生時代に『俺が消える』という論文を書いたそうですが、一人の読者としては“藤原さんにもそうしたアイデンティティの危機があったのか”と意外な感じがしました。
藤原 自分が見つからないというよりも、もうちょっとフィジカルな感じかな。自分の存在を確認できないという気分。十代から二十代にかけて、それがひたひたと押し寄せてくるのを感じていたんだ。当時はまだ土着というものと地続きの感覚があった時代だった。六〇年代は前近代が現代に向かって急カーブを描いて上昇する時代だったわけだけれど、その中で遠くから聞こえてくるヴァーチャルな世界の足音に、“いま”が侵食される危機感を肌で感じていたのだと思う。それを肌で感じていると、自分の身体をいかに回復すればいいのかという気持にとらわれてしかたがなかった。
稲泉 そうして訪れたインドの旅で、藤原さんは体制的だったり権威的だったりするものを全て否定しようとしますよね。本書の醍醐味は世界に対して抵抗を続けるその藤原さんの姿でした。特に宗教に対する拒絶の姿勢は一貫していて、ホーリーのお祭で額にビンディという紋章を塗られるのを拒否しようとし、最終的には袋叩きに遭ったり。とにかく頑ななまでに宗教を拒む旅を続けていきます。そこにとても迫力を感じました。
藤原 インドに行くと宗教はすごく力を持っているのだけれど、それは僕にとってとても体制的なものに思えた。だから今の子のように、そうした大きな体制や権威に寄っていくことは僕にはあり得なかったんだ。