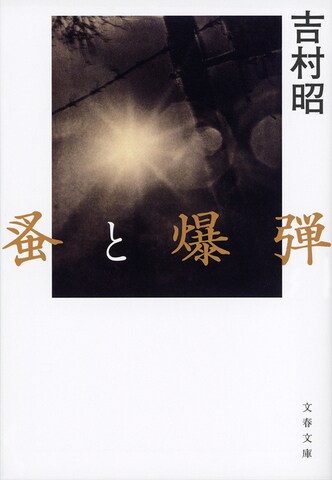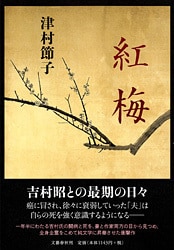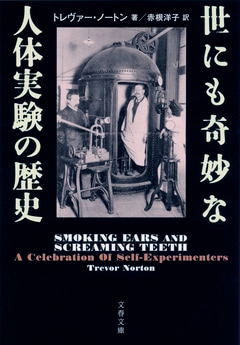本書には二つの大きな特徴がある。第一は曾根二郎という軍医は実在のある軍医をモデルにしていて、その人間像が適確に描かれていることだ。第二は、この時代(昭和の軍事主導体制下)の人間感情の歪みが「戦争の論理」に起因していることを、冷静な筆調で教えている点である。この二つの特徴を通じて言えることは何か。その問いを読者に問うているという意味で、本書は重い存在たりえている。
いうまでもなく二十世紀の二つの世界大戦は、戦争の本質を変えてしまった。科学技術が戦争を通じて進歩することで、それまでの限られた戦闘地域で、限られた戦闘要員(大体が二十代の兵士だった)が、自らの属する国家の国益の守護や国権の伸長、そして国威の発揚を求めて戦うという戦争は、その役割を終えた。第一次世界大戦では飛行機が登場して爆弾を投下したり、長い砲身の大砲がつくられて十キロ先にまで砲弾を飛ばしたり、はては戦車が登場して自在に戦場を走り回る戦争になった。そのあげくに毒ガスが登場して、相手国の戦闘員・非戦闘員を問わず殺戮に走った。
戦争はまさに国家総力戦となり、相手国の国民を抹殺する方向にと変わった。
第二次世界大戦はそれがなおのこと徹底し、軍事力はさらに科学技術によってより効率的になり、むしろ都市爆撃に象徴されるように相手国の国民を抹殺することが目的になった。その象徴が原爆の登場だったのである。
このような人類史の流れを踏まえたうえで本書を読んでいくと、曾根二郎のような特異な哲学を持つ医学研究者が生まれてくる所以がよくわかる。著者はそういう哲学・心情をとくに声高な形容句で語ることなく淡々と記述している。次のようにである。
「曾根は、細菌戦用兵器の研究という国防上重要なものにとりくんでいるかぎり、研究を達成するためにはかなり思いきった行動をとっても許されるはずだと考えた。動物をつかって実験をくり返すよりも、直接人体を使用して実験する方がはるかに効果的であることはまちがいない。戦場では、連日のように多くの俘虜たちが処刑されている。それらは銃殺され首をたたき落されて、土中に埋められてゆく」
曾根は、「それらの死体を惜しいと思った」だけではなく、医学者として「生きた人間を実験動物の代りに使用するという想像もできないことを、自分の手で満足のゆくかぎり実行してみたい」と考えるようになる。
こうした曾根の考え方はやがて関東軍総体の意思になり、蚤にペスト菌を植え、ねずみをコレラ菌の媒介者とし、そしてペスト菌の蚤を風船爆弾でアメリカに飛ばすといった戦略兵器に代えるべく一大工場をつくり、壮大な人体実験をくり返していく。延べにして三千人余の中国人・ロシア人捕虜がその犠牲となった。