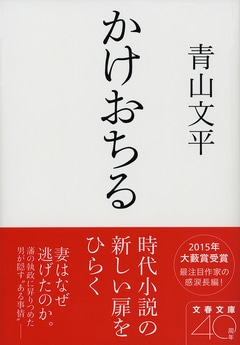未熟な若者が、巨大な社会悪と立ち向かい、見事に退治することで成熟し、結婚や社会的な地位の獲得など、ありとあらゆる幸福を満喫する。……
人間を成長させ幸福に導く、このような黄金のプログラムに対して、青山文平は異を唱える。社会正義の実現や結婚をもって最終ゴールとするタイプの歴史・時代小説は、もはや現代に適合しないのではないか。なぜなら、「社会悪」を退治することなど、若者にはとうてい不可能だからである。
三人のうちの青木昇平は、子どもを斬ろうとしていた浪人を斬り、その功績で非役の小普請組から脱出し、「御入用橋等出水之節見廻役(ごいりようばしとうしゅっすいのせつみまわりやく)」として召し抱えられた。だがこれは、お約束の「成長プログラム」ではない。昇平が斬ったのは、社会悪としての貧困ではなかった。狂気に陥った浪人は、貧困に負けた弱者でしかない。巨悪は、別にいる。しかも昇平は、兵輔の妹の佳絵(かえ)に好意を持つが、簡単には結ばれそうにない。彼は、人を斬っても、成熟できていないのだ。
本書の視点人物は、村上登である。剣の腕前で最も優れている登でさえ、「美しい佳絵と結婚したい、そして、薬草園で緬羊(めんよう)を飼育し、二人で平穏に暮らしたい」という夢を見たことがある。しかし、戦いもせずに幸福を手に入れたいと願うのは、虫が良すぎる。
話は変わるが、現代の青少年が熱中するゲームの世界には、その人物さえ倒せばゲームが終わりとなる「最終ボス=ラスト・ボス」、略して「ラスボス」なる存在が設定されている。だが昇平にも、登にも、そして兵輔にも、「ラスボス」が見つからない。
三人の師である佐和山正則は、はてしない武者修行の旅を繰り返している。それに対して登は、「そもそも、この天明の世に、立ち合うべき武芸者がいるのかも疑わしい」と疑問に思う。
その一方で登は、「この天明の世ならば誰が下手人になってもおかしくはない」とも思う。心の中に堆積した巨大なエネルギーは、自分のための成長プログラムが開始するのを渇望する。だが、いつまで待っても、プログラムは始まらない。成長プログラムから見捨てられた者は、遂に自らを「ラスボス」へと変貌させて、誰かが自分を倒して成長するための捨て石になろうとする。そうでもしないことには、この世に生まれた意味がない。
江戸時代の武士は、平和の獲得と同時に、閉塞というマイナスも手にした。武士の魂である日本刀も、無用の長物と化した。だが、人を斬る(傷つける)痛みや、人に斬られる(傷つけられる)痛みなくして、どうして文明の成熟や個人の成長など、ありえようか。
江戸の市中を、「大膾(おおなます)」という残忍な辻斬りが騒がせている。この大膾もまた、ラスボスを自ら買って出た敗者なのかもしれない。あたかも、昭和四十五年、昭和元禄の泰平の日本を震撼させた三島由紀夫のように。
人間の価値観は、絶えず二つの極の間で揺れ動く。文と武、平和と闘争、偽りの幸福と真実の幸福、正気と狂気。……
登は、本草学者の渋江長伯(ちょうはく)と接しているうちに、世界の限りない広さを知る。そして、「この世には、自分が慣れ親しんだ世界とはまったくちがう世界が重なっている」と感じた。
この「まったくちがう世界」とは、狂気の世界のことなのか。それとも、すばらしき新世界なのか。あるいは、実はどこにもない夢物語なのか。結局、どんなに酷薄であったとしても、「自分が慣れ親しんだ世界」に留まるのが、人間の使命なのか。
このような二つの世界の重層を、青山文平の文体は巧みに写し取ることに成功している。登と佳絵の恋を語る場面では、美しい比喩表現が多用される。すると、現実世界が「もう一つの理想的な世界」へと変容してゆくような期待が高まる。だからこそ、願いがかなわなかった時の絶望も深まる。
小説のラスト近くで、受け入れたくない現実を突きつけられた登は、「いま、時は誤って流れている」と、思う。誰かが目の前で、耳にしたくない残酷な現実の話をしている。だが、登は心の中で、現実とはなりえなかった心願の国を思い続ける。こういう錯綜する場面の描写で、二つの世界を自由自在に往還できる青山文平の文体の強みが発揮される。
二つの世界のあまりの落差の前に、三人の若者たちの友情も崩れた。最後に踏みとどまったのは、視点人物の村上登だった。登は、非役である自分が武士であることさえも信じられず、常に迷い続ける性格である。これが弱さではなく、強さに変じたのだ。
《「己が何者なのか……。橋を渡れなくなるほど迷うから、決めつけることがない。一つに固まって閉じることがない。」》
佐和山正則の不釈(ふしゃく)流の極意も、ここにあった。不釈流は、「諦めの剣」であるという。 相手に斬られて死ぬことを恐れず、わが身を死に任せることで、とっさのうちに生への本能が目覚め、無意識のうちに相手を斬る。
この小説のクライマックスは、登が体験した二つの真剣での立ち会いである。
「武士の突きがゆっくりと伸びてくる」とある。実際には、凄まじい気合いの必殺の突きだったに違いない。だが登には、それが「ゆっくり」と見えた。二つの世界と二つの時間の流れを知った登だからこそ、そして現実世界に留まる覚悟を固めた登なればこそ、ゆっくりと見えたのだ。
生と死が入り交じり、死の陶酔が一転して生への執着に変貌する。この瞬間、人間という存在が大きく変容する。これまで、一方的に運命によって受動的に生かされ、殺されてきた人間が、自らの意志と行動で世界を生きる能動性を掴(つか)み取ったのだ。
人生の形を一つに定めず、迷い続け、人間の成長プログラムを作動させないからこそ、登にはこの奇蹟が起きた。ついに、彼の主体的な生が開始したのだ。
迷いというマイナス、死というマイナス。マイナス同士が掛け合わされて、最強のプラスが出現した。言わば、人生の錬金術が施されたのだ。しかも、登は主体的に錬金術を自ら執り行った。これからも、真実の生を創り出すために、真剣を振るうことだろう。
戦いの直前に、「いまならば斬れる」と、登は感じた。青山文平も、本書を書き下ろしつつ、この場面で「いまならば書ける」という確信を持ったのではないか。
マイナスがプラスに変ずる奇蹟を起こした登の人生は、ここから始まる。自分が斬った者の思いを引き受け、登は生きてゆく。そして、青山文平の歴史・時代小説作家としての歩みも、ここから始まる。
青山文平の小説は、閉塞して久しい現代日本の扉を開くヒントを、読者に与えてくれる。だからこそ青山には、二十一世紀初頭の日本文化の申し子となってほしい。戦後日本文化の申し子だった松本清張の名を冠した「松本清張賞」に彼が輝いたのも、そのためではなかったか。
本書で見事な初陣を飾った青山文平は、これからも死と生、夢と現実の二つの世界が交錯・融合する奇蹟の瞬間を読者に、かいま見せてくれるだろう。それが、現代文化の閉塞感を吹き払い、未来を呼び寄せる。青山文平は、文学と文明のラスボスを、視界の彼方にしっかり捕えている。