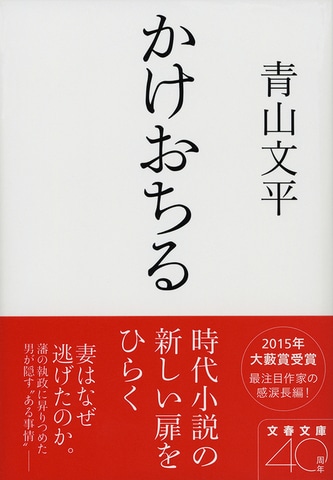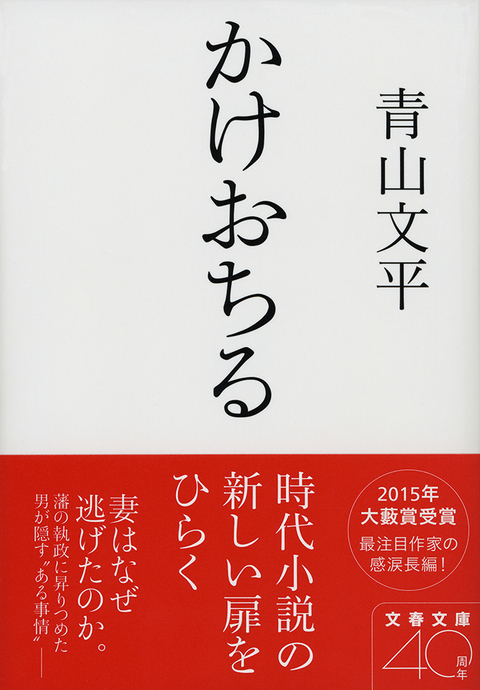「かけおちる」を読んでいただいて、ありがとうございました。
青山文平、と申します。
後書きのページを頂いたので、すこし、書き手としての自分を紹介させていただきたいと思います。
初めて、小説を書いたのは一九九二年です。ベルリンの壁が崩れて三年後ですね。
いわゆる純文学のジャンルで、題名は「俺たちの水晶宮(すいしょうきゅう)」。水晶宮というのは、一八五一年の第一回ロンドン万博のモニュメントとして建てられた、ガラスと鉄の建築を想定しています。現在のイギリス王立キュー植物園の、大温室をイメージしてもらえばよいでしょう。
これは、当年の中央公論新人賞を受賞しましたが、それからほぼ十年やって、純文学、というよりも小説じたいの執筆をやめました。充電、などではありません。もう、すっかり創作からは離れて、二度と書くことはないだろうと思っていたし、事実、そのとおりになりました。なのに、やめてからまた十年近くが経った二〇一〇年になって、再びキーボードに向かったのは、多分に経済的理由です。
私は中央公論新人賞に応募するのとほぼ同時に、十八年お世話になった会社を辞していました。
小説を書くという行為は因果なもので、夜、眠っても、書きかけていた次の文章が浮かんで目が覚めたりします。頭のその部分は眠っていないんですね。で、勤め人としてきちんと振る舞うには時間的に無理が出るようになっていたのです。
それからは、六十半ばの今日まで、ずっとフリーです。参考になるかどうか分からないけれど、勤続十八年の年金では喰えません。たいへんだ、とかではなく、はっきりと喰えません。奥さんは国民年金だけなので、独りになったら、もう絶対的に喰えません。十年間、小説の執筆とは無縁だった自分の指が突然動き出したのは、その事実を数字で突き付けられた夜でした。そうしてできたのが、二〇一一年の松本清張賞受賞作「白樫の樹の下で」です。
そのように、私の二度目の創作の営みはあくまで経済行為のつもりでした。だからこそ、純文学ではなく、時代小説のジャンルを選びました。当然、売れ筋を狙うべきなのですが、人はそう理屈どおりには動きません。いざ、創作と向き合うと、やはり表現行為になってしまいます。つまり、人の地肌を描きたくなってしまうのです。というよりも、それ以外には指が動かない。再び、書いてみて、そういうものであることを知りました。自分の思惑なんぞで、どうこうなるものでもありません。気持ちの底から突き動かそうとするものに、従うしかないのです。書けるものしか書けない。