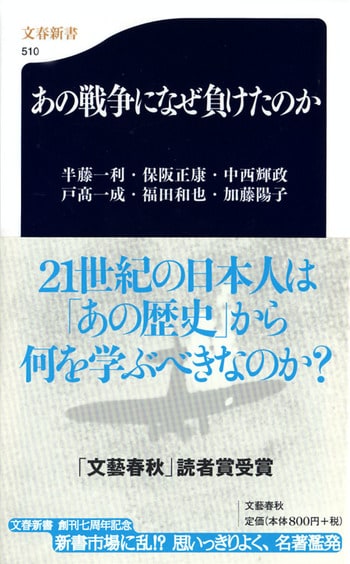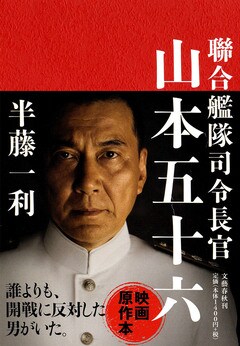昨年(平成十七年)は、「戦後六十年」ということで、メディアを中心にあの戦争をふり返ることが多かった。とはいえ、戦争それ自体を記憶している世代は極端なまでに少なくなっている。ふり返るといっても歴史のひとこまという見方になるのは仕方がなかった。
私見をいえば、戦後六十年は好むと好まざるとにかかわらず「同時代史から歴史への移行」を意味しているように思う。同時代史というのは、記憶が主、記録が従という構図があるし、あるいは政治や思想が軸になり、歴史的見方はそれに従うという枠組みであった。この構図や枠組みは、太平洋戦争そのものを好悪の感情で語ったり、ある史観のプロパガンダのために史実がツールとして利用されるという意味をもっている。当然ながらそこには見えないものがある。
私があえて「歴史に移行していく」というのは、この見えないもの(不可視の領域ということになろうか)をこれからは意識していかなければならないということだ。わかりやすくいうなら、太平洋戦争は確かに日中戦争の延長として対米英戦争に入っていくことでもあったが、同時にそこには昭和十年代の軍事主導体制が近代日本の建軍以来の矛盾と戦うという側面があったし、この体制を支えた軍事指導者たちがはたして日本陸軍の正統派であったかの問い直しも必要である。
こうした領域にまであの戦争の分析を進めていくということは、同時代史のなかでは容易にできることではなかった。そのような取り組みを試みても体験者の記憶や政治的、思想的解釈の前に圧倒されて正面からは取り組めなかったともいえるだろう。
戦後六十年は記憶にもとづく記録が実質的に役割を終え、記録のなかから教訓をひきだし、それを歴史上に定着させる出発点ではないだろうか。記憶の役割は終えたともいえるし、記憶と一体化した記録(たとえば聞き書きのようなものだが)も早晩役割を終えるのではないか。これからは記録の質が問われていくし、記録のなかにひそんでいる歴史的意味がもっとも重きをなしていくと私には思える。
戦後六十年の夏、六人の昭和史に関心をもつ論者がニューオータニの一室に集まって、「あの戦争に敗れたのはどのような理由によるものか」というテーマにもとづいて討論を行った。アイウエオ順に列記すれば、加藤陽子、戸高一成、中西輝政、半藤一利、福田和也、そして私となるのだが、年齢も異なるしその経歴もさまざまである。共通なのは、あの戦争に対する関心の深さといったところだろう。
自らが関わっているのに自賛まじりで語るのはいささか気がひけるのだが、この企画は太平洋戦争を同時代史で語る段階から歴史で語る段階へと進める書ではないかとも思う。なにしろ記憶をもつ者はなく、半藤氏が皇国少年という年齢であり、私が幼児であったほかは、他の四人の論者は太平洋戦争後に生まれた世代だからである。つまり、あの戦争を歴史的に語るとはどういうことか、という問いに対してもっとも適切な答を返せる論者であり、それが今回文春新書におさめられたのは意義があると再度確認しておきたいのだ。
私は、太平洋戦争に日本が勝つということはありえなかったと確信している。むろん軍事的にである。日米の軍事力の差は大きかったとか彼我の戦略はまったくかけはなれていたなどという理由で語っているのではない。軍事についての考え方、軍事を動かすシステムのなかに、日本は二十世紀の国際社会が諒解していた共通の認識をもっていなかった。軍事的に勝てない戦争だったことは認めなければならない。
しかしこの戦争は政治的には「勝つ」状態をつくりえた。つまり太平洋戦争を通して、日本が先駆的な人類共通のテーマ(たとえば人種差別反対とか植民地主義への戦いといったことだが)を掲げての戦争はできたはずだった。しかし、日本はそのような政策も選択しなかった。
歴史的に語るとは、このような視点をもちながら史実を見つめていくことである。そして私たちには太平洋戦争の諸相を分析しつくして懇(ねんご)ろに弔っていく心構えこそ望まれるのだ。