武田泰淳の「もの食う女」がこのように男性の手でなされた、女性のうちなる「惜しみなく与える」力の発見の記録であるとすれば、岡本かの子の「家靈」は女性自身によって書きとめられた、同じ力の発見の記録であるといってよいだろう。「家靈」のヒロインは「いのち」という屋号をもつ老舗のどじょう店の一人娘で、病いの床に臥せった母の跡を継いで、若くして女主人の座についた。けれども、彼女はこの家業にいま一つ気が乗らない。
「“くめ子”は七八ケ月ほど前からこの店に歸り病氣の母親に代つてこの帳場格子に坐りはじめた。くめ子は女學校へ通つてゐるうちから、この洞窟のやうな家は嫌で嫌で仕方がなかつた。人生の老耄者、精力の消費者の食餌療法をするやうな家の職業には堪へられなかつた。
何で人はあゝも衰へといふものを極度に惧れるのだらうか。衰へたら衰へたまゝでいゝではないか。人を押付けがましいにほひを立て、脂がぎろ/\光つて浮く精力なんといふものほど下品なものはない。くめ子は初夏の椎の若葉の匂ひを嗅いでも頭が痛くなるやうな娘であつた。椎の若葉よりも葉越しの空の夕月を愛した」
こうした生きもののなまぐさい精気に圧迫感のみをおぼえるような性(たち)のヒロインは、しかし、店の閉店間際に夜な夜な姿を現わす彫金工の老人からある晩、自分の母親とこの職人とがかつてどじょう料理を介して心を通わせ合ったという秘話を聞き、老人の、「たゞ/\永年夜食として食べ慣れた“どぜう”汁と飯一椀、わしはこれを攝らんと冬のひと夜を凌ぎ兼ねます。朝までに身體が凍え痺れる。わしら彫金師は、一たがね一期です。明日のことは考へんです。あなたが、おかみさんの娘ですなら、今夜も、あの細い小魚を五六ぴき惠んで頂きたい。死ぬにしてもこんな霜枯れた夜は嫌です。今夜、一夜は、あの小魚の“いのち”をぽちりぽちりわしの骨の髓に噛み込んで生き伸びたい――」という必死の嘆願に接して、心機一転する。彼女が老職人の願いを容れ、どじょう汁をつくるため、生簀から生きたどじょうをすくい上げると、「日頃は見るのも嫌だと思つたこの小魚が今は親しみ易いものに見える」。彼女の掌のなかでどじょうがぴくぴくとうごめく。「すると、その顫動が電波のやうに心に傳はつて刹那に不思議な意味が仄かに囁かれる――いのちの呼應」。このとき、彼女は「脂がぎろ/\光つて浮く」「いのち」の脈流におのが全身をひたし、そのなかで母親の秘められた思いを受け取り、そうすることで、消耗した客たちに「いのち」を恵んで生気をよみがえらせる役割を担った、立派などじょう屋の女主人の座を受け容れるための決定的なきっかけを掴んだのである。
「いのち」の脈流を泳ぎ回る女性と言えば、近藤紘一の「夫婦そろって動物好き」に登場する語り手の妻など、まさにその極めつけといってよいだろう。男性が“食”を通じて女性のうちなる神秘的な力にじかにふれて驚嘆をおぼえる話という点では、これは「もの食う女」と軌を一にするが、両者のタッチはいささか異なっていて、「もの食う女」が地味な黒白調で、穏やかなユーモア味を帯びているとすれば、こちらは派手な原色調で、ドタバタ喜劇のように凄まじく痛快である。読者は誰しも、本篇のヒロインである、日本人と結婚して日本に住むことになったベトナム人女性のすこぶる奔放不羈な言動にショックを受けずにおれぬにちがいない。

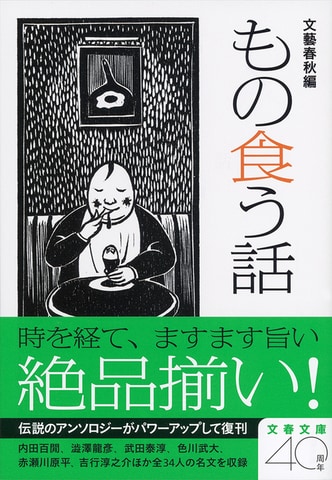


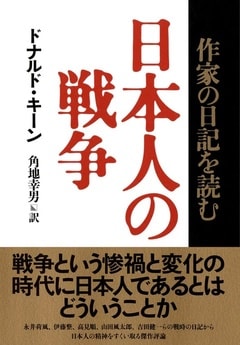
![[選者対談]小池真理子・川上弘美作家の全随筆を読んで見えてくるもの](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/9/9/480wm/img_99dfda8f29ff2d71bb2819048258a0de47962.jpg)










