本稿は旧文庫版(1990年刊)解説の再録です。
「飽食の時代」といわれてすでに久しい。たしかに今日の私たちは古代ローマ帝国の貴族のように居ながらにして全国各地、世界各国の料理という料理を心ゆくまで味わいつくすことができる。日本人の誰しもが知らぬまにひとかどのグルメとなり、日毎、山海の珍味に舌つづみを打つ。高度成長期の初めのころはさかんに「性の解放」が唱えられ、エロティシズムの讃歌が口ずさまれ、みんなが色情狂と化したかのように思われたものだが、低成長期に入ると、色気から食い気のほうにいつしか関心が移って、みんなが美食家に豹変したかのごとき観を呈した。十年来、“食”の情報量はうなぎ登りに増加して、いまや食味随筆、食卓の文化史、料理人を主人公にした漫画などが本屋の店頭にあふれ返っている。私など、正直なところ、もういい加減、うんざりなのだが、こんな“食”情報の氾濫は、まだ当分、少なくとも二十世紀末の間じゅう、延々と続きそうな模様である。
「飽食の時代」とは、言い換えれば、“食”が飽和状態に達することで、かえって“食”の根本が見失われ、食文化が最も貧相になり下がった時代なのではなかろうか。なるほど私たちはお金を出しさえすれば、何でも好みのものが食べられるが、そのかわり、ものを食べることの真の喜び、ありがたさ、かけがえのなさなどの実感をすっかりなくしてしまったのではないか。かつて“食”は人間のドラマのなかにその不可欠の因子としてちゃんと織り込まれていて、たとえ情報量が少なく、素材が限られていようとも、精神的な豊かさをたっぷり秘めていた。ところが今日、“食”は物量の面ではちきれんばかりに膨れ上がりながらも、人間のドラマから切り離され、孤立化して、内実がおそろしく貧弱になっている。この「飽食の時代」から自分を意識的に隔絶させでもしない限り、私たちが人間の精神における“食”の重要な役割を明瞭に自覚化することはとうてい不可能であるにちがいない。
人は、毎日、三度ずつ“食”に関わりながら、漠然とやり過ごして、およそ考えてみもしなかったその意義を、何らかのきっかけで発見することがある。“地”のなかに埋もれていた“食”が不意に“図”へと反転し、輪郭鮮やかにこちらに向かっていきなり迫(せ)り出してくる瞬間があるのだ。現に、本書に収められた文章の多くは、こうした“食”の意義の発見にともなう驚きや感動を読者に如実に伝えてくれるだろう。これらの発見の数々は“食”の欠如態をつねにその前提条件としている。端的に言えば、私たちは何らかの事情で食うに事欠いたときにこそ、“食”のかけがえのなさ、貴重さを身に沁みて思い知るのである。食うに事欠いたときというのは、本書所収の文章に即して言えば、病気のため食事を大幅に制限された場合(色川武大「大喰いでなければ」など)であり、生活上の貧窮ゆえ慢性的に飢えさせられる状況であり、あるいは、戦時中から戦後にかけて国民を苦しめ抜いた食糧不足と飢餓の時期(古川緑波「悲食記」など)である。

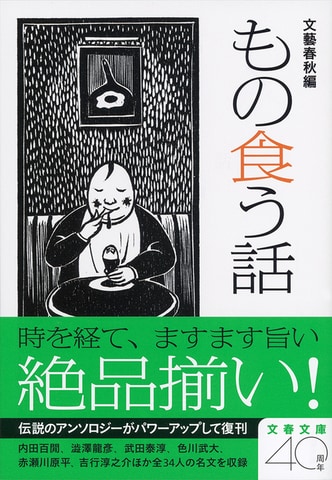


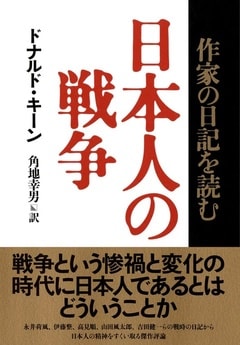
![[選者対談]小池真理子・川上弘美作家の全随筆を読んで見えてくるもの](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/9/9/480wm/img_99dfda8f29ff2d71bb2819048258a0de47962.jpg)










