彼女はアパートの部屋で禁断のウサギを飼い、とびきり上等の餌であるアザミの葉を刈り集め、ウサギをわが子のように溺愛する。そして、ウサギがじゅうぶん肥え太った頃合いを見はからって、一羽ずつ撲殺し、その肉をご馳走料理にして得意気に家族に供する。とりわけ、語り手である夫が夕方、胸騒ぎを感じながらアパートに戻ってみると、テラスが血の海と化し、物干しにウサギの本体がぶら下がり、その下に頭部や脚の先や毛皮などが散乱していて、ドアに背を向けてしゃがみ込んでいた妻が血染めの出刃包丁を握ったままこちらをふり返り、ウサギの末期の模様を報告してにっこり笑うというくだりがまことに圧巻であり、そっけないほど簡潔な筆致で描かれているので、ひときわ印象鮮烈である。
このベトナム女性にとっては、動物を真底かわいがることとその息の根をとめ肉を啖(くら)うこととのあいだには何の矛盾もない。彼女からすれば、両者のあいだに落差を感じてとまどう夫や、ウサギの死を知ってベソをかく日本化した娘のほうがよっぽどどうかしているのだ。
「彼女はこんごも動物を自らと等価値のものとして親身に遇し、かつ、必要とあれば彼らを平然と殺戮し続けるだろう。これは、感情や感覚の問題ではなさそうだ。彼女の国の風土と文化に裏打ちされた、然るべき行為であり、父祖伝来の生活の規範なのだろう」。しかし、彼女の一連の大胆な振舞いをベトナム人の習俗に還元するにとどまらず、国籍のいかんを問わず、すべての女性のうちにひそむ鬼子母神的な本性のまことに直截な表現をここに看て取る必要があるのではなかろうか。そういえば邱永漢の「食在廣州」に、筆者の妻が夫の制止も聞かずに、ゲンゴロウの黒光りする体を平然とぼりぼり食べるシーンが点出され、女性のほうが根っから食欲旺盛であり、生きものの生き死にに関しても男性よりはるかに不敵な気構えをもっていることが示唆されているけれど、たしかにそのとおりなのにちがいない。
赤瀬川原平が「食い地獄」で指摘しているように、人間はおしなべて食べることに漠然と後ろめたさを感じている。「ものを食うということは、いわば世の中にあるものを盗むことで」、「生きていくために必要なことだ、とかいってみても、とても恥ずかしいことなのだ」、「下品で軽薄でいやらしいことなのだ」。なるほど私たちは定かならぬ羞恥心や罪悪感に妨害されて、“食”についてまともに考えるのを避けて通ろうとする傾きがある。だが私たちは、食事というものがそもそも生きものが生きながらえるために他の生きものに容赦なく襲いかかる血まみれの地獄絵図であることを怯(ひる)まず確認し自覚した上で、“食”のうちに顕現する生命の根源的無垢性を信じ、故なき羞恥心や罪悪感をきれいさっぱり拭い去るべきなのではないか。「幼児のやうな無恥の食欲」(萩原朔太郎)を大いに発揮し、他の生きものを貪り食う行為をまるごと肯定することによって、人は初めて「いのち」の脈流を自在に泳ぎ回ることができるのである。
「飽食の時代」に生きる私たちに最も欠けているのは、「夫婦そろって動物好き」のヒロインにみごとに体現されているような、こうした生物の殺戮への晴れやかで朗らかな全肯定の意志なのではあるまいか。

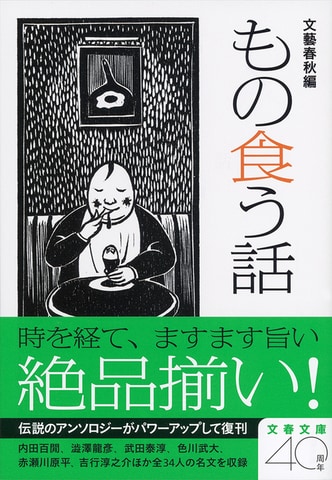


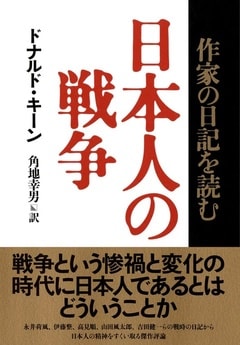
![[選者対談]小池真理子・川上弘美作家の全随筆を読んで見えてくるもの](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/9/9/480wm/img_99dfda8f29ff2d71bb2819048258a0de47962.jpg)










